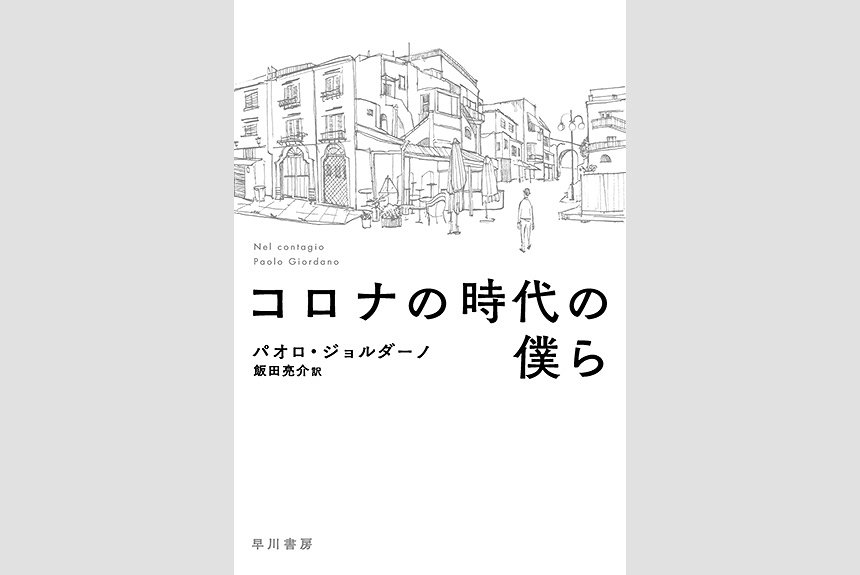世界で最も新型コロナウイルスの影響を受けている地の1つ、イタリアから届けられた気鋭の作家のテキストが、邦訳刊行前から日本でも話題となっている。2020年4月24日発売のパオロ・ジョルダーノ『コロナの時代の僕ら』(飯田亮介訳、早川書房)だ。
過日の本文48時間限定公開に加え、公開継続中の「著者あとがき」に見られる真摯な苦悩が、評判を呼んでいるのだ。これまでも人々を魅了してきた瑞々しい文章で綴られた本書、その問いを読み開くべく、一本の書評をお届けする。
いずれ過ぎ去る現在の状況。今私たちができること
「仮に車の外に何も見えなかったとして、車が動いていることも知らなかったとしたら、それが滴のせいなのか、僕たちのせいなのか分かりようがないんだろうな」彼は言った。
「何が誰のせいだって?」わけが分からなくなった父親は少しいらだっていた。
「滴がこうして斜めに落ちてくる原因のことさ」
(『素数たちの孤独』)
「とにかく、夜ってやつが多すぎて困るようになるんだ。次から次に夜が来て、本当、きりがねえ。どう時間を潰したものか見当もつかなくなるんだ――この先、いろんなことが山と待ってるぜ。忘れようにも忘れられないようなことがな。おまえはまだ若い。何もかもこれからさ」
(『兵士たちの肉体』)
思わぬ「空白」の時間の中、柔らかなタッチで紡がれた『コロナの時代の僕ら』をひもとくと、身動きができなくなった思考が、まるで潮の流れに導かれているような感触を覚える。コンパクトな書物であるのに、本当にさまざまなことが書かれている。
たとえば、感染流行の初期、友人から夕食に招かれた際の戸惑い。まるで自分が「透明人間」になったかのような孤独と不安。市民と行政と専門家の間の、関係のもつれ。つまりは日本語訳を読む人の多くが体験してきたことは、かのイタリアの地で既に起こっていたことなのだ、ということ。
重要なのは、そうした日常を共有した上で、新型コロナウイルスが「過ぎたあと」を、できる限りの想像力で考えてみることだ、ということにもハッと気づかされる。著者は語りかける。
たとえばこんな問いだ。すべてが終わった時、本当に僕たちは以前とまったく同じ世界を再現したいのだろうか。

断章形式で綴られたテキストを読み、また私たちは、考え込む。異なる流れを汲みこみながら、思考は緩やかに渦を巻く。視野狭窄になりがちな日々の中で、目が開かれることで生まれる奔流と、それによって発生する滞留。共に、とても大切なものだろう。著者がいうように、「僕らのさまざまな関係を侵す病」が広がった今なら、なおさらだ。
イタリア本国では200万部超、世界的なベストセラーとなり、日本でも好評だった恋愛小説『素数たちの孤独』、アフガニスタンに赴いたイタリア人兵士たちの群像劇『兵士たちの肉体』(邦訳は『コロナの時代の僕ら』と同じく早川書房より刊行、飯田亮介訳)などで展開されてきた端正な文章は、コロナ禍の渦中に書かれた本書においても、静かに輝きを放っている。素粒子物理学の博士号を持ち、少年時代より数学的思考に魅かれながら、文学の才にも恵まれたジョルダーノならではの筆致は、複雑な現状を解きほぐしてくれてもいる。
たとえば、私たちがここ最近、にわかに耳にするようになった「R0(アールノート、基本再生産数)」に関しては、人類を75億個のビリヤードの球にたとえて、うまくイメージさせてくれる。

まだ感染していない球の集団に、感染した球が1つ突っ込んで、2つの球にぶつかり、さらにその2つの球が2つの球にぶつかり……といった連鎖反応では「R0」が2であり、この値を1以下にしなければならない。それは「水道の元栓を開いたまま蛇口の修理をする」のに似ている、という比喩も含めて、とてもわかりやすい。「自然は生まれつき非線形なのだ」という端的な指摘も、パンデミックを非常なるものとして捉える基本姿勢こそを、鮮やかに問い直している。
一方で、「僕たちはビリヤードの球ではない。人間だ。欲望とストレスを山と抱える生き物だ。そして人間は何より、用事を山ほど抱えている」と、「関係の科学」としての数学の要素になかなか還元しきれない人間の面倒くささをも引き受けながら、彼は筆を進めている。数学的思考と文学的思考、双方を携えていることが、矛盾に満ちた現在を考えることの手立てとなっているのだろう。それは私たちにとっても、だ。いずれ恐怖と共に一時的なものとして去ってしまうかもしれない、ジョルダーノ曰く「揮発性の意識」を、少しでもとどめおく手立てーー。

今後の私たちに課せられた、いくつかの問い
ここで、一本の補助線を引いてみたい。『コロナの時代の僕ら』を読んでいる間、評者の頭の中にこだましていたのは、別の作家が、さらにもう一人の作家のことを語りながら口にした、あるフレーズだ。
コロナ禍が日本社会を徐々に侵しつつあった2020年3月、NHK Eテレで放送された番組『100分 de 名著』で取り上げられたのは、作品を通じて人類の未来を考え続けたSF小説の大家アーサー・C・クラークであり、解説を担当していたのは作家の瀬名秀明氏。その瀬名氏がクラークを引き合いに出しながら口にしたのが、「センスのよい好奇心」というフレーズだった。

「センスのよい好奇心」……今この状況の中で、牧歌的に響くだろうか。いや、そうではない、と思う。「好奇心」を「ベクトル」と言い換えてみてはどうだろう。来た道を振り返り、進む道を見据える、つまりは来し方行く末を捉える「センスのよいベクトル」。
私たちは、ジョルダーノが「義憤、遅れ、無駄な議論、よく考えもせずに付けたハッシュタグ」と並べるようなものの只中で、考えを巡らせねばならない。決して、議論が無駄だ、と書かれているのではない。むしろジョルダーノ自身、静かに怒っている。「いったい何に元どおりになってほしくないのか」と問う彼が、本書の後段で主に論じるのは、ウイルスと人類の接触の要因としての環境破壊だ(「僕らのほうが彼らを巣から引っ張り出している」)。これもまた、1つの「ベクトル」である。

『コロナの時代の僕ら』という書物に対して「センスのよい」という言葉を用いても、それは他の書物に比べてあれかこれかと優劣をつけられるものでもないし、ましてや情報商材に類する書籍のように、本書を読めば何かが解決する、という本でもない。しかし、ただ漠たる問いを投げ出しているのでもない。具体と抽象を行き来しながら、深められた苦悩と問いがここにある。本書を手に取り、ページを開くということは、その悩みと問いの「ベクトル」に、暫し賭けてみる、ということだ。
新たな問いも、その上でこそ可能となるだろう。ジョルダーノは感染症の流行時、町や州、あるいはイタリアやヨーロッパといった区分ではない「人類全体」、さらには自然の「生態系」も含めた「共同体」に一人ひとりが属す、と書く。ボリス・ジョンソン英首相は「社会というものは、たしかに存在する(There really is such a thing as society)」と述べたが、存在するものとしてそれぞれ述べられている「共同体」や「社会」の実とは何なのか、それに属する(とされる)ことはどういう意味を持つのか、いや、本当に(あるいは、どれほど)存在するのか、という問いも、今後の私たちに課せられているかもしれない。

しかもすべては、距離を隔て、生活を成り立たせ、ときに孤独に耐え、ときに声を上げながらなされなければならない。ジョルダーノはかつて小説の中で「話しながら、同時に考えようとするのは難しかった。2つの行為が互いを打ち消し合う」(『素数たちの孤独』)と書いたが、そうした難しい行為を、少しずつ私たちは試行していくのだろう。
薄い靄(もや)が満ちた道の最中で、足元を仄かに照らすーーそんなささやかな灯りに、本書はなってくれるに違いない。

- 書籍情報
-

- 『コロナの時代の僕ら』
-
2020年4月24日(金)発売
著者:パオロ・ジョルダーノ
価格:1,430円(税込)
発行:早川書房
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-