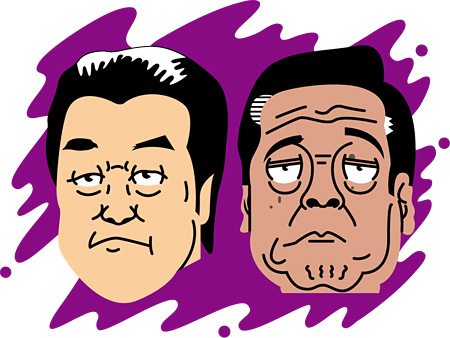其の二 小沢一郎と島田紳助
菅直人の後継を決める民主党党首選挙の動向は、結局のところ、小沢グループの投票先の動向、つまり小沢一郎が誰を推すかに握られていた。政治資金問題で鳴りを潜めた印象のあった小沢だったが、やはりここにきてもなお、真っ先にすがられる人物だったのだ。かつて小沢一郎の秘書を務め、昨年初頭に政治資金規正法違反で逮捕された石川知裕の著書『悪党 小沢一郎に仕えて』の中で、作家・江藤淳が小沢に対して放った言質が引用されている。「小沢一郎が永田町を去れば、永田町は反小沢の天下になるのだろうか? かならずしもそうとはいえない。そのときむしろ、無数の小・小沢が出現する可能性が開けると見るべきである。なぜなら、反小沢を唱えさえすれば能事足れりとして来た徒輩が、今度は一人ひとり自分の構造を語らざるを得なくなるからである」。江藤の予測は、小沢票を得ようと小沢に近付いていった小ツブ候補者たちの群れを前もって皮肉っていたかのようだ。「小・小沢」の群れが、こっちで何人あっちで何人と足し算引き算の小競り合いを経て、野田首相が誕生した。この連載で石原慎太郎を取り上げた際、江藤の石原評「無意識過剰」を引っ張ったが、江藤は小沢に対しても的確な評価を投げかけていたのだ。
お気付きだろうか、江藤の発言の「小沢」を「島田」に、「永田町」を「芸能界」に置き換えると見事に芸能界の現状を突き刺す指摘となる。後半部分を少しアレンジしてみるとこうなるだろうか。「島田紳助が芸能界を去れば、芸能界は反島田の天下になるのだろうか? かならずしもそうとはいえない。そのときむしろ、無数の小・島田が出現する可能性が開けると見るべきである。なぜなら、島田を礼讃しさえすれば生きてこられた徒輩が、今度は一人ひとり自分のやり方を模索せざるを得なくなるからである。しかし、今まで引っ付いて来ただけの面々、独自の道などすぐには探れまい。つまりは島田紳助の縮小版としてリプレイするだけだ」。江藤の小沢評は、こうして島田評にも置き換えることができる。ほらだって、まさに、小・小沢の登場と時を同じくして、小・島田が前線に増殖しているではないか。
小沢一郎について考えるとき、大抵は「裏で政治を操縦している人」という印象から始まるだろう。ニュースの短い時間に挟み込まれる彼は、十中八九、苦い顔をしている。苦い顔のまま固まってしまって元に戻せなくなってしまったのではと思わせるほど。問いかける記者に向かって無視を決め込んだり、傍若無人な態度を隠さずに適当にあしらったりする。打って変わって破顔している彼が映っていたら、それはおそらく「何がし君を励ます会」の類いで身内に囲まれてチヤホヤされている時だ。つまり、見事に閉ざされた政治イメージの中にある。談合政治、自民党政治の悪しき残り香、「田中角栄になれなかった男」なんてネーミングもあったけれど、とにかく時代を巻き戻す政治手法で生き長らえていると決めつけられている。しかし、相当早い段階(2007年)からニコニコ動画に出演していたり、記者クラブのフリー記者への解放にも積極的な立場をとってきたり、というような一面もある。記者クラブで金魚のフンのように引っ付いて、発表されるコメントを大人しく書き留めているだけのサラリーマン記者連中を何よりも毛嫌いする小沢のやり方は、思いのほか先進的なのだと考えていくことも出来る。過剰なまでに数の論理にこだわり、そこから内輪で舵取りし、そこでの決定項を強制的に外へ波及させていく権力行使は褒められたものではないし、岩手出身の彼が被災地に一切入らず、長老・渡部恒三との合同誕生会でわいわい騒いでしまう国民度外視の図太さには非難が向かうべきであるが、少なくとも「裏で操縦している人」の一言で断じられてしまうほど、彼の動作は閉ざされているわけでもないのである。伝えたいことを好都合に分断されるやり方が彼の報道不信を生み、跳ね返るようにこちら側の小沢不信を生んだのだ。
自分に都合の良い世界を築き守ることが第一、そしてその世界をそのまんま外に伝えるための人員・組織に執拗にこだわるのが第二、その流れを絶ち切るものは徹底的に認めないのが第三、どうだろう、小沢一郎から見えてくる指針は、そのまま島田紳助にも適用できそうだ。小沢一郎を分析する書籍は大量に出ているが、それらを適当につまむと、必ず、近しい立場からのコメントとして「テレビなどからのイメージだと仏頂面で話しかけにくそうですけど、普段はとっても情が深くて温かい人ですよ」というコメントが出てくる。おっと、これも島田紳助と一緒だ。島田紳助の近くにいる人間は、必ずそう言う。あれだけ毒舌で、人をぶっきらぼうに扱って傷つけているように見えるかもしれないけれど、裏ではとても思いやりのある人です、と。その温かい声が一方的に中から聞こえてくるのって、実に物悲しい。外に聞こえない内側からの大声は、外に開かれていない証拠にもなりかねない。角栄さんが道路を作ってくれた、小沢さんが誘致してくれた、と同じベクトルで、紳助さんがいたから今の私がいると、熊田曜子が言う。ああ、これでは、決して外に届かない。
島田紳助が主催してきた「M-1グランプリ」については、その審査員のラインナップにずっと疑問があった。最終回となった去年末の審査員は「中田カウス/宮迫博之/渡辺正行/大竹一樹/南原清隆/松本人志/島田紳助」である。好き嫌いの問題からくる疑問ではない。要するにこの人達ってもう、漫才やっていないでしょうという真っ当な疑問はどうしたって湧いてしまう。定期的に漫才をやっているのは何人もいない。中田カウスと大竹一樹くらいだろうか。松本人志はご存知のように漫才はせずとも笑いのためのあらゆる作法を探っている。でもあとは、司会業か、バラエティでの高級な添え物だ。そんな彼等に、一本のスタンドマイクを奪い合うように絡む漫才の斬新さを感知できるのかと。決まり事だらけで動作のある程度定まったバラエティを難なくこなし続ける皆様に、この一発勝負のライヴの醍醐味が見定められるのかと。ここでもやっぱり体育会系縦割り行政が発動していた。「昔やってたから今でも分かる」、そこからピラミッドを上から見渡し、その頂上を決める。決めるのは、頂上に住む自分たちだ。これでは、本当に上に突き抜けるものなど出て来ない。このグランプリで優勝した面々が、優勝後、尖った角を削り取られたようにバラエティで大人しくハジけているのを見ると(パンクブーブーや昨年の準優勝・スリムクラブなど特に)、これが何だか、小沢グループにスッポリおさまった民主党一期生と同じ光景に見えてくる。「小沢先生に一生ついていきます!」と豪語した谷亮子のごとし。
小沢から島田へ、互いにスライドし合う議論を続けているが、この関連項目を更にそのままスライドできる人物がいるとすれば和田アキ子だろう。芸能界のゴッド姐ちゃんと言われているが、何がどうしてそこまでの権力を持ちうるのかがちっとも見えてこない。街中で、誰が和田アキ子を待望しているのだろう。是非、お会いしてみたい。周囲にいる芸能人も、『偉そうにしてるから「よっ偉い!」なんておだててみたらご機嫌麗しくなって「イエーイ」とダブルピースしてきたので乗っかったら仕事も分けてくれてファミリー入り』って感じだ。近くでタムロする面々の軽薄さ、つまり、峰竜太と勝俣州和のあの薄さ。まあ、和田アキ子についてはいつかの機会に譲りたい。早めに閑話休題。
朝日新聞のオピニオンコーナーで「ロッキング・オン」社長の渋谷陽一が、鉢呂経産省大臣の失言辞任を受けて長いコメントを寄せている。肉体性のある言葉が必要だと、渋谷は言う。対極に、体温の無い、生気の無い発言は、世間の気分によって決められてしまう、とする。それがポジティブなら喝采を浴び、ネガティブなら失言になる。渋谷も言うように、鉢呂大臣の言った「死のまち」という言葉はとても肉体性を持っていた。住民が追いやられ、逃げ遅れた動物達が奇声を上げ、その横を白装束を乗せた車が走り抜けていく福島の今が「死のまち」なのは、どうしたって事実だ。お得意の、当事者ぶった「福島の人のことを思ったらそんな事言えない」という声にさらわれてしまったが(補足しておくが彼の「放射能つけちゃうぞ」発言は「死のまち」発言が問題視された後に付け足しで出てきた言葉。どういう発言だったかの確証もなく、各社バラバラの表現をしており、正確性に欠ける)、現地に入りその状況を表す言葉として、何ら間違った表現では無いだろう。「死のまち」を「ゴーストタウンだった」と英語にしてみたら、意外と何にも言われなかったんじゃないかという気もする。理解されるための言語と伝達テクニックが彼には欠けていた。肉体性のある言語がなくなり、言葉に飢えている今。だから、ネガティブであろうが、ポジティブであろうが、とにかく刺激のある言葉を掴んでみる。結局、言葉狩りのように、失言を見つけては辞めさせて、「ったくもう」と繰り返すサイクルが政治のメインディッシュになりつつある。渋谷は、「逆にそれを動物的に感じ取り、戦略的に利用している」のが橋下徹であり、石原慎太郎であるとする。大衆受けするために劇薬的な強い言葉を撒く。「攻撃は最大の防御」とでも言おうか、非難を浴びる可能性のある発言を吐き続けることで、ちょっとした発言を拾われて頭を下げさせられてしまう大臣のようにならないように仕向けている。しかし、「ならないようにする」が、イコールで肉体性を持つ、には全くなっていないところが橋下や石原の面倒くさいところであるのだが、それはこの連載の「石原慎太郎」の回を読んで下されば分かってもらえるだろうからそちらに譲る。で、島田紳助の話法、というのも、これと同質なのだ。攻撃を繰り返し、場が荒れたところを、自分で勝手に整理しにいく。やや乱暴に片付ける。打って走ってスライディングしてグラウンド整備まで担う。こう書けば、相当な実力を漂わせるけれど、本当のところは、打たせて走らせてスラィデングさせてグラウンド整備させた、であった。その名も島田紳助杯。主催と監督と審判を兼任する。これが彼の近年の実像だった。肉体性というか精神性というか、そういった生々しさを問われる現場(暴力団との交遊は除く/微笑)に一切いなかった。ナンシー関が中山秀征のことを「生ぬるバラエティの申し子」と書いたが、今彼女がいたら、島田紳助のことを、そう呼んでいたかもしれない。現状維持だけで物事がなんだかんだで進んでしまう生ぬるさ。小沢一郎と、ここも似ている。
では、何故、そんな彼がここまで頂上に居続けられたのか、体育会系、ヤンキーイズム、隠蔽体質の政治力、それを受け入れる生ぬるバラエティ、この全てに被さるように、島田紳助には「涙」があった。彼はとにかく涙もろい。ここを考えなければ彼の長寿は説明できない。島田紳助の失われた肉体性を呼び戻していたのはもしかしたら「涙」だったかもしれない。感動屋としての側面をキッチリと解析していきたい。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-