頻発する災害や、大規模開発による都市の画一化といった現実を前に、私たちは環境とどのような関係を築いていくべきなのか? 2月20日に閉幕した『第8回恵比寿映像祭』では、フランスの庭師・思想家、ジル・クレマンが提唱した人間中心の世界観からの脱却を軸とする庭作りのモデル「動いている庭」をテーマに掲げ、そんな人間と環境とのあり方への示唆に満ちた、多様なジャンルにまたがる作品が展示された。
今回、ゲストとして迎えたのは、アートからサブカルチャーまで、幅広い視覚文化に精通する気鋭の批評家であり、「日本最強の自宅警備員」としてニコニコ生放送でも人気の石岡良治。写真をもとに発展した映像技術が、インターネットテクノロジーと掛け合わさり、新しい空間体験を生み出しつつある昨今にあって、人と土地の関係性にあらためて着目したこの映像祭の試みを、彼はどう見たのか。映像祭の立ち上げから継続して企画に携わってきた岡村恵子を聞き手に、時代もジャンルも異なる出品作品の間に隠された「つながり」を、石岡は次々に浮き彫りにしていった。
「映像」って、じつは日本特有の言葉なんですよね。(石岡)
―先日行われた『第8回恵比寿映像祭』ですが、石岡さんは今回はじめてフェスティバル全体をご覧になられたそうですね。どんな印象を持たれましたか?
石岡:感じたのは、作品の幅広さが絶妙、ということです。いわゆるエンターテイメント作品は含まれていませんが、それ以外はほぼ揃っていますよね。アート寄りの実験映像もあれば、単館系映画ファンも楽しめる長編映画や、映像を介さないインスタレーションもありました。その多様さを可能にしたのは、「映画祭」ではなく「映像祭」とネーミングしたことにあると思うんです。「映像」って、じつは日本特有の言葉なんですよね。
岡村:そうなんです。「映像」という言葉には直訳の英語がなくていつも困るのですが(笑)、それゆえの自由度を『恵比寿映像祭』ではずっと大切にしてきました。
石岡:「映像祭」の英訳として「オルタナティヴ・ヴィジョンズ」という言葉を使っているのも、上手いなと思いました。日本では「映画」と「映像」を分けて、それぞれのファンが互いを牽制し合うという変な状況があるんですよ。たとえば、「シネフィル」と呼ばれるコアな映画ファンには、現代アートの映像作品を嫌う人がいまでも多い。そんななか「ヴィジョン」という、聴覚すら含んでいる言葉を選ぶことで、メディアやジャンルに限定されない広がりが生まれていると思います。
―幅広いジャンルの鑑賞者を包む枠組みとして、「映像祭」や「ヴィジョン」というワードが有効に機能していたわけですね。
石岡:そうです。それぞれのジャンルのファンコミュニティーには、特有の「名作」の基準が存在しますよね。その多様性は喜ばしいのですが、一方では限定されたコミュニティーの窮屈さも生じてしまいます。でも実際には、いろんな視点で作品を見る楽しみ方は一般的になっているし、作品自体がいくつものジャンルにまたがっている場合も多い。そうした映像文化の動的な状況が、この映像祭では捉えられていると思います。それと真面目な話、無料なのも重要でしょう。

中谷芙二子『霧の庭“ルイジアナのために”』2016年 インスタレーション 『第8回恵比寿映像祭』 写真提供:東京都写真美術館 写真:新井孝明
―無料であるということが、ですか?
石岡:少し前は映画や美術館に行くのも躊躇するぐらい金銭的に困窮していた時期がありまして(笑)、そうすると触れるのが必然的にテレビやネットで見られるエンタメ作品中心になるんですね。最先端のアートシーンを追っかけて、世界中のフェスティバルを回ることは、普通の人には到底できませんから。つまり言いたいのは、人が「オルタナティヴ・ヴィジョンズ」に出会うには、じつは金銭的時間的な問題が大きいということです。普段は美術館を訪れない人々が、ふらっと立ち寄れる場所に『恵比寿映像祭』があることが重要だと思う。
―人々の作品需要のあり方は、料金を含めたインフラによって規定されている、と。
岡村:入場無料について触れていただいたのは嬉しいです(笑)。当初は男性のお客様が多かったのですが、最近はカップルもたくさん観にきてくださるようになりました。この映像祭は、アートに新しい視点を与えることを目指すと同時に、一種の公共サービスとしての側面も持っています。なので、いつもは触れないジャンルや価値観を持つ作品に、偶然出会ってもらえるような枠組みを意識しているんです。
単なる「自然に優しいアート」だけを集めていないところに、視野の広さを感じました。(石岡)
―今年の『恵比寿映像祭』のテーマ「動いている庭」は、フランスの庭師であり思想家、ジル・クレマンの著作名から取られていました。近年、注目を浴びている彼の庭作りの特徴は、人が手を加えることを最小限に抑え、植物そのものの自然な動きを大切にしようというものです。このテーマを選ばれたのは、なぜだったんですか?
岡村:今回は、共同ディレクションでしたので、みんなでテーマを議論し構築していきました。その際、アートはアーティストの主観やオリジナリティーを中心に語られがちであるけれども、いまはその枠組みから逸脱した作品が面白いのではないか、という意識がスタッフにあったんです。つまり、作家性や人工性から一歩引いたような作品を集めてみよう、と。そこで参照したのが、人工と自然の葛藤を庭作りに生かしたクレマンの思想でした。

ジル・クレマン『アンドレ・シトロエン公園』1986-94年 Photo:Tomoki Yamauchi
石岡:なるほど。それで、集団制作を行うグループ作家や、昆虫や霧のように、人が完全にコントロールできないモノを扱う作品が多かったんですね。一方で、完全な「無秩序状態(自然)」を表現するような作品もなかった。人工と自然を混在させるという共通点が、多くの展示作品には見られました。
岡村:クレマンの庭作りも、まったく人が手を加えないわけではないんです。むしろ完全な野生の庭ではなく、植物の知識も哲学的な知見も持ったクレマンが微妙なさじ加減で手を加えていることが、とても重要だと思うんです。
石岡:ピョトル・ボサツキのコマ撮りアニメーション『自明の物事』では、まさにその秩序(人工)から無秩序(自然)までの過程が描かれていましたね。映されているのは身近な道具を使って組み立てられた合理的なシステムの姿で、それがあるルールのなかで無駄なく動いています。けれど、その合理的な世界が突き詰められていくと、どんどんおかしなことになってしまう。

ピョトル・ボサツキ『自明の物事』2013年 インスタレーション 『第8回恵比寿映像祭』 写真提供:東京都写真美術館 写真:新井孝明
岡村:どこか、箱庭的な世界のなかの秩序と無秩序を感じさせる作品です。
石岡:この作品が面白いのは、アニメーションに、作者の意図しないものが含まれることを見せている点だと思うんです。アニメという表現は、対象をコントロールできるものだとよく言われますが、作品内でも描かれていたように、たとえばコマとコマの間には、撮影した時間によって照明がブレていたり、わずかなズレが潜んでいるわけです。そういった各コマの間にある時間の変化を強調した点が面白いと思いました。
―他には、自然空間を大胆に使った作品を制作するランドアートの巨匠、ロバート・スミッソン(1938-1973年)も展示されています。彼もまた、廃墟のような人工物と自然の混在に着目した作家でした。

ジェーン・クロフォード&ロバート・フィオーリ『ランダウン』1994年 シングルチャンネル・ヴィデオ Courtesy Electronic Arts Intermix(EAI), NewYork
石岡:最近は日本でも、街おこしのためのアートプロジェクトが盛んになり、土地とアートの関係の大切さが叫ばれていますが、スミッソンの展示は、彼に代表される初期のランドアートと、現在のアートプロジェクトとの大きな違いを浮き彫りにしていたと思います。
―というと?
石岡:スミッソンなど初期のランドアートは、自然破壊的と批判を受けることも多かったんです。彼の代表作、ユタ州の湖に作られた『スパイラル・ジェティ』(1970年)の映像を見ると、湖をブルドーザーでガンガン埋め立てている。そこには彼なりの自然観があったのですが、一方でいまのカルチャーは、土地固有の景観や文化を大事する傾向が強いですよね。たとえば、アニメの舞台を観光名所として巡る「聖地巡礼」ブームも一例でしょう。ただ一方、スミッソンの作品でも、彼の死後数十年を隔てた『マンハッタン島を周遊する島』(2005年)では、自然破壊的な側面はだいぶ和らぎ、マンハッタン島におけるセントラル・パークの持つ豊かな自然の意味が感じられます。今回スミッソンの作品は違う時代のものが二つ展示されていますが、そこにはこの半世紀ほどのアートやサブカルチャーと土地との関わりの変化が浮き彫りになっていた。

ロバート・スミッソン『マンハッタン島を周遊する島』 2005年 シングルチャンネル・ヴィデオ Estate of Robert Smithson, Courtesy James Cohan Gallery, New York / Shanghai and Electronic Arts Intermix(EAI), NewYork
岡村:おっしゃるとおり、スミッソンの作品を映像祭のなかでどう位置づけるのかには議論があったんです。初期の作品のように「自然との共生」というテーマと直接結びつかない部分もあるので、メインフロアから少し離れた場所に展示しました。彼はむしろ、自然と向き合ったアーティストの先達という位置付けなんです。
石岡:やはりそうですか。「動いている庭」を提唱したクレマンも、自然を過度に崇拝するような、狭義のエコロジーには批判的な人物でもある。単なる「自然に優しいアート」だけを集めていないところに、視野の広さを感じました。
土地の固有性をあまりに尊重しすぎると、「外来種はすべて排除しろ」といった、排他的思想にもつながりかねない。(石岡)
―自然の空間を扱いつつ人工性の強い初期のランドアートと、土地の固有性に寄り添う現代のアート。自然と向き合ったアーティストの先達である巨匠スミッソンの二作品にその幅を見るというのは、面白い視点ですね。
石岡:非常にリアルな植物のレプリカを展示した、クリス・チョン・チャン・フイの『固有種』も示唆的だと思いました。その土地にもともとある営みを大切にする視点は、近年、アートに限らず観光やもの作りの分野でもたいへん尊重されています。ただ、土地の固有性を安直に批判することはできませんが、その価値があまりに暴走すると、「外来種はすべて排除しろ」といった、いま難民や移民に対して向けられがちな排他的思想にもつながりかねない。この作品は、レプリカを使うことで、そうした「固有種」の字義通りの意味を巧みにズラし、拡張していました。

クリス・チョン・チャン・フイ『固有種』シリーズ 2015年 インスタレーション 『第8回恵比寿映像祭』 写真提供:東京都写真美術館 写真:大島健一郎
岡村:一方で、複製の固有種を通して「オリジナルな生き方とはなにか?」という想像を広げてくれる作品でもありますね。
石岡:グローバリゼーションによって、人だけでなく植物も世界的に動いている。そんな地球規模での変化のなか、ある土地の固有種が他の場所で生きていくこともできるというメッセージを、ぼくは受け取りました。それと、JODIというハッキング系アーティストの『GEOGOO』という作品も、現代の映像環境や自然との関係を考えるうえで面白かった。

JODI『GEOGOO』 2009年-2012年 インスタレーション 『第8回恵比寿映像祭』 写真提供:東京都写真美術館 写真:大島健一郎

ジャナーン・アル=アーニ『グラウンドワークスIII』2013年
―『GEOGOO』は「Google Maps」や「Google Earth」など、現実空間をシミュレーションするサービスの画面の動きやアイコンを使って、自然に対する人々の感受性の変化を問うような作品ですね。
石岡:初期のランドアートは、誰もたどり着けない未踏の地で制作することも重要なテーマだったんですが、いまやスミッソンの『スパイラル・ジェティ』は、ユタ州の観光名所になっています。「Google Maps」でこの作品名を検索すると、「休日に家族で訪れてとても楽しめました」みたいなコメントが出てくる(笑)。美術館やギャラリーから抜け出そうとして荒野を目指したのに、そのカッコいい造形性が、写真や映像を介して人気になってしまった。
岡村:隔世の感がありますよね。手元のスマホで僻地のランドアートがいつでも見られるとは。
石岡:JODIの作品は、そんな現代人の土地に対する感覚を、新しい映像環境への介入を通して見せてくれるものだと思います。考えてみると、スミッソンやアンディー・ウォーホルらが活躍し、現代アートが大きな変化を遂げた1960年代という時代も、テレビなどの新しいメディアが世界を覆った時代でした。この時代のアートには、それまでの絵画や彫刻のような伝統的なメディアを超えて、たとえば音楽とアートの融合、ビデオとアートの融合といったアプローチも数多く生み出された。つまり、一種の「オルタナティヴ・ヴィジョンズ」が展開した時期だった。
―デジタルテクノロジーが普及した現在にも、似たような状況があるのではないか、と?石岡:そうですね。「Google Maps」は、手軽に観光気分を楽しめる一方、個人が追い切れない世界の諸相をGoogleがすべて統制しているような恐怖も感じさせる。その状況に対して、アーティストが読み替えやハッキングを行い、異なる視点を見せようとするのは自然な流れでしょう。同じ意味では、ビデオカメラを持ってホームレスに突撃インタビューしたアーティスト集団・ビデオアース東京の『橋の下から』(1974年)も、倫理的な批判を招きかねない作品ですが、つながるところがあるように思います。
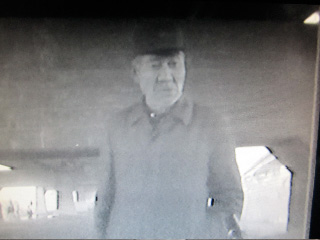
ビデオアース東京『橋の下から』
岡村:この作品を展示したのは、欧米のランドアートだけでなく、日本における土地とアートの関係も紹介したかったからです。「ビデオアース東京」のメンバーたちは、橋の下で生活する男性に話を聞きに行き、最初は怒られながらも徐々に打ち解けていきます。そこには、高度経済成長の都市に生まれた一種の「荒地」で暮らす男性に、カメラをコミュニケーションツールとして歩み寄ろうとする彼らの姿が描かれている。現在では、街からこうした「荒地」を一掃しようとするジェントリフィケーション(再開発による都市の高級化)の議論も盛んですが、『橋の下から』はそんな現代の荒地との共生の試みとも捉えられる。スミッソンのように、忘れてはならない先人の取り組みとして展示しました。
石岡:アーティストが「アート」の名のもと、どこまで一般の人々に介入していいのかには議論の余地がありますが、行政や大企業、マスメディアなどによって整えられた環境のなかで「オルタナティヴ・ヴィジョンズ」を提示する際には、なんらかの衝突が避けられない場合もあると思います。「ビデオアース東京」やJODIのような視点は、映像によって地球全体が包まれた現代にこそ求められるものだと思います。
ミニシアターの相次ぐ閉館に代表されるように、若い人が「オルタナティヴ・ヴィジョンズ」に出会う機会が減っている。(石岡)
―『恵比寿映像祭』に展示された作品の間に、いくつもの共通点が見えてきました。ただ、インターネットであらゆる動画を見られる時代に、あえて難解なビデオアートを見たり、美術館でさまざまな映像表現に触れたりする意義とは、どこにあると考えますか?
石岡:ぼくは、他ジャンルからの侵入を許さないマッチョな文化意識が苦手なんです。たとえば、厳しい技術的達成を重んじることが多い写真や映画業界の一部には、アート系の映像作品に対して「基本がなっていない」と批判する人たちが少なからずいました。美しい構図に満ちたジョウ・タオの『青と赤』などは、こうした技術重視の人にも受けいれられる精度を持った作品でしたね。

ジョウ・タオ『青と赤』2014年 インスタレーション 『第8回恵比寿映像祭』 写真提供:東京都写真美術館 写真:大島健一郎
―じっと見ていたくなるような、美しさのある映像作品です。
石岡:でも、よく見ると意識的に、映像の文法からは外れる、荒っぽい構図も織り交ぜられている。このように「入口がたくさんあること」が重要だと思うんです。そもそも1960年代の初期ビデオアートも、「美しい映像を撮ろう」なんて動機からは出てきていません。代表的なビデオアーティスト、ブルース・ナウマンは貧乏で彫刻の素材が買えなかったから、カメラの前でおかしな姿勢をして、それを作品にした。そのビデオアート作品は彼にとって彫刻の延長にあるもので、だからこそ面白い表現になったと思うんです。
―純粋性の追求によっては出てこない視点が含まれている、と。
石岡:映画の例で言っても、シュルレアリスム映画の名作『アンダルシアの犬』(1929年、サルバドール・ダリが脚本を担当した)に、眼球と月を結びつける有名なシーンがありますが、これは映画監督のルイス・ブニュエルと画家のサルバドール・ダリの共作だからこそ生まれたものでしょう。つまりあのシーンには、形態の類似からイメージを飛躍させるダリの絵画的センスが関わっていると思うんです。エンタメ好きとアート好きが互いに避け合う光景もよく目にしますが、作家自身は雑多な文化から刺激を受けているし、見る人もその越境性を意識する場があることが大事だと思います。
―なるほど。今年の『恵比寿映像祭』はこれまでにも増して、多様な作品が展示されていたと思うのですが、今後もこの多様性は引き継がれていくのでしょうか?
岡村:今回は、本来のメイン会場である東京都写真美術館が改修中だったため、恵比寿ガーデンプレイス全体を使った、いい意味で美術館展示の呪縛から解放された試みを行えました。来年からは美術館に戻りますが、映像祭のアイデンティティーとしては変わりません。恵比寿周辺のさまざまな文化施設やギャラリーと関連プログラムを行ったり、地域的な広がりも模索し続けます。石岡さんのように、こちらが意図しない多面的な見方をしてくれるお客さんをどんどん増やしたいですね。
石岡:今回、会場を回ってみて、高校生時代にこの映像祭があったら頻繁に通っただろうな、と感じたんです。なにしろ、しつこいようですが、無料ですしね(笑)。最近は、ミニシアターの相次ぐ閉館に代表されるように、若い人が「オルタナティヴ・ヴィジョンズ」に出会う機会が減っている面がある。そんななか、『恵比寿映像祭』の試みは、新しい世界に触れる場所として意義あるものだと思います。
- イベント情報
-
- 『第8回恵比寿映像祭 動いている庭』
-
2016年2月11日(木・祝)~2月20日(土)
会場:東京都 恵比寿 ザ・ガーデンホール、ザ・ガーデンルーム、恵比寿ガーデンシネマ、日仏会館、STUDIO38、恵比寿ガーデンプレイス センター広場ほか
時間:10:00~20:00(最終日は18:00まで)
出品作家:
ジャナーン・アル=アーニ
ビサネ・アル・シャリフ&モハマド・オムラン
ピョトル・ボサツキ
クリス・チョン・チャン・フイ
銅金裕司
葉山嶺
平井優子+山内朋樹+古舘健
クワクボリョウタ
ロバート・ノース&アントワネット・デ・ヨング
中谷芙二子
オリヴァー・レスラー
ベン・ラッセル
ビデオアース東京
ジョウ・タオ
ほか
- プロフィール
-
- 石岡良治 (いしおか よしはる)
-
1972年東京生まれ。批評家・表象文化論・ポピュラー文化研究。東京大学大学院総合文化研究科(表象文化論)博士後期課程単位取得満期退学。青山学院大学ほかで非常勤講師。著作として『視覚文化「超」講義』(フィルムアート社)、『「超」批評 視覚文化×マンガ』(青土社)がある。
- 岡村恵子 (おかむら けいこ)
-
東京都写真美術館学芸員。東京都現代美術館学芸員を経て2007年より現職。『MOTアニュアル2000 低温火傷』(2000)、『イマジネーション 視覚と知覚を超える旅』(2008–09)、『躍動するイメージ。石田尚志とアブストラクト・アニメーションの源流』(2009–10)、『フィオナ・タン まなざしの詩学』(2014)ほかを企画。プレ・イヴェントとして手掛けた『映像をめぐる7夜』(2008)をふまえ、2009年に『恵比寿映像祭』を立ち上げ、第1から5回までのディレクターを務める。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-







