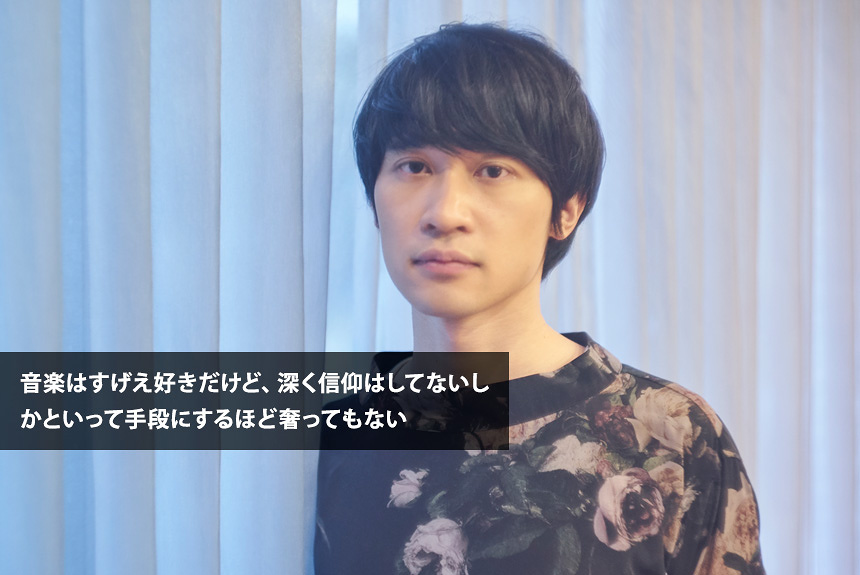Base Ball Bearというバンドは「ギターロック」というフォーマットに誰よりも愛憎を持ち、自らの音楽性を多角的に検証すると同時に、作品ごとにニューウェイブやブラックミュージックなどさまざまな意匠を取り入れながら、その核心を研ぎ澄ませてきた。結成15周年、メジャーデビュー10周年のメモリアルイヤーとなった2016年、彼らはギターの湯浅将平の脱退というバンド史上最大の危機に直面する。しかし、小出祐介、堀之内大介、関根史織は3ピースバンドとして活動を止めないことを決意し、多彩な顔ぶれのサポートギタリストを迎えてイベント出演やツアーを敢行。さらに彼らはライブ活動と平行して間断なく制作を続けた。
ニューアルバム『光源』は、その結晶といえる全8曲からなる。テーマは「2周目の青春」。サウンド面では、シンセやエレピ、ブラスなどを導入し新たなサウンドプロダクションを提示しているが、それでもなお際立っているのは、三人のしなやかで過不足ないアンサンブルであり鉄壁のグルーヴである。そのうえ、どの曲もグッドメロディーをまとっており、歌としての求心力も申し分ない。近年のインディーシーンと共振するようなアーバンポップな曲や滋味あふれるAORのような曲もあるし、これぞ王道をいくBase Ball Bearのギターロックだと思わせてくれる曲もある。
Base Ball Bearというバンドの理念と、湯浅脱退後から本作が完成するまでの道のりを、小出が余すところなく語ってくれた。
音楽はすげえ好きなんだけど、深く信仰はしてないし、超最高だと思っているけど、心酔はしてない。かといって手段にするほど奢ってもなくて。
―Base Ball Bearはギターロックというフォーマットに対して、誰よりも愛憎を持ち、主観と客観を戦わせながらその音楽性や立ち位置を相対化して、バンドのアイデンティティーを明確にしてきたと思うんですね。そのうえで作品でもライブでも同期は使わずに、四人の生音だけで構築するという絶対的なルールも生まれて。でも昨年、湯浅くんが脱退して、ニューアルバム『光源』でその禁じ手を解いた。だからこそ、あらためてこれまでのBase Ball Bearというバンドについて小出くんに語ってもらいたくて。
小出:感覚的にはずっと違うことをやってきたバンドなんですよ。『夕方ジェネレーション』(2003年)から『C2』(2015年)まで、作品ごとにテーマも目指していることも違って。サウンドも歌っている内容も違う。
メジャーデビューミニアルバム『GIRL FRIEND』(2006年)収録曲小出:別のインタビューでも話したんですけど、ミュージシャンのなかにはまず「音楽の神様」を信じている人たちがいるじゃないですか? 一方で音楽が手段というか、よく言えばコミュニケーションツールで、悪い言い方をすれば単なる商売として音楽を使っている人たちもいる。それもエンターテイメントの一側面だし決して間違ってはいないんですけど、僕らは音楽を「神様」と捉えている側と、「ツール」と捉えている側の両方と距離を取ってきたバンドだと思うんですよね。
―そのスタンス、詳しく教えてもらっていいですか?
小出:音楽はすげえ好きなんだけど、深く信仰はしてないし、超最高だと思っているけど、心酔はしてない。かといって手段にするほど奢ってもなくて。だけど、どちらの面白さも理解しながら、どちらとも適度な距離を取っているから、客観的に見ても他のバンドと比較しにくいところがあると思っているんですよね。
―なるほど。国内でシンパシーを覚えるバンドはほとんどいないですか?
小出:日本のバンドではあまり思いつかないんですよね。チャットモンチーとはかなり近いけど、絶妙に違う気がするし。バンドではないけど、松任谷由実さんは究極ですよね。
―同じくバンドではないけど、RHYMESTERは?
『THE CUT』(2013年)収録曲。RHYMESTERをフィーチャーしている小出:マインドはもちろん近いと思います。ただ、ヒップホップはジャンル自体の属性が強いからハッキリと言いきれないかも。
―ビートが打ち込みであれ、生であれ絶対にラップはするわけですからね。
小出:そう。僕らは、「ギターロックバンド」だとずっと言っているけど、「これってギターロックの範疇なのかな?」という怪しいところまでいってるから(笑)。
『CYPRESS GIRLS』(2010年)収録曲『新呼吸』(2011年)収録曲
近年の同期を使うバンドって、ほとんど同じ雰囲気に感じるんですよ。
―『光源』もまさにそういうアルバムですよね。
小出:うん。言ってしまえば、ずっとそうなんですけどね。「え、これはその範疇なの?」っていう。そのうえで「ギターロックバンドです」って言い続けてきたので。海外でいうと、自分が一番影響を受けたのはXTCですし。
―本質的なオルタナティブを地でいく感じね(笑)。
小出:彼らも毎作やってることが違うんだけど、どれもXTCだと言えるんです。途中でアンディ(・パートリッジ)がライブ恐怖症になってライブをするのをやめちゃうんだけど、ライブをやめてからの作品もすごい。それってバンドとしては、やっぱり変なんですよ。すごく変なんだけど、アンディはそのとき興味のあることだけをずっと表現しているっていう。そうしたら必然的に音楽性も推移していくわけで。
―そのときどきの興味が第一っていう志向の裏には、XTCの存在がある。一方で、小出くんは「バンド」というフォーマットにこだわっているし、ライブでは今後も同期を導入するつもりはないんですよね?
小出:そうですね。
2012年に開催された武道館公演より―譲れない美学の領域がある。
小出:そこは最初に憧れた日本のバンドが、NUMBER GIRLだったというのも大きいと思う。肉体的でカッコいい音を出すバンドが好きなんです。そういう意味で、日本のバンドで一番カッコいいと思ったのはNUMBER GIRLだったし、少なくとも僕が聴いてきた音楽は肉体的なものが多かった。
あと、僕のルーツはハードロックで、「ギターのテクニックだけで押しきるってカッコいい!」という感覚が原点にあるんじゃないかな(笑)。でも、演奏の凄味で魅せきるっていうのは本来的だとも思うんですよね。だから、自分が音楽をやるときも、バンドサウンド以外の音が鳴っているのは想像してなかった。―ただ、Base Ball Bearがメジャーデビューした2006年前後って日本でも同期を使って、いわゆるダンスロックを鳴らすバンドがどんどん増えてきたじゃないですか。以降、フロアライクなサウンドにかぎらずロックバンドでもエレクトロニックな音を導入するのが当たり前になっていて。でも、Base Ball Bearは頑なにそこにはアクセスしなかったですよね。
小出:単純に、自分はそこにマジックを感じなかったからでしょうね。特に近年の同期を使うバンドって、ほとんど同じ雰囲気に感じるんですよ。音楽の作りが同じというか、手法が同じというか。
何万人が一斉に「オイオイ!」って叫んでる画は積極的に欲してないけど、それが起きるなら起きたでいいし、じっくり聴いてもらうでもいいし。もうどちらでもいい。いいから楽しもうぜと。
―エレクトロニックな音を導入したバンドらが、画一的なサウンドに陥っていることに違和感がある。
小出:っていうか、「エレクトロニックな音を導入したい!」という意志よりも、そういう音をいい感じにまとめやすくなったというシステムや状況のほうが、まだまだ先行していると感じるんですよね。システムの発達によって新しい音楽トレンドが生まれること自体は全然否定しないんですけど、近年の音楽制作ソフトからはみ出た何かを生んでいるバンドって、まだそれほどいないんじゃないかと思っていて。少なくとも国内に関しては。
『光源』では、僕らも「Logic」(音楽制作用のソフトウェア)を制作に導入したし、バンド以外の音の要素もいろいろと入れましたけど、あくまでも空気づくりの範疇ですね。バンドの演奏を上回ることをやってしまうと全然面白くないんですよ。アレンジに関しても、基本的に同期なしでも成立する作りになってます。
―そこは変わらないと。でも裏を返せば、表現手段における人間力を信じているということですよね。
小出:うん、フィジカルの不思議というかね。オールマイティーでなくても、ひとつだけでいいから突出した能力なりセンスがある人って強いと思うんです。めっちゃ速弾きができるでもいいし、プレイ自体がめっちゃグルーヴィでもいい。何かいいところがあればいいんです。そういう個性が集まって、バンドという集団になっていることが魅力的なんでしょうね。だから、そうなったところにわざわざ能面みたいなのっぺりしたシンセを敷く必要はないんじゃないかと(笑)。
―『二十九歳』(2014年)や『C2』のころはフェス文化が盛り上がると同時に、4つ打ちの曲だったり、刹那的に盛り上がるための即効性ばかり求められ、日本のバンドシーンがどんどん画一化しているんじゃないか? という話を小出くんとよくしたんですけど。
小出:してましたね。
―『二十九歳』や『C2』のサウンドは、ロックバンドが提示するグルーヴの気持ちよさは刹那的な快楽だけじゃない、というカウンターでもあったわけじゃないですか。それで、ブラックミュージック由来のアプローチも積極的に取り入れて。
『二十九歳』収録曲『C2』収録曲
小出:そうですね。
―でも『光源』はもはや、そういう外側の話はどうでもいいという境地にいますよね。SuchmosやD.A.N.といったような、シーンの画一化に追従しないバンドたちが出てきたこともあると思うけど、今作ではただ自分たちだけを見つめている。
小出:やりたいことに素直に、本当になんでもいいなと。
―『光源』の全8曲はリズムパターンもアレンジの意匠もこれまで以上に多彩で、シンセやブラスやエレピも入っているんだけど、音数は必要最低限で。それは3ピースバンドとしてのサウンドの構築が念頭にあり、そのうえでグルーヴが盤石だからこそだと思う。そして、最終的には、まさにどの曲もBase Ball Bearのギターロックでしかないというか。
小出:うん。曲の機能として、フェスの現場で演奏しても盛り上がりそうな曲はあるし、そこはもう問題ないだろうっていうね。最初からこちらとしては、数万人が一斉に「オイオイ!」って叫んでる画を積極的に欲してるわけじゃないけど、それが起きるなら起きたっていいし、じっくり聴いてもらうでもいいし。もうどちらでもいい。お客さんも演者もいいから楽しもうぜと。そういう境地です。
2010年に開催された武道館公演より湯浅と連絡が取れなくなった時点で、もし戻ってきても俺は受け入れられないかなと思っていた。
―今のBase Ball Bearは、さまざまな音楽が鳴っている場所にアクセスできると思うんですよね。たとえば、『人間交差点 2017』(RHYMESTER主催のフェス)に、KIRINJIやKREVAと並んでBase Ball Bearがラインナップされているのはすごくいいなって。
小出:自分のなりたかった立ち位置をだいぶ確立できてきたという実感はありますね。どっちでもないし、どっちでもあるみたいな。
―いわゆるバンドシーンにおけるメインストリームとオルタナティブ、どちらとも距離を取っているけど、どちらにも片足を突っ込んでいるということですよね。
小出:そう。だから『人間交差点』でも、お客さんを楽しませる演奏ができると思うし、これまでどおり大型のロックフェスに出ても対応できると思う。
『C2』収録曲―そこは『C2』で、ギターロックにおけるひとつの高みに到達したところも大きいんだと思う。それに、湯浅くんの脱退という危機を乗り越えて、またさらにBase Ball Bearはタフなバンドになったよね。
小出:湯浅が抜けたとき、メンバーは誰も感情的になってなかったのは大きいと思うんですよね。堀之内(大介 / Dr)ですら表向きには感情的になってなかったからね。あんなに感情的で、『キン肉マン』的な世界観で生きてる人が(笑)。
―(笑)。
小出:まあ、感情的になる時間さえなかったというのもあるんですけどね。目の前にある、実務的にクリアしなければいけない問題があまりに多くて。まず、三人でバンドを続行しようと思った。じゃあ、そのために何をやらなければいけないのかを整理して、すぐにそれに取りかかろうって頭を切り替えたのも大きい。傍から見たらちょっと淡白に映るくらいだったと思いますよ。
―わりと近い場所で当時の状況を見ていた身としては、淡白とは思わないまでも全然取り乱してるようには感じなかった。
小出:そうだよね。全然取り乱さなかった。あとになって、ああいう状況になったら取り乱す人もいるだろうなとは思った。
―取り乱さず、バンドの状況をそのままドキュメントとして見せるようにイベントのライブ出演やツアーを回ったじゃないですか。
小出:そうですね。メンバー全員がまず冷静だったから、立て直しも早かったしね。バンドは歪なカタチになったかもしれないけど、フルカワユタカさん(ex.DOPING PANDA)を迎えてツアーを敢行したり、歪さごとショーにしようと思って。
それで4月の『日比谷ノンフィクションV』では、フルカワさん、田渕ひさ子さん(bloodthirsty butchers、toddle、LAMA / ex.NUMBER GIRL)、石毛輝くん(lovefilm、the telephones)、ハヤシさん(POLYSICS)をサポートギターに迎えて開催したり。
―湯浅くんと連絡が取れなくなった直後、ツアー前にまずはチャットモンチーが地元の徳島で開催した『こなそんフェス』(「チャットモンチーの徳島こなそんそんフェス2016~みな、おいでなしてよ!~」)の出演を控えていて。それが去年の2月27日。あそこで石毛くんをサポートに迎えるという、人選も含めて「そうくるか!」というウルトラCを敢行したのもすごいなと思った。
小出:そうだね(笑)。『こなそんフェス』の本番って、湯浅がいなくなってから10日後とかだから。そんな状況で石毛くんにオファーを快諾してもらって、時間のないなかで曲を覚えてもらい、2日間集中してリハーサルするっていう。
―いくら冷静でも、なかなかできることではないと思う。
小出:湯浅と連絡が取れなくなった直後は、さすがにみんな不安がっていたんですよ。脱退の意思表示があるまでは。でも僕は最初の時点で内心、もし湯浅が戻ってきても受け入れられないかなと思っていて。
この状況も含めてエンターテイメントにするしかないなと。
―湯浅くんが戻ってきたとしても受け入れられないと思った、というのはどういうことなんですか?
小出:四人の積み重ねや、四人にしかわからないバイブスなど説明しにくいことも多いので、そのときの自分の気持ちだけを抜き出して簡潔に言いますけど、僕としては「このずっと張ってきた糸を切るんだ」と思ったんですね。安否に関しては心配でしたけど、自分の意志で連絡を断ったとしたら、戻ってきたとしても一緒にやっていくのは正直難しいだろうなと感じたんです。反射的にそう思ったからこそ、そのあと脱退が決まってからも切り替えが早かったし、この状況も含めてエンターテイメントにしていくしかないなと。それで石毛くんにサポートをお願いすることになったんです。
―正直、これまでBase Ball Bearにはバンド同士の横のつながりが広い印象はなかったけど、あの窮地をさまざまなミュージシャンのサポートを得て乗り越えたのはすごく印象的だった。
小出:意識してなかった積み重ねがあったんだと思います。あとは音楽的につながっていたというよりも、プライベートでつながっていた人が多くて。ハヤシくんとはずっとメールで特撮ヒーローの話をするような関係性だったし、でんぱ組.incとの2マンライブでサポートしてもらった赤い公園の(津野)米咲ちゃんと石毛くんは、GARAGE(Base Ball Bearのホームグラウンドである下北沢のライブハウス)で会う人って感じだから。だから、GARAGEという場所も大きいね。
―気を遣わないコミュニティーが、音楽的なユニオンのように機能するのはいいことだなと僕も思います。
小出:そうだね。フェスのバックヤードとかだと、「CD聴いてください」って音源を渡して挨拶するくらいしかできないけど、GARAGEで会えればそれまで接点のなかった人たちともスッと会話できるし。最近はSANABAGUN.のメンバーとGARAGEで会ったりするんですけど、それだっていつか現場で活きてくると思うし。
―そうだね。それに田渕さんをサポートに迎えて、一緒にNUMBER GIRLの“透明少女”を演奏したという事実は、小出くんのルーツを思えば夢のよう話じゃないですか。それこそ『光源』のテーマのひとつである、パラレルワールド感があるというか。それも湯浅くんの脱退がなかったら起きなかったことなので、なんとも言えない話ではあるんだけど。
『増補改訂完全版「バンドBのベスト」』(2016年)収録曲。田渕ひさ子を迎えて再録されたもの小出:いろんな意味で異常事態ですよ、まったく想像もしてなかったから。サポートギターを入れるということ自体も想像してなかったですし。
―田渕さんと“透明少女”を演奏するってどういう感覚だったの?
小出:「勝ったな!」って感じですよね(笑)。
―何に?(笑)
小出:「これは間違いない!」って感じというか。それを小さなライブハウスのサプライズではなく、フェスで大勢のお客さんの前にぶち込むっていう。田渕さんが“透明少女”を演奏している画はNUMBER GIRLのファンも見たかったものだと思うし、それを僕らのようにNUMBER GIRLの文脈をちゃんと汲んでリスペクトしているバンドがやったということも重要だと思うんですよね。何より、Base Ball Bearのライブステージとして、面白い画になっていたし。
僕にとって「青春」は永遠に解決されない問題だから、無限増殖するんですよ。
―『光源』は「2周目の青春」を主題に掲げているけど、田渕さんとの共演も伏線のひとつになっているとさえ思える着地の仕方をしていて。

Base Ball Bear『光源』ジャケット(Amazonで見る)
小出:そうだよね。去年1年間の活動を通して、なんとなく今一度青春を歌おう、フレッシュなことをやろうと思っていて。
―会話のなかで「フレッシュ」というワードもよく出てましたよね。
小出:「フレッシュ」っていうと、キラキラした音のイメージに変換されがちかもしれないけど、厳密に言うと、うちらの身内的かつ感覚的な言葉なんですよ。
これはあまり言ってないんですけど、僕らはとにかくゲラゲラ笑いながら「それウケるわ~」っていうことをやりたいだけで。「何この音色!?(笑)」とか「このフレーズ、おじさんみたいじゃないですか~(笑)」とかメンバーと言い合いながら曲を作りたくて。
―その行為自体にも「2周目の青春」感があるというか。
小出:うん。「2周目の青春」という言葉で、いろいろ回収することができましたね。僕らが直面したさまざまな現実的問題や楽曲の世界観も、全部かすめ取って次の場所へ投げたという感じです。
―先日、小出くんと話したときに『光源』の本質を指して「青春という未解決事件」と言っていたじゃないですか。それがすごく印象的で。
小出:僕にとって「青春」は永遠に解決されない問題だから、無限増殖するんですよ。それはもう遠ざかった時間の出来事なので。
音楽がなかったら、「青春という未解決事件」の闇に埋もれて自分は消えていったかもしれない。
―「青春」が無限増殖する、というのはどういうことなんですか?
小出:たとえば今、当時死んでほしいとさえ思っていた中学時代の同級生と再会し、仲直りして、一緒に酒を飲んだとして、「それで解決するか?」っていうと絶対しないんですよ。
むしろ、「あのとき他にも何か可能性があったんじゃないか?」という気持ちや思考が無限に増殖する。だから僕の「解決しない青春」は、感情と思考を生み出し続ける永久機関なんですよ。自分が年齢を重ねるとともに、歌う内容は変化していくかもしれないけど、振り返れば永久機関がある。
―小出くんの場合、「振り返れば奴がいる」っていう感じで、表現者として、呪いのように「青春」がずっとつきまとっているというか(笑)。
小出:そうそう(笑)。バンドを結成したばかりの15年前には、15年後にこういうふうに思っていることが想像できなかったみたいに、15年後もどう思っているかわからない。でも、この「源」ともいえる、僕のミュージシャンとしての本質に関しては普遍だと思うんですよね。
―永久機関といえば、今回のテーマに紐づくパラレルワールドの「あったかもしれない人生」というのも無限に広がるじゃないですか。これも前に小出くんと話したときに、「どれだけパラレルワールド的視点を持っても、音楽をやっていない自分は想像できない」と言っていたのがすごく印象的で。
小出:音楽をやってなかったら、そもそも「未解決事件」のエリアを突破できなかったと思うんです。音楽のおかげで、窓ガラスをバリーン! と突き破って外に出ていくように強行突破できた。そうじゃなかったら、「青春という未解決事件」の闇に埋もれて自分は消えていったかもしれない。
僕は「未解決事件」を音楽に置き換えることができたんだけど、渦巻く負の呪いエネルギーをコントロールできないまま、暴走して終わっちゃった可能性もあって。だから、音楽に置き換えることで呪いエネルギーを吐き出すことができたというのは本当に大きかった。
―今言ってくれたことは、さっきの、音楽が「神様」でも「ツール」でもないっていう話にもつながる部分のような気がします。
小出:うん。だから、パラレルワールド的な視点を持って何度自分の人生を巻き戻しても、音楽を表現し始めた前の自分には戻らないんですよ。
このアルバムを作ってるときに「時間は神様だな」って思ったんです。
―“逆バタフライ・エフェクト”の歌詞が本当に素晴らしくて。<自分こそだよ 運命の正体は><決められたパラレルワールドへ><自分こそだよ 運命を愛しな>ってパンチラインだらけだなと。
小出:書き方はちょっと理屈っぽいけど、こういう書き方をしないと自分が捉えている感覚を説明できないなと思って。<決められたパラレルワールドへ>とかね。
―決定的なフレーズですよね。
小出:今話したように、ただのパラレルワールドに向かっていくという感覚じゃなかったから。
―だからこその、<自分こそだよ 運命の正体は>だしね。
小出:そうそう。<自分こそだよ 運命の正体は>と言っておきながら、実際は感知していない数々の選択肢を選択済みで。自分の意志で選択肢を掴むときもあるけど、人の運命なんて総じて自分ではコントロールできないものだと思うんです。だから<決められたパラレルワールドへ>でもある。
いくらでもポジティブ前向きソングにできるお題ではあるけど、そうじゃなくて、僕が捉えている時間感覚とか運命論を表現しようとすると、こういう歌詞にならざるを得ない。
―でも、想像力が豊かな人ほどこの歌詞に救われるだろうなって。
小出:僕もそう思います。僕もこの歌詞の感覚で今を捉えているからラクですよ。
―だからこのアルバムは、もしかしたらどこかのパラレルワールドで、湯浅くんが脱退していない四人のBase Ball Bearが存在しているかもしれないということさえ想像させるじゃないですか。でも、今の三人のBase Ball Bearが<決められたパラレルワールド>であると力強く提示している。
小出:うん、それも否定しないのがこのアルバム。でも、“逆バタフライ・エフェクト”とか、“すべては君のせいで”とか“SHINE”がラジオでオンエアされ始めて、いろんなリアクションを見たんだけど、やっぱり“すべては君のせいで”というタイトルにインパクトがあったみたいで(笑)。
―ああ、湯浅くんを思わせるという意味で?
小出:そうそう。でもそれはハッキリ言うと、全然意図してなくて。制作中にエンジニアの人に指摘されて「ああ!」って思ったくらい。それもアルバムを聴いてもらえばわかると思います。
―小出くんは「時間が解決する」って常套句を信じてないですよね?
小出:だって解決してないでしょ、って思う(笑)。その言葉って「現実の肯定化」なんですよね。解決したと思っても、最悪のどんでん返しはいつだってあり得るから。時間はそんなに生易しいものじゃないですよ。だって、15年経っても青春が未解決事件のまま、そこだけ穴が空いたまま、刻一刻と時間が流れてるわけですよ。
時間は次の状態に向けて容赦なく続いていく。だから、このアルバムを作ってるときに「ああ、そういうことか。時間は神様だな」って思ったんです。
―時間は無慈悲で、人間の力では抗いようがないものだと。
小出:でも、それはあえて歌詞にしなかった。それを歌にしたら信仰になるから。
―そこにも主観と客観、両方の目線を光らせるのは小出くんらしいですね。では最後に、『光源』というタイトルについて小出くんのなかに浮かんでいるイメージを教えてもらえたら。
小出:青春を対象化できたのが大きいんですよね。対象化された青春を表現するためには『光源』というタイトルじゃないとダメで。『光』だったらそのものになっちゃうから。つまり、時間が過ぎて、そこ(青春)に音楽を表現するうえでの光の源が存在してるというイメージで。
―つまり、「青春」そのものではなく、「未解決事件」のことを表現したかったと。
小出:自分自身と光を発信しているポイントの間にある距離を――人生における光を発しているポイントは聴き手一人ひとり違うんだけど、その「時間」と「距離」をタイトルにしたかったんです。僕にとって『光源』は、「青春」という呪いが転じて光になったという感じですね。
- リリース情報
-

- Base Ball Bear
『光源』初回限定盤(CD+DVD) -
2017年4月12日(水)発売
価格:3,780円(税込)
UPCH-29252[CD]
1. すべては君のせいで
2. 逆バタフライ・エフェクト
3. Low way
4. (LIKE A)TRANSFER GIRL
5. 寛解
6. SHINE
7. リアリティーズ
8. Darling
[DVD]
『COUNTDOWN JAPAN 16/17』 at GALAXY STAGE 2016.12.31&Tour「バンドBのすべて 2016-2017」ドキュメント
- Base Ball Bear
『光源』通常盤(CD) -
2017年4月12日(水)発売
価格:3,000円(税込)
UPCH-204481. すべては君のせいで
2. 逆バタフライ・エフェクト
3. Low way
4. (LIKE A)TRANSFER GIRL
5. 寛解
6. SHINE
7. リアリティーズ
8. Darling
- Base Ball Bear
- プロフィール
-

- Base Ball Bear (べーす ぼーる べあー)
-
2001年、同じ高校に通っていたメンバーが、学園祭に出演するためにバンドを結成したことがきっかけとなり、高校在学中から都内のライブハウスに出演。その高い音楽性と演奏力が大きな話題を呼び、東芝EMI(現UNIVERSAL MUSIC)より、ミニアルバム『GIRLFRIEND』でメジャーデビュー。これまで2度に渡り、日本武道館でのワンマン公演を成功させる。2016年3月、結成当初からのメンバーであった湯浅将平(Gt)が脱退。同年同月から、サポートギターにフルカワユタカ(ex.DOPING PANDA)を迎え、ツアー『LIVE BY THE C2』を開催。ファイナルの『日比谷ノンフィクションV』では、フルカワユタカの他に石毛輝(lovefilm、thetelephones)、田渕ひさ子(bloodthirsty butchers、toddle、LAMA)、ハヤシ(POLYSICS)という豪華ギタリストを迎え、3人体制となって初のシリーズライブを成功に終える。サポートギターに弓木英梨乃(KIRINJI)を迎え、全36公演に及ぶツアー『バンドBのすべて2016-2017』を敢行。2017年4月12日、新体制後初となる7thフルアルバム『光源』をリリースする。
- フィードバック 14
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-