変化というのは、いつだって刺激的だ。そこに不安や揺らぎが伴おうと、行く先にたしかさなんてなくても、人が変化する瞬間には刹那的な美しさが宿る。大阪を拠点に活動する5ピースバンド、YAJICO GIRLは、今そんな瞬間を迎えているバンドだ。彼らがリリースした新作『インドア』は、バンドの魅惑的な変化の瞬間を捉えたドキュメントのようなアルバムといえるだろう。
2016年に『未確認フェスティバル』や『MASH FIGHT』といった大型オーディションでグランプリを獲得して話題になった彼らは、その時点では蒼さが光るギターロックの新星として認知されていたが、2017年リリースの前作『珍百景』のあたりから、同じ場所に留まることができない、自らの衝動と野心に自覚的になっていったようだ。
フランク・オーシャンやChance the Rapperが作る名作の存在やリスニング環境の変化も含めて、この数年の間に世界中で巻き起こったポップミュージック大革新の波をその身に感じながら、前作以降、YAJICO GIRLは自らの音楽をアップデートしようと試みた。『インドア』は、その試みのなかから生まれたピュアに輝く宝石のような作品集だ。サウンドは刷新され、言葉はより生々しさを増した。
素晴らしいのは、本作が海外のトレンドをまとうだけの空虚な音楽ではない、ということ。この音楽の中心にはあくまでも「歌」があり、その歌はあまりにも正直に、コンポーザーである四方颯人の心象風景を伝えている。伝えるべきことがあるから、変わらざるを得なかった――そんな必然性を、今作からは感じることができる。バンドとして、恐らく最初のエポックメイクなタイミングを迎えた今、四方颯人にその想いを聞いた。
耳が変わってしまったんですよ。なにもかも今までと違った。そうなるともう、あとには戻れない。

―新作『インドア』には、世界で鳴っている音楽を積極的に吸収するバンドの好奇心が反映されているように感じました。この作品を聴くと、YAJICO GIRLは非常に実直に、正直に、そのとき自分たちがやりたいことに向き合いながら音楽を作っていくバンドなんだなと感じます。サウンドも歌詞も、前作『珍百景』から、大きな変化を遂げていますよね。
YAJICO GIRL『インドア』を聴く(Apple Musicはこちら)
四方:そうですね。リスナーとして僕は世界で流行っている音楽を聴いているので、自分が聴いている音楽とやっている音楽との差が大きくなっていくことに違和感があって。前のアルバムの『珍百景』が出たのが2017年でしたけど、その前の年に、Chance the Rapperの『Coloring Book』、フランク・オーシャンの『Blonde』、Solangeの『A Seat at the Table』が出たじゃないですか。
―2016年はすごかったですよね。他にもカニエ・ウェストの『The Life Of Pablo』があったり、ビヨンセの『Lemonade』があったり、大作がバンバン出ました。
四方:その前後にケンドリック・ラマーがアルバム出していたり(2015年リリースの『To Pimp A Butterfly』と2017年リリースの『DAMN.』)。全体的にブラックミュージックが盛り上がっていく流れもあったし、僕個人としてはそういうものを聴いて刺激を受けていたんですけど、当時の日本のロックシーンを全体的に見渡すと、自分たちも含めて、全然そこにアジャストしていない感覚があったんですよね。
ceroとかは世界に目を向けて、その流れに素直に向き合いながら新しい音楽を作っていたと思うんですけど。そういうなかで、「自分たちも変わらなきゃいけない」っていう意識が出てきたんです。

―世界の動きと、そこにアジャストできていない大半の日本の音楽……その間にはどんな違いがあり、なぜ四方さんはフランク・オーシャンやChance the Rapperの作品に惹かれたんだと思いますか?
四方:たとえば、ストリーミングサービスを使うようになると、そこに適している音楽があることに気づくじゃないですか。当時、自分もストリーミングサービスで音楽を聴くようになり、リスナーとしての環境も変わっていったんですけど、海外のラップミュージックなんかは、そこにすごくマッチしていたんだと思うんです。
ただ、「フランク・オーシャンのどこがいいんですか?」ってよく訊かれるんですけど、ぶっちゃけ、簡単に言葉にできない(笑)。だから素晴らしいんですけど、あのアルバムは未だに僕にとっては謎だらけなんですよ。
フランク・オーシャン『Blonde』を聴く(Apple Musicはこちら)
―たしかに、フランク・オーシャンの『Blonde』は「永遠の謎」ですよね(笑)。だからこそポップだし、素晴らしい。僕は、あのアルバムによって「耳が変わった」くらいの感覚があったんです。四方さんもきっと、フランク・オーシャンやChance the Rapperが作る革新的な作品、あるいはそれらがリリースされている状況を、「他人事」ではなく「自分事」として受け止めたわけですよね。
四方:そう。ファッションとして受け止めたわけじゃなくて、本当に、彼らの作品を聴いて、耳が変わってしまったんですよ。なにもかも今までと違った。そうなるともう、あとには戻れない。
僕らも、「これ以降」の音楽表現をしないといけないなって感じざるを得ないくらいに衝撃が大きかったんですよね。……でも正直、「今の音楽をちゃんと聴いてたら、その音にはならんやろ」っていうようなミュージシャンも日本には多いなと思っていて(苦笑)。

四方:もちろん、海外に合わせたらなんでもいいわけでもないし、世界の動きを知ったうえで、あえて「合わせない」表現をしている人たちもいると思うんです。そういう人たちの音は聴けばわかるし、闘っているなって思うんですけど……。
―そうですよね。でも、「知らない」「知ろうともしない」というのは、土俵にすら立っていない、という感じがしてしまう。
四方:うん、そうなんですよね。
結局、自分がやりたい音楽しか作ることはできないですから。
―2016年頃に四方さんが海外の音楽に刺激を受けたという体験は、他のメンバーともすんなり共有できたものなんですか?
四方:いや、僕がひとりで勝手に変わっていった感じですね。今作のデモも、僕が勝手に作りはじめてメンバーに共有していったので、最初は彼らも戸惑ったと思います。

四方:うちのメンバーは、みんなが僕のように「今」の音楽を求めて聴いていくタイプではなくて。だから最初はギャップも大きかったし、僕から「こういう音楽も聴いてみたら?」っていう感じで勧めながら対話していって、ちょっとずつ感覚をシェアしていきました。
対話のなかで、「今回の作品は自分の思うところがあるから、自分のやりたいやり方でやらせてくれ」って、他のメンバーにずっと言っていて。サウンドが変わると、歌の音域も譜割りも変わってくるけど、そういうのも含めて、根本から変えていきたかったんですよね。
―そうした変化を遂げることで、これまでのYAJICO GIRLを聴いていたリスナーから戸惑いが生まれるんじゃないかという危惧はなかったですか?
四方:ガンガン危惧してました(笑)。不安は大きかったし、この作品ができるまではネガティブな気持ちも大きかったんですよね。そもそも、僕らは2016年にいろんなコンテストでグランプリをいただいたんですけど、“いえろう”っていう曲がいろんな人に響いて事務所に所属することになって。だから関係者含め周りの人たちは、この曲のような方向性で活動していくとイメージしていたと思うんです。
四方:でも結局、自分がやりたい音楽しか作ることはできないですから。今回の『インドア』は、これまでの僕らの音楽を聴いて好きになってくれていた人たちに、「変わってしまった」って思われても仕方ないなって思いながら作っていました。逆に、これをいいと思ってくれる人もきっといるだろうっていう部分も信じていたし。
―それだけ、四方さんは音楽に対して正直な人なんだろうなと思います。
四方:そうなんですかね?……逆に、正直じゃなく創作に向き合う方法はわからないです。「自分がいいと思っていないけど、作りました」みたいな曲をライブでも演奏したくない。そういう曲は歌ったって、気持ちが入らないから。
自分のなかにあるものを吐き出さないとどうにもできなかったし、前に進めなかった。
―結果として『インドア』は、いわゆる「バンドサウンド」という範疇を超えた音作りが大きな特徴になっていますよね。昨今のR&Bやヒップホップにも通じる、エレクトロニックなプロダクションが全面的に入ってきた作品に仕上がっている。「この曲ができたことによって、作品が見えた」みたいな1曲はありますか?
四方:デモ段階では“2019”が最初のほうにあったんですけど、アルバムの軌道が見えてきたっていう意味では、“NIGHTS”が大きかったです。
四方:ビート感が強くて、アンビエンスがあって、でも、海外の音楽をニュアンスだけ真似るのではなく、日本語の言葉や歌がしっかり入ってくる……そういうプロダクションを目指して作っていたんですけど、そうなると、どうしても、最近のラッパーやソロアーティストの作品みたいになってくるんです。
作るたびに、「これ、バンドの作品じゃないよね?」っていう感覚に陥って。バンドの名義でソロ作品を作っても面白くないし、バンドでやるからには、バンドである意味は考えないといけないじゃないですか。それで“NIGHTS”を作ったときに、「これならバンド感がある状態で、今の自分がやりたいことをできるかもしれない」って思ったんです。
―結果として“NIGHTS”は作品の1曲目に収録されていますけど、この曲は<東京の夜にはもう到底ないような 感情を確かに僕らは見つけたよ>という歌い出しからも、大阪を拠点に活動するYAJICO GIRLのリアルな心象風景を強く感じさせますね。
四方:僕らは今、大阪の千里ニュータウンっていう場所に住んでいるんですけど、事務所の先輩はみんな東京にいるし、いずれは僕らも東京に出てくることになるとは思うんです。でも、「東京じゃないと面白いことできないのか?」って言われると、「そんなことはまったくないよな」って思うんですよね。

四方:去年、『ここは退屈迎えに来て』(2018年公開、監督は廣木隆一。原作は山内マリコ)っていう小説が映画化されたので観に行ったんですけど、あの作品も地方都市を舞台にした映画で。
あの映画では、大都会でもド田舎でもない、僕らが普段暮らしているのと同じような街の景色がすごく美しく描かれていたんですよね。それを観たときに、こういう街の美しさって、みんながわかっているようで本当は気づいていないことなのかもしれないって思ったんです。だとしたら、それをテーマに歌詞を書けるかもしれないなって。
―それは、今作の全体的なテーマになっている?
四方:テーマということではないんです。ただとにかく、このアルバムでは「自分のなかにあるものを全部吐き出したい」っていう気持ちが大きかった。さっき話した自分がやりたいことと周りからのイメージとのギャップみたいな話にも通じるんですが、自分のなかにあるものを吐き出さないとどうにもできなかったし、前に進めなかったんです。なので、自分と向き合っていくなかで、自分のアイデンティティーのひとつとして「地方都市に住んでいる」という部分が大事なものだったんだろうと思います。
ライブハウスでいろんなバンドで集まったときも、僕らだけは浮いているというか(笑)。

―今作で吐き出されたものを客観的に見たときに、「四方颯人とはこういう人間なんだ」っていうことが、自分自身で見えてきたりしますか?
四方:う~ん……質問の答えとは違うかもしれないですけど、この作品を作り終わったあとに、すごく気持ちが晴れやかになったんですよ。ということは、自分のなかにあった鬱憤やモヤモヤを、ここにアウトプットできたんだろうとは思っています。
人間としてもちょっと変わったのかもしれない。ただ、「ここで表現されている自分がどういう人間であるのか?」っていうことは、もう少し時間が経たないとわからないことなのかなって思います。本当にぐーっと自分に入り込んで作ったので、まだ客観的には見れていないんですよね。

―今回のタイミングから、YAJICO GIRLは「Indoor Newtown Collective」という言葉も掲げていますよね。こういう言葉を見ても、今、YAJICO GIRL自分たちのアイデンティティーについて、すごく自覚的になにかを語ろうとしているのかな、と思ったんですよ。
四方:これまでの活動のなかでも、他の人からキャッチコピーやキャッチフレーズをつけられることはあったんですけど、どれだけラベリングされても全部しっくりこなかったんですよね。
そういう、周りがつけたラベルに対して、自分からカテゴライズされにいくのも嫌だし、それなら、自分たちのスタンスや楽曲の雰囲気に、自ら名前をつけてあげたくなったんです。それで、「Indoor Newtown Collective」という言葉を考えました。
―まず、「Collective」という定義の仕方が面白いですよね。
四方:「バンド」っていう言葉じゃなくても、この5人を定義づけられるなって思ったんです。それで、「Collective」っていう言葉を選んだんですけど、たとえば、Odd Future(タイラー・ザ・クリエイターをリーダーに、フランク・オーシャンやThe Internetを輩出する)は「Collective」じゃないですか。ああいう繋がりのほうが僕は魅力を感じるし、しっくりくるんですよね。

四方:僕らは5人とも、あんまりバンドマンっぽくないんですよ。「俺たちで這い上がっていくぜ!」っていう感じもないし、ガチっと5人で固まっている集合体っていうイメージもない。でも、高校の同級生だし、シンプルに友達で、居心地はいいしな……っていう感覚。僕らはずっと自分たちでグッズを考えたり、ミュージックビデオを作ったりもしてきましたけど、そんなインディペンデントな感覚も、「Collective」っていう言葉がしっくりくるなって思ったんですよね。
それにライブハウスでいろんなバンドで集まったときも、僕らだけは浮いているというか(笑)、あんまり交われないんですよ。コミュニケーション能力がないだけかもしれないですけど、打ち上がれないんです(笑)。

―「Indoor」という言葉に関してはどうですか? これは、作品のタイトルにもなっているし、重要な言葉だと思うんですけど。
四方:僕たちは外でバーベキューをするよりも、家で音楽を聴いたり、Netflixを見たりしているようなタイプの人間なんです(笑)。外に出るといっても、本屋にこもる、みたいな(笑)。そういう自分たちの性格を明確にしたかったんです。
僕、海に行きたいとか、ドライブに行きたいとか、そういう気持ちが一切ないんですよ。それやったら、月に1000円くらい払うだけで楽しめる充実したコンテンツが今はいっぱいあるんだから、家にいたいなって思うタイプで。
―「インドア」な感性というのは、今作の作品性に見事に反映されていますよね。たとえば6曲目“熱が醒めるまで”には<集めたレコード盤のアートワークを並べて見てた>というラインもありますし。今作の歌詞は、全体的には個人的で内省的な自分語りなんですけど、そのなかに、自己の外側にある文化や社会のニュアンスが絶妙に入り込んできているところがいいなと思って。
四方:ありがとうございます。SNS疲れみたいなのもあったと思うんですけど、今は「個人」がないがしろにされている感覚があって。歌詞を書いているときには、「個人」っていうのをもう一度考えてみようよ、みたいな感覚はありました。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONの『マジックディスク』に出会ってから、「言葉」に対する憧れや畏怖を持ち続けている気がします。
―8曲目“IMMORTAL”は<魔法の円盤を買い 言葉の海に呑まれた2010年から 何が変わったのだろうか 何も変わってないような気がする>というラインではじまりますけど、この「2010年」というのは、四方さんの個人史的にどういった年なんですか?
四方:そのラインは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの『マジックディスク』のことを歌っているんです。2010年にあのアルバムがリリースされた頃、僕は中学生だったんですけど、すごく大きな出会いだったんですよね。
「こんなにも、音楽のなかで言葉が強く出ているアルバムがあるのか!」っていう衝撃がすごくて。そこから、自分は「言葉」に対する憧れや畏怖を持ち続けている気がします。慎重に、言葉というものを見るようになった気がするんですよね。
―たしかに、あのアルバムは1曲目の“新世紀のラブソング”からして言葉が強烈ですよね。
ASIAN KUNG-FU GENERATION『マジックディスク』を聴く(Apple Musicはこちら)
四方:正直、中学生の頃の自分は、あそこで歌われていることのすべてはわかってなかったと思うんです。でも、意志はすごく感じたし、「わからないもの」に対する憧れが生まれるきっかけになったような気がします。僕は音楽に目覚めるまではバスケをしていたんですけど、中学生の頃に怪我をしてバスケを辞めざるを得なくなって、それから音楽や映画のようなカルチャーに目がいくようになったんです。
そこで、アジカンやBUMP OF CHICKENを聴きはじめたんですけど、そこで生まれ変わった感じがしたというか……自分の世界がガラッと変わった感じがしたんですよね。その感覚って、自分が作り手になった今も、ないがしろにはできないものなんですよね。
―“IMMORTAL”では<僕はひたすらただ祈ったんだ>とも歌われていますけど、四方さんはご自身が音楽を鳴らすときの態度、あるいは音楽そのものに対する態度を言語化してみたときに、「祈り」という言葉はしっくりきますか?
四方:振り返ってみると、「嘆き」や「叫び」の表現から、「祈り」のような表現に、自分の好みは移っていったような気はします。
YAJICO GIRL“IMMORTAL”を聴く(Apple Musicはこちら)
四方:大学の軽音部でいろんなバンドをコピーしていた時期に、最初は日本のロックバンドをやっていたんですけど、ソウルミュージックを歌いはじめたときに、すごくしっくりきたんです。それもあって、ブラックミュージックを聴くようにもなったんですけど、そのとき、自分のシンガーとしての魅力を一番引き出せるのは、「祈り」のような音楽なんじゃないかなって思ったんですよね。
―四方さんがブラックミュージックから感じたものは、「祈り」だった?
四方:もちろん、そればかりではないと思うんですけどね。でも、自分が好きなソウルミュージックには、「祈り」のような感覚があるように思います。
停滞感のあった2010年代はここで終わりにして、次の時代にいきたい。
―“2019”というタイトルの曲で今作が締められているのは、とても象徴的ですよね。ここにはどういった想いが込められているのでしょう?
四方:この曲は2017年の時点で歌詞もできていたんですよ。最初は「バンドっぽくないからアルバムには入れない」っていう感じだったんですけど、アルバムの全体像が見えてくるなかで、「あの曲を最後に入れれば完成するんじゃないか?」っていうビジョンが見えてきて。それで、タイトルを“2019”にしたんです。
カルチャーって、10年区切りで語られるじゃないですか。今年は2019年だから、来年から2020年代がはじまる。じゃあ、「ここまでの2010年代ってどんな時代だったんだろう?」って自分なりに振り返ってみたときに、『マジックディスク』が出たあの頃から、なにかがいい方向に変わったのかといえば、あんまり変わっていないような気がするんですよね。すごく停滞感があった時代のような気がするんです……日本は、特に。

四方:でも、そんな2010年代を僕はこのアルバムを出すことで終わらせて、次に行きたい。この曲ができた2017年の時点から、それは思っていました。
―じゃあ、今作が“2019”というタイトルの曲で締めくくられているのは、2010年代に対するレクイエムという側面が強い?
四方:そう、「ここから新しい時代をはじめていきたい」っていう感覚があるんです。なんだか、今って時代にひとつの区切りがついていっている感じがするんです。この間の吉本興業の問題とかもそうですけど……。
―価値観が揺さぶられるような出来事は多いですよね。「本当にこのままでいいんだっけ?」って、常に問われているような感覚が今はあります。
四方:そうですよね。だからこそ、停滞感のあった2010年代はここで終わりにして、次の時代にいきたい。そういう気持ちが強いです。
―時代は、人は、変わっていけると思いますか?
四方:変わっていけるかどうか、確信は持てないです。でも、変えていきたいし、貢献したいですよね。「さすがに、変わらなきゃいけないだろう」って思います。

―お話を聞かせていただいて、四方さんの視点は常に、ミクロなものとマクロなものを同時に見ている感じがしました。自分の内側に潜ることと、どこか遠くの世界を想像することが自然と両立されている。そのスタンスが、ときに「時代性」という言葉になったり、「祈り」という言葉になったりすると思うんですけど。
四方:僕はカルチャーが発展していってほしいんですよね。そのためには、カルチャーが時代性を内包するのは不可欠だと思います。カルチャーって、「娯楽」ではすまされないものだと思う。自分がカルチャーに触れることで豊かな人間になれてきた確信があるからこそ、そう思いますね。
―YAJICO GIRLの音楽も、時代と共に語られるものであってほしいと思いますか?
四方:うん、そうじゃないと嫌ですね。

- リリース情報
-
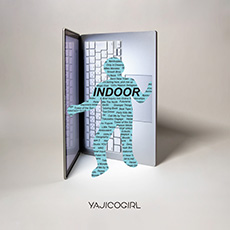
- YAJICO GIRL
『インドア』 -
2019年8月7日(水)発売
価格:2,000円(税込)
MASHAR-10071. NIGHTS
2. ニュータウン
3. 汽水域
4. ニケ
5. indoor
6. 熱が醒めるまで
7. CLASH MIND
8. IMMORTAL
9. 2019
- YAJICO GIRL
- イベント情報
-
- 『ヤジヤジしようぜ! vol.3 ワンマン編~やじこの番です~』
-
2019年9月20日(金)
会場:大阪府 心斎橋Pangea
- プロフィール
-

- YAJICO GIRL (やじこ がーる)
-
5人編成で自身の活動スタンスを「Indoor Newtown Collective」と表現する。結成してまもない2016年、大学在籍中に日本最大級音楽フェスティバル『SUMMER SONIC』の登竜門『出れんの!?サマソニ!?』を通過。その後『eo Music Try』や『十代白書』など地元関西コンテストでの受賞を重ね、同年全国38局ネットのラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』が企画する10代アーティスト限定ロックフェス『未確認フェスティバル』、そしてロックプロダクション「MASH A&R」が手がけるオーディション『MASH FIGHT』でグランプリをW受賞。翌2017年、タワーレコード内のインディーズレーベルから初の流通作品『沈百景』をリリース。その後も音源制作、ミュージックビデオの撮影から編集、その他全てのクリエイティブをセルフプロデュースし、2019年夏、自分たちの音楽の同時代性に向かい合った作品群としてアルバム『インドア』を発表。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


