『東京オリンピック・パラリンピック』を来年に控え、来るべき2020年への期待も不安も交錯する報道があふれる今日このごろ。その喧騒のなか、五輪イヤーのさらに一歩先を見据え、「2021年以降の東京」を考えるアートイベント『TOKYO 2021』が動き出している。
舞台は東京、京橋のTODA BUILDING。老舗ゼネコン、戸田建設の拠点であり、新社屋建設のため解体予定のこの場所で、実験的な建築展とアート展が繰り広げられる。牽引役となったアーティストの藤元明と建築家の永山祐子に加え、建築展を手がけた中山英之と藤村龍至、美術展をキュレートする黒瀬陽平に、それぞれが目指す『TOKYO 2021』について聞いた。
おそらく2020年は歴史上で大きな意味を持つ数字のひとつになる。2021年はその影でスルーされている感もあるけれど、実は重要。(永山)
―『TOKYO 2021』のコンセプトの起点は、藤元さんが2016年から始めたアートプロジェクト『2021』ですね。これは『東京オリンピック・パラリンピック』開催が決定したあと、新国立競技場の建設予定地前に『2021』の数字をかたどった巨大木製オブジェを設置したのが始まりでした。以降もこれを全国各所に出現させています。
藤元:今回の『東京オリンピック・パラリンピック』に向けて、メディアなどを通して国内外向けに演出されていく価値観や都市像がある。『2021』はこれらに対して、「その先」を僕ら自身に問う作品です。

1975年東京生まれ。東京藝術大学美術学部大学院デザイン専攻修了。FABRICA(イタリア)に在籍後、東京藝術大学先端芸術表現科非常勤助手を経てアーティストとして活動。都市における時間的 / 空間的余白を活用するプロジェクト「ソノ アイダ」を主催。人間では制御出来ない社会現象をモチーフとして、様々な表現手法で作品展示やアートプロジェクトを展開。主なプロジェクトに「NEW RECYCLE®」、広島-New Yorkで核兵器をテーマに展開する「Zero Project」など。2016年より開始した「2021」プロジェクトは現在も進化中。

藤元:コンセプトはシンプルですが、現場では仲間と一緒に高さ3.6m、幅10mのデカいオブジェを、自家用車とトラックで自力輸送して設置して……という泥臭い作業。毎回少人数で、強風のため立てられない時に、通りかかった少年たちに助けられたこともありました(笑)。基本的に誰に頼まれもせず出かけて行き、ビルの屋上に設置して、Google Earthだけが見てくれている、みたいなときもあります。

永山:彼は実行するのに夢中で、告知をすればいいのにと思いつつ(笑)、私はその様子を見てきました。でも少しずつ広がりも生まれ、東京の京浜島で行われた『鉄工島FES』や、福島県で黒瀬陽平さんが企画した『カオス*ラウンジ新芸術祭』の市街劇へ参加するようにもなりましたね。
『DESIGNART TOKYO 2018』で南青山に『2021#Tokyo Scope』を展示した際は、私も協働して時間軸に加えて空間、都市の視点を取り入れました。そうした流れが、今回につながっています。

1975年東京都生まれ。1998年昭和女子大学卒業後、青木淳建築計画事務所を経て、2002年永山祐子建築設計設立。2005年JCDデザイン賞2005奨励賞を受賞した「ルイ・ヴィトン京都大丸店」にて注目を集める。2006年AR Awards(UK)優秀賞「丘のあるいえ」、2014年JIA新人賞「豊島横尾館」、2018年山梨県建築文化賞、JCD Design Award銀賞、東京建築賞優秀賞「女神の森セントラルガーデン」等国内外受賞多数。現在、ドバイ万博日本館(2020年)、新宿歌舞伎町の高層ビル(2022年)などの計画が進行中。


―失礼ながら、数年前に『2021』を初めて見た感想は「恐ろしくシンプルだな」というものでした。『東京オリンピック・パラリンピック』を肯定も否定もせず、ただ静かに「それ以降」を問うている。でもお話を伺って、そのシンプルさゆえに今回のような広がりあるプロジェクトの器になり得たようにも感じます。
永山:確かに『2021』はただの4つの数字で、ある年を指し示すだけです。でも、それゆえの強さと、多様な解釈が生まれる可能性もある。何かへのアンチテーゼありきではないからでしょうね。
もちろん、『東京オリンピック・パラリンピック』への考えは人それぞれあると思うけれど、この場ではニュートラルに、「2020という数字が各所で踊るこの時代、その先の2021以降に意味あるものを考えよう」ということです。おそらく日本において2020は歴史上で大きな意味を持つ数字のひとつになる。2021はその影でスルーされている感もあるけれど、実は重要だと思います。

建築は団体競技的。話し合ううちに、何かが像を結び、その場にいる全員がハッとする瞬間があるんです。(中山)
『TOKYO 2021』の建築展は、8月3日から8月24日にかけて開催された。それは模型や写真を並べた展覧会とは全く異なる。気鋭の建築家13人が公募参加者と複数チームを組み、未来への提言として、ある課題に1か月かけて取り組み、議論するプロセスを公開するというものだ。ここでは、開催前に行ったキーパーソン2名のインタビューを紹介したい。
参加建築家は、土木、オフィス、商業空間、美術展会場など、得意領域も多様なメンバー。そして課題は、都心にある1㎢の敷地を対象に大規模開発プロジェクトを考え、議論することだという。ディレクションは建築家の中山英之が担った。
―中山さんがこのような建築展を考案した真意はどんなものでしょう?
中山:建築は基本的に大きな経済規模で動き、人々が関わる時間も長いものです。そしてしばしば、予想を超えた広がりも生む。
たとえば、建物単体の例ではありませんが、明治神宮は森を含めて全てが人工的な空間です。表参道は全国から寄進された木を運び上げるために掘り出されたスロープだったし、森の生育は今もって長期計画の途上にある。現代の都市を考えることもそんなふうに、より広い視野と長い射程の中にありたいと思いました。

1972年福岡県生まれ。1998年東京藝術大学建築学科卒業。2000年同大学院修士課程修了。伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て、2007年に中山英之建築設計事務所を設立。2014年より東京藝術大学准教授。主な作品に「2004」、「O邸」、「石の島の石」、「弦と弧」、「mitosaya薬草園蒸留所」、「Printmaking Studio / FMC」主な著書に『中山英之/スケッチング』(新宿書房)、『中山英之|1/1000000000』(LIXIL出版)『, and then: 5 films of 5 architectures/建築のそれからにまつわる5本の映画』(TOTO出版)。
中山:一方、いま大学で建築を教えていますが、このところの学生たちの卒業制作には「シェアハウス」や「シャッター街の再生」のような縮小社会を見据えたものがとても目立ちます。けれども、世界的な視野で見たら前回のオリンピックから地球の人口はほぼ倍増して、今も増え続けている。次の時代を背負う人たちが大きな課題に向き合いにくい状況を、自分たちの教育が生み出してしまってはいないかと、心を痛めてもいました。
―建築教育における課題の多くは架空の設計だとすれば、よりスケールの大きい挑戦があってもいい。でも社会状況や様々な要因から、実際はそれが非常に少ないということでしょうか。
中山:そうですね。だから今回は、僕ら建築家と参加者、さらに戸田建設の社員さんたちが一緒に「2021年以降の東京」のような大きな視野の課題に取り組み、かつそのプロセスを公開してみたいと考えたのです。最終日にはひとつに統合したプランを発表し、ゲストを招いて批評し合う公開討論会も行います。

中山:講評会は建築系の大学では日常的なものですが、そこで交わされる言葉って、すごく面白いんですよ。架空の計画を討議し合うという意味では、知的なエンターテインメント性もあると思います。そうした討議の中で、「こうしたら?」「いや、こうでしょ」と話し合ううちに、新しい何かが像を結び、その場にいる全員がハッとする瞬間があったり。今回もそんな場が生まれたらいいですね。
東京は小さな地域=「島」からなる、集合体=「島京(とうきょう)」に変容したともとれる。その将来を「島」スケールの新たな開発プランを通じて考えていきます。(藤村)
―藤村龍至さんは今回、中山さんに指名されて課題を作成したそうですね。「島京(とうきょう)2021」と名付けられたこの課題は、都心にある1㎢の敷地を対象に、予算1兆2000億円の開発プランを考えるというものです。そこにはどんな意図が?
藤村:東京では1990年代まで、行政主導で「多心型の都市」という目標が示され、2000年代以降はバブル崩壊後の「都市再生」が目指された20年だったと言えます。その過程で大手町、日本橋、京橋、銀座、六本木、渋谷、品川など、地域ごとのイメージが際立っていき、競争も本格化した。結果、渋谷が生活文化の街、日本橋が歴史の街、というように各所の個性が打ち出されます。

建築家。1976年東京生まれ。2008年東京工業大学大学院博士課程単位取得退学。2005年藤村龍至建築設計事務所(現RFA)主宰。2010年より東洋大学専任講師。2016年より東京藝術大学准教授。2017年よりアーバンデザインセンター大宮(UDCO)副センター長 / ディレクター、鳩山町コミュニティ・マルシェ総合ディレクター。2018年より日本建築学会誌『建築雑誌』編集委員長。住宅、集合住宅、公共施設などの設計を手がける他、公共施設の老朽化と財政問題を背景とした住民参加型のシティマネジメント、ニュータウン活性化、中心市街地再開発のデザインコーディネーターとして公共プロジェクトに数多く携わる。
藤村:こうした流れは、東京が小さな地域(島)からなる集合体「島京(とうきょう)」に変容したともとれる。近年目立つ、地下鉄駅直結の複合型巨大建築など、日本独自の要素も生まれ、2020年の『東京オリンピック・パラリンピック』は「都市再生」の総仕上げとも見なせます。
ただ、「島」ごとの発展は成功例が各所で模倣されたりすると、新たな均質化の心配もある。今回の課題ではそうした現状をふまえ、東京の将来を「島」スケールの新たな開発プランを通じて、皆で考えていきます。
―それは単なるアイデア合戦にとどまらず、歴史を読み解き直すことにもつながる?
藤村:そう期待したいです。1960年代は建築家たちによる大きな都市計画が活発に提案されたまぶしい時代で、今はそうしたものは非常に少ない。一方、現実社会のプロジェクトとしては、1960年代に超高層ビルの先駆けとなった霞が関ビルがあり、21世紀に入っても六本木ヒルズや東京ミッドタウンなど、開発は続いています。
このあたりは俯瞰すると一種の捻れもあるように思えて、そこから「もうひとつの東京建築史」も議論できたらと思います。そうした議論を幅広い層の来場者にいかに伝えられるかも、工夫したいですね。

「災害と祝祭」は歴史的に入れ替わりで繰り返されてきた。そこに並走するアーティストを「慰霊のエンジニア」ととらえ、2021年以降を創造する力につなげたい。(黒瀬)
建築展の後に始まる美術展は、黒瀬陽平がキュレーターを務める。彼は東京、そして日本に「災害と祝祭」を繰り返す歴史を見いだし、そこで文化や科学が新たな想像力や技術を生み出してきたと考察。その「慰霊のエンジニアリング」の営みには表現者たちも関わってきたとの視点から、日本現代美術史を再構成する。
―黒瀬さんが今回掲げた美術展のテーマ「un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング」について聞かせてください。
黒瀬:最初に考えたのは、やはりゼネコンの戸田建設と一緒に美術展をやる意味です。同社は東北の災害復興などにもインフラ面から貢献しているので、そこから、ポストオリパラにつながる視点を見いだせないかと考えました。
そうして出てきたのが「災害と祝祭」。両者は対照的ながら、歴史的にみると常に入れ替わりで繰り返されてきました。たとえば1964年『東京オリンピック』の前には第二次世界大戦と原爆投下が、今回の『東京オリンピック・パラリンピック』の前には東日本大震災があった。

1983年、高知生まれ。美術家、美術批評家。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。『思想地図』公募論文でデビュー。美術からアニメ・オタクカルチャーまでを横断する鋭利な批評を展開する。また同時にアートグループ「カオス*ラウンジ」のキュレーターとして展覧会を組織し、アートシーンおよびネット上で大きな反響を呼ぶ。著書に『情報社会の情念 —クリエイティブの条件を問う』(NHK出版)。
黒瀬:多くの祝祭は厄災を乗り越えるべく開かれてきた歴史があります。さらに、その現場では建築家やアーティストも関わる。
そして慰霊は、宿命的に繰り返される災害から立ち直り、前進しようとする営みです。災害の内容も文明と共に変化するならば、対応する学術や技術も、また慰霊の行為も更新されてきたはず。今回はこうした視点を日本現代美術史と重ねた展覧会を考えています。

―紹介される作品は、霧のアートで有名な中谷芙二子が1970年代に水俣病の抗議運動を扱ったビデオ作品や、メーヴェ型飛行具で知られる八谷和彦が阪神・淡路大震災を機に生んだ初期の名作。またオウム事件以降に美術活動を休止した飴屋法水の語りや、宇川直宏が東日本大震災以前に災害をテーマに取り組んだ作品など、幅広いですね。
黒瀬:情報社会化の始まりである1970年代を起点とし、現在までつながる日本現代美術の系譜を提示できればと思っています。美術がいかに同時代の文化やテクノロジーを取り入れながら、作品をある種のシミュレーターとして、様々な災害記憶を扱ってきたのかを考えたい。
災害と祝祭を繰り返す歴史の中で、慰霊の行為とテクノロジーもパラレルに関わり合い、変化し続けています。今回は、時代と並走するアーティストたちの試みを「慰霊のエンジニア」としてとらえることで、2021年以降を創造する力につなげられたらと考えています。
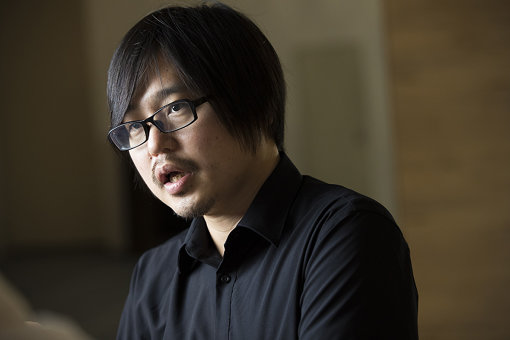
ゼネコンVS建築家、アーティストのような対立関係は考えていない。様々な違いを超えて、共にこれからを考える場が広がればいい。(永山)
最後に、再び藤元と永山に聞く。『TOKYO 2021』の報道資料にあった「開発とアート」という言葉について、彼らはそこにどんな可能性を見るのだろう。
―永山さんは『TOKYO 2021』の記者発表会で、今回の『東京オリンピック・パラリンピック』を機になされるさまざまな開発をめぐり、建築家が必ずしも十分コミットできなかったことへの「モヤモヤ感」を語っていました。これは新国立競技場の設計コンペをめぐる騒動や、ゼネコン主導で各種開発が進んだことなども含めての言葉かと推察します。その上で今回、戸田建設と協働することはどうとらえていますか?
永山:ゼネコンVS建築家、アーティストのような対立関係とは考えていません。もともと建設会社と建築家は協業して街を作っていく関係ですからね。

永山:ただ、2020に向かう動きの中では、私たち建築家の声は届かなかったという思いも確かにある。だからその上で、これから一緒にどんな都市の未来像を描けるか、だと考えています。
それは今回、戸田建設さんの、特に若い方たちと関わる中で実感していることです。様々な違いを超えて、共にこれからを考える場が広がればいい。
藤元:もともと自分の作品『2021』は、美術館やギャラリーではないパブリックな場で問いを投げかける試みでした。それが今回「開発とアート」を考える形に発展してきたのだと思います。
以前、アメリカの大型アートフェア『アート・バーゼル・マイアミ』を観に行ったとき面白かったのが、アートと街の関係でした。アートバーゼルには世界中のアート関係者、オーディエンスが集まります。会期中は地元美術館の最上階で、各界のベテランから若手が、街の将来にアートをどう活かせるかを議論している。

藤元:かと思えばダウンタウンでは、ふだんイリーガル(違法)に描かれるグラフィティーが店舗の依頼で街の各所に合法的に現れていたりする。フェアが終わったとたん、一斉に(イリーガルに)上から描き直されるんだけど、それぞれの場とやり方で、街の開発にアートが活用されているのを見ることができたのは、いい経験でした。


丹下健三はすごいけれど、むしろ彼を同時代で見ていた人たちが時代を作ったとも言えるのでは。だから、多くの熱量とアイデアが集中することに期待したい。(藤元)
―今回の『TOKYO 2021』に、どんな成果を期待しますか?
永山:クリエイションと社会の関係を考える上で、この『TOKYO 2021』が意義ある事例になればと願っています。会期後、会場になっている建物は解体されますが、新たな戸田建設社屋はアート等の文化発信機能も検討していると聞いています。
どれだけこれから日本が、文化やクリエイション全般の重要さを将来の経済発展や社会全般とつながるものとして認識していけるのか。これについては危機感を覚えることもあり、だからこそ大切だと思う。
藤元:こうゆうモヤモヤした思考や議論こそアートの意義だし、未来への参加だと思います。そのきっかけは『東京オリンピック・パラリンピック』だし、一番便乗しているのは僕ですからね(笑)。


―藤元さんは今回の『TOKYO 2021』について、どんな期待をしていますか?
藤元:アーティストの視点から言うと、建築家たちは本当に面白いこと考えている人が多い。ただ破天荒なのでもなく、困難なプロジェクトを現実的に前進させる力に魅力を感じます。
今回は全体がアートプロジェクトなので自由度があって対話もしやすいし、建築展と美術展の2つがあることで生まれる思考の厚みにも期待しています。でも、完璧な答えなんて出ないんですよ、きっと。
丹下健三みたいな人はそういう答を示したかと言えば、彼の提案は「問い」になったんだと思います。アートは答ではなく「問い」だし、その質感が重要なんです。むしろ彼のしたことを同時代で見ていた多くの人たちが時代を作っていったとも言えるのではと思うんです。
だから『TOKYO 2021』でも、多くの人たちというか、熱量とアイデアが集中することに期待したい。完成したものを披露するというより、ここから生まれるものがあると思って取り組んでいます。

Jacket / Cap : ANREALAGE x 2021(Youtubeで見る)
- イベント情報
-
- 『TOKYO 2021 課題「島京2021」』
-
2019年8月3日(土)~8月24日(土)
会場:東京都 京橋 TODA BUILDING
- 『TOKYO 2021 un/real engine - 慰霊のエンジニアリング - 』
-
2019年9月14日(土)~10月20日(日)(毎週火曜日定休)
会場:東京都 京橋 TODA BUILDING
料金:無料(Peatixサイトより事前登録)
- プロフィール
-
- 藤元明 (ふじもと あきら)
-
1975年東京生まれ。東京藝術大学美術学部大学院デザイン専攻修了。FABRICA(イタリア)に在籍後、東京藝術大学先端芸術表現科非常勤助手を経てアーティストとして活動。都市における時間的/空間的余白を活用するプロジェクト「ソノ アイダ」を主催。人間では制御出来ない社会現象をモチーフとして、様々な表現手法で作品展示やアートプロジェクトを展開。主なプロジェクトに「NEW RECYCLE®」、広島-New Yorkで核兵器をテーマに展開する「Zero Project」など。2016年より開始した「2021」プロジェクトは現在も進化中。
- 永山祐子 (ながやま ゆうこ)
-
1975年東京都生まれ。1998年昭和女子大学卒業後、青木淳建築計画事務所を経て、2002年永山祐子建築設計設立。2005年JCDデザイン賞2005奨励賞を受賞した「ルイ・ヴィトン京都大丸店」にて注目を集める。2006年AR Awards(UK)優秀賞「丘のあるいえ」、2014年JIA新人賞「豊島横尾館」、2018年山梨県建築文化賞、JCD Design Award銀賞、東京建築賞優秀賞「女神の森セントラルガーデン」等国内外受賞多数。現在、ドバイ万博日本館(2020年)、新宿歌舞伎町の高層ビル(2022年)などの計画が進行中。
- 中山英之 (なかやま ひでゆき)
-
1972年福岡県生まれ。1998年東京藝術大学建築学科卒業。2000年同大学院修士課程修了。伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て、2007年に中山英之建築設計事務所を設立。2014年より東京藝術大学准教授。主な作品に「2004」、「O邸」、「石の島の石」、「弦と弧」、「mitosaya薬草園蒸留所」、「Printmaking Studio / FMC」主な著書に『中山英之/スケッチング』(新宿書房)、『中山英之|1/1000000000』(LIXIL出版)『, and then: 5 films of 5 architectures/建築のそれからにまつわる5本の映画』(TOTO出版)。
- 藤村龍至 (ふじむら りゅうじ)
-
建築家。1976年東京生まれ。2008年東京工業大学大学院博士課程単位取得退学。2005年藤村龍至建築設計事務所(現RFA)主宰。2010年より東洋大学専任講師。2016年より東京藝術大学准教授。2017年よりアーバンデザインセンター大宮(UDCO)副センター長/ディレクター、鳩山町コミュニティ・マルシェ総合ディレクター。2018年より日本建築学会誌『建築雑誌』編集委員長。住宅、集合住宅、公共施設などの設計を手がける他、公共施設の老朽化と財政問題を背景とした住民参加型のシティマネジメント、ニュータウン活性化、中心市街地再開発のデザインコーディネーターとして公共プロジェクトに数多く携わる。
- 黒瀬陽平 (くろせ ようへい)
-
1983年、高知生まれ。美術家、美術批評家。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。『思想地図』公募論文でデビュー。美術からアニメ・オタクカルチャーまでを横断する鋭利な批評を展開する。また同時にアートグループ「カオス*ラウンジ」のキュレーターとして展覧会を組織し、アートシーンおよびネット上で大きな反響を呼ぶ。著書に『情報社会の情念 —クリエイティブの条件を問う』(NHK出版)。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


