京都発の4ピース、the engyがメジャーデビュー作となるミニアルバム『Talking about a Talk』を完成させた。グルーヴィな生演奏とプログラミングを融合させたトラックの上で、味のあるしゃがれ声のボーカルが感情豊かに歌う楽曲は、時流とリンクしつつも、その一歩先を提示する。すでにストリーミングで音楽ファンから高い注目を集めているが、来年あたり車のCMに起用されて、お茶の間でバンバン流れていてもおかしくはない。
そんなバンドが「おしゃれ」と形容されるのは自然な流れではあると思うが、それでもthe engyに関してはそこからどうにもはみ出しているように感じる。鍵を握るのはバンドの中心人物である山路洸至(やまじこうし)で、もともと楽器の構造が気になって音楽を始めたという、かなりの研究者タイプ。知的好奇心旺盛な一方で、「熱さ」をなにより重視する姿勢は、そのままインテリジェンスとエモーションの同居したバンドの個性に繋がっていると言えよう。CINRA.NET初インタビューで、バンドの成り立ちと山路独自の哲学に迫った。
「おしゃれバンド」みたいに呼ばれることが多くなった。ありがたいんですけど……。
―昨年リリースされたミニアルバムのタイトル『Call us whatever you want』、つまり「好きなように呼んで」というメッセージは、the engyというバンドの性格をよく表していたように思うのですが、なぜあのタイトルをつけたのでしょうか?
the engy『Call us whatever you want』(Apple Musicはこちら)
山路:2017年に最初のEP(『theengy』)を自主で出して、「おしゃれバンド」みたいな呼ばれ方をすることが多くなったんです。ありがたいんですけど、自分たちとしてはそこを目指していたわけではなかったので、「そういうふうに言ってもらえるんや」って新鮮に感じて。あと、音楽業界以外の人に「バンドやってます」と言うと、絶対「どんなバンド?」って聞かれるんですよ。
―「ジャンルはなに?」とかですよね。
山路:そう、でも「どんなジャンル?」って聞かれるのが一番困るんです。結成当初から「なんて言ったらいいんやろ?」ってずっと思ってて、そうしたら、「おしゃれバンド」みたいに言われるようになって……じゃあもう、「好きに呼んでもらえればいいですよ」っていう。「そういう言い方は僕らの音楽性と違うんで」って小っちゃなことを言ってもしょうがないですし、とにかく僕らは僕らがかっこいいと思うものを作りたいだけなので。

左から:山路洸至、濱田周作、藤田恭輔、境井祐人
京都発。山路洸至(Vo,Gt,Prog)と濱田周作(Ba)、境井祐人(Dr)、藤田恭輔(E.Gt,Cho,Key)からなるロックバンド。山路のスモーキーかつブルージーな歌声とソウル、ヒップホップ、ダンスミュージック、エレクトロニックなどあらゆるジャンルを取り込みつつ緻密に構築されたトラックメイクとロックサウンドが特徴。2019年は『Touch me』『Still there?』と配信シングルを立て続けにリリースし、Apple Music「今週のNEW ARTIST」への選出、Spotifyでは国内外複数のプレイリストに取り上げられるなど注目度を上げている。
―その人が「おしゃれバンド」って思ったら、別にそれを否定するつもりはなくて、そう呼びたかったら呼んでくれてもいいと。
山路:これまでの人生で「おしゃれ」って言われることが少なかったので、全然嫌ではないですし、ありがたいです(笑)。ただ、僕らがバンドを組んだ動機って、「こういう曲をやりたい」とか「こういうバンドをしたい」ではなくて、「とにかくいい曲が作りたい」という、ただそれだけを考えていたんです。
―では、山路くんの思う「いい曲」の基準とは?
山路:そうですね……聴いた人が確実になにかを食らう曲、ということかもしれないです。僕、熱いミュージシャンが好きで、MOROHAの大ファンなんですよ。去年『ボロフェスタ』で同じ日に出たんですけど、会場全体で僕が一番泣いてましたもん(笑)。とにかく刺さって、抜けなくなる。そういう曲が自分の中の「いい曲」なので、自分の作る曲もすべてそうなればいいなって。

―確かに、the engyの曲からも「熱さ」を感じます。
山路:熱さを持ってないアーティストはつまらないと思うんです。でも「熱さ」にもいろいろあって、たとえばアリシア・キーズにはアリシア・キーズの熱さがあるし、toeにはtoeの熱さがある。それらを比べて「どっちの方が熱い」とかはないですけど、いい曲の尺度として、どんな形であれ、「熱さ」は欠かせないと思いますね。
「わからないから知りたい」みたいな欲求が、ずっと根底にあるんだと思います。
―the engyの曲には確かに「熱さ」があって、すごくエモーショナルだと思うんですけど、その一方で、サウンドは作り込まれていて、知的な興奮もある。山路くんは研究者タイプでもあるのかなと、楽曲を聴いていると感じます。
山路:おっしゃる通り、僕は研究したいタイプというか、物事を突き詰めていきたいタイプで。そもそも「研究」って、すごく熱い作業なんですよ。
僕は大学院まで行ったんですけど、研究者が本を読むときって、「この本に載ってることは、あの本のあれか! 今すぐ図書館行こう!」みたいな、すごく熱い作業で(笑)。そういう研究の熱さも音楽に出てるかもしれないですね。

―そもそも音楽に興味を持ったのも、「この曲が好き」とかではなくて、楽器の構造が気になったのがきっかけだったそうですね。
山路:そうなんです。ピアノを触ってる人を見たときに、なんであんなにきれいな音が鳴るのか全然わからなくて、知りたいと思ったんですよね。幼稚園のときに急に言い出したらしいんですけど、「わからないから知りたい」みたいな欲求が、ずっと自分の根底にあるんだと思います。
逆に「このままやり続けたら、いつかできるようになる」みたいなものには興味が持てないんですよ。たとえばスポーツは苦手で。「あと100回素振りすれば、打てるようになる」って言われても、「じゃあ、やったらええんやな」ってなってしまうから、全然入り込めなくて。
―でも、楽器は違った?
山路:中学からギターを始めたんですけど、僕、ジョン・フルシアンテが大好きで。あの人のギターを聴いたときに、「ギターって、こう弾く楽器だったんや」みたいに思ったんです。あと何回弾こうが、なんぼ時間を費やそうが、絶対この人みたいにはできないなと思った。そういう、できないもの、わからないものに、のめり込むんですよね。

SuchmosとかNulbarichのライブで同期が使われているのを知って、意識が変わった。
―the engyの楽曲においてボーカルのインパクトも大きいと思うんですけど、「歌」にのめり込んでいった理由にも、「わからないから知りたい」と近いものがありますか?
山路:もともとギタリスト志望だったんですけど、曲を書いても誰も歌ってくれないから、大学のときに「このままじゃ4年間無駄になる」と思って弾き語りで歌い始めて。
エド・シーランが好きだったので、最初はルーパーを使って似たようなことをしていたんです。自分としてはギターを褒めてもらえると思ったら、「全然リズム感ないからルーパーやめた方がいい。せっかく歌はいいのに」みたいに言われて、「え、ギターじゃないの?」みたいな(笑)。そのあとにサークルでthe engyの前身のバンドを組んで、ライブをしたときに、PAさんが「めっちゃ声いいね」って言ってくれて、そこからちゃんと歌い始めました。

―the engyの楽曲は生演奏と打ち込みの融合もポイントだと思いますが、打ち込みをやり始めたきっかけは?
山路:最初のEPに入ってる“She makes me wonder”という曲は、エンジニアを目指している後輩が「DTMできる」って言うから、そいつと一緒に作ってみたんです。そうしたら「こんなこと身近でできんのや」ってわかって、「今iPadでもできますよ」って言われたので、自分でもやり始めました。
山路:もともと曲を作るのが好きで、弾き語りではすごい数作ってたんですけど、ギターで作るのにちょっと飽きてきていたところで。打ち込みで作るようになったらめちゃくちゃ楽しくなったんですよね。
―言ってみれば、研究の対象がDTMに移ったというか。
山路:ジョン・フルシアンテも言ってたんですけど、DTMで作るのって、最初のアイデアが必要ないんですよ。とりあえず音を出してみれば、そこからアイデアが広がって、どんどん曲が生まれる感覚になるんです。
しかも、ちょうどその頃に、SuchmosとかNulbarichのライブを観た人が「同期使ってた」って言ってて、「もうそういうふうにライブをやるのは普通なんやな」と思って。だったら、同期をもっと大胆に使った方が面白いものができるんじゃないかと思ったので、しっかりトラックを作ることを意識するようになりました。
―そこに関しては、時流の影響もあったと。
山路:twenty one pilotsとかも好きで、彼らのライブはドラムとピアノだけで、あとはオケなんですよ。でも、ドラムはめっちゃ叩いてるし、ボーカルはピアノからジャンプしたり、すごい熱量を感じて、同期を使おうがなにしようが、「大事なのは見せ方なんやな」と思って。それからは同期をどんどん使って、機材自体にハマっていった感じです。

ひねくれた作り方をする上では、「匂い」が大事なんですよね。
―新作『Talking about a Talk』のサウンドは、『Call us whatever you want』以上に、かなり作り込まれていますよね。
the engy『Talking about a Talk』(Apple Musicはこちら)
山路:『Call us whatever you want』はライブを意識して作ったんですけど、その上で、さらに曲の完成度を上げたいと思ったのが今回のアルバムで、アナログの、温かみのある音を意識しました。
デジタルはどうしてもきれいというか、汚れてなくて、CGみたいなんですよ。でも、ちょっと汚れとか匂いが音自体についてる方が僕の曲には映えると思って、それを意識してやってたら、どんどん機材が増えて、今家が機材の段ボールだらけです(笑)。
―今はソフトさえあればある程度のクオリティのサウンドを誰でも出すことができるけど、よりオリジナリティを強くするために、アナログがポイントだったと。
山路:自分はちょっとひねくれてるのか、王道にはいけないんです。たとえば、「ファンクっぽい曲にしたい」って言ったら、普通エンジニアさんは全部の音をファンキーにしようとするじゃないですか。でもそうじゃなくて、「フレーズだけファンキーで、音も全部ファンキーだったらダメ」って言うんです。そうすると「なんで?」ってなるんですけど、一回やってみると、そっちの方がむしろファンキーだったりして。
そういうひねくれた作り方をする上では、「匂い」が大事なんですよね。今回だと声やギターをICレコーダーで録ったりして、それもいい質感になったなと思います。
―リード曲の“Sick enough to dance”のサウンドに関しては、どのように作っていったのでしょうか?
山路:この曲は今回一番最後に作ったので、それまでに得たいろんなノウハウを詰め込んで、音にはものすごくこだわりました。サンプル音源は一個も使ってなくて、キックの音は打ち込みなんですけどシェーカーは自分たちで振ってるし、スネアはわざわざ電話回線を通して録っていて。
―電話回線を通して?
山路:その方が遠くで鳴ってる感じがして、クラップと混ざったとき気持ちいいと思ったんです。“Sick enough to dance”はそうやっていろいろ積み上げつつ、遊びつつ、楽しんで作った曲ですね。ただ、積み上げれば積み上げるほど、逆に壊したくもなっちゃうんですよ。

―やっぱり、そこはひねくれてる(笑)。
山路:アメリカの音楽のずるいところって、結局「ジャーン!」ってやるとかっこいいんですよね。Bon Joviが「ドーン!」ってやれば、「かっけえ!」みたいな(笑)。そういう気持ちよさも出したくて、“Sick enough to dance”は「やりすぎ」をテーマにしました。パーティーすぎるし、バンドサウンドすぎるし、キック気持ちよすぎるし、メロもよすぎる。そういう方向性が面白いんじゃないかなって。
―今のサウンドメイクの流行りとしては、音数を減らして、空間を作って、ちゃんと帯域を分けて、それぞれの音をよく聴こえるようにするっていうのがあると思うんですね。でも、そこであえて「やりすぎ」を選んだと。
山路:「音数が少ない」ということに対して、僕は思うところがあって……。

休符で遊んでる音楽のことを「音数が少ない」という言葉で表されているのだと思う。
―ぜひ聞かせてください。
山路:「楽器の数が少ない=音数が少ない」ではないんですよね。僕たちの中で常に一番の曲が“ルビーの指輪”(寺尾聰、1981年)で、あの曲は本当にすごくて。めっちゃ音入ってるんですけど、全部の住み分けがちゃんとできてるんです。あれには勝てないなって思う。
つまり、音色ごとの役割がはっきりしていて、すべての楽器がそれぞれの役割を全うしてることが「音数が少ない」のだと思う。だから、ちゃんとその状態を保てれば、楽器の数を増やしても「音数が少ない」という状態にはできるんです。それを「やりすぎ」でできないかなって、今回は思ったんですよね。
―やりすぎてるんだけど、でもその全部がちゃんと役割を全うしてる曲を目指したわけですね。
山路:休符で遊んでる音楽のことを「音数が少ない」という言葉で表されているんだと思っていて、そのかっこよさもすごくわかるんです。ただ、その一方で、「ダーン!」もかっこいいと思うから、その両方に手を伸ばしたかったんです。

曲を作るときの大きなテーマとして、「芸術性と大衆性は結びつく」と考えている。
―the engyの歌詞は基本英語ですが、新作では日本語の歌詞も登場しています。これはどんな考え方の変化の表れだと言えますか?
山路:もともとは、中学生のときに「もしかして日本語って、自分がやりたい音楽にハメるための言葉じゃないんじゃないか?」と思って、英語で歌うようになったんです。最初は使えそうなフレーズを書き溜めることから始めたんですけど、「これは膨大な時間がかかるから、しゃべれるようになった方が早い」と思って、英会話学校に行って。
今回は……まあ、「日本語を聴きたい」という声が多かったので、やってみたら、意外とよかったということなんですけど(笑)。日本語で歌詞を書く上では、文字に起こしたときにきれいじゃないと嫌だし、耳に入ったときに心地よくないと嫌で。(マキシマム ザ)ホルモンとか日本語使うのが上手いなって思うんですけど、僕も全部音で捉えてて、音に当てはめた結果、ラップっぽいフロウになった感じです。
まだまだ日本語は模索中ではあって、今度はちゃんとしたメロにどうやったらハメられるのかも試したいんですけど……そこに関してはサカナクションがすごく高いところにいると思うので、同じことをやっても意味がないし、僕らの現状はこれ、という感じですね。
the engy“In my head”(Apple Musicはこちら)
―ホルモンやサカナクションもそうだと思うんですけど、すごく研究されていて、作り込まれてるんだけど、決して難しい印象ではなくて、あくまでポップミュージックですよね。そこに関してはthe engyも一緒かなって。
山路:そうですね。曲を作るときの一個の大きなテーマとして、「芸術性と大衆性は結びつく」というのは考えていて。芸術性を突き詰めた結果、大衆性から離れちゃうと、狭いものになっちゃいますよね。でもーー語るのもどうなんって話ですけどーーThe Beatlesにしろ、ゴッホにしろ、すごく芸術的で、すごく大衆的でもある。そういうものがかっこいいとはずっと思ってます。広くに働きかけるけど、すごく尖ってもいる。そういうのを作りたいという欲求がありますね。
―やっぱり、「おしゃれバンド」というイメージからはかなり遠いところにいますよね。
山路:よかったです。まあ、そう呼んでくれても全然いいんですけどね。

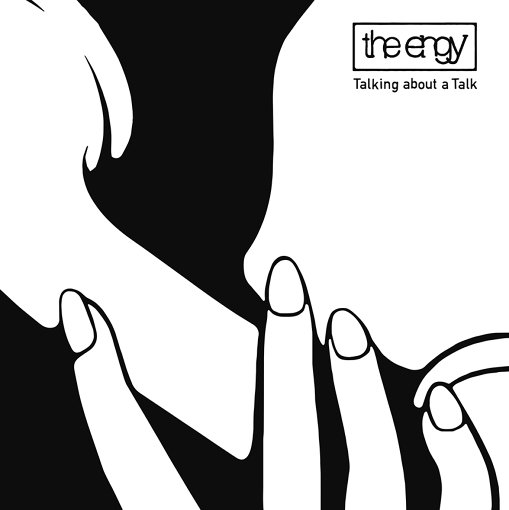
the engy『Talking about a Talk』(Apple Musicはこちら)
- リリース情報
-

- the engy
『Talking about a Talk』初回限定盤(CD) -
2019年10月30日(水)発売
価格:2,530円(税込)
VICL-652571. At all
2. Still there?
3. Sick enough to dance
4. In my head
5. Touch me
6. Hey
7. I told you how
8. Have a little talk
9. Sick enough to dance [Pf ver.](ボーナストラック)
- the engy
『Talking about a Talk』通常盤(CD) -
2019年10月30日(水)発売
価格:2,200円(税込)
VICL-652581. At all
2. Still there?
3. Sick enough to dance
4. In my head
5. Touch me
6. Hey
7. I told you how
8. Have a little talk
- the engy
- イベント情報
- プロフィール
-

- the engy (じ えんぎー)
-
京都発。山路洸至(Vo,Gt,Prog)と濱田周作(Ba)、境井祐人(Dr)、藤田恭輔(E.Gt,Cho,Key)の4人からなるロックバンド。山路のスモーキーかつブルージーな歌声とソウル、ヒップホップ、ダンスミュージック、エレクトロニックなどあらゆるジャンルを取り込みつつ緻密に構築されたトラックメイクとロックサウンドが特徴。 2017年5月に自主制作盤1st EP『theengy』を発売。未流通の自主制作盤ながら耳の早いバイヤーがYouTubeなどで楽曲をキャッチし、コアな専門店やアパレル店などで取り扱いされ関西を中心にジワジワと存在感を増しいく。2019年には『Touch me』(6月12日配信)、『Still there?』(8月28日配信)と配信シングルを立て続けにリリースし、Apple Music「今週のNEW ARTIST」への選出、Spotifyでは国内外複数のプレイリストに取り上げられるなど更に注目度を上げている。
- フィードバック 2
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


