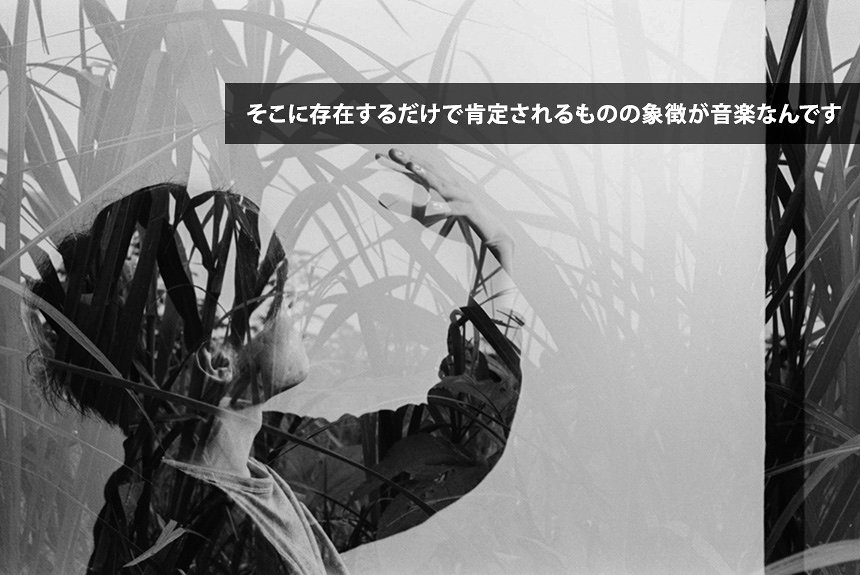元the cabsのコンポーザー・ギタリストであった高橋國光が、the cabsの活動終了後に、高橋國光がSoundcloudにソロ楽曲をアップし始めたのがösterreich(オストライヒ)の創始である。たったひとりで、しかし確かに人の目と耳と心に触れることを求めて、音楽を作り続けることで彼はバンド喪失の悲しみや、本来的に抱えている内省の痛みを浄化しようとしていた。そしてTVアニメ『東京喰種』への楽曲提供を契機にして、ゆっくりと「人と音楽を作る喜び」を取り戻していったという。もちろんバンドマンとしての生理もそこにはあったと思うが、かつて彼がthe cabsの『再生の風景』に込めていた想いと同じく、家族と呼べる人との邂逅を求める気持ちが何よりも強かったのだろう。cinema staffの飯田瑞樹(Vo)、三島想平(Ba)のような古くからの盟友をはじめ、鎌野愛(Vo)をゲストに迎えるなどして、österreichはソロプロジェクトからバンドへと変貌し、音楽と活動を拡張していった。
そして2019年の秋、TK from 凛として時雨のゲストアクトとして初のライブを行なった。これが、österreichがバンドとしての実態と未来を提示したターニングポイントだったのは間違いないだろう。事実、先日リリースされたEP『四肢』は、この日のバンドメンバーを軸にして制作された作品だ。曲ごとにゲストボーカルを迎える柔軟な音楽広場でありながら、高橋と彼の音楽を囲む人々の強固な絆も、ここには刻まれている。三島想平(cinema staff / peelingwards)、飯田瑞規(cinema staff)、鎌野愛、佐藤航(Gecko&Tokage Parade)、GOTO(DALLJUB STEP CLUB)、須原杏に加えて、小林祐介(THE NOVEMBERS)、紺野メイ(あみのず)も参加。高橋の「これはバンドです」という言葉は、「バンド」を型ではなく、連鎖して繋がっていく人と人の関係、あるいは場所そのものだと捉える彼の価値観を表していると言ってもいい。なおかつ、音楽的にも概念的にもバンドの在り方が刷新されている今において、この在り方はむしろジャストだと言えるだろう。高橋が音楽を通して築きたい桃源郷とはなんなのか。österreichが存分に躍動し始めた理由とはどこにあるのか。全部語り尽くした。
本当にパーソナルなものだったらアップする必要なんてないのに、外に向けて発表して……ひとりで音楽を作れば作るほど、人を求めてるっていうことを強烈に自覚していくことになったんです。
―当初はSoundcloudや『東京喰種』への楽曲提供という形で楽曲を発表されていたösterreichですが、昨年の秋にTKさん(TK from 凛として時雨)のゲストアクトとして初めてライブをされて。あのライブでösterreichがバンドとして実態を持って、本格的に始動したと言って間違いないですか。
高橋:うん、俺もそういう感覚を持ってますね。
―では、ライブに出演された方々と新たなゲストとともに『四肢』という作品を作り上げた今、österreichの音楽とはどういうものだと思えてます?
高橋:それこそ最初はSoundcloudに曲を上げるだけのパーソナルなものだったので、österreichという名前にも意味を持たせてなかったんですよ。でも言われた通り、ライブをしたことでösterreichが具現化された実感があったんですね。であれば、その肉体をちゃんと動かしてみようと。その気持ちが『四肢』というタイトルになりました。俺のソロプロジェクトとは謳っていても、好きな人と一緒にライブをしたことでバンド的なメンタリティになったし、そのメンタリティを形にして残すことに意味があるのかなと思って。

österreich(おすとらいひ)
高橋國光(ex. the cabs)のソロプロジェクトとして始動。2015年、ゲストボーカルに鎌野愛(ex. ハイスイノナサ)を迎えてTVアニメ『東京喰種トーキョーグール√A』のオープニングテーマ“無能”を発表し、ゲーム『東京喰種 JAIL』にも主題歌“贅沢な骨”を楽曲提供。『東京喰種トーキョーグール:re』では第2期エンディングテーマとして“楽園の君”を書き下ろす。2019年10月には、TK from 凛として時雨のゲストアクトとして初のライブを行う。2020年6月には、飯田瑞規(cinema staff)、小林祐介(THE NOVEMBERS)、鎌野愛、紺野メイ(あみのず)、佐藤航(Gecko & Tokage Parade)、三島想平(cinema staff / peelingwards)、GOTO(DALLJUB STEP CLUB)、須原杏を迎えて制作された『四肢』をリリースした。
―そもそも、パーソナルなものだった自分の音楽を人とともに鳴らそうと思えたのはどうしてだったんですか。
高橋:これはいろんなところでも話してるんですけどーー今のメンバーに集まってもらう前の頃、石田くん(石田スイ / 『東京喰種』の作者)と話している時に「今の(高橋の)状態を表す言葉って何?」って訊かれて。僕は「幻肢」って答えたんですね。その言葉に自分でも納得したというか……まさに自分を表す言葉だなあと思って。
―「After Sensation」とか「Phantom Pain」と言われるものですよね。たとえば、切断した体の一部分なのに触覚が残っていたり痛みを感じたりするっていう。
高橋:そう、本当はないものなのに、あるように感じて痛いっていう現象。だから『四肢』っていうのは、バンドメンバーが来てくれたことによって、本当はないのに「痛い」と思っていた部分を動かせるようになったっていうことなんです。
österreich『四肢』を聴く(Spotifyを開く)
―つまり、高橋さんが「本当はないのにあると感じていた部分」とは、ひとりではなく人と一緒に音楽を鳴らす実感だったということ?
高橋:そうだと思います。やっぱり俺は元々バンドから始まった人間なので、どうしても誰かと一緒にやることを前提にして音楽が出てきちゃうんですよ(笑)。振り返ると、the cabsが終わってösterreichという名前がない頃も、ひとりで音楽を作り続けてたんです。で、本当にパーソナルなものだったらSoundcloudにアップする必要なんてないのに、結局は外に向けて発表して……ひとりで音楽を作れば作るほど、俺は人を求めてるっていうことを強烈に自覚していくことになったんです。
その矛盾と向き合うことが痛みになってたんだと思うし、それを「幻肢」と表現してたんでしょうね。で、自分の中の矛盾をスッキリさせられたのが、去年の初ライブだったのかもしれない。やっぱり人と一緒にやりたいんだっていうことを受け入れられたといいますか……もちろん、自分の中の痛みと言ってもたくさんあって複合的なものだと思うんですけど。

―実際の音楽と歌を聴いても、生きる上でのいろんな痛みを浄化させるように表現されてきた方だと感じるし、それはthe cabs時代から変わらない部分なんだろうなと思っていて。ただ、この『四肢』を聴いてみると、痛みを痛みのまま表現するだけじゃなく、もっと美しく彩ってもいいんじゃないかっていう発想が強くなっているように感じるんです。
高橋:ああー、はい。
―具体的に言えば、ギターの爆音じゃなく鍵盤とストリングスが主役になっている楽曲が多い点。それに伴ってメロディがしなやかになっている点に感じることなんですけど。自分で何か自覚的なものってあります?
高橋:まさに、俺は自分の中の痛みを音楽にしてきたところが間違いなくあって。でも今は……ちょっと疲れちゃったんだと思うんですよ。たとえばthe cabsは、3人とも脊髄反射で衝動的にやってたバンドで。だけど反射だけで鳴らすと、「痛い」っていう表現をした時に「痛い」が100%自分たちにも飛んできちゃって、衝動を捌き切れない感覚が大きくなっていって。だけど今は、「生きていく上で痛みがあったとして、それを騒ぎ立てる必要があるのか?」って思うようになった気がします。
―それはどうして生まれてきた感覚なんだと思います?
高橋:やっぱり、他者と関わることが増えたからだと思います。周りの人に助けてもらう経験が増えたのは圧倒的に大きいことで。まあ昔も助けてもらってたはずなんだけど、それを見たり実感したりする余裕すらなかったんですよね。で、結局the cabsはなくなって、底なしに落ち込んで……音楽なしで生きていくしかないってところまで一度は行ったんです。
それでも『東京喰種』をはじめとして俺の音楽を必要としてくれる人がいて。一度底まで行ったからこそ、人とともに音楽をやれる喜びを素直に感じられたんですよ。だとしたら、自分の痛みから始まる音楽なのは変わらなくても、ただ痛みを騒ぎ立てるだけじゃない音楽を作りたいと思ったんでしょうね。


俺には家族の風景がなかったから、自分の作る音楽が何年経っても帰れる家であってほしいし、人を求めて音楽を作ってしまうんだと思います。
―「人と鳴らす前提で音楽を作っていた」と話してもらいましたけど、原風景がバンドシーンにあったからという理由だけではなく、そもそもご自身の本質として、人を求めて音楽を歌い鳴らしてきたところがあるのかなと。今のお話を伺って思ったんですが。
高橋:そうなんでしょうね。それに、好きな人たちが集まってくれることで、人にも自分にも赦せることが増えた気がしていて。the cabsの時なんて、とにかく自分の想い通りにならないと気が済まなかったんです。だけど振り返ってみると……そんなに俺ひとりの音楽でもなかったなって思うんですよ。やっぱり自分は人と一緒だから音楽ができてたし、人と複雑に絡まり合うことで曲を作れてたんだなって思えたんです。
the cabs『再生の風景』を聴く(Spotifyを開く)
―はい。
高橋:これは今だから言えることだけど、当時はふたり(元the cabsの首藤義勝と中村一太)に対して劣等感があったんですよ。あのふたりは本当にすごいプレイヤーだったから。でも俺はその劣等感を認めたくなくて、「自分が、自分が」って喚いて独りよがりになってたんです。
だからösterreichでは、その反省というか……これまで自分の居心地の悪さや鬱憤をそのまま音楽化してたのとは違って、人と一緒に存在できる場所を作ろうとしてる気がしていて。まあ、音楽を作るのが辛いのはずっと変わらないんですけど(笑)。

―音楽を作るのが辛いのは、高橋さんにとってはどうしてなんですか。
高橋:それこそ作曲って、技術的にも精神的にも自分のコンプレックスを目の前で見せられてる感じがして。「作曲よりも作詞のほうが辛い」と言う方のほうが多い気がするんですけど、俺は作詞より作曲のほうが辛いんですよ。それに、そもそも俺は音楽に限らず劣等感に苛まれて生きてきた気がするし、その痛みを音楽や歌にしてきたと思う。そういう自分の暗部に向き合うことになるから作曲が辛いのかな。よくわからない自分の暗部が複合して、作曲の瞬間に出てきてしまう感覚があるんですよ。
―劣等感に苛まれてきたこと、拭えない痛みや居心地悪さが音楽のガソリンになってきたと話してもらいましたけど、そういう自分の暗部の背景にあるものって、なんなんだと思います?
高橋:……家族と、家庭だと思います。これはあまり言語化できていなかったことなんですけどね。2、3年前に、姉と10年ぶりくらいに話すことがあって、それまでは「とにかく辛かった」っていうことくらいしか覚えていなかった自分の家の記憶が、悲しいものとして蘇ってきて。

―自分の中のブラックボックスが開いたというか。
高橋:自分の血に対するコンプレックスや劣等感の根底が見えて。これが自分の中にあった感情なんだなって、自覚しちゃったんですよね。自分に流れている血を思うと、常に自分勝手に人を傷つけてしまう予感があって、それが自分の居心地の悪さや帰る場所がない感覚、拭えない痛みの大きな部分を占めている気がする。
―以前、“楽園の君”には<間違えたまま僕ら生まれてきたね><最後のページ書いてあった / 「愛すること」 / 何一つ赦せずに生きていくか / 笑った顔も思い出せずに>という言葉が綴られていて。生まれてきたこと自体を疑ったり、命を赦そうとする言葉が出てきたりするのは、今おっしゃったことが大きいんでしょうか。
高橋:……自分が生きていること自体を疑うところは間違いなくありますね。それが、ただ楽しいだけで音楽ができないって部分に繋がるのかもしれない。音楽を作っているんだけど、音楽を作っているっていうひと言で表せないところがあります。
―突飛な質問に聞こえるかもしれないけど、音楽を作るという以上に、自分を含めたいろんな人が集えて、存在できる場所を作っているっていう感覚はありますか。
高橋:ありますね。もっと言えば、自分が帰れる場所や帰り道を作ってる感覚に近い。それこそthe cabsの『再生の風景』のジャケットには、家が描かれてるじゃないですか。あの時の俺は特に「帰りたい」っていう欲求が強くて。その想いは、今も脈々と続いてるのかもしれないですね。俺には帰る場所も家族の風景もなかったから……家族幻想というか、家への憧れが出てきてしまう。だから自分の作る音楽が何年経っても帰れる場所であってほしいし、人を求めて音楽を作ってしまうんだと思います。

バンドって、固定された型のことではないんですよね。他者との関係性があって初めて成立する場所を、バンドと呼ぶんです。
―場所という話はバンド論にも置き換えられると思っていて。たとえばギターとベースとドラムとボーカルーーっていう典型的な「バンド」の型は、2000年代後半には編成的にも概念的にも更新されたと思うんですね。
高橋:うん、うん。
―その後のバンドの概念として、音楽を拠り所にしていろんな人が出入りできて、自由に繋がりを拡張していける場所というのが重要だと思っていて。そういう意味で、バンド音楽の更新を体現しているプロジェクトのひとつがösterreichだと思うんです。
高橋:そうなんですよね、僕がösterreichをバンドだと言い続けているのもそこで。バンドって、固定された型のことではないんですよね。他者との関係性があって初めて成立する場所をバンドと呼ぶんだと気づいてきたんですよ。自分は何かと関与して生きているんだと知れるのがバンドなんです。

―そうですよね。
高橋:で、これはちょっと違う話かもしれないけど……そうして大事な人たちと混ざることを学べば学ぶほど、俺は「自分が機械なのか動物なのか」っていうことを考えちゃうんですよ。
―というと?
高橋:「楽しい」にせよ「悲しい」にせよ、100%ひとつの感情だけに従順になってしまうことはあまりに動物的すぎて、いろんな感情を零して、人を傷つけてしまう気がするんです。一方で、感情を介さずにただ決められた型を繰り返す生活じゃあ、機械と変わらない。自分の感情に従順になり過ぎることも、ただ感情を無視してしまうことも、俺は怖いんですよ。自分勝手になって人を傷つけないように、でも確かに人間として生きていると言えるように、動物にも機械にも寄りたくないなっていうのが今のテーマなんです。
―逆に言うと、いろんな感情の間で揺れ続けることや、一瞬の感情に対して慎重であることが、自分を人間たらしめると。
高橋:そう。たとえば大多数が「この絵は綺麗だ」って言っても、それが本当に「綺麗」で表せるものなのか、俺はわからないと思ってしまうんですよ。絵に限らず、いろんな色や線が複雑に織り混ざって存在しているものばかりだと思うから。
―その感覚は、音楽にストレートに出てますよね。ABサビという様式はあってもオケの構造が全箇所違うし、拍子もリズムも定型がない。そういう複雑さや一種の混沌を一発で繋ぎ止めていくのが高橋さんのメロディの美しさで、そこが素晴らしいと思うんですけど。
高橋:まあ、拍子のいびつさはしょうがないとしか言いようがないんですけど(笑)。だって気持ちよくギターを弾いて曲を作っただけなのに、ドラムを乗せたら拍子が変っていうパターンばっかりだから。“swandivemori”なんかはその極地ですね。メンバーに教えてもらいましたから、「ここは○拍子だね!」って。
―ははははは。
高橋:だから言ってもらったように、リズムよりもメロディに執着があるのは間違いなくて。やっぱり歌が美しくないと意味がないと思っちゃうんですよ。俺は海外のハードコアやemoに憧れてきたけど、それこそ血を全部入れ替えるくらいのことをしないと、本当の意味ではオリジナルのemoにはなれないんです。
―ただ、Penfoldへの愛が爆発している“きみを連れていく”を象徴にして、90’s emoへの憧憬はこの音楽の強い個性になってますよね。
高橋:だからこそ憧れで終わらないように、J-POPが全盛だった頃に音楽を聴き始めた世代として、歌とメロディを大事にするしかないんですよね。でも逆に言えば、自分の立脚点は歌にあると自覚できているから自由に音楽を作れるとも言えるわけで。なんなら、メロディだけで全部を語り尽くせていないと嫌だって思うんですよ。
―人を求める気持ちが、人を選ばないメロディへの執着に表れていると言えるかもしれないですよね。
高橋:それは間違いなくあると思います。だからメロディを作るのに比べて、歌詞はストレスがないんですよ。

俺は映画の登場人物じゃないっていう感覚がある。世界に出てこない存在というか……帰る場所や愛を知らないっていう無力感が大きくて。
―逆に言うと、メロディを翻訳して映すのが歌詞である、みたいな感覚もありますか。
高橋:ああ、メロディを際立たせるために歌詞があるっていう感覚はありますね。起承転結があって、場面転換があって、ストーリーのあるもの……たとえば映画に憧れがあるんですけど、メロディを映画の物語にしながら、歌詞で「ここが俺にとってグッとくる場面なんですよ」って見せているイメージに近い。
―まさに高橋さんの歌詞には<映画>という言葉がよく出てくるし、“swandaivemori”には<「愛を歌うな、誰もそれに触るな」>、“楽園の君”では<「愛すること、叶わなくとも」>というラインがあって。愛や優しさをスクリーンの奥の触れられないものとして描かれたり、ご自身が映画の登場人物になるんじゃなく、愛や家族への憧れを描いた映画をただ眺めるだけの歌になっているところが特徴的だと感じたんですが。
高橋:確かに。そうですね。
―自分で描いた物語の登場人物になるんじゃなく傍観している感覚や、物語への憧れとはどういうものなんですか。
高橋:俺は映画の登場人物じゃないっていう感覚が強烈にあるんですよ。やっぱり目の前の世界を見ると、「俺は帰る場所や愛を知らない」っていう無力感が大きくて。だから、自分には理解し得ないアンコントロールな物語として世界を見てると思うし、それが<映画>という言葉になるのかもしれない。逆に言えば、自分の物語ではなく憧れの物語だから純粋に美しいと思えるのかもしれないし。それが、映画や物語に惹かれる理由なのかな。……自分が介入できない不条理さがあるものだからこそ、神聖なものとして見てるんだと思います。

意味とかじゃない、どう伝えたいとかじゃない。ただそこに存在するだけで肯定される無垢なものの象徴が音楽なんです。そういうものを見たいのかもしれないし、自分がそうなりたいのかもしれない。
―“swandivemori”には<映画は続いていく、また誰か殺して>というラインがあり、“ずっととおくえ”では<人の死なない話を>と綴られている。言ってみれば死も不条理の究極形なわけですけど、ここには自分の何が表れているんだと思いますか。
高橋:あまりに無力感がいき過ぎると、ふと「今も誰かが死んでるのに、なぜ俺は生きてるんだろう?」って思うことがあるんです。だけど、いつまでも死んでほしくない人も現実的にいるじゃないですか。人が死んでいくところを遠巻きに眺めるしかない現実もあるけど、この人だけ生きていてほしいって思う存在はいて……ああ、そうか。死んでほしくないと思える人が周りに増えたっていうことなんだろうな。

―そうですよね。愛には触れられないと言われましたけど、愛をどう受け取るのかよりも、まず自分が「死んでほしくない」と思う人を愛そうとしているっていう話だと感じたんですが。
高橋:俺は、自分が死ぬっていうことに対する恐怖感はなくて。でも、みんなは登場人物だから死なないでほしい。「どうかこの人たちだけは」って懇願する気持ちは確かにありますね。
俺は自分の感情ひとつにも名前をつけられないし、愛してもらっても、これが自分だと胸を張れない。それじゃあ登場人物にはなれないんですよ。でも、自分以外の誰かが入ってくるから予想もできない物語が生まれて、自分が存在できている。それだけは実感してきて。まあ……表に立って作曲をやって、しかも好きな人たちに集まってもらってるのに「僕は登場人物じゃない」なんて言っちゃう卑屈さも相当だと思うんだけど(笑)。
―確かに(笑)。
高橋:ただ、これまでは劣等感に苛まれる自分のことを赦したい、赦されたいっていう求め方をしてきたけど、その手前にもっとやることがあったんですよね。どんなに「家を作りたい」「帰り道を作りたい」と言っても、周りの人がいてくれなければ、居場所すら具現化できないから。まず必要だったのは、愛を素直に授受できる関係性で。だとしたら、僕が登場人物じゃなかったとしても、せめて愛することはしたいと思うようになったのかもしれないですね。
―今、<愛すること>と歌われている通りのご自身になれると思えますか。
高橋:自分がただ好きでいた人たちがスクリーンから飛び出してこちらに歩み寄ってきてくれている感覚があるなら……そうですね、愛の扱い方がわからないって言ってるだけじゃ嫌だと思う。自分から関与して、人を知っていくことが大事だと思います。


―飯田さん、鎌野さん、紺野さん、小林さん。高橋さんがメロディを手渡したボーカリストたちは、総じて母性と神秘性とイノセントさを感じさせる歌を持っている方々ばかりで、今おっしゃった温かな気持ちを鮮明に表現されている歌声だと思うし、それはやっぱり高橋さん自身が求めた声なんじゃないかと思います。
高橋:確かに……声への執着があるのは言われて初めて気づきました。やっぱり歌って、音楽に触れて一番最初に入ってくるものじゃないですか。たとえば赤ちゃんも、子守唄に触れて音楽を知るわけで。だから、人に一番最初に届く歌にだけは一切の痛みを求めないんでしょうね。the cabsも音像的には激しいけど、声はただただ優しかったから。赤ちゃんが初めて聴くような歌にしたいっていう気持ちがあるのか、わからないんですけど。
―これまでの歌詞で言うと、<子宮>という言葉も印象的で。自分の人生を疑い続けてきたとおっしゃる高橋さんとして、歌の中でならもう一度生まれることができるんじゃないか、母のように優しい歌を作れば自分自身がイノセントな存在になれるんじゃないか、みたいな気持ちもあるんでしょうか。
高橋:上手く言えないんですけど……「ただそこに在るだけでいいんじゃないか?」って思うことがあるんですよ。そこに在るだけで赦されてもいいじゃないかって。
―それは自分自身のことでもある?
高橋:そうだと思います。それに、そこに在るだけでいいものの象徴が、俺にとっては音楽なんだと思います。意味とかじゃない、どう伝えたいとかじゃない。ただそこに存在するだけで肯定される無垢なもの。自分がそうなりたいのかもしれないし、そういうものを見たいと思っているのかもしれないんですけど。存在することを赦される家を作るっていうのは、まさにそういうことだと思うし。
―そうですよね。
高橋:まあ、これだけ自分のことを話しておきながら、全部無意識な気もするんですけどね(笑)。結局のところ、原始人が寒い時に自然と火をくべてるようなプリミティブな行為に近いというか。それこそ拍子の話がそうですけど、作為的な意識がマジでないから。
―本当に、ただそこに存在するだけの旋律と音楽というか。今日の話を聞いてひとつ思うんですけど、特にコロナ以降の時代になって顕在化したのは、どこへ向かって行くのか以前に、どこに帰ることで自分は存在していられるのかを模索する意識だと思うんですよ。生きて存在し続けるための居場所がどこなのかを見つめ直すという意味で、帰り道が何より能動的な生きる道になることもあるんじゃないかって。
高橋:うん。そこには「帰る」も「還る」もあると思うんですけど、本当にそうだと思う。たとえばフェスに出る、テレビに出るーーみたいに脈々と受け継がれてきたバンドの成功ルートが破綻して久しいと思うんですけど、もっと自由に、自分たちの場所を作ることが大事だと思うんですよね。で、僕らの音楽はどこに存在してもいいと思ってるし、この音楽自体が場所になれればいいなって本当に思うんです。

- リリース情報
-

- österreich
『四肢』(CD) -
2020年8月中旬より公式通販および一部CDショップにて販売予定
価格:2,200円(税込)
PMFL-00211. swandivemori
2. 映画
3. きみを連れてゆく
4. ずっととおくえ(CD盤先行収録曲)
5. 動物寓意譚
- österreich
『四肢』 -
2020年6月26日(金)配信
1. swandivemori
2. 映画
3. きみを連れてゆく
4. 動物寓意譚
- österreich
- プロフィール
-
- österreich (おすとらいひ)
-
高橋國光(ex. the cabs)のソロプロジェクトとして始動。2015年、ゲストボーカルに鎌野愛(ex. ハイスイノナサ)を迎えてTVアニメ『東京喰種トーキョーグール√A』のオープニングテーマ“無能”を発表し、ゲーム『東京喰種 JAIL』にも主題歌“贅沢な骨”を楽曲提供。『東京喰種トーキョーグール:re』では第2期エンディングテーマとして“楽園の君”を書き下ろす。2019年10月には、TK from 凛として時雨のゲストアクトとして初のライブを行う。2020年6月には、飯田瑞規(cinema staff)、小林祐介(THE NOVEMBERS)、鎌野愛、紺野メイ(あみのず)、佐藤航(Gecko & Tokage Parade)、三島想平(cinema staff / peelingwards)、GOTO(DALLJUB STEP CLUB)、須原杏を迎えて制作された『四肢』をリリース。
- フィードバック 79
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-