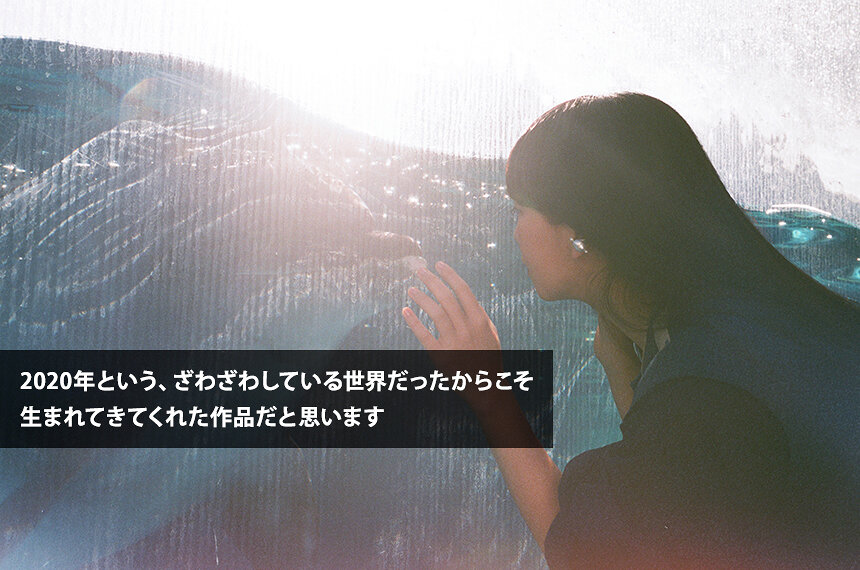青葉市子『アダンの風』は沖縄の地で書かれた生命をめぐる物語が元になっており、「架空の映画のためのサウンドトラック」として2020年12月に発表された。その物語をここでは詳しく説明はしないが、神話のように詩的で、皮膚を突き破って生命の奥底に触れるような生々しさを私は感じた、ということだけ記しておこう。
作曲家の梅林太郎らとともに紡がれた『アダンの風』の歌たちには、生まれては死んでいく生命の根源を見つめ、そして日本語で歌われる歌のアイデンティティを編み直すかのような不思議な「響き」がある。ジャンルも、国籍も、ジェンダーも、あらゆるラベルが剥がれた姿で、青葉市子、梅林太郎、そしてエンジニアの葛西敏彦、写真家の小林光大の4人がお互いの境界線を失い、ひとつに溶け合ってそのまま歌になるような……話を聞く限り、非常に稀な工程を経て『アダンの風』は制作されている。本作はいかにして形作られ、どんなものを捉えようとしていたのか。その深淵に触れるべく、青葉市子と梅林太郎に話を聞いた。

音楽家。1990年1月28日生まれ。2010年に1stアルバム『剃刀乙女』を発表以降、これまでに6枚のソロアルバムをリリース。うたとクラシックギターをたずさえ、日本各地、世界各国で音楽を奏でる。弾き語りの傍ら、ナレーションやCM、舞台音楽の制作、芸術祭でのインスタレーション作品発表など、さまざまなフィールドで創作を行う。活動10周年を迎えた2020年、自主レーベル「hermine」(エルミン)を設立。体温の宿った幻想世界を描き続けている。12月2日、「架空の映画のためのサウンドトラック」として、最新作『アダンの風』を発表した。
ギターと声の響きの奥に、様々な音の気配が漂う青葉市子の歌
―はじめに、梅林さんは青葉さんをどういう音楽家と見ていらっしゃいましたか?
梅林:市子ちゃんにも伝えたのですが、「小が大を兼ねて居る」という印象を持っています。弾き語りでやっているけど、歌声とギター、一つひとつの音が巧みにオーケストレーションされていて、そこに的確な言葉も乗って世界観を作り上げているという印象です。
―シンプルなギターと歌のバックに壮大な音世界を感じさせる。
梅林:そうですね。僕の場合、基本的に演奏家の方にお願いすることが多いので、そのスタンスと逆の印象です。
青葉:梅先生とは『アダンの風』を作る前に、配信シングル“守り哥”の作曲と編曲でご一緒していただいたのですが、「じつはギターと歌の後ろには、ここにはオーボエ、ここにはファゴットがいて、ここから弦の群がきて……」というように、最終的なアウトプットは弾き語りでも、脳内にはたくさんの楽器が存在していることをお話ししていました。
そうして何度も対話を重ねていく中で、梅先生の深い理解があり、自分の中ではぼやけて霞んでいた部分をより明確に音の粒として導いていただいたと思っています。とても豊かな作業でした。
梅林:エンジニアの葛西くん(葛西敏彦)が常々「話そう話そう」と言っていて、制作陣同士の対話がこのアルバムの制作過程では特に大事で、その積み重ねが作品に繋がっていると思っています。
青葉:本当に、役割分担がはっきりしていたプロジェクトだったなと思っています。無理をしなくていいというか、私たち以外も、葛西さんも小林光大さん(当記事の撮影も行った写真家)もみんなが自分の一番得意なことを突き詰めていけるバランスだったのでとっても楽しくて。同じ船に乗っている船員たちがそれぞれの舵を取ってるみたいな感覚でした。

作曲家。2012年よりmilkとしてソロ活動を始める。「Rallye Label」より1stアルバム『greeting for the sleeping seeds』をリリース。現在2ndアルバムを制作しつつ、楽曲提供、映画音楽、アニメ音楽、CM音楽と幅広いジャンルにおいて国内外、数多くのアーティストと作品を発表している。
―シングルの時点でアルバムもご一緒することは決まっていたんですか?
梅林:一度ピントを合わせる意味でも1曲作ってみて、それがよければきちんとアルバムを一緒に考えようみたいな感じだった気がします。
青葉:ちょうど去年の今頃ですよね、“守り哥”を作ってたの(取材は2020年12月に実施)。
―今回、映画のような架空の物語のプロットが存在していますよね。『アダンの風』は「架空の映画のためのサウンドトラック」というコンセプトですが、そういった構想は“守り哥”の時点で青葉さんの中にあったのですか?
青葉:“守り哥”のときはまだ、航海の始まるワンシーンがイメージできているだけの状態で、物語としての全体像は、沖縄に行ってから一気に膨らみました。
青葉市子“守り哥”を聴く(Apple Musicはこちら)
青葉市子の脳内の音世界を形にするために、全ての根幹となる物語が沖縄で書かれた
―そもそもどうして沖縄に行かれたのでしょう?
青葉:2019年は演奏の機会も多く、海外ツアーがあったり、『Reborn-Art Festival』という芸術祭では石巻に数か月滞在していたりと怒涛の暮らしをしていたので、静かに重心を低くしたいという考えがありました。
南は冬でも暖かいですから、大気と皮膚の温度ができるだけ近い場所に身を置くだけで、強ばらなくても滲み出てくるものがあるんじゃないか、と。鯨も冬には南下するので、一緒に移動している感覚もありました。あとは『ユリイカ』(2020年3月号 特集=青葉市子-『剃刀乙女』『檻髪』『うたびこ』『0』『マホロボシヤ』『qp』…青葉市子の10年-)の巻頭撮影も兼ねてです。
―沖縄は沖縄本島に行かれたのですか?
青葉:本島を拠点にして、久高島や慶良間諸島の座間味島含め、2週間ほど滞在していました。2020年、1月ですね。梅先生からは「プロットや文字で共有できるものがあるとより作曲しやすい」と聞いていたので、沖縄で書き始められたらいいなと思っていました。

―プロットは梅林さんからの提案だったんですね。どういう意図があっての提案だったんですか?
梅林:市子ちゃんは色々な世界観を舞台芸術のように表現できるから、それをプロットにしてリブレット(オペラやミュージカルなどの台本)のようにしたら市子ちゃんが志向していた、架空のサウンドトラックのような作品が作れるんじゃないかなと思ったんです。誰かが「ここをこうしたほうがいい」って言うんじゃなくて、市子ちゃんの頭で鳴っているものを実際の音に置き換えたら素晴らしい世界ができるだろうから。
―青葉さんの頭にあるものを音楽に変換していくと。
梅林:プロットを共有することで、音響監督は葛西くん、ビジュアルは光大くんというふうにそれぞれの持ち場が明確になりますし、プロジェクト全体としてもそうするのがいいなと。
―そのプロットはスラスラ出てきたものなんでしょうか?
青葉:いいえ、なかなか書けずにいる中、滞在後半で座間味島に渡ったとき、初めてアダンの実を認識したんですよね。沖縄では珍しくない植物なので、ずっと見てきたはずなのですが、急にフォーカスが合ったような感じがありました。まだ何も書き始めていない状態でしたが、「タイトルは『アダンの風』になるような気がする」と、初めてアダンを認識したその場で口にした覚えがあります。

青葉:そのあとに本島に戻ってきて、居酒屋さんで海ぶどうを食べようとお箸ですくい上げたとき、光に透けた小さな粒たちが一気に身体の中へと入ってくるイメージが湧き起こりました。まるで、一粒一粒がプランクトンのように発光しているようなイメージで、そのキラキラした存在を「クリーチャー」と名付けて、何枚も写真を撮りました。物語の核となるキーワードが急に揃ったような日でしたね。
―それは同じ日に、時を同じくして青葉さんの中でぎゅっと凝縮したというか。
青葉:そうですね。そしてそのとき、ちゃぶ台の上の食器の間にノートを広げて書き始めたのが、「その島には、言葉がありませんでした」という一文でした。そこからは早かったです、スラスラと。
『アダンの風』という大作誕生の原初の感覚ーー頭上で風に吹かれるアダンの実をかじり、日毎の太陽の照りに触れ、踏みしめる砂やサンゴの擦れる音に耳を澄ませる

―私、生まれが奄美でアダンというのは嫌というほど見てきましたけど、それがタイトルになった作品を知ったのは初めてです(笑)。特別な植物でもないですし、食べられないし、匂いもきついですから。
青葉:匂いしますよね。私、かじりましたよ。
―どうでした?
青葉:ちょっと薄い柿みたいな味。ほんとにほんのり甘い感じでした。昔、神様のお供え物の料理とかに使われていたんですよね。
―でもあんまり食べないですよ(笑)。
青葉:ね。奄美大島と加計呂麻にも行きました、二度。3月と9月に。
―“Porcelain”のビデオは奄美ですよね?
青葉:奄美です。
―映像を拝見して、沖縄の海の色じゃないと思いました。
青葉:嬉しい感想です。
―沖縄の空気と奄美の空気は色が違いますよね。海も島ごとに全然違う色がする。どっちかというと沖縄のほうが奄美より赤が多い。奄美はどっちかというと緑が基調で若干炭っぽいくすんだ色をしてる。それより北に行くともうちょっと土っぽい色、種子島とか屋久島まで行くともうあそこは本土の色ですね。
青葉:うんうんうん。島の人ほどはわからないですが、奄美と沖縄だけじゃなくて、石垣島にも行っていたので、なんとなくそれぞれの違いはわかります。何日かその島に滞在して、ひとつの場所でじっと制作していると、定点観測のように「この太陽の照りだと葉っぱはこういう色になるのか」と、ちょっとずつわかってくるんですよね。突き詰めて作品を作るなら、1年くらいは滞在しないとわからないだろうなと思いながら渋々帰ってきました。名残惜しい……。
―土地土地からの音楽的なインスピレーションもあるんですか?
青葉:あります。たとえばサンゴの浜を歩いていたら、シャリシャリという音が聞こえていて、それを音階に当てはめてメロディを書いたり。サンゴたちが擦れることで生まれた微かな響きも、ちゃんと音楽の栄養分になります。私たちは食べたご飯でできてるじゃないですか。だから食べてきたものが音楽になるんだろうなと思いますし、それと同じようなところでしょうか。
青葉市子“Sagu Palmʼs Song”を聴く(Apple Musicはこちら)
沖縄や奄美をはじめとする島々の記録を手がかりに、生命の根源に対する感覚にピントを合わせていく
―佐喜眞興英さん(沖縄県宜野湾市出身の民俗学者)の『シマの話』(1925年、郷土研究社)が“血の風”の参考文献としてクレジットされていますが、沖縄や奄美に関する資料を集めてらっしゃったんですか。
青葉:はい。沖縄や奄美だけじゃなく、様々な離島で行われてるお祭りのこと、島の面積や人口や歴史、海の生物、プランクトンのことなども調べていました。あとは混血と純血の違いを、植物から学んだり。
―プロットも近親交配で純血を守ってきた集落に生まれた少女の物語ですよね。
青葉:はい。ノロさんやユタさんに関しては衣装を作ってくださった横山キミさんがリサーチしてくれました(ノロは琉球神道における女性の祭司、ユタは沖縄県と鹿児島県奄美群島の民間霊媒師=シャーマン)。その資料の中に(“血の風”の歌詞で参照した)「チヨ チヨ」から始まるおまじないが載っていたんですね。
青葉市子“血の風”を聴く(Apple Musicはこちら)
―資料を集めたり、目を通すだけでも大変だったと思うのですが、その動機についてもう少し詳しくお話いただけますでしょうか。
青葉:ただひたすらに焦点がそこに合っているーーそこに焦点を合わせてるとき、とても豊かな時間が流れてることを感じるんです。
もう体は離れてしまったけれどかつて繋がっていた母親のこと、その母親とまた体が繋がっていたおばあちゃんのこと……そうやってずーっと辿っていくとプランクトンに還っていくし、私たちが海に漂っていたときの記憶にまで巡り巡っていけるんですよね。ノロさんやユタさんは人が作った文化ですけど、もっと前の原子の感覚に立ち返ろうとしていたのだと思います。
―それは『アダンの風』という作品を作りたかったから、というわけではない?
青葉:必然的にでしょうか。時代がそうさせているのかもしれないですし。
―青葉さんの生きてきたバイオリズムの中でたまたまそういう時期だった?
青葉:50年後くらいにそういうこと言ってるかもしれない(笑)。
―ある種、根源的なものと言いますか、そういったところに向かおうとしていたわけですね。
梅林:今回僕は沖縄に行っていませんが、どうして市子ちゃんと認識を共有できたかというと、「万物に生が宿っていて、それが織りなす秩序が自然のありとあらゆる場所に存在している」という捉え方をして制作に取り組んでいたからと思っています。
青葉:世界において「私たちが今生きていること」っていう、この根元に流れているエネルギーみたいなものの解釈が近いのだと思います。

―その解釈をもう少し噛み砕いてお話しいただけますか?
青葉:たとえば料理好きな人が、目の前にある卵がここに来るまでの歴史を考えて料理をするのと同じことです。ここの土にはこういう微生物がいるからこのニンジンはこう育つのか、じゃあこのニンジンにはこれと合わせてあげようと考えたり、これだけ油に熱して時間をかけてあげようとか考えるようなことです。
そういう根底に流れる気の回し方というか、気の使い方です。気を使うというのは、他人に配慮することではなくて、本当に気の粒子を使うこと。それはどんなアウトプットしている人でも、同じものだと思っています。
楽曲制作段階からエンジニアを交え、彼らは説明困難なほどの不思議な時間を過ごすことになった
―前提となる感覚を共有しつつ、プロットや架空の映画のサウンドトラックという構想を踏まえて、どういうふうに音楽を作っていかれたのでしょうか?
梅林:プロットは神話に近いものがあったので、既存の神話の世界観と重複しないよう、「どこの国の音楽だろう?」という印象を可能な限り出したいと考えていました。その上でプロットを元に「このシーンにこういう音楽はどうですか?」と、市子ちゃんに聴いてもらってやりとりを重ねて作っていく感じでした。
青葉市子“Porcelain”を聴く(Apple Musicはこちら)
―梅林さんからの音源に対して、青葉さんは音楽的にはどんなリアクションを?
青葉:シンセで書いてくださっていたメロディ部分を、ハミングや自作語に置き換えて戻したりしていました。
梅林:市子ちゃんは目の前に広がる色々な事象を、音と置き換えています。たとえば「この楽器はカモメの音」と言うように、聞こえてる音を提案してもらってアレンジに落とし込んでいったりもしました。
―相互作用的に。
梅林:そうです。「クリーチャーはこういう雰囲気の生き物で」といったことを話し合いながら音にして、プロットと照らし合わせて短い尺のスケッチを作りました。それを並べたり、順番変えたり、起承転結を考えて「これは違う」となったり、だからボツになった曲もあります。
―どんな基準で「これは違う」となったのですか?
青葉:地図を広げるみたいに、葛西さんのスタジオの壁に大きな紙を2枚貼らせていただいて。そこに、曲名や曲のイメージなどを書き込んだ付箋を貼って、ピッタリと物語にはまるものを残していきました。
―ボツになったのはその地図からこぼれたものだと。おもしろい作り方ですね。制作の段階から葛西さんも含めたチームだったんですね。
梅林:核にあるのは市子ちゃんの声ということを念頭に、みんなできちんと意見を出し合いました。バンドのように制作できたらいいなと考えていたんです。

―青葉さんとしては、音楽面はなるべく委ねようという感じだったんですか?
青葉:何て言えばいいんでしょう、難しいな。
梅林:難しいですよね。どこからどこまでを作ったみたいなのがなくて。市子ちゃんの一声をきっかけにフレーズができたり、葛西くんの音響に導かれて作曲することもあるし、光大くんの写真にインスピレーションを受けて楽曲の芽が生まれたり、具体的にどうかと聞かれると難しいラインですね。そもそも市子ちゃんの言葉やプロットがなかったら作れていなかったので、どう定義したらいいかわからないですね。
「怒ってもいいし、泣いてもいいし、連絡が取れなくなってもいい」(青葉)
―とはいえ、采配はするんですよね?
梅林:ディレクションはその状況で適任の人がやるのですが、ただ、かなり深いところでやっていたので、自分でもどうやってできてたのか把握できてないんです。冷静になって聴くと「できあがった」って思うんですけど、どういう設計で、っていうふうには全く考えてなくて。
青葉:たとえば、目の前に海が広がっているとして、私と梅先生、葛西さんと小林光大さんの、核となる4人が海女さんみたいに身ひとつで何かを取りに行くんですね。でもドボーンって海に入った瞬間、体がなくなっているような状況で、みんながプランクトンの群れみたいになっちゃうんです。その群れが潜っていって、果実や何か音のかけら、物語のかけらを拾ってくる。陸に上がってきたときには4人とも人の姿に戻って「取れたー!」と言ってて。だから誰の仕事なのかわからない。
―(笑)。
青葉:上がってきたときは人間になっているから、一応あなたと私、というように別れてはいるけれどってことが、音楽だけではなくて音響や写真やビジュアルも全て混ざり合っていたんです。スタッフも同じような状況で、みんな海になっていました。

―そのレコーディング期間はどれくらい続いたんですか?
青葉:正式なレコーディング期間は7月くらいから始まって10月19日の朝まで。
―あー、終わりはもう明確にわかっているんですね。
青葉:マスタリング日の朝までです。
―マスタリングって最終調整ですよね? 変なことをおっしゃってますけど(笑)。
青葉:葛西さんもとても柔軟に動いてくださって、最初から最後まで一緒に作ってくださいました。一般的なレコーディングだと、録音をして、それをミックスしてマスタリングに持っていくのですが、今回は、作曲する、レコーディングする、ミックスするという工程が同じ列で進んでいったんです。
イレギュラーなやり方だと思いますが、そうでないとこの音楽は生まれなかった。徹夜で、みんなで「あと何時間後にマスタリング!」って言いながら新しい音をレコーディングしました。マスタリングはオノ セイゲンさんにお願いしていて、セイゲンさんも「マスタリングの日の朝に音源があればいいよ」という感じだったので、それもすごいなと思いましたけど。
―(笑)。すごいですね。フィールドレコーディングの音なども加えて音楽を作るというのは、エンジニアの葛西さんも含めて大変だっただろうなと想像していましたが……制作上の境目があまりないようなレコーディングですと、事前に想定していないものに即興的に試したりもしました?
青葉:そういうのはたくさんしてます。決めごとだけではやっぱり楽しくないので。
青葉市子“帆衣”を聴く(Apple Musicはこちら)
青葉:軸となる決めごとは必要ですけど、プラスである「遊び」が音楽の彩りになりますし、聴く人の想像力を掻き立てると思います。私たちも物語の中でクリーチャーであることを忘れない、ということが制作においてとっても大事なポイントでした。だから怒ってもいいし、泣いてもいいし、連絡が取れなくなってもいいし。
―連絡が取れないのはさすがに困りませんか?
青葉:いやいや、もう全員が信じて待つモードなんですよ。誰かがそういうふうになっちゃったら「これは物語がそうさせてるからしょうがない」と割り切りました。一人ひとりほんとに禊タイムみたいなのが回ってきたんです。おもしろい(笑)。
―(笑)。
青葉:私もありました。みんなそれぞれ。怒っちゃう人がいたり。
―梅林さんはありました?
梅林:ありましたよ(笑)。それはもう……もちろん。ないとできないです。
青葉:全部の感情や自分の持ってるかけらみたいなものーートラウマや自分の嫌な部分まで全部ひっくり返してみんなで見せ合う中で「こことここは繋がるね」というようなことまでできた間柄なんです。本当にもう家族ってと言ってもいいくらいのチームだったと思います。
―濃密というか、不思議な時間ですね。あくまで他者ですけど、そこまでお互いの境界線を越えあってる感覚の中で作っていったと。
青葉:本当にそういうことです。海に潜ってそれぞれがプランクトンになって混ざり合うような、そんな日々でした。

様々な土地に由来する楽器の「響き」に着目し、『アダンの風』を紐解く
―今回、音響設計としても大変なことをやられてると思います。ストリングスや打楽器、笛の関係もいくつか取り入れて、フィールドレコーディング含めていろんな音をひとつの作品空間に落とし込むのはかなり冒険的だったと思うのですが。
梅林:市子ちゃんと作ったスケッチ、和声感、メロディ作りが骨子としてあり、それをすぐ形にする環境がそうさせていると思います。録音も長期に渡るものだったので、全体を見渡しつつ、何かあればすぐに改変できるように葛西くんがプロジェクトをまとめてくれていました。それと何かアイデアがあったらすぐに試せるように目的に沿った環境を適宜セッティングをしてくれていたり。
―楽器の音そのものよりも、もっと抽象的なハーモニーが出発地点になった?
梅林:基本、楽器ひとつのハーモニーで世界観を演出できるようにしたかったという思いがありました。
―響きに着目していくつか具体的に聞きたいのですが、“Pilgrimage”はちょっとケルトっぽいイメージがしました。
梅林:もともと語り部のような人が弦楽器を弾きながら物語のはじまりを演出する、というようなイメージがありました。弾き語りのような形で作品の導入部となる曲が欲しいなと思っていたのですが、ケルトをイメージして作ったわけでは全然なくて。実際に使っているのはチャランゴという南米の楽器なんですよ。
―楽器の選択は直感的なものなんですかね?
梅林:先ほど話した、「どこの国の音楽だろう?」という印象の響きを調性音楽の範疇でどうやって出したらいいかはすごく考えました。聴いたことのない響きを探しながらチャランゴを使っています。
青葉市子“Pilgrimage”を聴く(Apple Musicはこちら)
―“Easter Lily”で使われてる楽器はチェレスタ(アップライトピアノのような形態の楽器で、フェルト巻きのハンマーにより、共鳴箱付きの金属音板を叩いて高音域を発生させる楽器)ですかね?
梅林:そうですね。もともとアルバム全体のことを考えているときに、チェレスタは使いたいなと考えていたんです。
―それは作品や物語の持つ響きを想像したときに?
梅林:声、世界観に合う楽器だなという思いがあったので使いました。市子ちゃんが自分用の鍵盤でローズ(Rhodes Pianoというエレクトリックピアノのこと)の音色をよく使っていて、そのイメージがあったのと、「Easter Lily(テッポウユリ)」の写真を市子ちゃんに見せてもらったこともそうだし、「沖縄」と「ガムラン」もヒントになっています。
青葉市子“Easter Lily”を聴く(Apple Musicはこちら)
―それで言うと、“Parfum d'étoiles”のピアノはプリペアドしてる(ピアノの弦に金属やゴムなどを載せたり、挟んだりし、音色を打楽器的な響きに変える行為のこと)わけではない? ちょっとサティ(エリック・サティ、19世紀末に登場したフランスの作曲家で20世紀の音楽に大きな影響を与えたといわれる)っぽい感じですよね。
梅林:この曲のピアノはフェルトをかけて弾いています。フェルトに関しては先ほどのチェレスタと同じように、声、世界観に近かったので採用しました。もともと管弦楽用に作曲していたのですが、“Porcelain”が管弦楽アレンジだったので全体のバランスを見てピアノアレンジにしました。ハミングする市子ちゃんの声に関しても葛西くんが面白い録音方法を試してくれたり、結果としてとてもよい形になりました。
青葉市子“Parfum d'étoiles”を聴く(Apple Musicはこちら)
時代のざわめきの向こう側で、青葉市子が見つけたもの
―歌ではない部分、言葉ではない声も含めた響きにすごく気を遣った作品だと思いましたね。そういう側面で見ても、青葉さんの新機軸のように感じました。
青葉:そうですね。でも、弾き語りでしてきたことと変わってはいないんです。もともと頭の中にあった音像に対して、身がひとつだったから歌とギターで表現していました。『アダンの風』ではこれだけたくさんの人が関わって一緒に取り組んでくださったので、本当にやりたかったことや自分の一番底のほうで響いていたものが出しやすくなってたんです。
歌の本質ーー赤ちゃんが生まれたときに泣くような、動物が何かに触れてフって声を出すところに立ち返れたことで出てきた言葉やハミング、まだ存在しないどこかの言語になる前の響きを取り出せた感覚はあります。

―様々な響きを取り込んでいることが『アダンの風』という作品を独自のものにしていますよね。しかもそれを実験音楽ではなく、ポピュラー音楽の領域でやっているのがおもしろい。
梅林:今は自分の作品においてジャンルという捉え方は必要ないと考えていますし、今回のテーマに適うことを考えたら、ジャンルを作らないことが一番大事だなと思ったんです。もちろん全部が全部そういうわけではないんですけど、ジャンル分けしてラベルを貼るってことが僕は得意ではないなと感じています。
青葉:それは私の中にはありました。さっきのプランクトンの話じゃないですけど、そこまで戻ると、もうどこの国の人とか、どの音楽とか、男か女とかそういうジェンダーのこととかも全部なくなっていくんですよね。もちろん日本語を扱ってはいるんですけど、私たちがつけてきたラベルが、鱗が剥がれるみたいにバラバラバラってなくなって最初の発光生物に戻るーーそれはこの作品作りの根底にあったことだから。
―わかるような気がしますね。それが作品性を形作っているように思います。
青葉:嬉しい。自己表現ではなく、『アダンの風』がみんなの作品になればいいって思っていたから。どうしても私たちを通っているから4人の音楽にはなってしまうけれど、根底の部分にピントを合わせておけば、あなたの音楽でもあります。
青葉市子“Dawn in the Adan”を聴く(Apple Musicはこちら)
―デビューから10年が経って、記念碑的な作品になりましたね。
青葉:2020年という、ざわざわしている世界だったからこそ、生まれてきてくれた作品だと思います。
この時代に私たちはこの年齢だったということ、4人それぞれのタイミングでトラウマや思い出、そういったものをひっくり返して見つめることで、『アダンの風』は生まれました。私の作品というよりは、時代が生み出した結晶という感じがしていますね。


- リリース情報
-

- 青葉市子
『アダンの風』(CD) -
2020年12月2日(水)発売
価格:3,300円(税込)
DDCZ-22681. Prologue
2. Pilgrimage
3. Porcelain
4. 帆衣
5. Easter Lily
6. Parfum d'étoiles
7. 霧鳴島
8. Sagu Palmʼs Song
9. chinuhaji
10. 血の風
11. Hagupit
12. Dawn in the Adan
13. ohayashi
14. アダンの島の誕生祭
- 青葉市子
- プロフィール
-

- 青葉市子 (あおば いちこ)
-
音楽家。1990年1月28日生まれ。2010年に1stアルバム『剃刀乙女』を発表以降、これまでに6枚のソロアルバムをリリース。うたとクラシックギターをたずさえ、日本各地、世界各国で音楽を奏でる。弾き語りの傍ら、ナレーションやCM、舞台音楽の制作、芸術祭でのインスタレーション作品発表など、さまざまなフィールドで創作を行う。活動10周年を迎えた2020年、自主レーベル「hermine」(エルミン)を設立。体温の宿った幻想世界を描き続けている。12月2日、「架空の映画のためのサウンドトラック」として、最新作『アダンの風』を発表した。
- 梅林太郎 (うめばやし たろう)
-
東京出身の作曲家、編曲家。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。2012年よりmilkとしてソロ活動を始める。「Rallye Label」より1stアルバム『greeting for the sleeping seeds』をリリース。現在2ndアルバムを制作しつつ、楽曲提供、映画音楽、アニメ音楽、CM音楽と幅広いジャンルにおいて国内外、数多くのアーティストと作品を発表している。
- フィードバック 12
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-