音楽家・君島大空が、3rd EP『袖の汀』をリリースした。全6曲30分弱。その時間を言葉にすれば淡泊なものだが、この『袖の汀』を聴いている30分弱の間には、「この世界に、こんなふうに流れる時間があったのか」と静かな感動を覚える、そんな時間が広がっている。この時間の流れは静謐で、同時に混濁していて、とても個人的である。しかし、個人的であるということは、閉じているということではない。それは海のように開かれている。この作品を聴いた人は、自分自身の大切なことを、自分自身の生きることの秘密を、改めて見つめるかもしれない。この世界に、こんな時間が流れていることがとても尊いと、私は思う。
君島大空が去年、2nd EP『縫層』(2020年11月)のリリース後から演奏しはじめた新曲“光暈(halo)”を聴いたとき、見えた景色がある。それは、ゆらゆら揺れる波の動きに、ぷかぷか身を任せているような景色。波の動きと共に過ぎてゆく時間の残酷さがチクチクと胸を刺すが、それでも波は動き、季節は移ろい、人もモノも変わっていく。流動。過ぎゆく時間のなかでどうしようもなく失われていくものがあり、それでも、あるがままの形で残しておきたいものがあり、その狭間で、どこかに向けて動いていること、運ばれていることを感じている。記憶は未来のビジョンに変わり、胸に小さな決意が宿る。それを抱いて、いま、揺れる……ゆらゆら、ぷかぷか。“光暈(halo)”は、本作『袖の汀』の1曲目に収録されている。
今回、『袖の汀』のリリースに際して、CINRA.NETではインタビュー記事を2つに分けてお送りする。まずこのインタビューでは、『縫層』以降の季節における君島の心境の変化、そしてそれを象徴する楽曲“光暈(halo)”にフォーカスを当てて話を聞いた。ゆらゆら、ぷかぷか……帰り道を見つけるように、揺れ動く波を捉えた君島の眼差しは、とても柔らかかった。

君島大空(きみしま おおぞら)
1995年生まれ日本の音楽家。ギタリスト。2014年から活動を始める。同年からSoundCloudに自身で作詞 / 作曲 / 編曲 / 演奏 / 歌唱をし多重録音で制作した音源の公開を始める。2019年3月13日、1st EP『午後の反射光』を発表。2019年7月5日、1stシングル『散瞳/花曇』を発表。2019年7月27日『FUJI ROCK FESTIVAL '19 ROOKIE A GO-GO』に合奏形態で出演。11月には合奏形態で初のツアーを敢行。2020年1月、Eテレ NHKドキュメンタリー『no art, no life』の主題曲に起用。同年7月24日、2ndシングル『火傷に雨』を発表。2021年4月21日、3rd EP『袖の汀』を発表。ギタリストとして吉澤嘉代子、高井息吹、鬼束ちひろ、adieu(上白石萌歌)などのアーティストのライブや録音に参加する一方、楽曲提供など様々な分野で活動中。
3作目で提示するのは変化ではなく、君島大空の音楽活動の原点といえる音の姿
―前作『縫層』から約半年が経ち、3作目のEP『袖の汀』がリリースされます。『午後の反射光』から『縫層』までのスパンを考えるととても早いペースだと思うのですが、今作の構想はいつ頃から考えていましたか?
君島:去年末くらいには、ぼんやりと頭にありました。というのも、『縫層』を出した前後の時期はこれまでの人生で一番、バンドでライブをやった期間だったんですけど、12月にLIQUIDROOMで配信ライブをやったあたりでひと区切りがついた感覚があったんです。
「いまの自分が合奏でライブをするとこうなるんだな」って、客観的に見ることができるくらい向き合えた感覚があった。で、そのくらいの頃から、「もとからずっと自分のなかにあったものを出しておきたいな」と思いはじめて。
―今作は『縫層』に比べてもすごく穏やかな作品という印象を受けましたけど、「いままでやっていなかったことをやろう」ということではなかったわけですよね。
君島:そうですね、「いろんな変遷を経て作風が変わりました」という感じではなくて、むしろ自分の内から自然に出てくるものだからこそ、前作から間を開けずに出せたのはあると思います。
『午後の反射光』よりも前に、初めてつくった4曲入りのデモCDがあるんですけど、今回の作品はそういうものに近い気がするんです。「弾き語り」という言葉はあまり好きではないんですけど、声とギターとドローン(編註:楽曲のなかで音高の変化と関係なく持続的に鳴っている音のこと)だけで成り立っているような作品というか。
今作のようなガットギターと声だけのものって、ずっと根底にあったもので、『午後の反射光』より前の自分はそういうものをつくっていたんです。なので、「これこそ自分だ」と思う部分がある。もちろん、『縫層』も自分らしいなと思うんですけどね。でも、こういう作品も、すごく自分だなと思う。
「ずっと、状況によってかたちが変わる音楽をしてきた」――ギタリストとして即興演奏の場数を踏んできているからこその特異な歌の感覚
―「弾き語り」という言葉を好きでないというのは、どういったところに起因する感情なのだと思いますか?
君島:偏見とコンプレックスにまみれた部分だと思うんですけど……(笑)、なんなんでしょうね、この感覚は。結構、いろんな人を見ていても思うんです。
「弾き語り」というのは手段の呼称でしかないと思っていて、でも逆に、その様式ととても親和性の高い人もいると思っていて。この違いを説明するのは難しいんですけど、少なくとも自分は、弾き語りをやっているつもりはなくて。ただ昔からずっと、状況によってかたちが変わる音楽をしてきたという感覚があります。場所性が強い音楽というか、そのときの自分のコンディションに抗わない音楽というか。
―なるほど。流動的なものということですよね。
君島:調子が悪い日は、「その日調子が悪い人間がいいと思うもの」をやるし、そこで「いつも通りの変わらない自分」みたいなものを出そうとは思わない。その都度、時間や場所にすごく左右されるので。自分がやってきた音楽はそういうものだと思うし、それは微妙にいわゆる「弾き語り」という言葉にはそぐわない気がする。「即興演奏」という言い方のほうが自分の感覚的には近いです。

君島:そもそも僕はギターを弾きはじめた頃から、インプロビゼーション(編註:即興演奏のこと)や、すごくフリーなセッションをやる機会が身近にあったし、そういう場所で実際に声を出して歌わずとも、歌うように「自分はこうである」とギターで示すことをやってきたし。そういうところから繋がっているものなので、自分のやっていることは「弾き語り」とは言い切れないなと思います。
いま、取り繕わない裸の音の姿を聴かせる胸の内
―君島さんの音楽の根底にあるのがとても即興的、流動的なものであることはライブを観てもすごく理解できるんですけど、それを今回のようにレコーディング作品としてパッケージングするのって、すごくアンビバレントな行為でもあると思うんです。
君島:はい、はい。
―そこは君島さんのなかで、どういうふうに落としどころを見つけていくものなんですか?
君島:そうですね……録るときに、あまり気を張らないようにしました(笑)。
―なるほど(笑)。
君島:たとえば1曲目の“光暈(halo)”はギターを録ったあとから声を重ねているんですけど、「いいギター録れたな」と思って、そのままのテンションで歌った仮歌をほぼ採用しているんです。
「いつか本チャンを録ろう」と思っているうちに、その仮歌が一番いいような気がしてきて、「これをよしとしよう」みたいな(笑)。聴こえる音が少ないからか、つくっている間は、ずっと自分の裸を見ているような感じがしました。いままでの作品は、裸を隠して隠して、いろんな装備を重ねていくけど、どこかの点でそれが裏返ってめちゃくちゃ裸が見える、みたいな感じだったと思ってて。
君島大空“光暈(halo)”を聴く(Apple Musicはこちら)
君島:それはそれですごく自然な行為ではあったんですよね。裸を隠すのは自然なことだし、そのうえで、底のほうに隠したはずの裸の自分がいつの間にか浮き出てくるって状態をいままではつくっていたような気がする、でも今回は「まあ、いいじゃん」って(笑)。
好きなときに録って、好きなときに聴いて、聴きたくないときは聴かなくてもいいしって感じで、いろんなことをOKにしていった感じがありました。時間も切迫していなかったし、ゆるっとつくった感じはありますね。それこそ初めてのデモCDは2日間くらいでパッとつくったんですけど、いまあらためて、そういうことをしたかったんだろうなと思います。
―『袖の汀』を初めて聴かせてもらったとき、いまの君島さんからこういう穏やかな音楽が生まれてきたことにすごく驚いたと同時に、嬉しかったんです。いま、君島さんがこの作品を出していいと思えているのなら、それはなんというか、すごくいいなあって(笑)。
君島:(笑)……でも、そうなんですよね、「出していい」と思えている。いま、音楽に対する感情や感覚が、すごくいいなと思えているんです。去年の年末辺りから、風通しがすごくよくなっている感じがしていて。

―具体的に、どんな変化を感じていますか?
君島:……ぼくは性格的に、大切にしている感覚や景色を抱きしめ過ぎてしまうところがあると思うんですけど。でも、そんなに抱きしめていなくても、誰もそれを奪いにはこないという当たり前のことに気づいたんですよね。パッと手を放しても、自分の大切なものはずっとそこにあるから、そして力を入れ過ぎると、形を歪めてしまうこともあるから、いたずらに力む必要はないんじゃないかなって、最近思います。
実際に誰かにそう言われたわけではないんですけど、耳元で誰かにそんなことを言われたような気がしたんですよね。で、「あ、本当にそうかも」って。去年の終わりくらいからずっと、自分の内側でそういう話をしていたような気がします。
君島大空“星の降るひと”を聴く(Apple Musicはこちら)
「ここからもう一度はじめられるのかな、自分は」――ずっと大事にしてきたガットギターの響きに改めて立ち返った理由
―そもそもの話なんですけど、君島さんはなぜガットギターを使うんですか?
君島:小さい頃に家にあったガットをずっと使っているんですけど、それがすごくよくて。フォークギターも同じくらい弾いていたはずなんですけど、でも、(ガットギターは)すごく体に近い感じがしたんです。力を必要としない感じというか、ガットの音って独り言っぽいんですよね。
人に伝えようとしているような、していないような、どちらともつかない感じがあるし、部屋で弾いてると、自分の代わりになにか言ってくれるような感じがある。弾いていると、寂しくなかったんです。「温かい」というより、「寂しくない」。音が体から出てきてくれている感じがすごくする。ガットギターの音が、楽器のなかで一番好きかもしれないです。
―昔から同じガットギターを使っているんですね。
君島:そうですね。録音も全部それです。気づいたら、いま使っているガットギターは代わりが見つからないものになっていました。ずっと弾いているから、自分の体にすごく合ってきているんですよ。「こうだよね?」「そうだよ」って、こっちが思った音でそのまま鳴ってくれるので、一度壊れたことがあるんですけど、同じものを直しながらずっと使っているんです。
―『午後の反射光』以前にデモ音源をつくっていた頃に近いという話でしたけど、制作中の感覚みたいなものも近かったですか?
君島:もちろん、違う感じもありました。デモCDをつくっていた当時は、とにかく曲を録ることができればよかったから、バッと録ってバッと混ぜてOK、みたいな感じだったけど、その頃に比べたら、いまの自分は聴こえるものが増えている。
だから、音が少ないぶん、疲れましたね。ずっと自分の声がすぐそこで鳴っている感じで、それに対して自分で「はい、ちゃんと聴きます」って応え続けるみたいな。疲れたけど、全く悪い疲れではない感じがしました。
……でも、やっぱり「変わった」というより、「戻ってきた」という感覚のほうが強いかもしれないです。『午後の反射光』をつくって、『縫層』をつくって、人の作品に参加したりバンドをやったり、ひとりでライブをしたりしてきて、また最初に戻ってきた感覚がある。「ここからもう一度はじめられるのかな、自分は」って思えているというか。

―循環しているものが、一周して戻ってきた感じですか。
君島:そう、大きな循環。そのゼロのところに戻ってきた感じがします。
生きて時間を重ねることの意味に気づけた2020年。失うだけではない、その人生の巡り合わせ
―これはレポートでも書いたんですけど、去年12月の合奏形態での配信ワンマンを見たときに、円形になって向かい合うように機材をセッティングしていたし、“光暈(halo)”が独奏と合奏で2回演奏されたこともあって、「循環」というものをすごくイメージしたんですよね。反復しながら、変化しながら、一周して同じところに戻っていく感じというか(関連記事:君島大空が鳴らす『縫層』の次の季節 『遠隔夜会「層に電送」』評)。
君島:そうですね、繰り返し……そういうことは最近よく考えます。ぼくはずっと巻き戻そうとしていたんです、いろんなことを。それは現実世界では無理なことだけど、それでもずっと、過ぎてしまった時間や過去の記憶を取り返そうとしてきた。
忘れないように、いつでも思い出せるように、強く握っていなきゃいけないって、ずっとそういうことを意識していたと思うんです。
君島大空“午後の反射光”を聴く(Apple Musicはこちら)
君島:でも、そんなに力を入れなくても、自分は最初に戻っていくだろうって最近は思うんですよね。開き直りとかとは多分違って、意識が何回も同じ道を通って、どんどんと最初のイメージが強くなっていくような感覚というか。
―大切にしている感覚や景色は誰かが奪いにくることも、消えることもないし、むしろ時間を重ねてより鮮明になっていく。なぜ、そう思えたのでしょうね。
君島:「もう会えないかもしれない」と思っていた人に、去年、会えたりしたんです。そのとき、「回るもんだな」って思ったんです。「ああ、生きてんなあ」って、すごく自然に思った。だからこその今回の音源なのかもしれないなって思います。
―1曲目の“光暈(halo)”は、歌詞やサウンドに「波」のイメージがあると思うんですけど、よく考えると、波の動きって巻き戻しようがないんですよね。ゆらゆらと揺らいでいる姿そのものが変化であり、時間の経過であり、二度と同じものには戻らない。
波だけでなくても、自然はそういうものだと思うんですけど、“光暈(halo)”を聴いていると、そうやって時間が過ぎていくことに対して、抗いたい気持ちを胸に抱きながらも、でも、波には乗り続けているというか、ゆらゆらと漂いながら、最終的には、時間が流れ、物事が変化していくことを肯定しているような感覚があるなと思ったんです。
君島:うん、うん。肯定している感覚はあります。でも、それは決して諦めではなくて。「時間が過ぎていっちゃうのは仕方がないよね」とはあんまり思っていない。
時間が過ぎていったことにあとから気づいて、それを肯定しているんだと思います。だから、「こんなに時間が経ったから、また会えたんだな」と、ある地点まで来たときに振り返って、納得して、大きく時間を肯定しているような感覚があります。
―ぼくは去年11月、石橋英子さん、七尾旅人さんとのオーチャードホールでのライブで“光暈(halo)”を初めて聴いたんですけど、この曲が生まれてきたときのことは覚えていますか?
君島:すごく覚えていて。それこそ、オーチャードの1週間くらい前に海に行ったんですよ。たまに「海の近くにいたいな」と思うことがあるんですよね。海は見たくないけど、海が近くにあるっていう状態が自分を洗ってくれるような気がして。
その頃は、『縫層』のときに考えていた息苦しさというか、閉塞感は晴れていたけど、次になにかをする気持ちにもなれなくて、コロナでライブもできないし、ただなんとなく慢性的に疲弊していた時期だったんです(関連記事:君島大空、苦闘の第二作。狂騒と覚醒の狭間で、ひっつかんだ実感)。それで小さいギターを持って海に行って、なんとなくレコーダーを回しながらパラパラと弾いていたら、“光暈(halo)”が、本当に収録されているこのままの尺で出てきたんです。
歌詞は出てこなかったけど、全部そのままのかたちで自然に出てきて。それを聴いて、すごく救われたんです。これが塊として自分のなかから出てきたっていうことがすごく嬉しかった。とても個人的な感動なんですけど。
―そのときの君島さんにとって、すごく自然な音楽だったんですね。
君島:うん、すごく自然なものでした。メロディーも、そのときの自分の身に降りかかったことと、自然と重なるような感覚があって。“光暈(halo)”のシングルのジャケットを描いてくれた子って、高校生の頃の知り合いで。
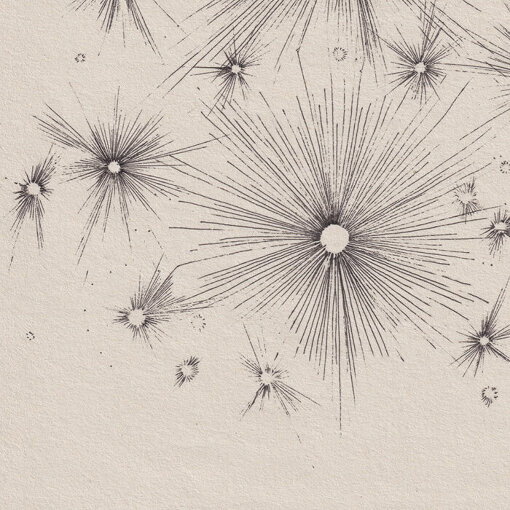
君島大空『光暈(halo)』ジャケット(Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く)
君島:その頃のぼくはバンドもやっていなかったし、外に自分の音楽を発表してもいなかったんですけど、その子はその当時からライブハウスに出入りしていたんですよね。で、ぼくの知らない音楽やその他の表現に詳しくて、教えてもらうものがいつも刺激的で、話をするために、その子の好きな音楽を聴いていたくらいで(笑)。その子は当時から絵を描いていて、ぼくは彼女の絵がすごく好きで。どこかでそれを引きずっていたからこそ、「自分も何かしたい」と思ってコラージュをつくりはじめた部分もあって。
高校の終わりくらいに音信不通になってしまったんですけど、去年、“火傷に雨”を出して『Love music』(フジテレビ系、2020年9月27日放送)に出たとき、放送があった日の夜中に10年ぶりくらいに連絡があったんです。「テレビ出てたでしょ? 君島くんだよね?」って。「うっそー! 生きてたんだ!」とか思って……っていうか、「俺、生きてたんだ」と思って(笑)。
―ははははは(笑)。
君島:あれは忘れられないです。代々木八幡の路上でタクシーを待ちながら、その子から連絡が来たときのことは。こんなことがあるんだなと思いました。生きているとまた会える……月並みで擦り切れている言葉だと思うけど、でも、自然にその言葉のままにそう思えました。それですごく元気になったんですよね。「生きていたんだな」って。
君島:ぼく、「生きていてよかった」と思うようなことって、人生でそんなになくて。それは当たり前になっちゃっていることだし、その子のことも「もう会えないんだろうな」と勝手に思っていたし。でも、また会えた。
そのときに、「生きる」とか「生きていた」って、自分の言葉としてやっと言えるようになった……26歳にして、やっと(笑)。
「生きていてほしいし、生きていたらまた会える」
―すごく大きな出来事ですよね、それは。
君島:そうですね。……なんというか、「生きていてください」と言いたくて音楽をつくっているような気が最近すごくしていて。作品を世に出してから、「死にたいなと思っていたけど、その度に君島さんの曲を聴いて救われています」ということを何人かの人から言ってもらったことがあって。
そういう言葉を聞くと、「ああ、よかったな」って思うんです。特に『午後の反射光』って、そういう人を救えなかった自分が、どこか作品のテーマにあったんですよ。
君島:それがいま、ひとりの人に対してでも「生きていてください」と言えるものになっているものであれば、よかったなと思う。生きていてほしいし、生きていたらまた会えるし。
―そうですね。
君島:……でも、「生きたい」と「死にたい」って、極端な欲求なんですが、強烈に同居しているなと思うんです。生死に関わらず、強烈な感情の二極が発作みたいに自分に対して見えてしまうことがよくあって。最近あったのは、めちゃくちゃぶん殴ってほしいし、ぶん殴るのと同時に、めちゃくちゃ撫でてほしいってことで(笑)。
どちらかだけじゃ絶対にダメで、セットじゃないと嫌なんです。いまよくわかんない話をしてるかもしれませんけど(笑)。すごく好きな人に対しても喧嘩なんかしたら「消えてしまえ!」と思うときもあるし、その次の瞬間に「僕が消えてしまえよ!」と思って、自分を殴っていたり……矛盾を抱えているのが人の常態なのだろうなと、最近はそんなことを、起きている間はずっと考えている気がします。

海という存在に抱くシンパシー。境界線の上に立ち、「あわい」そのもののような音と声と言葉を紡ぐ
―それでいうと、さっき言っていた「海は見たくないけど、海のそばにいたい」という感覚もなかなか複雑そうですよね。
君島:海を見たいと思うこともよくあるんですけど、「そこに海があります」というところにいたい(笑)。そうすると、すごく安心するんです、昔から。海が見えてしまうとワクワクが終わっちゃう感じがあって。
この前、「海って、いろんなものの境目だから落ち着くのかな」って友達と話をしていたんです。海は命の源でもあるし、死んで帰っていく場所でもあるだろうし。その境界が浜辺だと、その友人は言っていて。死と生が当たり前にある場所。そういうところが自分を安心させてくれるのかなって思います。
―なにかとなにかの境界線や狭間にいる感覚って、君島さんの音楽に根深く刻まれているものでもあると思いますね。
君島:ああ、そうかもしれないです。境界線って、言葉からイメージにすると1本の線みたいな感じだけど、ぼくの思う境界線って、それこそ浜辺のような、ストロークがすごく長い帯のような、余白のようなものなんですよね。
「あっち」と「こっち」の間にある余白、空白……そこにあるもの、そこにいること、自分の音楽ってそういうものなのかなと最近思います。
君島大空“きさらぎ”を聴く(Apple Musicはこちら)
君島:「あわい」に自分がいること、そこから声を出したり音を出したりすることが自分の仕事というか、自分の生命活動として、すごく自然なことなんだと思います。
人が心の内に隠してしまっている部分を愛おしく思うからこそ、君島大空には歌えることがある
―君島さんの音楽を聴いて、「自分」という存在のなかにもさまざまな境界線があることに気づく人は多いんじゃないかと思うんですよね。少なくとも、ぼくはそうでした。
君島:すごく抽象的な言い方になるんですが、ぼくは人と、何かを共有しようとすることが極端にできない気がしていて。でも、そんなことは誰にもできはしないんじゃないかって最近思います。ほとんどのことは共有できないんじゃないかって。最近気づいて、「悲しいな」と思ったんですけど。
どんなに仲がよくても、一緒に何かをつくっていても、価値観や感情でできた見えない自分の塊の、その30パーセントくらい共有できたらたぶんいいほうで、それ以外はほとんど共有なんてできない。誰もが言葉を過信しすぎているし、ぼく自身そうだった。人って、本当に誰ともわかり合えないんだろうなって思ったんです……強く。
言葉への諦めみたいなものを、すごく感じていて。でも、それでも、みんなが……「みんな」という言い方にも違和感があるんですけど、その、すごく底のほうに共通項がある気がするんです。
本当に誰にも言えないこととか、自分のなかで「人に言うにはくだらないことだ」と思ってしまったり、「大人だからこの気持ちはしまっておこう」と思ってしまったり、それだけの理由で、死ぬまで誰にも言えないことが人にはきっとあると思う。それはすごく些細なことなんだけど、ぼくはそういう打ち明け話のようなことを人から聞きたいし、人のそういう部分をすごく可愛いと思う。
君島大空“白い花”を聴く(Apple Musicはこちら)
―うん。
君島:どんな音楽を聴いていても、「自分の、ここだけはやっぱりどうしても救ってもらえないんじゃないか」と思う、見えてしまう部分がいくつか明確にあって。でも、つくっている人と自分は違う人間だから。決して全ての音楽にその救済に似たものを求めているわけではないんですけど、ぼくは自分の音楽に、自分の「そこ」を救ってほしいから音楽をつくっているんだと思うんです。だから、すごく自己満足的な話なのかもしれないけど、まずは自分でそこを救えると思えるものをつくらないといけない。
まず圧倒的に、自分に向けてつくっているんだろうなと思う。……でも、遠く離れた誰かが内に隠してしまっている部分に、ぼくの音楽がもし入り込むことができるのだとしたら、それはすごく嬉しい、奇跡のようなことだなと思うんです。入り込んだあと、どうなるのかは、わからないけど。
君島大空“銃口”を聴く(Apple Musicはこちら)
―“光暈(halo)”で、<聴いて>と歌うじゃないですか。歌詞としてすごく強い言葉だと思うんですけど、君島さんが歌うと、ある一方向へ向かうものとしてその言葉は歌われていないような気がして。この<聴いて>は、境界線から、その内側にも外側にも、あらゆる方向に向けて優しく発せられている感じがするんです。そこが、すごく心地いいなと思います。
君島:「自分には使えない」と思っていた言葉がたくさんあるし、それはいまもたくさんあるんですけど。いままで<聴いて>なんて怖くて書けなかった。自分が歌おうとすると「聴け!」みたいなことになっちゃうかもしれないと思い込みすぎたり、そうなってしまうことが怖くて使えない言葉がいっぱいあって。
たとえば、「愛してる」もそうです。でも最近は、自分の根本は絶対に変わらないし、ぼくが言えば、ぼくの響きになるんだろうなと思えている。だから書けたんだろうなと思う。本当に聴いてほしいから、<聴いて>と書けたんだと思います。


- リリース情報
-

- 君島大空
『袖の汀』(CD) -
2021年4月21日(水)発売
価格:2,200円(税込)
APLS20151. 光暈(halo)
2. 向こう髪
3. 星の降るひと
4. きさらぎ
5. 白い花
6. 銃口
- 君島大空
- プロフィール
-

- 君島大空 (きみしま おおぞら)
-
1995年生まれ日本の音楽家。ギタリスト。2014年から活動を始める。同年からSoundCloudに自身で作詞 / 作曲 / 編曲 / 演奏 / 歌唱をし多重録音で制作した音源の公開を始める。2019年3月13日、1st EP『午後の反射光』を発表。2019年7月5日、1stシングル『散瞳/花曇』を発表。2019年7月27日『FUJI ROCK FESTIVAL '19 ROOKIE A GO-GO』に合奏形態で出演。11月には合奏形態で初のツアーを敢行。2020年1月、Eテレ NHKドキュメンタリー『no art, no life』の主題曲に起用。同年7月24日、2ndシングル『火傷に雨』を発表。2021年4月21日、3rd EP『袖の汀』を発表。ギタリストとして吉澤嘉代子、高井息吹、鬼束ちひろ、adieu(上白石萌歌)などのアーティストのライブや録音に参加する一方、楽曲提供など様々な分野で活動中。
- フィードバック 41
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-




