もし「不老不死」になる施術を受けることができるとしたら、10代、20代のまま永遠に生きることができるとしたら、その道を選ぶだろうか。生が死によって意味をもたらされているのだとしたら、死のない人生はどう生きればいいのか。現代SFを代表するアメリカ人作家のひとり、ケン・リュウの短篇小説『円弧(読み:アーク)』はそんな問いを私たちにつきつける。
物語の舞台をアメリカから移し、『愚行録』『蜜蜂と遠雷』の石川慶監督が本作を日本で映画化した『Arc アーク』が2021年6月25日に公開される。芳根京子が17歳から100歳以上まで生きる主人公を演じ、「人類史上初めて永遠の命を得た女性の一代記」を描くこの作品。リュウ自身もエグゼクティブプロデューサーとして携わり、その仕上がりに「あなた方はこの物語に生を与えるのに唯一にして最高の方法を用いました」と賛辞を送る。
今回は映画の公開に際して原作者のリュウにインタビューを敢行。テクノロジーとそれを使う人間の関係、未来を想像するSFにおいて、いま足りていないと考えること、社会における集団的意思決定にかかわる「ソーシャルテクノロジー」への関心──「自分のことをSF作家だとは思っていない」と語るケン・リュウの現代社会とテクノロジー、そして人間への鋭いまなざしが浮かびあがった。
※本記事は映画『Arc アーク』の内容に関する記述が含まれています。あらかじめご了承下さい。
「不老不死」を「悪」ではなく、少しポジティブかつ恐ろしい物語として綴る
―映画の原作小説『円弧』の執筆時、死を克服することをテーマに据えた理由はなんだったのでしょう。映画でも小説でも、「死の克服」を人間にとってある種ポジティブなものとして描いているのが印象的でした。
リュウ:寿命の延長が過去数世代にわたって繰り返されていることに、とても興味があるんです。いまの人は、過去の人間に比べると、かつてないほど長生きしていますよね。さらに現在の予測では、今後、ある程度の若さを保ちながら150歳、200歳まで生きられるようになるかもしれないと言われています。
そういう大きな変化を創作の題材としたとき、ディストピア的なシナリオが頭に浮かびがちです。たとえば、「一つの仕事に100年くらい就くことになるから、新しいアイデアが生まれなくなる」とか、あるいは「カップルがある程度の年月を過ごしたら、ともに成長するということができなくなって別れてしまうだろう」といったネガティブな反応があるかもしれません。いまはシニアの離婚が多くなってきていますしね。でも、すぐそう考えてしまうのは安易なことだと思うんです。

1976年、中国・甘粛省生まれ。8歳のときに米国に移り、以降カリフォルニア州、コネチカット州で育つ。ハーバード大学にて英文学、コンピューターサイエンスを学ぶ。プログラマーを経て、ロースクールにて法律を勉強したのち、弁護士として働く。2002年に作家デビューし、2011年に発表した短篇『紙の動物園』で、『ヒューゴー賞』『ネビュラ賞』『世界幻想文学大賞』の短篇部門を制する史上初の3冠に輝く。短編を中心に執筆しており、2015年に、初の長篇となる『蒲公英王朝記』を刊行。日本での初翻訳となった『もののあはれ』では、日本人を主役とした作品がある。Photo: © Lisa Tang Liu
―不老の技術は、多くの作品で「悪」として一方的に描かれがちですね。
リュウ:ぼくの狙いとしては、もう少し面白くてポジティブで、同時に恐ろしくもある物語を綴ることでした。
「永遠の若さは、私たちをずっと成長させてくれる。それによって私たちはもっと人間らしくなれる」という見方と、「永遠の若さによって私たちの人間らしさが損なわれる。あるいは完全に失われてしまう」という見方。その両方の視点から、永遠の若さを持った当事者への想像力を持って描きたいと思ったんです。それが面白いストーリーにつながるはずだという思いで、原作小説を書きました。

舞台はそう遠くない未来。17歳で人生に自由を求め、生まれたばかりの息子と別れて放浪生活を送っていたリナは、19歳で師となるエマと出会い、彼女の下で「ボディワークス」を作るという仕事に就く。それは最愛の存在を亡くした人々のために、遺体を生きていた姿のまま保存できるように施術(プラスティネーション)する仕事であった。エマの弟・天音はこの技術を発展させ、遂にストップエイジングによる「不老不死」を完成させる。リナはその施術を受けた世界初の女性となり、30歳の身体のまま永遠の人生を生きていくことになるが……。©2021映画『Arc』製作委員会
―映画版にはエグゼクティブプロデューサーとして参加されていますね。本作について「アメリカのフィルムメイカーにはつくることのできない作品だ」とコメントを寄せていましたが、この言葉の意味を教えていただけますか?
リュウ:制作が始まった頃、石川監督が『円弧』について「ぼくはこのストーリーがとても好きだ。自分が読んでいる他のSF作品と比べて、なにか違うムードを感じる」と言ってくれました。そして彼は「油彩ではなくて、水彩や水墨画を思い起こさせる。その点によって、この作品をどのようにビジュアル的に脚色するか、方法を見出せた」と言っていたことも思い出します。ぼくはいま、それがすごく重要で象徴的な言葉だったんじゃないかと感じています。
なぜなら、この映画で重要になっているのが「ネガティブスペース」……つまり、「余白」の部分だからなんです。
劇中で語られている言葉と同じくらい、語られていない言葉は重要だし、語られるべきものと同じくらい、語られないままでいるものが重要だと感じています。石川監督は、テクノロジーそのものにはあまりフォーカスせず、原作の「人間らしさ」を強調して映画にしています。画面をガジェットで埋め尽くしたり、いかにも「これが未来なんだ」というような記号を入れたりする絵づくりはせず、観客自身が考える余地を残している。

―たしかに、現実的な日常のシーンを中心にドラマが構成されていましたね。
リュウ:アメリカのフィルムメイカーの多くは、このようなアプローチはとりません。ハリウッドのビジュアル言語やSF映画の制作は、未来を象徴するようなあからさまで記号的なものをたくさん登場させて、観客を圧倒したり驚嘆させたりするようなやり方をする。だから、今回の映画はアメリカの映画人からはなかなか出てこない発想だと言えると思います。
「ぼくらは時に文化の違いというものを強調しすぎなんじゃないか」
―原作の舞台はアメリカでしたが、映画では明言されていないものの、日本を舞台にしたと思われる物語になっています。演出手法のみならず、今回の映画では日本の文化や東洋の考え方が作品に影響していると感じました。
リュウ:それは、やっぱり避けられないところなんじゃないかなと思います。どんなストーリーテラーも自分のユニークな文化的視点から物語を伝えることになりますから。映画のストーリーは、石川監督のビジョンや、彼が携わっているストーリーテリングの伝統というものが確実に反映されているでしょう。
ただ、ぼくらは時に文化の違いというものを強調しすぎなんじゃないかなとも思うんです。人々が考えるほど、じつはそんなに違いがないんじゃないかって。
この映画の東洋的な要素が、アメリカの観客にとって文化的に距離を感じるものかというと、そうではないと思う。さまざまな理由から、アメリカの映画演出の伝統が、本作のようにストーリーを語る方向にはあまり進化しなかったというだけで。だから、日本の観客がアメリカの映画を楽しむように、アメリカの観客もこの作品を楽しめると思っています。

―原作との違いとして、映画のなかでエマ(寺島しのぶ)という登場人物が自分のパートナーの遺体にプラスティネーション(死者の身体を保存する技術)を施す描写が追加されていました。本作のエグゼクティブプロデューサーでもあるリュウさんは、その部分にはタッチされていたのでしょうか?
リュウ:そこはぼくが考えたアイデアではないですが、すごく良い選択だと思ったし、理にかなっているとも感じました。フィルムメイカーは自分の物語を語らなくてはいけない。そして映画メディアの強みを利用して、その物語を可能な限り説得力あるものしなくてはいけない、というのが、ぼくの物語をアダプテーションするときの哲学です。
映画に加わった要素のなかで、プラスティネーションによって遺体のポーズをつくるときに、生者と死者をつなぐことを連想させる「ストリングス」を物理的に見せるという趣向は素晴らしかったです。仰ったようにエマのパートナーがプラスティネーションを施されたというようなメタファーも、ぼくの小説の単なるコピーを超えて、オリジナルと平等に対話できる独立した作品として昇華されている証拠だなと感じます。

人間がテクノロジーをどう使い、いかに自分自身を表現するか
―『円弧』もそうですが、リュウさんの作品は未来のテクノロジーのようなスケールの大きなものを描きながらも、同時に、家族などのごく身近な関係性が登場します。こういった特徴について、ご自身ではどのように考えていらっしゃいますか?
リュウ:それは、多分ぼくの「テクノロジスト」としてのバックグラウンドと関係しているんじゃないかな。
―作家としての地位を築く以前は、マイクロソフトなどの企業で、エンジニアとしてソフトウェア開発をされていたそうですね。
リュウ:その時代にぼくが学んだのは、誰かに製品を買ってもらうよう説得するとき、どこが強みでどんな機能を持ってるのかを説明するだけでは不十分だということです。それは売り込みの場ではあまり役に立たない。
本当にやるべきことは、自分自身を物語るうえでそのテクノロジーがいかに役に立つのか、を説明すること。なぜなら、「自分が誰であるか」というストーリーこそが、人間の最大の関心事だからです。

―人々が自分自身を表現するうえで、そのテクノロジーが役に立つかどうか、ということですね。
リュウ:そう。たとえば良い父親になりたいと思っている人にとって、この製品が良い父親になるために、いかに役立つか。飢餓の世界を救いたいと思ってる人にとって、このテクノロジーがいかに助けになるのか。育児中の母親が、子どもに自分のストーリーをよりうまく伝えるのに、いかに役立つのか。重要なのはそういうことなんです。なぜなら、人はそうやってテクノロジーに共感するからです。ぼくにとっては、その部分を掘り下げることが、面白い作品をつくることにつながるんです。
ぼくが小説を書くとき、テクノロジーそのものに主眼を置くことはありません。ロケットとかソフトウェアとかチップとかギアとか、そういうことに関心があるわけではない。いかにそのテクノロジーによって、自分たちが誰であるかというストーリーを、より力強く、説得力があって、勇気づけられるような物語として伝えられるか。どうしたらテクノロジーによって、もっと深くて面白い形式で、自分が誰であるかを表現できるか。ぼくが関心があるのは、そういったストーリーを伝えることなんです。
「自分のことをSF作家だと思ったことは一度もない」
―それは、ご自身がSF作家ではないということなんでしょうか。それとも、SF小説とはそもそもそういうものだ、と考えているということでしょうか?
リュウ:ワオ、それはすごく難しい質問だな(笑)。告白してしまうと、自分のことをSF作家だと思ったことは一度もないんです。なぜなら、ぼくはジャンルやラベルをまったく気にしていないからです。
ぼくが関心ある物語の種類は、自分では「触れられるメタファーのストーリー」と呼んでいるものです。それは、普段比喩的に語られているものを、フィクションの世界のなかで「触れられるリアルなもの」に変えるということ。そういうストーリーをぼくは綴っているんです。

―実際にはメタファーに過ぎないはずのものを、作品のなかで現実のものにするのですね。
リュウ:そのとおり。そうすることでぼくたちは、いままで以上に人間の性質を知ることができるし、そうしなかったら学べなかっただろう、自分たち自身についても学ぶことができる。そして、この「触れられるメタファー」を考えるとき、テクノロジストとしてのキャリアがぼくのバックグラウンドにあることで、テクノロジーの要素が自然に出てきてしまうんだと思います。
―一般的にSF作家だと言われることについてはどうですか?
リュウ:周りからSF作家だと思われることについては、嬉しいとは思っています。なぜなら、読者がSF作品を探しているときにぼくを見つけてくれるわけですから。
でも意識的にSF作品を書こうと思って書き始めたことはないし、「これがSFの書き方だ」みたいな考え方も、ぼくのなかにはない。ぼくが伝えたいストーリーのことを、人はSFと呼ぶけれど、ぼくのフォーカスは常にテクノロジーではなく、テクノロジーをストーリーテリングのツールとして使う人間のほうにあります。

今後のSFに期待するのは、社会的、集団的な意思決定の仕組み──「ソーシャルテクノロジー」を描いた作品
―リュウさん自身はSF作家だと思っていないということでしたが、ジャンルとしてSFが今後こうあってほしい、また、こうなっていくんじゃないかという展望を、ぜひお聞きしたいです。
リュウ:これからの予測をすることは難しいですが、コンピューターやロケットみたいなテクノロジーではなく、「ソーシャルテクノロジー」にフォーカスした物語が増えてほしいとは思っています。
ここで言う「ソーシャルテクノロジー」というのは、人々が一緒になって決定をするような仕組みのことです。たとえば、議員制、陪審員制、裁判、官僚制、選挙、世論調査。ぼくはこういったものを社会的、集団的な意思決定のテクノロジーだと考えています。こういうものは、人々を一つのものとし、危機に直面したときなどに、ぼくらみんなに影響する意思決定をすることを可能にしています。

リュウ:多くのSFは機械的なテクノロジーのほうにばかり目が向いていて、ぼくの思うソーシャルテクノロジーに注目したSF作品は、まだ十分に出てきていない。そちらのほうがはるかに重要だと思うのに。だからぼくは、みんなが直面している実存的な危機に立ち向かうために、人間が集団で決断を下すより良い方法を題材にしたり、それについての推測を盛り込んだりしたSFをもっと読みたいですね。
「ぼくたちもまた、自分たちの時代に囚われ過ぎているのではないか」
―そういった新しい仕組みが、現実の社会にも必要だと。
リュウ:そう思います。ぼくたちが未来について考えるとき、かならず盲点というものが存在しているんです。たとえば1950年代、60年代のSF作品を読むと、科学やテクノロジー、ハードのマシーンについては、いま読んでも合点がいくものが多いですし、いつか実現するかもと思うようなものもあったりするけれど、ジェンダー間や人種間の関係についての表現は、ばかばかしいくらいおかしかったり、いまでは通じないようなものもあったりして、明らかに時代に囚われていることがわかります。
いまも、未来を見据えるはずのSF作品が、いまだに帝国を登場させたりしていますよね。社会的・集団的な意思決定のテクノロジーについても同じような問題があると思います。代表制民主主義はまだ不完全で、現実に不満を持っている人も多いなかで、「これが人類が生んだ最高のかたちだ」という風に描かれたりしているSFも目にします。
そういう意味では、1950年代、60年代の人々と同じで、ぼくたちもまた自分たちの時代に囚われ過ぎているのではないでしょうか。もっとベターなものがあるかもしれないけど、そういうふうに思考することができていないのかもしれない。だからこそ一歩踏み出して、大胆な考え方をしない限り、より良い社会には到達できないと考えています。

―社会基盤の構築もまた、未来の世界のかたちだということですね。そのお話で、ケン・リュウさんがSF作家として受容されながらも、自身をSF作家だと考えていないという意味がわかった気がします。
リュウ:そうですね。だからぼくは、アーシュラ・K・ル=グウィン(『ゲド戦記』で知られるアメリカの作家。ファンタジーのほか、SF作品も執筆。2018年に逝去)は、とても素晴らしいと思っているんです。彼女は、ジェンダーや権力についてのテーマを描くことが人気になるずっと前から、深い洞察で描いていた。先見性を感じます。
その意味ではオクティヴィア・E・バトラー(アフリカ系アメリカ人SF作家。著書に『キンドレッド―きずなの招喚』など。2006年に逝去)も同様で、彼女も人種やジェンダーについて、とても早い時代から書いていました。
ぼくは、彼女たちの小説で描かれているように、機械的な仕組みだけではなく、「社会的に新しい考え方によって未来はより良いものになる」という推測を盛り込んだ物語をもっと読みたいんです。
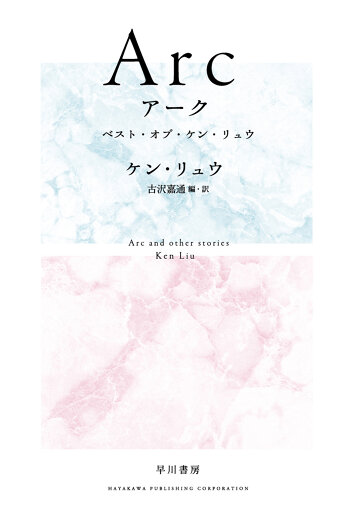
パンデミックによる社会の変化、死生観の変化をどう見るか
―最近はコロナ禍によって世界的に社会が変化を余儀なくされています。このことは今後のSFにどう影響をおよぼすでしょう。
リュウ:ぼくらが未来についてどんなふうに語るか、ということに、このたびのパンデミックが変化を与えるのは疑う余地がないと思いますね。
でも、実際にどんな風に変えるのかを予測するのはまだ難しいですね……。そういう意味では、9.11のときと近いんじゃないかと思います。あの事件が起きたとき、人々はすぐに反応して、世界はこんなふうに変わるんじゃないかと言い合ったけれども、その予測のほとんどは間違っていた。10年以上も経ってから初めて、ぼくらは9.11がどう世界を変えたかを、深い意味で本当に理解したんです。
だから今回のパンデミックも、即時的な反応が正しいとはあまり思っていないんです。いまから何十年も経ってからじゃないと、このパンデミックが世界にもたらしたインパクトの本質は見えてこないんじゃないかな。
―コロナ禍によってご自身の死生観は変化しましたか?
リュウ:個人的な変化を言葉で明確にするのは少し難しいんですが、パンデミックによって、自分の「死」というものをより意識することになったのは確かだと思います。キャリア的なことから一歩下がって、より家族のことを考えようと思うきっかけにもなりました。
でも、一方でポジティブにとらえられる部分もあると思うんです。こんなひどい状況のなかで、人類が一つの目標に対して動くことができるということがわかりましたし、それは美しいことだとも感じました。そう考えると、まだ人類という種には希望があるのかな、と思いますね。
- 作品情報
-

- 『Arc アーク』
-
2021年6月25日(金)から全国公開
監督:石川慶
脚本:石川慶、澤井香織
原作:ケン・リュウ『円弧』(ハヤカワ文庫『もののあはれ ケン・リュウ短篇傑作集2』所収)
音楽:世武裕子
出演:
芳根京子
寺島しのぶ
岡田将生
清水くるみ
井之脇海
中川翼
中村ゆり
倍賞千恵子
風吹ジュン
小林薫
上映時間:127分
配給:ワーナー・ブラザース映画
- プロフィール
-
- ケン・リュウ
-
1976年、中国・甘粛省生まれ。8歳のときに米国に移り、以降カリフォルニア州、コネチカット州で育つ。ハーバード大学にて英文学、コンピューターサイエンスを学ぶ。プログラマーを経て、ロースクールにて法律を勉強したのち、弁護士として働く。2002年に作家デビューし、2011年に発表した短篇『紙の動物園』で、『ヒューゴー賞』『ネビュラ賞』『世界幻想文学大賞』の短篇部門を制する史上初の3冠に輝く。短篇を中心に執筆しており、2015年に、初の長篇となる『蒲公英王朝記』を刊行。日本での初翻訳となった『もののあはれ』では、日本人を主役とした作品がある。マイノリティとして生きることをテーマに据えた作品が多く、社会問題への無関心をSFの世界に昇華させ、ロボットや宇宙などSFの舞台の中でノスタルジーと切なさが漂う、中国からアメリカに移住したケン・リュウならではの東洋の香りが魅力。中国SFの翻訳家としても活躍。アメリカ、マサチューセッツ州在住。日本での書籍で代表的なものは、ケン・リュウ短篇傑作集シリーズとして、『紙の動物園』、『もののあはれ』、『生まれ変わり』、『草を結びて環を銜えん』、『母の記憶に』、『神々は繋がれてはいない』があり、また、新作『宇宙の春』が3月17日に発売された。
- フィードバック 4
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-





