下北沢のギターロックシーンが隆盛を誇っていた1999年に結成され、2003年にはインディーズバンドとしては異例の新宿リキッドルームでのワンマンライブを成功させるも、2004年に解散の道を選んだBURGER NUDS。ルーツミュージックの独自解釈を志向し、編成を変えながら数多くの作品を発表するも、現在は活動休止中のGood Dog Happy Men。そして、孤独や悲しみを描いた本名名義のソロアルバム『Nobody Knows My Name』を経て、門田匡陽が新プロジェクトPoet-type.Mをスタート。「清く。正しく。美しく。」を意味するデビューアルバム『White White White』を発表した。
このアルバムが到着したときに、2013年が始まりの年であるという予感は確信に変わった。僕らは震災を経験し、その後の社会状況を何とも形容しがたい気持ちで見続けてきた。誰かはそれを「荒野」と呼び、誰かはそれを「My Lost City」と呼んだ。そして、僕らはそろそろ本当に新たな一歩を踏み出さなくてはならない。Poet-type.Mはプラネタリウムを会場とした初の独演会に『A Whole New World』というタイトルを掲げていた。そう、僕らが今聴きたいのは、本当に新しく、それでいて普遍的な音楽。門田の言う「帰る場所のない美しさの翻訳」とは、まさにそんな音楽を生み出す唯一の方法であるはずだ。
CINRA初登場となる今回の取材では、Poet-type.Mの話にとどまらず、いつの時代も常に異彩を放ち続けてきた門田匡陽という生粋の芸術家のルーツを改めて確認し、現代の音楽をめぐる状況について、様々な角度から話を訊いた。取材を終えて感じたのは、やはり彼がどこまでも音楽を愛し、その身を捧げているということ。もう一度繰り返そう。清く。正しく。美しく。それがPoet-type.M、門田匡陽の世界。
自分が選んだ芸術に対して真摯な姿勢でいないと、話ができなかったんですよ。
―門田さんのこれまでの活動というのは、非常に強い音楽への愛情に裏打ちされていて、それは「音楽への献身」と言ってもいいものだと思うんです。まずは、その基本姿勢がどのように形成されていったのかをお伺いしたいのですが。
門田:それは門田家の話になっちゃうんですけど、家族みんなが芸術家という、ちょっと特殊な環境なんですよ。親父が映像ディレクターで、写真家の叔父がいて、小説家の叔父がいて、あと従兄弟がニューヨークで建築デザインをやってたり。なので、いないのが音楽家だけだったんですよ。僕生まれたときから指がきれいだったから、「お前はピアニストか産婦人科医にしかなれない」って言われてたんですけど(笑)。
―でも、ギターも手にしてしまったわけですね(笑)。
門田:そうなんです(笑)。そういう芸術ごとに携わる一族の中で普通に生きてると、自分が選んだ芸術に対して真摯な姿勢でいないと、話ができなかったんですよ。芸術家特有の人間性なんでしょうけど、子供であろうと話に手加減がなくて、生半可な理解で芸術を語ると「お前に何がわかるんだ!」って言われてしまうような感じで、小学校の頃から扱われてて(笑)。みんなそれなりにそれぞれの世界で成功してる人たちだったから、僕も音楽を選んだ以上、それで認められたいっていうのは小さい頃から思ってました。
―実際、すぐ音楽の道に進んだんですか?
門田:生まれた瞬間から音楽でした。っていうのは、ピーター・バラカンさんが僕の生まれる前から家に出入りしてて、家にものすごい量のレコードがあったんです。僕にとってのおもちゃはそれでしたね。
―門田さんとしゃべってると、いろんな音楽の話が、いろんな角度から出て来ますけど、それはピーター・バラカン仕込みだったんですね(笑)。
門田:そう言っても過言ではないと思います。例えば、ブリットポップが流行った1995年あたりに、「今BLURっていうかっこいいバンドが好きで」って言うと、「僕にはTHE KINKSに聴こえる」って言われるみたいな(笑)。
―ちょっと面倒くさい(笑)。
門田:でも、それでTHE KINKSを聴いてみたり、そういうミュージックツリーをつなげてくれましたね。
―若い頃はヒーローみたいな存在っていたんですか?
門田:小学校のときに限定すると、最初に憧れたのはプリンスとかデヴィッド・ボウイだったんです。デヴィッド・ボウイが『Let's Dance』を出した年に僕は生まれて、物心ついて初めて見た映画が『Labyrinth』(デヴィッド・ボウイ出演)だったりもして、「何だこのきしょいおっさんは」と思いました(笑)。そうかと思えばプリンスは『Purple Rain』を出して、やっぱりあれも「何だこのきしょいおっさんは」と思って(笑)。
―(笑)。
門田:何かこう、自分の世界観をぶつけてくるアーティストに憧れましたね。ビビッドでわかりやすいっていう側面もあるんだけど、今思い返すと彼らは音楽的レベルがずば抜けて高かったから、そういうところも無意識に感じてたのかもしれないです。
1人が1人であっていい。共有ではなく、共鳴なんです。
―Poet-type.Mの活動に関しては、「帰る場所のない美しさの翻訳」という言い方をしていますよね。音楽とは曖昧なものであり、作り手が規定するものではなく、受け手が解釈するものだと。この考え方っていうのは、どのように培われたものなのでしょう?
門田:絵でも、映画でも、器は何でもいいんだけど、アーティスト側がコントロールすればするほど、作品はつまんなくなるんですよね。それが今、日本の音楽とか映画がつまらない一番の理由だと思うんだけど、アーティストが最初から「この曲はこれを言おう」と考えて作ってしまってるんですよ。言うなれば飛行機が離陸するところから、着陸するところまでを見せられて、その軌道以外には何もない。僕はそういうのがものすごく嫌で。
―いま日本人がなぜその軌道上でしか楽しめないのかっていうと、ライブの場とかで顕著ですけど、同調圧力が強まっていることが理由として考えられると思うんですね。例えば、門田さんがBURGER NUDSで活動を始められた時期と比較して、今って現場を取り巻く雰囲気って変わったと思いますか?
門田:変わったと思いますね。この間もかなりの数のバンドが出たイベントに出演して、その打ち上げに行ったんですけど、そこでバンドマンたちが和気あいあいとやってる感じがすごく馴染めなくて、これじゃあ何も生まれないと思いましたね。5分もいれなかった。
―ぬるま湯感があった?
門田:一言で言ったら、完全にそうですね。どこを見てるのか全然分からない。自分の活動のことをホントに大事に考えてたら、ああいう雰囲気にはならないんじゃないかな。別にその人たちの音楽がどうっていうんじゃないですけど、僕は打ち上げのときも自分の音楽のことをずっと考えてますし、その日のパフォーマンスのことを考えながら話すけど、そこが分断されてるんですよね。そういう文化になってしまったのは、すごく寂しいなって思います。下北沢って、昔はそんな街ではなかった。
―BURGER NUDSで活動していた頃は、馴れ合いではなかった?
門田:良くも悪くもみんな心に壁を作ってましたし、例えば、打ち上げが朝までになろうと、話してることは下世話な話ではなかったと思います。友達作りじゃないんだから、共感し合えるやつとだけいればいいんですよ。
―ちょっと前にdownyの青木ロビンさんに取材をしたときも似たような話になって、やっぱりdownyが活動していた00年代初頭っていうのは、ちょっとピリピリした空気があったとおっしゃってました。
門田:まさに同調圧力という話で、フェスの功罪もあると思いますね。みんなでユナイトすることが音楽の第一至上になってしまったから。00年代頭にはそんな価値観はなかったですよね。
―では、門田さんにとって、音楽をやる上での第一至上とは?
門田:僕は僕みたいな人を救いたいと思ってます。ステレオの前で音楽に飢えてるリスナーです。本当の誠実さが感じられるもの、そういうものを伝えたくて、音楽をやってるんだと思います。例えば、僕が高1のときにジェフ・バックリィの“Last Goodbye”を初めて聴いたとき、僕は「こういう人がいれくれてよかった」と思ったんです。その恩を返したい。僕の音楽を聴いてくれる人、こういう価値観で鳴らしている音楽に共鳴してくれる人に、「よかった」って思ってもらいたい。1人が1人であっていい。共有ではなく、共鳴なんです。
震災以降の日本では、音楽が本来持っている力とは違うものを背負わされてる気がして、閉塞感を感じていたんです。
―Poet-type.Mの活動を始める前に、一度BURGER NUDSやGood Dog Happy Menの過去曲を録り直そうとしたものの、途中でやめることにしたそうですね。
門田:『Nobody Knows My Name』(2011年6月に発売された門田匡陽名義のファーストアルバム)をリリースする直前に震災があったんですけど、それ以降の日本では、音楽が本来持っている力とは違うものを背負わされてる気がして、閉塞感を感じていたんです。「原発を止めろ」って言われてる音楽がすごく可哀想で、そういうものじゃなく、もっと一人ひとりの心に、目に見えるもの以上の何かを残す力が音楽にはある。自分はそう感じていたけど、そういう風に考えているミュージシャンにあんまり出会わなかったんですよ。それで、自分もある種のパラノイアに陥ったというか、僕自身今自分がどこにいるのかを定めないといけなかったので、自分が通ってきた足跡を今の自分で奏でてみたいと思ったんです。そしてそれを、僕とは違う価値観の人がどう見るのかなとも思って。
―自分の位置を確認するためでもあり、ある種同業者に向けるような意味合いもあった?
門田:ホントに何かを変えたくて言ってる人と、ただ流れに身を任せて言ってる人って、全然違うのがわかるじゃないですか? ただ流れに身を任せて言ってる人に聴いてもらいたかったんです。そのためには、新しいものを作るよりは、足跡をもう1回っていう雰囲気だった。去年あたりは、まだ悲しみの先に目は行ってなかったですからね。
―実際レコーディングを進めてはいたんですよね?
門田:去年の夏にレコーディングをしたんですけど、実際にやってみたら、まったく音楽にはならなかったんです。わかりやすく言ったら、10年前の新聞を見て、「10年前はこんなことがあったね」って、ノスタルジーとして思い返すだけのものだった。それは一番やっちゃいけないことだと思ったから、いろんな人に迷惑かけたけど、「申し訳ありませんでした」って心からお詫びをして、そこでやめました。セルフィッシュでしたね。
気をつけないといけないのは僕たちものを作る側の姿勢だと思います。第三者が触れる可能性のあるものを作って、それで1円でもお金を儲けてる立場の人たちが使う「言葉」が大事なんです。
―先日くるりの「15th Anniversary」って銘打たれたツアーを観たんですけど、いわゆるヒット曲中心のセットではなく、むしろレアな曲が多くて、今やりたい選曲やアレンジをやってるのがすごくよくて。やっぱり表現をする人は自分勝手な部分を持ってないとダメだと思ったんですよね。
門田:多分ひとつのバンドをやってる人にとって、15周年なんてアニバーサリーでも何でもないんですよ。それは対外的にそう銘打った方が都合がいいからで、別に30年やってようと、現在進行形でやってる人には、何の意味もないはず。例えば、今ポール・マッカートニーが来日してますけど、もしもジョン・レノンとジョージ・ハリスンが生きてて、THE BEATLESとして来たら、それはアニバーサリーですよ(笑)。でも、そこまで行かないとアニバーサリーとは言わないと思うんですよね。
―この前downyの取材をしたんですけど、彼らのアルバムのタイトルは常に『無題』で、「アルバムごとに名前をつけて区切ることの意味がわからない」とおっしゃっていました。それも「現在進行形のバンドにとって、アニバーサリーは意味がない」っていう今の話に通じるかなって。
門田:すべての言葉は潜在的な建物なんですよ。言葉をつけることによって、その建物の中にすべての感情を押し込めてしまうことになるから、そこを意識してる人としてない人では、だいぶ違ってくると思いますね。デザインひとつとってもそうで、デザインをするっていうのは、そのデザインにどんな合理性が含まれているかが説得力になるんですよね。ただ表層だけ「これっぽく」とか、「これはデザイン性関係ないからこれでいいや」とか、そういう舐めたことは一切したくないんですよ。音楽をやるってことは、総合芸術なんです。音ひとつ選ぶにしても、それはデザインだし、どういう景色が歌われてるかってことを、ホント細部まで突き詰めないと、恐ろしくて言葉で囲めないですよ。
―今のバンドシーンを見てると、また言葉の時代になってるなって思うことが多いんです。ただ、言葉のみで成り立ってしまっていることが多くて、音楽なんだから、本来は言葉と音が組み合わさって、初めて意味を成すべきだと思うんですよね。
門田:それはホントにすごく思いますね。「このことが言いたいがために曲を作ってるんだろうな」っていうのを、そのままタイトルにしちゃうようなバンドが多いじゃないですか? その言葉が音楽の中でどういうハーモニーを生み出すのか、どういう風に音に溶け込むのか、そここそ音楽の一番素敵な魔法がかかるところなのに、はなからそこを捨てちゃうのはホントにもったいないですよね。
―やっぱり、ちょっと独特な感じがしますよね、日本の歌詞文化って。
門田:ひとつ僕がはっきりわかってるのは、日本は「日記」がありがたがられるってことです。昔は詩的な言葉とか、センテンスとしての美しさが求められてたと思うんですよ。職業作詞家がいた時代までかな。そういった頃の歌謡曲は、詞を読むとすごく景色も情念も伝わってくるんですよね。でも今はそうではなくて、Twitterをそのまま歌にする、LINEの会話をそのまま歌にするのがありがたがられる。そこは音楽だけの功罪ではなく、テレビ番組や、映画や、そういったものがまったく詩的な言葉を使わなくなって、そういう風に教育されてきちゃったからで、それは僕が詩人として一番抗いたいところなんです。
―じゃあ、どうすればこの状況を変えていけるのかって考えると、それこそ話が教育論にまで及びそうですよね。
門田:いや、教育は放っといていいと思いますよ。教育は昔からどうしようもないものだし、実際に僕も学校の教育から、自分の音楽のペーソスになったものは何もないと思っています。ただ、僕は自分の周りから「美しさ」を学べたから、そこは運がよかったと思ってます。そういう風に、教育外のところで学ぶものがもう少し美しくなればいいと思うし、気をつけないといけないのは僕たちものを作る側の姿勢なんだと思うんです。第三者が触れる可能性のあるものを作って、それで1円でもお金を儲けてる立場の人たちが使う言葉が大事なんです。
―発信する一人ひとりの言葉が、教育の代わりになると。
門田:絶対そっちの方が重要だと思います。何かをガラッと変えようとするムーブメントはもううんざりですよ。そうじゃなくて、それぞれがそれぞれの場所で、今までより少しでも頑張るっていうことが大事だと思うんです。
僕はただの音楽を、何よりも一生懸命大事にして、恩返しをしたいんです。
―今日は門田さんのお話を伺って、ものを伝える立場として、改めて襟を正しました。最後に、今後の活動についての話も訊きたいのですが、今月末からはツアーが始まるんですよね。
門田:僕の中で今回のツアーは1回原点に立ち返るという意味があるので、僕にとってのホーム的な、一番最初のメンバーと一緒にツアーを回って、『White White White』という序章をちゃんと終わらせようっていう気持ちです。特に12月8日の新代田FEVERでのワンマンに関しては、『White White White』の集大成になると思います。
―9月に行われたプラネタリウム公演のライブ盤を会場で販売するそうですね。
門田:あの日はすごくよかったんですよね。僕は音楽を演奏する立場として、受け手側と逆の立場にいないといけないっていう気持ちでステージに上がってるんです。ただ、あの日の僕は受け手側の1人として、お客さんと一緒に楽しめた。そういうライブってホントに数えるぐらいしかないから、あの刹那で終わらせるのはもったいないかなって。
―プラネタリウムだったから、キャパも限られてましたもんね。だからこそ、親密な空気が生まれたとも言えると思うんですけど。
門田:外で聴かないで、部屋を真っ暗にして聴いてもらいたいですね。僕は、その場にいなかった人がライブを疑似体験できるっていう意味で、ライブ盤をすごく肯定してるんです。だって、寂しいじゃないですか? 僕はフィルモアイースト(1968年から1971年までニューヨークにあったコンサート会場で、重要なコンサートが多数行われた)に行ったことはないですけど、あの興奮を味わいたいですよ(笑)。だから、『Live at Fillmore East』があると嬉しいし、ジェフ・バックリィがニューヨークのカフェで2日間連続でやったライブの2枚組は、僕の宝物ですもん。
―名古屋と大阪には、ゲストにLEO今井さん、大阪には踊ってばかりの国の下津君も出るし、すごくいいラインナップですよね。途中の話でいえば、彼らはいい意味でセルフィッシュなミュージシャンだし、門田さん同様に、すごく音楽に対して真摯な人たちだと思います。
門田:LEO今井君は僕、昔から大好きなんですよ。自分の表現とすごく真摯に向き合ってると思う。門田匡陽の音楽を好きな人が、LEO今井の音楽も好きかどうかは全然わからないけど、だからこそ一緒にやりたいなって。あと下津君に関しては、発言が面白い(笑)。
―(笑)。あとこれは以前話したときにすごく印象的だったことなんですけど、門田さんは「僕は生涯ステージ上からお客さんを煽ることはしないと思う」っていうことをおっしゃってましたよね。途中で出たコントロールの話にも通じると思うんですけど、改めて、ライブにおいて大事にしていることを話していただけますか。
門田:ミュージシャンがライブで煽るっていうのは、その音楽や空間をコントロールしてる動かざる証拠ですよね。僕は自分の思い通りにお客さんをコントロールしたいんじゃなくて、むしろ僕が意識してないようなところまでみんなが行ってくれたらいいなって思うんです。みんなが同じ風にタオルを振ったりっていうのも、それをお客さんが自主的にやるのであれば、それには何も言いません。ただ、僕がそれを煽ることは絶対しないと思います。絶対にしないと思う。
―2回言いましたね(笑)。
門田:だって、それは違うもん。もっと音楽を一生懸命やればいいじゃん。
―以前CINRAで取材した人の中で、門田さんと同じことを言ってたのが、ZAZEN BOYSの向井さんなんですよね。一人ひとりの感情なんて絶対違うんだから、当然それぞれの楽しみ方があるはずだって。
門田:そうそう、ホントにそうですよ。
―でもね、向井さんは「スタジアムにTHE ROLLING STONESを観に行って、“Brown Sugar”のイントロが鳴ったら一緒に盛り上がります」とも言ってました(笑)。
門田:僕もTHE ROLLING STONES観に行きましたけど、ポカンと見てました(笑)。
―(笑)。今日話して、門田さんは常に音楽と真摯に向き合ってきた人なんだなっていうのが改めて確認できたような気がしています。
門田:今日話したこととたぶん矛盾してないと思うんだけど、音楽はただの音楽だから。僕はそのただの音楽を、何よりも一生懸命大事にして、恩返しをしたいんです。そこを履き違えないで、これからも生きていきたいと思います。
- イベント情報
-
- 『Poet-type.M「White White White」TOUR』
-
2013年11月29日(金)OPEN 18:30 / START 19:00
会場:愛知県 名古屋 CLUB UPSET
出演:
Poet-type.M(『White White White TOUR』ツアーメンバー:門田匡陽[Vo,Gt]、楢原英介[Gt]、伊賀航[Ba]、gomes[Key]、伊藤大地[Dr])
LEO今井
Mi-Solfa2013年11月30日(土)OPEN 17:30 / START 18:00
会場:大阪府 阿倍野 ROCKTOWN
出演:
Poet-type.M(『White White White TOUR』ツアーメンバー:門田匡陽[Vo,Gt]、楢原英介[Gt]、伊賀航[Ba]、gomes[Key]、伊藤大地[Dr])
LEO今井
下津光史(踊ってばかりの国)2013年12月8日(日)OPEN 17:30 / START 18:00
会場:東京都 新代田 FEVER
出演:Poet-type.M(『White White White TOUR』ツアーメンバー:門田匡陽[Vo,Gt]、楢原英介[Gt]、伊賀航[Ba]、gomes[Key]、伊藤大地[Dr])料金:各公演 3,000円(ドリンク別)
- リリース情報
-
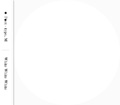
- Poet-type.M
『White White White』(CD) -
2013年10月2日発売
価格:2,310円(税込)
DDCZ-19051. 光の粒子 埃の中で(Departures)
2. 何もかも越えて、吐き気がする(Down To Heaven)
3. 永遠に柔らかな罰を(Cheek-to-cheek Dancing for Broken hearts)
4. 調律するかのように(Over The Rainbow)
5. 君と僕(flowers)
6. 祈り(It's show time)
7. 名も無い景色の中で(I Will Say Good Bye)
8. 長い序章の終わり(Law Name)
9. 誇りの響き 光の中へ(White White White)
- Poet-type.M
- プロフィール
-
- Poet-type.M(ぽえと たいぷ どっと えむ)
-
1980年東京都生まれ。1999年より3ピースロックバンド「BURGER NUDS」のメンバーとして活動。新宿リキッドルームを完売させる勢いを持ちながら2004年解散。同年、ファンタジックで独創的な世界観を持つツインドラムの4ピースロックバンド「Good Dog Happy Men」を結成。数々の大型フェスに出演し、多くのファンを魅了させるが2010年にメンバーの脱退を受けて活動休止。2011年 門田匡陽として初のソロアルバム「Nobody Knows My Name」をリリース。その後わずかな休息を経て、2013年4月1日よりソロ名義を「Poet-type.M」に変更し活動を再開。10月2日には初のFull Album「White White White」のリリースが決定。
- フィードバック 6
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-





