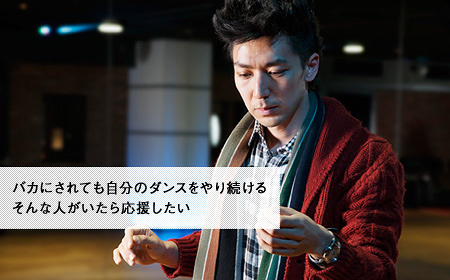ブラックカルチャーの聖地とも言われる、ニューヨーク「Apollo Theater」。数々のミュージシャンやアーティストを生み出してきたこの劇場で、1930年代にスタートしたイベント『Amateur Night』は、今も昔も世界最高峰を目指すアーティストの登竜門として知られている。観客の拍手の大きさがその日の優勝者を決める、というこのイベントの覇者には、The Jackson 5、スティービー・ワンダー、マーヴィン・ゲイ、ダイアナ・ロス、ビリー・ホリディ、エラ・フィッツジェラルド……スターの枚挙にいとまがない。その『Amateur Night』を勝ち抜いた者だけが、プロとして臨むテレビ版のショーイングで、2006年に史上初の9連覇、殿堂入りを果たしたのが、TAKAHIROこと上野隆博だ。
子どもの頃からダンスに親しみ、その技を磨いてきたのかと思いきや、ダンスに夢中になった経緯には意外な物語が。しかし、そこには人生の転機を巧みに掴み取る柔軟さとおおらかさがあった。その魅力的な人柄にインタビューを通して少しでも触れてみてほしい。
初めてダンスを観たとき、「僕だったら、もっとこうするのに」というアイデアが自然と湧き出てきたんです。そしてなんとなく自分でも「できる」気がした。
―TAKAHIROさんは、『SHOW TIME AT THE APOLLO』を9連続優勝して殿堂入りを果たし、マドンナのワールドツアーに専属ダンサーとして参加されるなど、輝かしいキャリアの持ち主です。今日はそこに至るまでのお話なども伺えたらと思います。
TAKAHIRO:わかりました。よろしくお願いいたします。
―じつは取材にあたって、少し調べさせていただいたのですが、小学校から高校まで、財界人や文化人などのご子息が多く通っている有名私立男子校のご出身なんですよね。
TAKAHIRO:はい。小・中・高を通して「紳士教育」という授業があるようなエスカレーター式の学校に通っていて、僕自身もわりと親の言いつけを守るような「良い子」でした。着る服も学校の制服か親が与えてくれた服のどちらか。家に帰ってくつろぐときもワイシャツに着替えていましたし。
―現在のダンサーのイメージからはまったく想像できないのですが(笑)。ではダンスやブラックミュージックに出会われたのはいつ頃だったんですか?
TAKAHIRO:ダンスに興味を持ち始めたのは高校生の終わり頃で、大学生になって初めて踊り出しました。それまでは、渋谷や原宿へ出かけたこともなかったんです。大学生になって自分で服を買うようになってからも、コーディネートというのは、頭からつま先まで一色で揃えることだ、くらいに考えていました。しかもそれを自分の好きな色で統一しちゃうから、今思うと奇妙なことになっていましたよ。全身緑とか(笑)。
―ちなみにお父様はどんなお仕事をされていたのですか。
TAKAHIRO:親族で会社を経営していました。僕は3人兄弟の長男として生まれたので、大人になったらその会社の経営陣に入るものだと言われていましたし、それを当然のように考えていました。学校の友人を見渡しても、それぞれの家業を継ぐのが当たり前、決められたレールの上を進むのが自然、という人が多かった。しかもみんなそれぞれのレールの上を楽しみながら前進している感じだったので、当時は将来の夢なんて考えたこともありませんでした。
―学生の頃は、会社経営に興味があったんですか?
TAKAHIRO:ある種のイメージはありましたが、そこに情熱を持っていたかといえば違うように思います。僕の人生はその頃までずっと、あらかじめ設定されていた答えに向かって進んでいたようなものでした。自分から枠を超えてリスクを背負うことはなく、必ずたどり着けるゴールに向かって、より安全で楽な道を選択していく。目の前に分かれ道が現れたときは、できるだけ早く、手軽に行ける道を選んでいたと思います。すでに答えは用意されているのだから、大きなマイナスにさえならなければいい……。でも、そういう生き方に結果はついてこないですよね。
―結果?
TAKAHIRO:ビリにはならないけれど、ずば抜けたところがあるわけでもない。勉強もスポーツもそこそこで、ぱっとしない、わりと地味な存在でした。けれども、クラスには必ず一番になる人、目立つ人っているでしょう? そんな存在に対して、憧れに近いコンプレックスを抱いていました。
―じゃあ、ダンスに目覚めたのは、「モテたい」とか「目立ちたかった」とか、そういう単純なことから?
TAKAHIRO:高校生の頃、初めてテレビでダンス番組を観たり、他校の文化祭でストリートダンスを観たとき、「僕だったら、もっとこうするのに」というアイデアが自然と湧き出てきたんです。それまではなにを観ても人ごとで、「わあ、すごいなー」とかしか感じなかったのが、ダンスを観たときだけはなぜか批評家になっている自分がいた。そして、なんとなく自分でも「できる」気がしたんです。
―具体的な振付のアイデアみたいなものが湧いてきたんですか? それまで踊ったこともなかったのに?
TAKAHIRO:そうなんです、僕も不思議でした。子供の頃からの憧れの人の1人がトーマス・エジソンなのですが、身体を通してなにかを作りだす感じに、発明的な「エジソン感」を感じたのかも知れません。たぶん「作る」ということに憧れていたんでしょうね。
―生まれて初めて、用意されたレールから飛び出そうとした瞬間ですね。
TAKAHIRO:そうです。今でもはっきり覚えています。大学に入ってダンスを自分で作りだすようになったある日、「これが自我の目覚めだ……」って、自分につぶやいたんです。それまでリスクのあるボールに触れもしなかった僕が、いきなりハイリスクのボールをつかんだ、そんな感じでした。
ダンスに集中しているときは「無敵」な気分になれた。わからないということは強いですよ。
―大学では、一気にダンスの世界にのめりこんでいった感じですか?
TAKAHIRO:じつは大学にはダンスサークルがなかったので、キャンパス内でブレイクダンスを踊っていた先輩に、自分から声をかけて教えてもらいました。そんな大胆な行動を取ったことも、それまでの僕にはあり得なかったこと。背中で回るウインドミルという技をとにかく習得したくて、講義の合間に10分でも時間ができると、ガラスを鏡に練習していましたね。
―ご家族の反応はどうだったんですか? つい最近まで原宿も知らなかった長男が、いきなりブレイクダンスを踊り始めたという状況に対して。
TAKAHIRO:高校までは厳しい家庭だったんですが、大学に入ってからは本人の責任に任せるという感じで、なにも言われませんでした。さらに、大学2年になったある日突然、父が会社の経営陣から手を引くことになったんです。僕にとっては、その会社に入るのが当然だと思って、それまでずっと生きてきたわけですから、価値観や人生の全てがひっくり返るくらいの衝撃でした。でも、それもあって、ますますダンスに集中するようになりました。ダンスに集中しているときは、なんだか「無敵」な気分になれたんです。ダンスのことをなにも知らずに飛び込んだからこそ、そんな気分になれたんでしょう。わからないということは強いですよ。
―それはものすごい体験ですね……。予定の書きこまれていない真っ白な未来と、ダンスという創造・表現の発見が同時にやってきたわけですね。そこからの自分自身は大きく変わっていきましたか。
TAKAHIRO:それまでの僕は、安全なレールに乗せられていたことで、苦労してなにかを発信するという必要性を感じていなかったんでしょう。「受信する側」という殻の中に閉じこもっていたように思います。両親が厳しかったこともあり、自ら発信することで欲望を叶えようというよりは、周りの人に喜んでもらうことで、自分の立場を安定させていたようなところもあったのかもしれません。しかし、思いがけず自分自身で人生を切り開かなければいけない状況になり、それによって自分の役割を演じる必要もなくなりました。人との接し方も少しずつ変化していって、昔より腹を割って話すことができるようになったと思います。簡単に言うと、かっこつけずにすむようになりました。
―大学卒業後、1年間の会社員生活を経て、いよいよ単身渡米されます。『Amateur Night』への挑戦は、いつ頃から意識していたのですか。
TAKAHIRO:卒業後の進路を考え始めた頃、自分がおじいさんになったとき、「僕の人生ここまでやったぞ」と思えるものが果たしてあるのだろうか? って、自分に問いかけたんです。ダンスに出会うまでの僕は、なにかに本気で向かっていくということがほとんどなかった。人生で初めて「こんなにやった!」と思えるものがダンスでした。このまま就職しても会社の役に立たないかも知れないし、僕にとってダンスは切っても切れないものになっている。ダンスに対して情けない自分にはなりたくなかったし、いずれダンスを辞めなくてはならない日が来るのなら、そのときに「精一杯やった」という充足感を感じられる自分でいたい。ならば、目一杯大きいことをしよう。それがApollo Theaterへの挑戦だったんです。
―Apollo Theaterで勝ち抜いて有名になりたいというよりは、チャレンジすること自体に意味があった?
TAKAHIRO:まず行って、ぶつかってみる。その行為を求めていたのだと思います。自分自身にけりをつけるために。
―Apollo Theaterは、ブラックカルチャーの聖地ともいえる場所ですよね。そこに1人の日本人ダンサーとして乗り込んでいったわけですが、コンテストでは得意だったヒップホップやブレイクダンスで挑戦したのですか? 本場の人たちからはどのような目に映ったのでしょう?
TAKAHIRO:ダンサーとして後悔のないように、全てをぶつけるつもりだったので、それまで踊ってきたようなヒップホップのスタイルだけじゃなく、完全にオリジナルなスタイルで臨みました。音楽も自由だし、急に倒れ込んだり、パントマイムもロボットダンスも、『スーパーマリオ』も『ドラゴンボール』もミックスした、自分だけのダンスです。
―そうだったんですね。しかしその後、『Amateur Night』で毎月のように勝ち抜き、年間優勝者として、テレビ番組『Show Time at the APOLLO』に出演し、史上初の9大会連続優勝で見事に殿堂入りを果たします。そこまで勝ち続けることができた理由を、ご自身ではどう捉えていますか。
TAKAHIRO:心理戦です。
―えっ?(笑)
TAKAHIRO:じつは一番最初に出演したとき、僕は落とされそうになったんですよ。ジュゼッペ・ヴェルディの“レクイエム”で踊ったら「すごく面白いけど、これのどこがヒップホップなんだ?」「もう少し、ヒップホップをリスペクトした形でやれないのか?」って、審査員の1人に言われたんです。
―オリジナルすぎて、ヒップホップの枠からはみ出しちゃったんですね(笑)。
TAKAHIRO:彼らの言うヒップホップとはスタイルだけでなく、マインドも含めた、幅広いものではあるのですが、だからといってなにをやってもいいわけではない。なので、まずヒップホップと友達になればいい、味方になってもらえばいい、と考えました。まず日本人である僕を伝えるために、空手のような動きを取り入れ、「ふんふん、じゃあ観てやるか」という気分にさせたところで、ムーンウォークを入れる。「おっ!? こいつ……」と思わせたところで、ロボットダンス。最後はやるだけやって、日本人らしく「礼」。音の使い方も見せ方も、「観客はなにを求めているんだろう?」ということを常に考えて、わかりやすさを追求しました。
高みに上がれば上がるほど、踏み台にしてしまった人たちの気持ちも考えなければいけない。せめて「昔、TAKAHIROと競ったことがあるんだぜ!」って、自慢話のネタにしていただける程度に大成したい。
―以前に発言された「経過は己が為に、結果は他が為に」という言葉が気になっていたのですが、これはどういう意味だったんですか?
TAKAHIRO:『Show Time at the APOLLO』で、殿堂入りになったことで有名人になって、ちょっと天狗になっていた時期があったんです。でも、半年も経ってしまえば周りの人も落ち着いて、殿堂入りでもただの人。チャンピオンベルトを持っていても、結局自分自身は変わっていません。本当に自分が変わるためには、肉体も精神も日々鍛え続けなければいけない。だから、経過は己の為にあるんです。
―「結果は他が為に」というのは?
TAKAHIRO:『Amateur Night』や『Show Time at the APOLLO』のような勝ち抜き戦は本当に残酷です。誰もが夢を持って戦っているのに、誰かが勝つたび、負けた人は踏み台にされる。勝ち続けることはキツイし、ただ楽しいわけではありませんでした。だから、高みに上がれば上がるほど、僕が踏み台にしてしまった人たちの気持ちも考えなければいけない。せめて、「昔、TAKAHIROと競ったことがあるんだぜ!」って、自慢話のネタにしていただける程度には大成しなくてはならない。だから、結果というのは他人の為にあると思うんです。
―……すごくいい言葉ですね。殿堂入りを果たすだけでなく、『The New York Times』で「驚愕の表現者」と評されたり、『Newsweek Japan』の「世界が尊敬する日本人100人」に選出されたことで、それは完全に実現されましたね。その後は、マドンナのワールドツアー『STICKY & SWEET TOUR』の参加やPV出演。シルク・ドゥ・ソレイユへの参加、ラスベガスでのショーなど、ニューヨークを起点に世界的に活躍されてきました。ここ数年は、日本での活動も目立ちますね。
TAKAHIRO:今でも日本とニューヨークを行き来していますが、日本での比重が高くなっています。きっかけは2011年の東日本大震災でした。いろんな問題は山積みですが、今こそ日本に帰るときなんじゃないかって思ったんです。それと、精神的にも体力的にも充実しているこの時期に、一番好きな故郷である日本で活動したいと思いました。
「流行」や「型」をマスターできる人は多いけど、壊す人は少ない。バカにされても自分の思うダンスをやり続ける。そんな人が出てきてくれたら応援したい。
―最近はダンサーとしてだけでなく、プロデュース公演を始め、テレビ番組やコマーシャル、ミュージカル、舞台への振付、プロアマを問わずダンス選手権での審査員、そしてファッションショーには出演だけでなくプランニングにまで関わるなど、本当に多彩に活動されていますね。
TAKAHIRO:その仕事に愛があるなら、なんでもやってみたいんです。
―昨年には、ご自身が主宰するダンススタジオ「TOP FIELD DANCE CENTER」を立ち上げられましたね。コンクールの審査員としての活動も長いTAKAHIROさんの目から見て、後進の若手にはどんなことを望みたいですか?
TAKAHIRO:僕より上手くて魅力ある人に、どんどん出てきてほしい。僕が持っている知識や技術でよければいくらでも提供しますから。若い世代の感性あふれるダンスに触発されながら、僕もまた新しいものを作りだしたいんです。
―まだ、「これ!」という人は出現していないようですね。
TAKAHIRO:もうそろそろ現れそうだと思っています。今はダンスと言う1つの列車の中で、みんなが同じ出口から出て行こうとしているような感じがします。1つの出口をみんなが一斉に目指したら、そこは混雑して通りにくくなります。たぶん出られるのは、運良く出口の近くにいた人か、ごく少数の天才的に能力のずば抜けて高い人、あとは周りの人たちをなぎ倒せる人とか(笑)。でも、ダンスという表現はもっといろんな可能性、扉を持っています。自分で扉を作って、そこから出て行ったっていいと思うんです。
―あえて、他人と違うことを目指してみる?
TAKAHIRO:いろんな踊り方ができると思うのに、上手くなればなるほど、踊り方が似てくるんです。「流行」や「型」をマスターできる人は多いけど、壊す人は少ない。バカにされても自分の思うダンスをやり続ける。そんな人が出てきてくれたら応援したい。ここは受信よりも、発信する力を伸ばすためのスタジオですから。
―ガツガツした子は、少ないのかな。
TAKAHIRO:はい。もっと思いを解放してほしいです。結局、人生におけるコンプレックスというマイナスパワーを、どう前へ向かうエネルギーとして使っていくかが大事なのではないでしょうか。失敗もまた学びの場です。他人の評価ばかりを気にして縮こまってしまうのでなく、自分の内側から湧き出るものを大切にしてほしい。夢は大きく、欲は小さく。
- リリース情報
-

- 『世界が認めるスーパーダンサーTAKAHIROが考案! アニソン・エクササイズ』(DVD)
-
2014年1月31日(金)発売
価格:3,990円(税込)出演:
TAKAHIRO
柳谷登志雄
加治みなみ
元気☆たつや(げんきーず)
航多
- プロフィール
-
- TAKAHIRO(たかひろ)
-
本名、上野隆博。プロダンサー / 大阪芸術大学客員准教授 / トップフィールドダンスセンター主宰。2005年全米「Apollo Theater」のコンテストで年間ダンス部門第1位に輝く。翌年同コンテストテレビシリーズで番組史上初の9大会連続優勝を果たし殿堂入りし、米国プロデビュー。07年『ニューズウィーク』紙「世界が尊敬する日本人100人」に選出。09年マドンナの世界ツアーやPVに参加。12年イスラエルと日本の国交60周年記念式典、13年にはハリウッド映画に出演するなど、世界的に活躍。日本では、『大阪世界陸上』開会式、FIFA公式大会・閉会式の振付、総合演出などを手がけ、自身のプロデュース公演他、テレビ、CM、舞台、映画他、多方面で活動中。
- フィードバック 3
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-