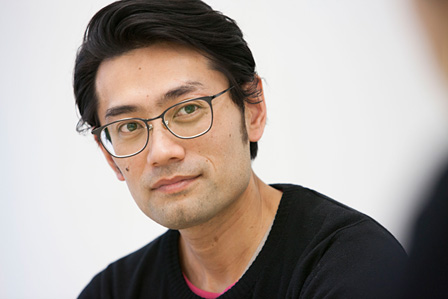演劇祭と名のつくイベントは日本中にあふれているが、静岡県舞台芸術センター(以下SPAC)の『ふじのくに⇄せかい演劇祭』のような成功例は稀だ。芸術総監督・宮城聰が中心になってプログラムする作品は、「超一流」ではあっても「権威」ではない、「話題」にはなっても「話題作り」ではない国内外の刺激的な作品たちで、GWにかかる開催期間中は全国から多くの観客が詰めかける。
今年の同祭のテーマは「さっ、出かけましょ! 空気を読まなくていい世界へ」。明るいトーンの呼びかけの裏には、昨今の日本に対する宮城の危機感が込められている。宮城と、同祭で初となる移動型の演劇作品『例えば朝9時には誰がルーム51の角を曲がってくるか知っていたとする』を作るアーティスト、鈴木一郎太と西尾佳織の三人に、空気を読まずにすくい取ろうとしている大切なことを聞いた。
僕も含めて芸術をやっている人は、どこか「世の中の役に立ってないかもしれない」という後ろめたさを抱えている。(宮城)
―宮城さんは、昨年の『ふじのくに⇄せかい演劇祭』でも上演された演出作品『マハーバーラタ~ナラ王の冒険~』が、フランス『アヴィニョン演劇祭』のメイン会場に招聘され、大変な賞賛を浴びました。その後「演劇を始めたときの大きな目的が実現してしまい、この先、何を目指せばいいのかわからなくなってしまった」とおっしゃっていましたが。
宮城:あはは、そうでした。しばらくそういう気分でした。
―ところが、今年の『ふじのくに⇄せかい演劇祭』のテーマは「さっ、出かけましょ! 空気を読まなくていい世界へ。」と、言葉は平易ですが、深い思索と強い意志が感じられる内容になっています。少し前の脱力状態から、このアグレッシブさに行き着いた経緯を、まず伺えますか。
宮城:アーティストとしてやり残したことがひとまずなくなって「まだ死にたくないな」という理由もなくなったんです。それで今なら、あんまり失うことを考えないで危険なものに触ってもいいか、と思うようになった感じです(笑)。
―危険なものと言うのは?
宮城:やっぱり今、日本全体が間違いなく戦争ができる方向に進んでいますよね。しかも、空気を読んで口を閉ざすのが利口だという流れがあって、それは、第二次大戦前夜の空気ととても似ているように思います。たとえば、「国が行くなと言った地域へ行ったヤツが悪いんだ」みたいな風潮は、それ自体が驚くべき意見だと思うんだけど、実際には圧倒的多数だったりするそうじゃないですか。
―たしかに「波風を立てないことが良い」という同調圧力が高まって、「自由=危険」というイメージが急速に広まりつつあります。
宮城:一方で僕らが取り組んでいる、公立劇場を地域に根付かせることもまた、空気を読むことだと言えるんですよ。SPACは設立して18年経ちますが、公立劇場という文化は日本にまだ根付いておらず、何のためにあるのかという地域住民の理解も十分に得られているとは言い難い。これは演劇に限らないでしょうけど、僕も含めて芸術をやっている人はどこか「世の中の役に立ってないかもしれない」という後ろめたさを抱えています。そんな中、公立劇場で働く人たちは、自分たちは変なことを考えているのではない、役に立つ人たちだと認識されたいと思うわけです。つまり地域住民が求めるものを尊重して、その要望からズレちゃいけないと。でもそれは、劇場の存在目的の1つである、多様な価値観の提示や担保とは、真逆の方向性になりかねないですよね。今、そんな状況になっているという問題意識が、演劇祭のテーマの大きなベースにあります。
―今年の『ふじのくに⇄せかい演劇祭』で、宮城さんが演出される『メフィストと呼ばれた男』は、ナチスが第一党になった頃、ドイツの国立劇場芸術監督だった実在の人物を主人公に、「創作を続けるために権力と手を組むか、創作できなくなっても良心に従うのか」という、芸術と政治の永遠の命題が描かれた作品ですが、宮城さんの今の悩みを、怖いくらいダイレクトに反映していますね。
宮城:『メフィストと呼ばれた男』は1932年のベルリンを舞台にした話ですが、当時のベルリンの状況って、今の日本とあまり違わないんです。オリンピックが4、5年後に控えているとか、貧富の差が広がってきて「自分たちは報われていない」と感じている人が増えているとか。そういった中で公立劇場がどう見なされていたかというと、経済的、文化的に余裕のある人々のいる場所だったんです。
―芸術は特権の象徴の1つだった。
宮城:僕は東京で小劇場的な活動をしていた頃、演劇界にいる人間が恵まれた人たちだなんて考えてもいなかったですよ。しかし、静岡に来たら「演劇は敷居が高い、自分には知識がないから観に行ってもわかるのか……」とすごく言われる。それは、かつてのヨーロッパにおける劇場のイメージと近いんですね。そしてナチスの文化政策は、芸術を民衆のものにすることだったんです。中国の文化大革命でもそうでした。体制をひっくり返すために「芸術が特権を持った者だけに独占されている!」と批判して民衆を味方にする手法はよく使われてきた。
―民衆に被害者意識を持たせるために利用されたんですね。
宮城:日本の公共劇場がその轍(わだち)を踏まないためには、むしろ劇場側から「私たちはすでに民衆的な活動をしています」と言い張れるようにならなければいけないと僕は思う。空気を読んですり寄るのではなく、一定の距離を取った上で、「私たちは民衆的な活動をしています、誰も排除していません」と開いていかなければならないんですよ。「じゃあ民衆的って何?」ということをSPACだけで考えていても仕方がないので、なるべくいろんな人と一緒にこの問題を考えたいと思って、このテーマにしました。
僕は「演劇」に対しても「空気を読まなくていい」と思っているんです。それができなければ、ここに呼ばれた意味がない。(鈴木)
―今回『ふじのくに⇄せかい演劇祭』に初参加となる鈴木さんは、静岡で空き店舗を再利用して地域のニーズを掘り起こしたり、アートと民衆を繋げる、アートが人々の役に立つことを考えて活動をされている方だと思います。今の宮城さんのお話は、まさに鈴木さんのようなアーティストも地域とどう向き合うかが問われる話だと思ったのですが。
鈴木:たしかにそうですね。ただ、普段から自分に問うている部分でもあるんです。たとえば、幼稚園の先生と一緒にアートプロジェクトを進める場合、まずは先生たちの空気を読むというか、ある程度の同調はするんです。だけど一方で、ちゃんとアーティストらしく振舞わなければいけないとも思う。ただ幼稚園の先生に同調して引っ張られていたら、呼んでもらう意味はないと思うので。今回、僕は演劇の人じゃないのに、この演劇祭に呼んでいただきました。だから「空気を読まなくていい」というテーマは、僕にとって「演劇」に対しての姿勢でもあると思っているんです。それができなければ、僕がここに呼ばれた意味はないし、これまでやってきたこともおそらくできなくなってしまう。「空気を読まない」ってことを、ちゃんとしなきゃいけないと思っています(笑)。
―宮城さんもそれを期待して、鈴木さんに声をかけられたわけですよね。
宮城:鈴木さんとは、彼が浜松のNPO法人クリエイティブサポートレッツというところにいたときに知り合ったんです。障がいのある子どもたちのクリエイティビティーを発見していく活動を根気よく、したたかに持続している、とても芯のある団体です。鈴木さんはその後、設計・建築やイベント企画を手掛ける「大と小とレフ」という会社を立ち上げられ、アーティストでありながら絵を描かず、アートとは何か、アーティストとは何かをきちんと問いながら活動をしている人で、経歴も含めて面白い人だと思って声をかけました。僕、自分の表現を疑っていないアーティストって、あんまり面白いと思えないんですよ(笑)。
本当に面白い芸術っていうのは、その時代の支配的な美意識からも距離が取れているものだと思う。(宮城)
―なるべくいろいろな人と一緒に「民衆的」という問題を考えたいと言われてましたが、鈴木さんはやってくれそうだと。
宮城:「どうすれば劇場が開くのか?」という。さっき「民衆的な活動って何?」と言いましたけど、たとえばナチスが教科書的に「こういう表現が民衆的です」と載せた作品は、面白いものじゃないんですよね。あるいはソ連もそう。民衆的な表現の典型とされた作品って、今見ると全然面白くないわけです。ドミートリイ・ショスタコーヴィチ(ソ連時代の作曲家)の“森の歌”のように、政府の意向どおり職人運動を讃えているように見えて、じつはいろいろ隠し細工を施したものは面白いんだけども(笑)。なんで面白くないかっていうと、その時代の多くの人があらかじめ持っている価値観、美意識にただ乗っかっているだけだから。本当に面白い芸術っていうのは、その時代の支配的な美意識からも距離が取れているものだと思います。
―つまり、空気を読んでいない。
宮城:わざとね。ショスタコーヴィチが面白いのは、共産党が求めているのはこういうことだろうな、こういう曲を書けばあいつら喜ぶんだろうなとわかっていて、3分の2くらいまで書いてから、「でもなあ……」って、考えたんじゃないかな(笑)。空気をわかっていつつ距離が取れていれば、面白いものになるんだけど、距離が取れずに過半数の美意識をそのまま引き受けた表現は、ちょっと時間が経ってみれば結局面白くないわけです。だけど、その時代には民衆的に見えたりする。

『ふたりの女 平成版 ふたりの面妖があなたに絡む』 Photo:橋本武彦

『觀~すべてのものに捧げるおどり~』 Photo:CHIN Cheng-Tsai
―「空気を読む」とは、安直なマーケティングだと言い換えられる側面もある。
宮城:僕ら表現者は、少なくとも同じことを繰り返しているようではダメで、過半数の人が「こういうの可愛いよね」「素敵、かっこいい」「勇敢だよね」と、いつの間にか刷り込まれている価値観とは距離を取らなくちゃいけない。距離を取ったうえで「でも私たちは民衆的な表現をしているんです、排除してないです、誰もが参入できる開かれた表現なんです」ということをどうやったら実現できるのか? ……まったく答えのない問いですよね(笑)。
―そういった視点から、あらためて共感できる、参考になるアーティストはいたりしますか?
宮城:最近、ベートーヴェンもこんなことを考えていたんだろうな、と思うようになって、急に親近感が湧いてきたりして(笑)。誰一人排除していない表現、誰でも参入できるはずの表現。でも、すでに世の中の大勢がカッコイイ、美しい、と思っているものをただなぞるんじゃないっていう。このままほったらかしておくと、やっぱり劇場は一部の人に囲い込まれているって、外側から見えるだろうし、自分たちもいつの間にか劇場の内側にいる人の考え方になってしまうでしょう。そんなときに、鈴木さんに関わってもらえると、門戸が開くんじゃないかと思って。
鈴木:むちゃくちゃ荷が重いじゃないですか!(笑)
宮城:あはははは!(笑)
―「荷が重い」とのことですが、宮城さんから渡されたバトンを、鈴木さんは鈴木さんで、西尾さんに渡されたわけですよね。
鈴木:荷が重くない感じで渡しているつもりでは、いるんですが……。
西尾:本当ですね……あんまりわかってなかったです(笑)。
「地域の人とこんなに仲良しになりました」っていうのは胡散臭いと思っていて……。もちろん仲良くなるのはいいことですが、何でそれをわざわざ主張するのかなって思うんです。(西尾)
―これまでのお話は、『ふじのくに⇄せかい演劇祭』のプログラムに実際に反映されているわけですが、中でも、鈴木さんや西尾さんたちによる『例えば朝9時には誰がルーム51の角を曲がってくるか知っていたとする』は、同演劇祭初の町歩き型演劇作品で、劇場と地域を考えやすい仕掛けになるのではないかと思います。西尾さんは、劇団鳥公園の作・演出として、さまざまな場所で作品を作っていらっしゃいますが、鈴木さんとの共作はどういうきっかけで?
鈴木:西尾さんが静岡県の袋井という場所で『「話せなさ」を亡きものにしないで話す』というワークショップを開催されて、タイトルが面白そうだと思って参加したら、とても楽しかったんです。その後、たまたま東京に行ったときに鳥公園の公演も観に行って。
西尾:ある日電話がかかってきて「町で作品を作るので手伝ってもらえませんか」と言われました。そのときに(鈴木)一郎太さんがおっしゃっていた「町を歩くんだけど、『町の人とこんなに仲良くなりました』とかじゃないことがしたい」「生まれ育った人間でなければ、いくらそこにいても疎外感はある」という言葉に共感したし、特に印象に残ったのが「生活圏とは何だろう? と考えている」ということで。
―昔にくらべて今は、交通網が発達して、コストも安くなって、生活圏は広くなったと言われています。
西尾:でもそうなったからといって、自分の持っている時間もエネルギーも有限なので、世界が広がることにはならなくて、薄まる部分もあるんじゃないかと考えていたんです。どこで生きているとか、誰と生きているという感覚が、うかうかしていると薄まっていく。一郎太さんの話では、それが「生活圏」という言葉で表されていて面白いなと。あと私も、よその町で作品を作って「こんなに仲良しになりました」と主張することが胡散臭いと思ってしまう性質なので……(苦笑)。もちろん仲良くなるのはいいことなんです。でも、何でそれをわざわざ言うのかなって思うんですよ。それで、電話口ですぐに「やります」と(笑)。

『例えば朝9時には誰がルーム 51 の角を曲がってくるかを知っていたとする』
鈴木:地域でアートプロジェクトをやっている人は、何かにつけて言いがちですよね。「あそこのおっちゃんと仲良くなってさ」「今日もあそこのおばちゃんにお漬物もらっちゃった」とか勲章みたいに。自分たちは外側から来た人間なのに、そこでまた「もうこんなに内側の人間として認められた」というテリトリーを作っても仕方ないですよね。それはまったく地域を開くことにならないんです。
西尾:町って何だろう? と考えるとき、私の中でもちゃんと実感できていない。今回の作品制作で、一郎太さんや制作メンバーに会いに静岡に行くことが増えましたけど、私の中では東京と静岡が隣り合っていて、間にある町は認識できていないんですよね。その一方で、静岡を認識するときには、会いに行く具体的な人なり場所なりを通じて町を捉えている。それは何だか、ライナス(「スヌーピー」シリーズの登場人物)が毛布を引きずって歩いてるような感触に似ています。くっきりしたプレーンな静岡ではなくて、いろんなものがズルズルとつながっているというか。
―目的とか関係性という「事情」を、町歩き作品に取り入れるということでしょうか?
西尾:作品はおそらく、実際には存在しない虚構の町を感じてもらうものになると思います。実在する静岡の町を歩いてもらいながら、そこにはない町を読み取ってもらうというか。……ちょっと話がズレるかもしれないんですけど、いいですか?
―はい(笑)。
西尾:ずっと以前から、私の中で続いているテーマで、東日本大震災を経験してからより強くなったんですが……。自分がどの時代の、どの土地の、どの家庭に生まれるかは本当にすべて偶然で、それをちゃんと受け入れていきたいと思っているんです。たとえば、ユダヤ人が第二次大戦中に虐殺されたときのように人は理不尽な目に遭うと「なぜ自分なんだろう?」「なぜ自分ではなく、あの人なんだろう?」という疑問が湧きますよね。

『ふたりの女 平成版 ふたりの面妖があなたに絡む』 Photo:橋本武彦
―圧倒的な理不尽の前では、人の思考はそこに行き着きますね。
西尾:先日読んだ本の中で、そうした理不尽に対して「神はいないということでしょうか?」と聞く人がいて、それに対してエマニュエル・レヴィナスという哲学者が「善行をしたらいいことが起きて、悪行をしたら罰が当たるという等価交換の原理より、神の考えはもっと大きいんじゃないか」と話していて、その感覚は少しわかると思いました。私は特に信仰はないんですけど、今ここに自分がいる事実を受け入れること、それって町の感覚にもつながると思っています。なぜか私は東京に生まれて、東京を拠点に演劇をしていて、出て行くこともできますけど、とりあえず今はこうだということをちゃんと考えるというか。すべて偶然なんだけど、そういった不如意なことと、それを引き受けてやっていく意志の両方を持つことが、町で作品を作ることにつながっているんじゃないかと思ってるんです。
―大きな理不尽と、すべて偶然のような日常を、「不如意」と「自分の意志」で重ねて作品にしたい、ということですね。
西尾:そうしたいと思っています。
政治的なことと、表現・芸術が分かれているべきだという空気がけっこう長く続いてきたような気がしていて。でも本当は、みんな自分なりに社会についての考えを持っていると思うんです。(西尾)
―それにしても、宮城さんが投げかけられたテーマは相当に大きく、また複合的ですね。一口に「地域の人の役に立つ劇場」と言っても、今すぐ役に立つのか、100年先も役立つのかという問題もあります。「それは100年先でしょう」と言えたのが芸術だったし、美しい理想ですが、今の日本の芸術を支えている助成金制度は「目の前」がベースになりがちで、多くのアーティストもそれを甘受している。そして「目の前」を重視すると、市民の通報で美術館から作品が撤去されたりという「不寛容」を助長することになりかねない。

『盲点たち』Photo:Pierrick Blondelet
宮城:そうなんです。今はまだ「劇場は必要だ」という前提が打ち立てられていなくて、「なんで税金使ってあんなものを作るのか」という段階ですから。せめて図書館と同じレベルで「自分たちの町に劇場を作るのは当たり前」というところまで行かないと。しかも同時に劇場を、不寛容を少しでも押しとどめる多様性の発信基地みたいにするのは可能なのか? その問いも、今みんなで話し合ったところで答えは出ないし、「しょうがない」という声が大きくなるだけの気もするんです。でもせめて考えたい。そのヒントとして、今回のプログラムには、唐十郎作の『ふたりの女』やモーリス・メーテルリンク作の『盲点たち』などを置き、かつてこういう時代にこういう人たちがいたんだ、ということを知り、どうやってそのときの荒波を乗り切ったのかを想像することで、少しでも考えを進めていきたいというのが、今年の演劇祭の狙いというか、願いなんです。
―今日の宮城さんのお話を受けて、鈴木さん、西尾さんは、ご自身も含めて2015年に日本で芸術に携わることを、どんなふうに捉えていらっしゃいますか。
西尾:私自身や、私の近くにいる人たちは、社会の出来事と表現を近づけなくては、と考えている気がします。これまで個人的な表現をしていた人が、「何かしないと」「それじゃダメだ」と言い始めている。でも、それもまたナイーブというか、二者択一的すぎるんじゃないかと思ったりもします。日本特有なのかわかりませんが、政治的なことと、表現・芸術が分かれているべきだという空気がけっこう長く続いてきたような気がしていて。でも本当は、みんな自分なりに社会についての考えを持ってるし、作品にはそれが当たり前に流れ込む。そういう意味で、すべての作品は「社会派」だし、政治的だと思うんです。それ以上に社会に直進しようとするのは、つまり芸術を手段にして課題を解決するみたいなことですけど、それは違うというか。
鈴木:アーティストがただの生活者になっている気がします。必ずしもアーティストが浮世離れしているべきとは思わないのですが……。極端に言えば、人が亡くなったとき、慈しみの念を持って喪に服さないといけないことはわかっている。だけど、そんなときでもアーティストは必要であれば、何事もなかったように表現を続けられるかどうかが、僕はとても大事な気がしていて。
―いわゆる「お上」だけでなく、「隣の市民」も不謹慎狩りに熱心な現在の状況もあって、アーティストも迷ってしまっているということでしょうか?
鈴木:ええ。地域のアートプロジェクトで活躍するアーティストも増えているので、非常に難しい。地域アートプロジェクトって、評価はあるけど批評ってあまりないんですよ。というか、できないんです。そこに住んでいる人たちのことも批評の対象にしなきゃいけなくなるので。
―アーティストも批評家も、生活者の側に引っ張られている。
鈴木:さっき東日本大震災の話が出ましたが、日本ではあのときをきっかけに「つながり」ということが言われるようになりました。でも「みんな、そんなにつながりたかったっけ?」と思うときもあるんです。特に最近は、「人との関係を大事にして暮らしたい」「手の届く所での生活を大切にしたい」「地元で獲れたものを食べたい」「個人ブランドを大事にしたい」とか、優しい感じがすごく流行っている。アメリカでも「ヒップな生活革命」でしたっけ? ポートランドあたりで、リーマンショックを契機に同じような趣向を求める人が増えていますよね。
―新しい生活スタイルの提案とともに、お行儀の良さが推奨されていくということですか?
鈴木:でも、そういう変化にアーティストが飲まれるのはどうかと思うんです。せめてそこは「飲まれているフリ」にしておいてほしいというか。最近、おしゃれなアーティストがすごく多いんですよ(笑)。しかも雑誌に出るようなおしゃれ感。人によく見られたい、優しく生きたいとかって、生活の話だと思うんです。できるだけアーティストは抗っていなきゃと僕は思う。不器用ですけどね、抗っている人は。
―私は昨年も宮城さんにインタビューをさせていただきましたが、今日うかがった『ふじのくに⇄せかい演劇祭』の今年のテーマの背景に、かなり深い危機感があることにショックを受けています。ここから大きな議論が広がっていったらいいですね。
鈴木:それは僕らの作品に期待されていることじゃないですよね?(笑)
―いや、先陣を切って劇場から町にガンガン飛び出して行ってください(笑)。それでいろんな感想や意見がぶつかり合うといいですね。長時間ありがとうございました。
- イベント情報
-
- 『ふじのくに⇄せかい演劇祭2015』
-
2015年4月24日(金)~5月6日(水・振休)
会場:静岡県 静岡芸術劇場、静岡県舞台芸術公園など
上演作品:
『メフィストと呼ばれた男』(演出:宮城聰)
『ふたりの女 平成版 ふたりの面妖があなたに絡む』(演出:宮城聰)
『盲点たち』(演出:ダニエル・ジャンヌトー)
『觀(カン)~すべてのものに捧げるおどり~』(無垢舞蹈劇場芸術総監督・振付・ビジュアルコンセプト:林麗珍)
『聖★腹話術学園』(演出:ジャン=ミシェル・ドープ)
『天使バビロンに来たる』(構成・演出:中島諒人)
『ベイルートでゴドーを待ちながら』(作・演出:イサーム・ブーハーレド、ファーディー・アビーサムラー ※サルマド・ルイの協力による)
『小町風伝』(演出:イ・ユンテク)
『例えば朝9時には誰がルーム51の角を曲がってくるかを知っていたとする』(演出:大東翼、鈴木一郎太、西尾佳織)
- プロフィール
-
- 宮城聰 (みやぎ さとし)
-
1959年東京生まれ。演出家。SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。東京大学で演劇論を学び、1990年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出は国内外から高い評価を得ている。2007年4月SPAC芸術総監督に就任。2014年7月『アヴィニョン演劇祭』から招聘され『マハーバーラタ』を上演し絶賛された。その他の代表作に『王女メデイア』『ペール・ギュント』など。2004年『第3回朝日舞台芸術賞』受賞。2005年『第2回アサヒビール芸術賞』受賞。
- 鈴木一郎太 (すずき いちろうた)
-
(株)大と小とレフ取締役。1977年生まれ。97年に渡英、アーティストとして活動。帰国後、浜松市を拠点に置くNPO法人クリエイティブサポートレッツにて、社会の多分野と連動し、様々な文化事業(場づくり・展覧会・トーク・人材育成事業・町歩き等)の企画を担当。2013年、(株)大と小とレフを建築家の大東翼とともに設立。主にプロジェクト企画、マネジメント、アートディレクションに携わる。Central St. Martins College of Art & Design, MAファインアート修了
- 西尾佳織 (にしお かおり)
-
劇作家・演出家、鳥公園主宰。1985年東京生まれ。幼少期をマレーシアで過ごす。東京大学表象文化論科にて寺山修司を、東京藝術大学大学院音楽環境創造科にて太田省吾を研究。2007年に鳥公園を結成以降、全作品の脚本・演出を担当。「正しさ」から外れながらも確かに存在するものたちに、少しトボケた角度から、柔らかな光を当てようと試みている。生理的感覚やモノの質感をそのままに手渡す言葉と、空間の持つ必然性に寄り添い、「存在してしまっていること」にどこまでも付き合う演出が特徴。東京を拠点にしつつ、様々な土地での滞在制作も積極的に行っている。『カンロ』にて、『第58回岸田國士戯曲賞』最終候補作品にノミネート。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-