自然と人間、自然とアートは、どのような関係を築いていけばいいのか。リサイクルやエコのブームが盛り上がる一方、私たちはどれだけ自然のことを知っているのか。「ナチュラル アメリカン スピリット」を販売するたばこ会社「サンタフェ ナチュラルタバコ ジャパン」が主催する、公募プログラム『FUTURE CULTIVATORS PROGRAM』でグランプリを受賞した相澤安嗣志は、そんなことを人に問いかける作品の作り手だ。弱冠24歳、大学卒業からまだ半年にも関わらず精力的に活動をする彼が一貫して素材として用いてきたのは、「錆」だ。
「キレイなものを見せること」だと一般的には考えられているアートの世界に、人工物に付着した「ノイズ」とも取れる錆を持ち込むのはなぜなのか。その自然観には、幼少期を過ごした里山での生活や、大学入学直前に起こった東日本大震災の影響があるという。日本画からワークショップなどのコミュニティー活動へ、そして現在の鉄を用いた作品へと移行してきた独特の変遷も含め、注目の若手アーティストに胸の内を訊いた。
「錆びる」というと、一般的にはネガティブに捉えられがちですが、実はそこに自然の力を感じることができるんです。
―今回の『FUTURE CULTIVATORS PROGRAM』は、「NEW RECYCLE®」がテーマに掲げられていますが、そこに相澤さんは錆を用いた作品『Flow(ov)er』を出品し、見事グランプリに輝きました。最初に、錆という珍しい素材を使いはじめたきっかけからお伺いできますか?
相澤:僕は育ったのが神奈川県相模原市にある城山という、わりと里山的な場所で、自然がとても身近にありました。小学校から授業でも「自然との共存」を学んだり、ホタルが生き延びられるよう餌の養殖をやったり、川の掃除をしたり。そうしたなかで、当然のように環境問題に興味を持つようになったんです。
―では、「NEW RECYCLE®」というテーマもすんなり入ってきた?
相澤:はい。錆のもとである鉄は地球をかたち作っている核になるものですし、錆という現象は「人間が自然に与えている影響のメタファー」でもある。
―メタファーというと?
相澤:人間の些細な行動で、われわれの気づかぬうちに環境や社会に影響を与えていることって結構多いと思うんです。鉄は人の影響を受けやすくて、たとえば人が新しい鉄に触れると、手の油をつけた部分以外は錆びてしまう。「錆びる」というと、一般的にはネガティブに捉えられがちですが、実はそこに自然の力を感じることができるんです。そこに面白さを感じて、大学時代から、環境に対する自分の関心を、錆や鉄といった素材に落とし込みはじめました。

『Flow(ov)er』 ©Atsushi Aizawa 2015年 Photo:表恒匡

『Flow(ov)er』(部分) ©Atsushi Aizawa 2015年 Photo:表恒匡
―最初はどのように鉄や錆を使いはじめたんですか?
相澤:最初は自分で調合した溶液で鉄板をどんどん錆びさせていき、絵画のようなものを描いていく作品でした。今回の作品『Flow(ov)er』は鉄粉で遊んでいたことから生まれた作品で、これまでの鉄板を使った平面作品ではなく、立体作品を作りたいという願望があったんです。それで、土台となるパネルに磁石を仕込んで、鉄粉と水溶液が混ざったもののうえに被せ、引き上げる際の磁力と張力で、花が咲いたような姿に鉄粉を固定しています。壁から花が生えたようなイメージで、正確な花のかたちにはできませんが、不自然でいびつなかたちが、いまのアンバランスな社会に見えてむしろ面白いかな、と。
皮肉なことに、津波でゴミが陸上に残されたことで、海は綺麗になったと言われている。極論ですが、最終的に人間は自然に勝てない。
―今回の作品のモチーフとしては何があるのでしょう?
相澤:都市の道でよく見かける、コンクリートの割れ目から生えた植物の姿です。それは人間界に対する自然界の抵抗のように見える。これを作品に昇華させたかったんです。

『FUTURE CULTIVATORS PROGRAM』展示でのプレゼンの様子 Photo:表恒匡
―少し大きな話ですが、一般に文明やアートなどの「人工物」は、「自然」の対立物と考えられていますよね。美術館が作品を保存するように、ふつう、作品は自然現象による経年劣化を嫌うものです。しかし相澤さんの場合、人工的に環境を管理したとしても出てきてしまう、自然の力に関心があるというのが面白いですね。
相澤:極論ですが、最終的に人間は自然に勝てないと考えています。それは、東日本大震災における津波でも明らかになったことですよね。とても皮肉なことですが、原発の問題は別として、あの津波でゴミが陸上に残されたことで、海は綺麗になったと言われている。僕自身、父の実家が津波の大きな被害を受けた宮城県の石巻で、家も全部流されてしまいました。鉄や錆に関心を持ちはじめたのも、育った環境に加えて、「最後は自然が勝つんだ」と思い知らされた「3.11」の影響が大きかったです。鉄は文明の発展の象徴ですが、人は、鉄は使っても錆は受けつけないような、いびつな付き合い方をしてきたと思っています。
―それでも、錆はどこかで生じてきてしまうわけですよね。鉄を使うのなら「良いとこ取り」はできない、錆も受け入れるべきだ、ということですか。
相澤:はい。自然のなかでは、人間から見た「劣化」は必ず起きるものなのに、人間はそれを抑圧してきたと思うんです。そもそもがそういう考えなので、作品もすべて自然に還る素材で作っています。
―錆のアートというとカオティックなイメージを抱きがちですが、相澤さんの作品を見ると、造形的に非常に繊細だったり、パネルを格子状に並べたりと、コントローラブルな要素とアンコントローラブルな要素が共存しているのも面白いですね。
相澤:出自が日本画だったことも影響しているのかもしれません。一応、錆の進行を止める処置も施しています。そのまま壁に設置すると重力に負けて、1週間ほどでボロボロになってしまうので(笑)。これは今後の課題ですね。
大学に行って何をすべきか、わからなかったんです。それで、浪人でも何でもないフリーター生活をしていました。
―いまおっしゃったように、相澤さんは大学2年まで日本画学科にいたそうですね。そこに至る経緯を知りたいのですが、どんなお子さんだったんですか?
相澤:小さいころから絵を描くのが好きな子どもでした。絵をよく褒められたので、夢を尋ねるアンケートにも「画家」と書いていました。外で遊ぶのが得意ではなく、軽度の色盲なので「色鬼」などやっても色がわからない(笑)。なので、みんなが外で遊んでいる間は室内で絵を描いていたんです。親が広告の裏紙なんかを用意してくれて。
―いい話ですね(笑)。どんなものを描いていたんですか?
相澤:身近な人の顔や風景、ゲームやアニメのキャラクターなど何でも手当たり次第に描いていました。小学校の友達の人物画などを描かされる授業では、良い評価をもらっていましたね。でも中学時代は「絵を描くのはオタク」みたいな風潮があって、思春期がゆえにそれが嫌でバスケをやり、高校時代は完全に遊んでいました。それで、大学受験を前に完全に行き詰まった(笑)。
―というと?
相澤:大学に行って何をすべきか、わからなかったんです。それで、しっかり考えたいと思って、浪人でも何でもないフリーター生活をしていました。街の健康食品のサプリメント工場で、ライン生産の仕事をしたんです。その生活が半年くらい続いたころ、自分が人より秀でているものは何かと考え、美術大学に進んでみようかな、と。でも予備校も行っていないし、きっちり絵を描いたことなんかない。それでとりあえず受験要項を取り寄せたら、他の学科には色彩構成などがあるのに、日本画学科には「水彩画とデッサン」しかない。「これならいける」と(笑)。
―それで美大合格はすごいですね(笑)。
相澤:だから、日本画に特別な思い入れがあったわけではないんですけど、実際に入ってみるといろいろ感じることはあって。一番大きかったのは、日本画学科では結局、作品が「絵の良し悪し」で語られてしまうんです。それが悪いというわけでは決してないのですが、でも僕が気になっていたのは、「良い絵」と言われるものが一般の人にどんな影響を及ぼすのかということで、日本画の「良い絵」ではそれがよくわからなかった。僕はもう少し、社会とのつながりを感じられる表現がしたかったんです。それで、多くの学生が学科を変える3年生になるタイミングに、メディア芸術の学科に移って、「コミュニティアート」というゼミを取り、ワークショップなど地域でのアート活動などに参加しはじめました。

『Effect - Old tree』 ©Atsushi Aizawa 2014年
―そのころから、個人の表現というより社会の課題に関心があった、と。
相澤:そうです。学生時代はとくに「これがカワイイ / カッコイイから作った」という動機の人が周囲に多かったのですが、僕はそこに関心がなかった。それでなんとか日本画で社会との接点を表現しようとしたのですが、どうしても1枚の絵として見られてしまう。それで挫折したんですね。ならば別の道に踏み出した方が活路は開けるんじゃないかと考えました。
―相澤さんの世代だと、大学入学のころに東日本大震災が起きたわけですよね。当時はプロのアーティストや関係者も、自分の仕事を見直すことを迫られました。
相澤:それは大きかったです。僕は「3.11」の1か月後に大学に入学したんですが、アートが社会に何をできるか、教え手である教授や講師自身が模索している時期でした。実際に僕も、高速道路が復旧してすぐに、被災地にボランティアで入りました。

『Effect - Hinomaru』 ©Atsushi Aizawa 2014年
―ただ、そうしたワークショップ的な活動を続けたあと、ふたたび個人としての作品を作りはじめたのはなぜでしょう? 勝手なイメージですが、一般の人も巻き込んだ制作となると、今度は作品のクオリティーが問題になるのではないか、と。人と関わる意義はあるけど、結果としての作品自体は、なかなか鑑賞向けにはなりにくいというか。
相澤:それもひとつありますね。一般の人々と作る作品では、できあがったもの自体が美しいかと問われれば、そうでもないのがふつうです。すると、その制作に関わった人にしか興味を持てないものになって、結局は鑑賞者の範囲が狭まってしまう。
―日本画でぶちあたった「絵」の狭さと同じ問題が出てきてしまうわけですね。
相澤:個人の制作に戻ったのは卒業制作からです。3年から4年の大半の時期は絵から離れていたのですが、「卒業制作をどうする」という段になって、現在の作品につながる三六判の鉄板4枚を使ったインスタレーション的な平面作品に戻りました。『Effect #1』という作品で、形式としては平面作品なのですが、言いたいのは絵としてどうかということではなく、先ほども言ったような錆という現象の意味だったんです。
アートは崇高なものではないのだから、一般の人の感覚を遠ざけて、アートシーンの枠のなかだけで作品を描くのはやはり違う。
―『Effect #1』は何の図像もなく、シンプルに鉄板を錆びさせた作品ですね。
相澤:最初は錆で何かを描こうとしたのですが、人に「それでは絵として受けとめられる」と言われ、抽象的な表現にしました。作り方もある程度は偶然に任せていて、コントロールとアンコントロールの繰り返しで、鉄板を斜めにして溶液を流すなど、自然の動きをそのまま使っています。絵を描いていたときに一番辛かったのは、「よくわからない」と言われることだったので、多くの人が普段からを目にしている現象を使って、目の前のモノが訴えかけてくる迫力を生み出したいと思いました。

『Effect #1』 ©Atsushi Aizawa 2014年

『Effect #1』(部分) ©Atsushi Aizawa 2014年
―たしかに、多くの人が感じる絵画に対するハードルに「絵の意味がわからない」ということがあるかと思いますが、錆びた鉄板に向かうのはとても身体的な体験と感じます。
相澤:「なんかかっこいい」と思わせられたら、まずはいいんです。最近は作品の流通の問題にも関心があって、質の高い作品をいかに偶発的に一般の人の前に持っていくか、ということも考えています。いま「REBIRTH PROJECT」のメンバーでアーティストの藤元明さんたちと、「ソノ アイダ」という都市の空きテナントを使った展示を行うプロジェクトをやっているんです。ギャラリーってアートに興味がある人しか行かない、ふらっと気軽に入れる場所にはなっていないので、それであれば作品を、人々の生活のなかに介入させてしまい、貸し物件や管理スペースに展示して、次のテナントが入るまでの「その間」を、空間メディアとして活用する試みです。
―鑑賞者の反応の変化は感じますか?
相澤:面白いですよ。ギャラリーのつもりではなく、ふらっと入った店が展示場になったりしていて、地域の評判もいいです。アートは崇高なものではないのだから、一般の人の感覚を遠ざけて、アートシーンの枠のなかだけで作品を描くのはやはり違うと思います。実際に日本画をやっていたときは自分の生活圏も狭まっていて、アトリエに食材を持ち込んでみんなでご飯を食べたりしていたのですが、そうするとどんどん塞ぎ込んだ環境で制作していることに気づきました。

『Effect #2』 ©Atsushi Aizawa 2015年 Photo:森田友希
―先ほど受賞後のスピーチで、「貸しギャラリーではないかたちでアートを展示する方法を考えたい」とおっしゃっていましたが、それも「ソノ アイダ」と関わるのですか?
相澤:はい。基本的に学生が展示をしようと思ったら、貸しギャラリーにお金を払って展示するわけです。たとえば銀座あたりだと、1週間で十数万円以上の費用がかかります。
―もちろん、そこで成果を得るアーティストもいると思いますが、展覧会の告知をしてくれないギャラリーなんかもあって、効率があまり良くない印象ですよね。
相澤:広報といっても、知り合いのギャラリーにDMを置いたり、閉じた世界での宣伝に留まっていると感じます。それなら「ソノ アイダ」のように、ギャラリー以外の場所に展示したり、自分で練った企画を商業ギャラリーに持ち込んで認めさせたりするような、別の関わり方を考えないといけない。いま腐るほどアーティストはいるので、正攻法ではないやり方を模索しないと埋もれてしまう。試行錯誤をしているところです。
「リサイクル=良いことだからやっている」という人は、「捨てる」場面だけではなく、「消費する」や「買う」場面でも、考えたほうがいい。
―そうした活動をされるなかで、意識されているアーティストはいますか?
相澤:僕のなかで印象的なアーティストは名和晃平さんなんです。大学に入学してはじめに観たのが名和さんの東京都現代美術館での展覧会で、とても衝撃を受けました。現象や素材に重きを置いているところも自分と重なりますし、名和さんが京都に作った様々なクリエイターの創作のためのプラットフォーム「SANDWICH」などの活動にも影響を受けています。
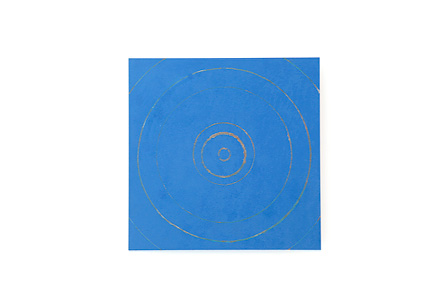
『EFFECT - Ripple #1』 ©Atsushi Aizawa 2015年 Photo:森田友希

『EFFECT - Ripple #2』 ©Atsushi Aizawa 2015年 Photo:森田友希
―たしかに名和さんの「SANDWICH」のような活動は、先ほどの相澤さんのアートの領域を広げていこうという志向性と被りますね。ところで、それほど高い社会への関心をお持ちでありながら、たとえば起業とか、就職とかは考えなかったのですか?
相澤:高校のときとは違って、一応そこは考えました(笑)。就職してお金を貯めるという方法もありましたが、それで中途半端になるなら、多少無理してバイトをしながらでも、短期間は腹を括って美術活動をしてみたほうがいい、と考えました。若いうちに成果を出してみたい、という思いもあります。覚悟を決めたというか。実際に半年間やってみて、就職することでは得られない、人のつながりは得られたと思います。
―相澤さんの作風だと、建築とのコラボレーションなどもあり得そうですよね。
相澤:実際、今年に個展を開いた際は、建築関係のお客さんが多かったです。また、これも震災に関係しているのかもしれませんが、自分にできることなんてたいして多くない、と思っているんです。だから今はまだ、起業などのように「新しい分野で何かをしたい」というよりも、「できることをいかに伸ばすか」という発想で生きています。
―あくまでも表現のなかで、社会に対する考え方をかたちにしたい、と。最後にもう一度、今回のプロジェクトについて訊くと、受賞スピーチで「ラディカルな意味でのリサイクルとは何かを考えたい」と語られていましたが、これはどういういう意味ですか?
相澤:今回のテーマは「NEW RECYCLE®」ですが、僕としてはより根本的に、リサイクルを考える必要があると思うんです。たとえば、なかには「リサイクル=良いことだからやっている」という人もいると感じるのですが、それであれば「捨てる」場面だけではなく、「消費する」や「買う」場面でも、それを考えたほうがいいと思います。
―よく言われることですけど、「クーラーがガンガン効いた部屋で、エコの本を読みながら何かを考えているフリをする」みたいな人はけっこういるわけですよね。
相澤:それだともう、意味がわからないですよね(笑)。「なぜこれを分別しなくてはいけないのか」や、「この商品や作品は自然環境に害を及ぼさないのか」といった、普段の生活のなかで出会う、もう少し現実的な部分にも目を向けたほうがいいと思うんです。コンクリートのうえに咲く花に注目したのも、そういった気持ちがあったからです。
―錆も含め、そこに自然の生命力や治癒力が宿っているわけですよね。
相澤:コンクリートのうえに咲く花を見ても、それを特別には意識しない人が多いと思います。しかしコンクリートから花が咲くというのは、やはりすごいことなわけです。だから、自然からの小さなメッセージに、もう一度、敏感になってほしい。そういう小さな部分にみんなが目を向けることで社会は変わると考えて、制作を続けています。
- イベント情報
-
- 『“FUTURE CULTIVATORS” PROGRAM #1「NEW RECYCLE®」curation by REBIRTH PROJECT』
-
2015年7月15日(水)~10月11日(日)
会場:東京都 渋谷 PUBLIC HOUSE
料金:無料(カフェ内のスペースのためオーダーが必要)
主催:サンタフェ ナチュラルタバコ ジャパン株式会社
- プロフィール
-
- 相澤安嗣志 (あいざわ あつし)
-
1991年、神奈川県生まれ。2015年、多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース卒業。2015年に個展『Effect』(ソノアイダ)を開催。同年には『現代芸術復興財団アートアワード 第2回CAF賞入選』(3331 Arts Chiyoda、東京)も果たした。
- フィードバック 3
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-








