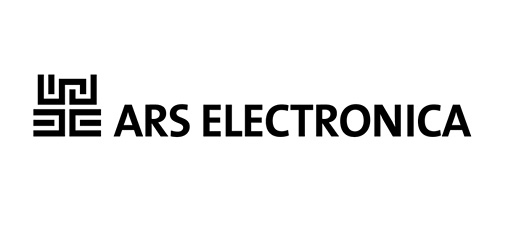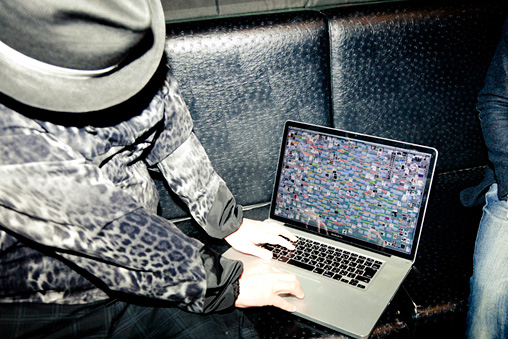12月18日、香川県高松市で『高松メディアアート祭』がスタートする。「高松でメディアアート? 需要はあるの?」。そんな素朴な感想を抱いた読者に伝えたいのは、今回の祭りが、そうしたわれわれの疑問のはるか斜め上を行くほど、あるいは「メディアアート」の概念すらひっくり返すほどの、とんでもない催しになる、ということだ。
ゼネラルディレクター・キュレーターを務めるのは、高松出身の現在芸術家・宇川直宏。自身の作品発表はもちろん、ライブストリーミングチャンネル / スタジオ「DOMMUNE」において、日々、世界の知られざる偉人を紹介し続ける彼が『The Medium of the Spirit-メディアアート紀元前-』のサブタイトルのもと招聘したラインナップには、1980年代にメディアを席巻した超能力者や、明治から昭和初期にかけて最先端のテクノロジーに注目し続けた「大本」の開祖、コックリさんをオートマティズムとして解析する現代アート、近年遺品として15万枚以上の写真が「発見」されて「20世紀の写真史を書き換えた」と噂される謎の女性写真家、自身の腕に第3の耳を移植した身体拡張アーティストなど、数々の逸脱した出展者が記されている。
先端テクノロジーを駆使する「メディアアート」の一般的イメージとはかけ離れた、このラインナップに隠された意図とはどのようなものなのか。その並びの先に見えてくる、人知を超えた「なにか」の今日的意義とは? 祭りの開催を目前に控え、常人には招集困難なアーティストたちのキュレーションに紛糾する、宇川のもとを訪ねた。
メディアアートが世界に溢れているけど、「メディアアートとはなにか?」という問いに対して、充分な定義ができていない。
―2015年末に突如、高松でメディアアート祭が開かれると聞いて驚きました。「なぜ高松なのか?」「なぜメディアアートなのか?」ということからお聞きしたいのですが。
宇川:そこはやはり、世界的に有名な『瀬戸内国際芸術祭』が同じ香川県で行なわれていることが重要でしょう。「ベネッセアートサイト直島」など、瀬戸内海の島々ではさまざまなアートプロジェクトが動いています。ただ、高松市がメインのものはこれまでなかったんですよね。そこで「自然と人間の交錯」をテーマにした島々での試みとの差別化を図る意味で、高松市のほうから「メディアアート」というキーワードが出てきたようです。そして、それを実現するなら、コンペを通してアーティストをフックアップするプロジェクトと、招待作家展示の両方をやってしまおう、と。そのディレクション / キュレーションと、コンペの審査委員長を任されたんです。

『高松メディアアート祭 第1回 The Medium of the Spirit -メディアアート紀元前-』フライヤービジュアル
―宇川さんに声がかかったのはなぜですか?
宇川:高松出身ということや、ここ3年間『文化庁メディア芸術祭』で審査員をやってきたこと、今年の『アルスエレクトロニカ』電子音楽部門の審査委員を担当した経験などから、声がかかったんだと思います。『文化庁メディア芸術祭』の審査員は今年で任期満了になりますが、今回のエンターテインメント部門の受賞作、素晴らしかったでしょう? 「ヒゲの未亡人」などで音楽活動もされる岸野雄一さんが、音楽劇『正しい数の数え方』によって強豪を押しのけ『大賞』に輝いた。これは、「人形劇+演劇+アニメーション+演奏」といった複数の表現で構成される、観客参加型の作品なんですが、安易なテクノロジーに埋没しない原初的なアニマ(生命、魂)についての批評を体現していました。そのように、高松の方もメディアとアートの融合を再定義するようなものを見せたい、と。そういった意志で、今回のメディアアート祭のコンセプトが生まれたんです。

アルスエレクトロニカ・センター Photo: Nicolas Ferrando, Lois Lammerhuber
―タイトルにもある『The Medium of the Spirit-メディアアート紀元前-』ですね。
宇川:いま世界はメディアアートに溢れていますよね。にもかかわらず、「メディアアートとはなにか?」という問いに対しては、誰も充分な定義ができていないと思うんですよ。100年残ることを希求するアートの普遍性と、日進月歩で進化し消費されるテクノロジーの急進性とは、そもそも相反するわけですが、両者の関係を深く掘り下げると、アートとオカルティズムの問題に行き着かざるを得ない。
―えっと……(笑)。
宇川:たとえば、いま人工知能が人類の知性を超える「2045年問題」、いわゆる「シンギュラリティー(技術的特異点)」が話題になっていますが、それは前世紀であれば、一種のオカルトに近い発想だったわけです(笑)。しかし、それがリアリティーを帯びてきた現在にあっては、急に科学史的考察の対象になっている。また「ディープラーニング」(人工知能による繰り返し学習)によって人工知能がクリエイティビティーを発揮している現在、人間が描くべき美とはなにか? そもそもポストヒューマンを考えるにあたって、ヒューマニズムをどう捉えればいいのか? といったことが問題になっています。あるいは、感情と意思と知識の総体が「心」ならば、生と共に朽ち果てる単なる器に過ぎない「身体」をどう考えるのか、も。
―ああ、じゃあ、このタイトルにある「spirit」というのも……。
宇川:本当は「spirituality(スピリチュアリティー)」と言い切りたかったのですが、江原啓之以降、ずいぶんと怪しい言葉に成り下がってしまったので(笑)。つまり、「テクノロジーと人間の潜在能力との間の、ギリギリの格闘のようなエネルギー」をメディアに写し取った作品を、世に問いたいのです。「メディアアート紀元前」としたのは、もし「メディアアート史」が存在したとしても、そのなかでは語られないであろう、「超自然的な領域とメディアとの本質的な関係」をあぶり出す存在を世に問おうということです。じつは彼らの表現にこそ、いまメディアアートを考える上での重要な問いが含まれている。この話は、具体的に作品を紹介すれば、よりはっきり見えてくるはずです。
ビッグデータや人工知能が目指す領域の1つは、誤解を恐れずに言えば、「超能力」についての考察だと思っているんです。
―参加作家の顔ぶれを見ると、「メディアアーティスト」とは呼ばれることなどなかった、非常に個性的な方が多いです。
宇川:「紀元前」という意味でまず挙げたいのは、清田益章さんです。彼は、1970、80年代にテレビメディアを席巻した超能力少年「エスパー清田」なんです。なにが重要かというと、広告や金融業界ですでに実用化されているビッグデータに基づく未来予測や、人工知能がディープラーニングを通して目指す領域の1つの側面というのは、誤解を恐れずに言えば、広義な意味での「超能力」についての考察だと思っているんです。
―人の「能力」を「超」えた領域の開拓ですからね。
宇川:これまでも人間は、テクノロジーによって一種の超能力を身にまとってきたと言えます。たとえば、カメラ発明以前は、日常の1コマを図像として切り取る能力なんて人間にはなかった。だけど1830年代のダゲレオタイプの実用化以降は、それを当たり前に行えていますよね。そんななかで清田さんは、既存の写真技術を使わず、心に思い浮かべる「観念」をポラロイドフィルムに感光させて図像に写し出す「念写」の実験を1980年代に行っていたんです。
―われわれが技術によってできるようになったことを、技術なしでも可能かどうか、実験していた、と。
宇川:そうです。ギリシア語の「テクネー(技術)」や、ラテン語の「アルス(人工)」が、英語の「アート」の語源だったように、「人間の潜在能力」というものを、メディアアート以前のテクノロジーと身体の問題を問うものとして、象徴的に見せられないか。つまり1970年代から清田さんがやっていたことは、現在のポストヒューマン的な問題の、生身の身体による実践だったのではないか? と思うわけです。具体的には、彼が過去にポラロイドに残した図像や、「脱超能力者宣言」をされた後の活動を再認識するような展示を行う予定です。
僕が日夜、写経のように修行を積んで、世界中のセレブに憑依し描き続けた偽サイン1000枚は、ネット時代だからこそ実現した、純粋な美術表現だと言い切ります(笑)。
―最初からぶっ飛んでいますね(笑)。それでいうと新興宗教「大本」の教祖・出口王仁三郎も参加アーティストとして登場しますね。リストを見ていて、その名前で思わず吹き出しました。
宇川:今回の展示会場は高松城の跡地にある披雲閣という御殿で、僕も子どものときに遠足で訪れたりした馴染み深い場所なんですが、そこに出口王仁三郎の作品を展示できるのは感慨深いです(笑)。本来、美術は宗教と密接だったわけですが、なぜ王仁三郎の作品がメディアアート紀元前かというと、彼は伝統主義的な宗教観を持っていたにもかかわらず、最先端テクノロジーを使ってその観念を世に伝え広めてきたからです。たとえば、登場間もないレコードに説法を吹き込んだり、日活系の撮影部隊を使って『昭和の七福神』(1935年制作)という映画を監督、出演までしていたりする。

出口王仁三郎
―そこにもメディアと超自然的なものの「紀元前」的な出会いがあった。
宇川:そう考えられます。しかもこの映画で重要なのは、民間信仰のポップアイコンであった七福神をテーマにしていることで、王仁三郎自身、七福神のコスプレをして登場しているのですよ(笑)。つまり、現在のヲタ系のポップカルチャーとも接続している。メディアを通してキャラクターに扮し、自らの身体を演劇的なパフォーマンス空間に投じているんです。
―一種の憑依的なパフォーマンスだったわけですか。なるほど、そこに現代美術家・岡崎乾二郎さんの「コックリさん」をベースにした作品や、宇川さん自身の「憑依サイン」シリーズ、そして真鍋大度さんのディープラーニング絵画が絡んでくるのですね。
宇川:そうです。岡崎さんが探求している世界の前提には、コックリさんのオートマティズムに対しての研究がある。コックリさんの動きというのは、超自然的な現象か、神のお告げか、コインに指を置いている誰かの意志なのか、わからないわけです。同じように岡崎さんは、絵を描く「手」は、それに絵を描けと命じる「作者」によって搾取されていると考えます。そこで、この「手」と「作者」の関係を反転させるため、固定された手の持つ筆の下で、プログラミングされた有名画家の筆跡どおりにキャンバスを動かす装置『テーブル・ターニング・ティルボット』を作った。つまり、キャンバスが勝手にピカソやゴッホの名画を描かせてくれて、そのとき手の主体は有名画家の主体を乗っ取ることになるはずなのですが、ここで重要なのは、キャンバスが同じ筆跡を誘導するにもかかわらず、生み出される絵は各人によって違うということです。ここには芸術作品における作家性の本質が顕在化されています。
―キャンバスにプログラミングされた主体と、手の主体の衝突が起きるわけですね。
宇川:もしくは、人間の意思がテクノロジーを越えた、とも捉えられますよね。そこに創作の秘密がある。同じ文脈で展示する僕の『UKAWA'S TAGS FACTORY!!! 1000 Counterfeit Autograph!!!』は、日夜、写経のように密かに修行を積んで世界中のセレブリティーに憑依し描き続けた偽サイン1000枚からなるシリーズです。なぜこれがメディアアートかというと、「オリジナルサインを検索→デジタルアーカイビング→サイン書写訓練→身体憑依→サイン着床」というプロセスで生まれる、ネット&クラウド時代だからこそ実現できた、極めて今世紀的なメディアに依存した作品だからです。写経的修行感やトランス感、印刷・コピー技術の変遷、また、偽サインが流通するネットオークションへの啓発、社会生活におけるサインの意味性、アートピースに内在される匿名性と作家性を問う、純粋な美術表現だと言い切ります(笑)。そしてビッグデータの処理技術と同じく、収集、取捨選択、保管、検索、共有、転送、解析、可視化が、これら憑依サインシリーズの課題となっています。
―憑依サインは、意外にもデジタル技術との関係によって可能になったんですね。
宇川:つまり、なにが作品の真性を担保しているのか? という話で、同じコーナーで展示する真鍋大度さんの「ディープラーニング絵画」と言うべき新作も、それに連なるものです。人工知能にディープラーニングをさせて調教し、描かせた作品なのですが、そのとき真鍋大度という作家はどこにいるのか? つまりこの三名の作品は、どれもデジタル技術と画像に基づく作品であり、コックリさんのオートマティズム、憑依におけるトランスドローイング、ディープラーニングを考えることによって、より根源的な生身の脳や身体性が浮き彫りになるはずだと考えているのです。
ブルース・ビックフォードは、フランク・ザッパとコラボしたことで知られるクレイアニメーションの偉人であり、究極的な奇人です。
―いずれも、最先端技術にこびりついた一種の人間性や「魂」の問題を扱う作品であることがよくわかりました。海外からも大物のアーティストが何名か参加していますね。
宇川:ブルース・ビックフォードは、フランク・ザッパと共同制作をしたことで世界的に知られるクレイアニメーションの偉人ですが、作品から作家そのものまで、とにかく究極的な奇人です。オーガニックな果物とフレッシュジュース、100%カカオのチョコレートしか口にしない極端なビーガンで、偏執狂的にストップモーションの独自世界を生み出し続けている(笑)。「アニメーション」は、ラテン語で「霊魂」を意味する「アニマ」が語源ですが、動かないものに命を与えて動かす、果ては精霊信仰や世界創造にまでつながる崇高な理念なんですね。そのビックフォードが初来日し、子どもたちとワークショップも行ないます。
―一方、ヴィヴィアン・マイヤーは、最近、日本でもプチヒットした映画『ヴィヴィアン・マイヤーを探して』で名が知れ渡った写真家ですね。
宇川:彼女は国籍も素性も明かさず、乳母として働きながら15万枚以上のストリートスナップを撮り続け、生前1枚も公表しなかった謎の天才写真家です。映画の監督でもあるジョン・マルーフが、オークションで写真や手紙、カメラといった彼女の遺品を380ドルで落札し、その写真をブログで紹介することで世界中から賞賛コメントが付き、バズを起こしたわけですが、生前付き合いがあった人々が口を揃えて「奇人だった」と言うわけです。さらには写真だけでなく、ポッドキャストのように音声日記をつけていたり、当時まだ高価だった8ミリフィルムでライフキャスティングのように日常を切り取っていたこともわかった。アンディ・ウォーホル的な記録魔なんです。
―彼女の生活と写真の関係は、まるで「Instagram」みたいですね。
宇川:まさにそのとおりです。当時の先端テクノロジーを使ってライフログを残した人だったんですよ。彼女の写真集は、現在アメリカで売上1位なんですが、今回はじめてオリジナルプリントを日本に上陸させます。つまり、ヴィヴィアン・マイヤーの物語は、SNS以降に生まれた神話なのです。彼女の活動はきわめてブログ的で、屈折したジャーナリズム的視点から、主観的現実のみを切り取った極私的メディアだった。「ファイナルメディア」と銘打って、日刊のライブストリーミングチャンネルDOMMUNEを自力で世に放つ僕としては、彼女の存在にこの上なき共感を覚えます。茶渋のように蓄積された個の生活履歴、その痕跡から作家性が浮き彫りになってくる。そのライフログそのものを、メディアアートとして再認識したいと思っています。
今回のテーマは、テクノロジーと人間の潜在能力のギリギリの格闘から生まれるエネルギーなんです。
―そうしたメディアアートを再定義するような作家が多くいる一方で、世界的なメディアアートの本拠地とも言える『アルスエレクトロニカ』の受賞作家もたくさん登場しますね。
宇川:インターネットは脳を拡張する装置なわけですが、今回来日するSTELARCは、第3の耳を左腕に移植した作家です。正確には軟骨細胞を培養した耳型に、BluetoothマイクやGPSを内蔵して腕に埋め込むというプロジェクトで、つまり人工器官を生み出し、自らの身体をメディアとして拡張する実践なんですよ。その意味でも今回のテーマとシンクロしています。また、今年の『アルスエレクトロニカ』でグランプリを受賞した赤松音呂さんの『Chijikinkutsu』は、日本庭園の水琴窟の概念をグローバルに進化させ、地球上に存在する地磁気を視聴覚化することを主題としています。
―さらにChim↑Pomの発案によって、現在、東京電力福島第一原子力発電所周辺の帰還困難区域内で開催されている展覧会『Don't Follow The Wind』のサテライト展示まであるという……。
宇川:目に見えない放射性物質に汚染された空間のなかで「現在」と「未来」を考えるという意味において、赤松音呂さんの作品と、近似したモチベーションを感じます。でも、さすがにいろんなアーティストを呼びすぎて、ここでは全然語りきれないですね……。やばい、どうしよう(笑)。
―(笑)。しかも、それらの作品が国重要文化財であり、松平家の別邸として建てられた「披雲閣」で展示されるのがすごい。
宇川:この御殿は迎賓館の役割も持ちあわせていたようですが、国の重要文化財である御殿にメディアアートを展示する試みは、ヴェルサイユ宮殿でジェフ・クーンズが現代アートを展示したような、異種格闘技的で歴史を超越した興奮が立ち現れる、新しいプロジェクトになると考えています。他にもコンペ受賞作の展示や、DOMMUNEのサテライトスタジオからの配信も行います。後者では、ホーメイの伝統や骨伝導マイクの発声を探求する山川冬樹さんや、アバンギャルドの巨星・灰野敬二さん、声のみで音響世界を構築するハチスノイトさん、電子音楽×映像の異種交配実験を続けるBRDG、僕が近年もっとも重要な音楽家の一人だと信じる七尾旅人さんのパフォーマンスなどを、10日間連続ストリーミングします。そしてなんと、地元高松のアバンギャルドの師匠、DEKUさん率いるビニール解体工場も30年ぶりに復活しますよ。
―お話を聞いてきて、今回の試みはメディアアートに限らず、いかにアートの神秘性や神話性を再発見するのか? を問うものだと感じたのですが。
宇川:そうだと思います。ただ、現在のアートにおける神話的世界の構築は、ブランディングやセルフマネジメント能力による部分も大きい。この世界を生き抜くには、それもたしかに重要でしょう。しかし今回のテーマは、メディアとアートに内在する急進性と普遍性、テクノロジーと人間の潜在能力のギリギリの格闘から生まれるエネルギーなんです。その背景には、いま多くのメディアアートは科学に寄り添いすぎてはいないか? という思いもある。つまり「魔法」と呼ばれたものが「科学」であったように、文明によって解明される以前の現象や意志の力を浮き彫りにする、そんな血の通ったフェスを目指しています。そうした意味で今回の展示は、メディアアート、そしてアートの本質を真剣に考える人にとって、重要な問題提起になると思いますよ。この10日間をめざして、ぜひ高松にお越しいただければ嬉しいですね。
- イベント情報
-

- 『高松メディアアート祭 第1回 The Medium of the Spirit -メディアアート紀元前-』
-
2015年12月18日(木)~12月27日(月)
会場:香川県 高松 玉藻公園披雲閣、常磐町商店街、南部三町ドーム、北部三町ドーム、サンポートホール高松ほか
時間:10:00~21:00(18日は18:00から)
料金:
前売 披雲閣入場券(玉藻公園の入園料含む)800円
前売 DOMMUNE入場券(披雲閣入場と玉藻公園入園料含む) 一般1,600円 高校生以下1,000円
前売 Nibroll 2,000円
当日 披雲閣入場券(玉藻公園の入園料含む) 一般1,000円 高校生以下500円
当日 DOMMUNE入場券(披雲閣入場と玉藻公園入園料含む) 一般2,000円 高校生以下1,500円
当日 Nibroll 2,500円
- プロフィール
-

- 宇川直宏 (うかわ なおひろ)
-
1968年香川県生まれ。映像作家 / グラフィックデザイナー / VJ / 文筆家 / 京都造形芸術大学教授 / そして「現在美術家」……幅広く極めて多岐に渡る活動を行う全方位的アーティスト。既成のファインアートと大衆文化の枠組みを抹消し、現在の日本にあって最も自由な表現活動を行っている自称「MEDIA THERAPIST」。2010年3月に突如個人で立ち上げたライブストリーミングスタジオ兼チャンネル「DOMMUNE」は、開局と同時に記録的なビューアー数をたたき出し、国内外で話題を呼び続ける「文化庁メディア芸術祭推薦作品」。今年は『アルスエレクトロニカ』サウンドアート部門の審査委員も担当。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-