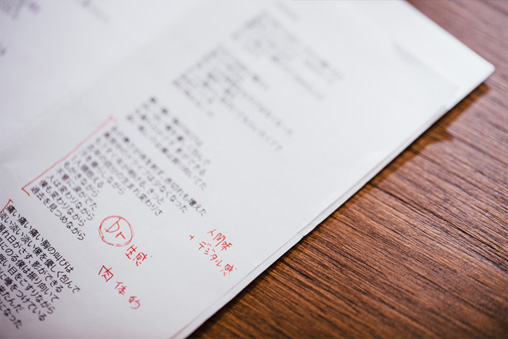ただの空気の振動。もしかしたら、LILI LIMITの牧野純平と土器大洋は、音楽をそんなふうに捉えているのかもしれない。そして、そんな「ただの空気の振動」に、人々が様々な感情や日常を投影させる――そんな音楽という奇跡に、何よりも深く感動しているのかもしれない。
去年、1stミニアルバム『Etudes』で全国デビューを果たした男女混成5ピースバンド・LILI LIMITが、2ndミニアルバム『#apieceofcake』をリリースする。ロックバンドの枠組みを大きく逸脱した、ハイブリッドで最先端の音像を持ちながら、クラシカルな室内楽や1960年代のファンクにも通じる、極めて原初的なポップスとしての野性も持っている彼ら。その音楽は常に、「音楽とは何か?」「ポップスとは何か?」という問いかけを聴き手に投げかける、そんな挑戦的な眼差しもはらんでいる。
今回、「a piece of cake」という言葉に「#(ハッシュタグ)」を付け、作品の名に冠してみせた彼らは、音楽を通して、一体何をわかち合おうとしているのだろうか。コンポーザーである牧野と土器に話を聞いた。
東京に出てきて、「自分たちなりのJ-POPを作りたい」という意識も出てきたんだと思います。(牧野)
―僕がLILI LIMITの音楽を聴いてまず感じたのは、とても緻密で論理的なものから、どんどん論理を剥いでいって、感情的、動物的なものを生み出そうとする表現だということなんです。
牧野(Vo):そういう部分はあると思います。彼(土器)は、どちらかと言えば家でパソコンと向き合って構造的に音楽を作るタイプで、僕はどちらかと言えば感情的に作るタイプで。この二人が主に曲を作っているバンドだから、そう思われるのかもしれない。
―実際、牧野さんと土器さんの対照的な個性が、LILI LIMITの核にあるのかなって思うんです。ただ、最初に山口県でLILI LIMITが結成されたとき、まだ土器さんはメンバーではなかったんですよね?
牧野:そうですね。土器と出会う前、僕がLILI LIMITを始めたときって、どんなバンドになりたいかは何も考えていなくて。ただ自分の内側から出てきたものを信じて、それをメンバーと共有して作っていく形だったんです。でも、18~20歳くらいの頃って、成長して大人になっていく時期だから、1年前に書いた歌詞を読むと「なんて俺は大人じゃなかったんだろう」って後悔するんですよね。そこが、段々とフラストレーションになっていって。土器と出会った頃には、自分が今までやってきた音楽が嫌いになっていました。
―土器さんと出会ってから、福岡に活動の拠点を移すんですよね。
土器(Gt):当時、僕は僕で牧野と同じように煮詰まっていて。お互い、出会う前は今とは全然違う、感情を吐き出すような音楽をやっていたんです。暗い音楽を、お客さんの方も見ずに激しく演奏して、数人に伝われば他の人が引いていても関係ないっていう。でも、大人になるにしたがって、「もっと伝わる音楽を作りたい」と思うようになったんですよね。
―そこで牧野さんと土器さんの意識が重なって、今の形のLILI LIMITが始まると。
牧野:ただ、福岡にいる時点では、THE NAKED AND FAMOUSとかMEWとかPASSION PITとか、自分たちが影響を受けた海外アーティストっぽい音楽を作るという範疇にいたと思うんです。でも、2014年に東京に出てきたことで、「もっと伝わる音楽をやるべきだ」という意識が本格的に根付きました。東京はバンドの数も多いし、たくさんの人と話す機会が増えたことで、やっとお客さんのことをちゃんと見始めたし、「自分たちなりのJ-POPを作りたい」という意識も出てきたんだと思います。
土器:自分らが出したい音を、どう伝わる音楽に落とし込むかを考え始めましたね。
―福岡で活動していた時代は、音楽はあくまで自己表現の手段だったのが、東京に出てきて、たくさんの人がいる空間を生み出すものだという考え方に変わった。
牧野:そうですね。ライブは、「いい歌」を歌うというより、「いい空間」の中で歌いたい。その空間に馴染むような歌を歌いたいっていう気持ちが強くあります。
土器:空間を作りたいという考え方は、一緒にやり始めたときから考えてはいたと思うんです。でも、どういう空間を作りたいのかという意識が、東京に出てきてから変わったのかもしれない。
ゆずさんのようなメジャーなJ-POPの曲作りと、LILI LIMITの曲作りって、かけ離れたものだと思っていたんですけど、意外と同じだと思う。(土器)
―今のLILI LIMITが理想とする「音楽空間」って、どういうものだと思いますか?
土器:楽しんでもらうのは前提として、こちら側がこだわって出しているちょっとした音にも気付いてもらえるような空間ではあってほしいです。僕らが発信した音一つひとつが耳に届いてくれたらなって思いますね。「あの瞬間の、あの隙間がよかったな」とか、「あの鍵盤のフレーズがかっこよかったな」とか。そういう音のパーツも覚えていてくれたら嬉しい。
―土器さんは、でんぱ組inc.の作曲や、ゆずの楽曲アレンジなど、メインストリームで活躍するミュージシャンともお仕事されているじゃないですか。そういった巨大なポップフィールドでの音作りの経験も、LILI LIMITとしての空間作りに影響を与えていますか?
土器:メジャーなJ-POPの曲作りと、LILI LIMITの曲作りって、かけ離れたものだと思っていたんですけど、意外と同じなんだなって今は思っていて。ゆずさんのアレンジ(“かける”の編曲を担当)をさせていただいていた時期と、今回のリード曲の“Festa”を作っていた時期は同じなんです。ゆずさんって、めちゃくちゃたくさんの人に届くメジャー性を持っていると思うんですけど、そのメジャー性を僕らの音楽に落とし込んだらどうなるんだろう? っていうところから、“Festa”のアイデアは出てきていて。向いている意識としては繋がる部分があるんじゃないかな。
―その「繋がる部分」って、具体的にどんな部分だと思いますか?
土器:まず、ゆずさんから依頼をいただいたとき、「すごく広い会場で、お客さんが波のように揺れる曲がほしい」と言われたんです。しかも、「繰り返すフレーズがほしい」とも言われたんですね。その2つのテーマって、多くの人に一発で曲を伝えるためのピースだなと思って。それでまず、“Festa”のイントロのコーラス部分ができました。とにかく歌えるし、繰り返される。
―「波のように揺れる」とか「繰り返されるフレーズ」って、ハウスの4つ打ちとか、あるいはファンクやヒップホップのループがわかりやすいですよね。音楽で「空間」を作るにはすごく有効な手段かもしれない。
土器:あと、僕に関していうと、ゲームからの影響も大きくて。家がゲームをやる家庭だったんです。糸井重里さんが作った『MOTHER』で流れる音楽が、小さい頃から耳に入っていて。「これはこの場面にいったときの音楽だ」とか、ロケーションやシチュエーションに応じて音楽が変わっていく感じに慣れ親しんできたんです。なので、アルバムをサウンドトラック的に捉える部分があるんですよね。どんな気持ちを表現したいときに、どんな楽器を使うのか……そういう部分でゲームから影響を受けてきたのは大きいかもしれないです。
美しい歌を作ったとしても、それを悲しいものや汚いものと思ってくれていい。そのすべての思いを共有できる空間を作りたいんです。(牧野)
―ただ、どれだけ音楽が「いい空間」を作ったとしても、そこに言葉が乗ることで、そこにはボーカリストの「個」が際立ってしまうし、その人の自己表現として受け取られてしまう可能性がありますよね。その点を、牧野さんはどう考えていますか?
牧野:僕は、抽象的な歌詞を書きたいっていう気持ちが強くあって。とにかく、全員が全員、同じ答えを出してほしくないんです。今回、『#apieceofcake』というタイトルに込めた願いがあって……。
―ハッシュタグも付いているし、すごく印象的なタイトルですよね。
牧野:心のケーキというか、美味しいものを共有するということなんですけど。僕らミュージシャンは、いろいろある感情の中の、ひとつの感情しか表現できないかもしれない。でも、LILI LIMITの音楽の面白さは、ある人がAだと思ったものが、他の人が聴くとBとかCとかに聴こえるときがよくあるということで。僕が「美しいものを歌いたい」と思って美しい歌を作ったとしても、それを悲しいものだと思ってくれてもいいし、汚いものだとも思ってほしい。そのすべての思いを共有できる空間を作りたいんです。僕らの音楽自体を「美味しくない」と思う人がいても、その人を拒絶するんじゃなくて、「そうだよね」って言ってもいい。
―正解や共感はいらない?
牧野:よくお客さんに「この歌詞って、こういう意味ですよね?」って訊かれるんですけど、僕、そういうことを訊いてくる意味がわからなくて。別にいいじゃないですか、毎日答えが変わったって。僕の歌詞は、美術的なのかもしれないなって思います。僕、TARO NASUギャラリーとか、いろんなギャラリーに行くのが好きなんですけど、美術って、作品に対して解説があるわけではなくて、自分で作品の意味を考える。たとえば木が描かれていたら、「この木は人の生活にとって癒しだな」とか「悲しさもあるけど、その悲しさの中には優しさがあるな」とか、いろんなことを想像するじゃないですか。そうやって、僕らの音楽からも、いろんな意見が出てきていいと思うし、いろんな人に想像してもらいたいんです。
―ただ、先ほど牧野さんは「自分たちなりのJ-POPを作りたい」と言っていたじゃないですか。J-POPって、少なからずスターやアイドルの絶対的な言葉を必要としてきた文化でもあると思うんですよ。
牧野:そうですよね。日本人って、常に何かしらのアイドルを探していて、その人が「イエス」って言うことに対して、みんなも「イエス」って言ってしまう……そういう傾向はあると思います。それに対して「はぁ?」ってなっちゃうときがあるんです。“vanilla ice claim”は、決して政治的なことを歌いたかったわけではなかったんですけど、結果として日本人の性質に対する苛立ちが歌詞に反映されていますね。
―それぞれの「自分」には様々な気持ちや変化が存在している。それこそが、牧野さんがLILI LIMITなりのJ-POPで表現したいことなのかもしれない。
牧野:押しつけがましくなりたくないんですよ。「俺を愛せよ!」なんて歌いたくないし、人の人生に対して「お前は大丈夫だから、前に進め!」とも言えない。「ありのままでいいんじゃない?」としか言えないです。だって、気持ちなんて日によって変わるじゃないですか。そっちのほうがリアルだと思う。
今って、「孤独だなぁ」って思ったときに、Twitterとかで「孤独だ」ということを発信できるじゃないですか。それが現代において一番問題なんじゃないかと思う。(牧野)
―牧野さんの描く言葉は、すごく自分自身に向き合おうとしている言葉だなって思うんです。それに、そうすることが今の時代においては難しいということにも向き合っている。こういう側面は、どうして出てくるんだと思いますか?
牧野:確かに僕はずっと「自分」というものを探している感覚があって。「これって本当に自分の頭の中で考えたことなんだろうか?」って考え始めることがよくあるんです。
―たとえば“Festa”の<日用品が自分を映す鏡だ>とか、“morning coffee”の<世界とは自分の目でしかない>という歌詞とか、世界と自分との関わりが牧野さんにとっては重要なのかなと思ったんです。
牧野:そうですね……今って、「孤独だなぁ」って思ったときに、Twitterとかで「孤独だ」ということを発信できるじゃないですか。それが現代において一番問題なんじゃないかと思っていて。「私、死にます」なんてことも共有できるのは恐ろしいことだよなって思うんです。
―人の気持ちって、そう簡単に他者に説明できるものでもなければ、一元的に共有できるものでもないですもんね。でも、“Festa”のこの歌詞がいいのは、「日用品」という言葉を使うことで、人それぞれの「日用品」を想像する。そこに解釈の余地があるなって。
牧野:<日用品のメモこそが自分を映し出す鏡なんだ>って歌詞は、自分の中では「名言を書いたな」っていうぐらいに思ってます(笑)。
サカナクションって、お客さんがどんどん広がっていくイメージなんです。でもセカオワは、また違う広がり方をしているというか。(牧野)
―実際、ライブの現場などでお客さんを見て、自分たちの音楽の受け取られ方に対して思うことはありますか?
牧野:すごく嬉しくなるときが大半なんですけど、ステージ上にいても、実際はステージ上にいる感覚がないんです。常にお客さんと同じ土俵にいる「普通の人」でいたいっていう気持ちが強いのに、ステージ上で「手を挙げてくれ!」なんていう言葉がすんなり出てくる自分もいて……。
―もしかしたらLILI LIMITはその差異を強く感じるのかもしれないですね。音楽で空間を作りたいだけであれば、匿名的なアンビエントミュージックを鳴らしていればいいと思うんですよ。でも、LILI LIMITには言葉が絶対的に必要になっている。その上で抽象的な「空間」を生み出そうと思うと、その苦しみは直面せざるを得ないかもしれない。
牧野:そうなんですよね。
―この先、LILI LIMITとして目指していきたいことはありますか?
牧野:いつになるかわからないですけど、メンバーみんながそれぞれの活動をちゃんとできたらいいなって思います。僕の兄がデザイナーをやっていて、バンドのデザイン面でも助けてくれているんですけど、そうやっていろんな分野において携わってくれる人を増やして、チームみたいにしていけたらいいなって。LILI LIMITがひとつの会社みたいになって、音楽とは別の方向にも手をのばせたらいいなと思いますね。
―今、日本ではサカナクションが、そういったチームとしての動きをとって音楽から他のカルチャーにも広げていこうとしていますよね。
牧野:サカナクションとは、よく似ていると言われます(笑)。だから、もっと考えないとって思ったりします。サカナクションはずっと好きなので、彼らとはちょっと違う、僕ららしい場所に落とし込んでいければいいなって。
―SEKAI NO OWARI(以下、セカオワ)はどういうふうに見てますか? 彼らの音楽性も、特殊なJ-POPの在り方としてあると思うんですよ。
牧野:ああ、サカナクションよりセカオワのほうが近いのかもしれない……セカオワにはパンク魂を感じるんです。“Dragon Night”が売れてから、次のシングル曲で英詞を取り入れていったりする。あの流れは絶対に何年も前から考えていたんだろうなって思うし。
土器:裏切りみたいなものがありますよね。見ていて「やられた!」と思わせる感じはかっこいいと思う。
牧野:サカナクションって、お客さんがどんどん広がっていくイメージなんです。でもセカオワは、また違う広がり方をしているというか……山口さんはロックスターというイメージですけど、Fukaseさん(セカオワのボーカル)はスターでありながらも、もうちょっとリスナーに近いイメージがあると思うんです。入る隙間があるというか。
―これは僕の解釈ですけど、山口さんには、オルタナティブなものを世の中に広めていこうという目的意識や使命感がはっきりとあると思う。それに対してFukaseさんは、すべてにおいて自らの「表現」を第一義に置く人だと思うんです。だから、「広める」よりも「巻き込む」に近い。そして「表現」である以上、そこには様々な解釈の余地が生まれるのかなって思いますね。表現って、曖昧なものだから。
牧野:うん、そうですね。僕が感覚的に作ったものを、土器がパソコンで向き合って論理的にする。そして、それをまた僕が感覚的に戻す。そのバランスが重要な気がします。そうやって音楽を作っていくことで、僕らの間に絶対に隙間が出てくるんですよね。お互いからまったく同じ意志は、絶対に出てこないから。その隙間が、聴いている人がいろんな解釈をしてくれるために重要なのかなって思いますね。今後はメンバー五人で作る曲があってもいいと思うから、また深く隙間が出てくるんじゃないかな。
土器:そうだね。考える余地とか、単純な音の隙間とか、そういう曖昧でぼんやりした部分は残しておきたいですね。聴いているときの心地よさはJ-POPと同じだけど、聴き終わったあとには「あれ?」って引っ掛かったり、ちょっと歌詞カードを読み返してしまいたくなるような、クエスチョンが残るようなものではありたいです。
- リリース情報
-

- LILI LIMIT
『#apieceofcake』(CD) -
2016年1月20日(水)発売
価格:2,160円(税込)
LACD-02671. Festa
2. Boys eat Noodle
3. N_tower
4. morning coffee
5. seta gaya
6. vanilla ice claim
7. lycopene
8. nnmnd
- LILI LIMIT
- イベント情報
-
- 『#apieceofcake release tour2016』
-
2016年2月21日(日)
会場:大阪府 心斎橋 JANUS2016年2月26日(金)
会場:愛知県 名古屋 APOLLO BASE2016年3月13日(日)
会場:東京都 新代田 FEVER
- プロフィール
-

- LILI LIMIT (りり りみっと)
-
男女混成5人組バンド。2012年、ボーカル牧野を中心に山口県宇部にて結成、その後福岡へ拠点を移動し現在のメンバーになる。2014年より東京にて活動を開始。自主制作CD“moduler”を残響SHOPレーベルよりリリース。2015年4月ラストラムより1stシングルを店舗限定にてリリース。発売日から完売店舗が続出するなど新人バンドとしては驚異的なセールスを記録。同年7月、初のミニアルバム『Etudes』を全国リリース。そして2016年1月20日、2ndミニアルバム『#apieceofcake』をリリースする。
- フィードバック 3
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-