繊細な魂が、世界に手を伸ばす瞬間――糸奇はなの音楽を聴くと、そんな、痛みに満ちて、でも愛おしい瞬間に立ち会っているような感覚を覚える。
幼い頃から本格的に声楽を学び、DTMを使ってオリジナル楽曲を生み出すシンガーソングライター、糸奇はな。ゲーム音楽をアレンジして動画サイトに投稿するところからキャリアを始め、楽曲制作から演奏、打ち込み、歌唱まですべて自分でこなし、イラストや漫画の執筆、刺繍や版画、果てはウェブ制作まで「創造」と名のつくあらゆるものに手を伸ばす。彼女の創造物の奥には、どうしようもなく世界を必要とし、世界に必要とされようとする自身の「実存」と「意志」を感じることができる。その表現の一つひとつには、彼女の震えるような息づかいが、とても生々しく刻まれている。
「ものを作る」ということは、決して何かを表明したり、象徴することではない。それはいつだって世界への問いかけであり、不安定さや曖昧さと共にある。糸奇はなにとって、きっと「作る」ことと「生きる」ことは同義であり、だからこそ彼女の存在は、同じように曖昧さと共に生きる人々にとって、ひとつの希望になり得るのではないだろうか。
ロンドンで『オペラ座の怪人』を観たときに「私は歌う人になろう」って決心したんです。
―本当にたくさんのインプットとアウトプットを持っている方なので、どこから話を聞こうかなっていう感じなんですけど(笑)、ご自身としては、「糸奇さんってどういうことをやられているんですか?」と聞かれたら、まずは何と答えますか?
糸奇:一番には、「音楽を作って歌っています」と言いたいです。そこから、「詩も書いています」「音楽から連想する絵なども描いています」と答えたい。
―SNSには日常的にイラストや刺繍を制作している様子をアップされていますけど、創作の軸足は音楽にあるんですね。糸奇さんが最初に音楽を作りたいと思ったのはいつ頃ですか?
糸奇:中学生ぐらいのときです。小さい頃からピアノをやっていたり、クラシックの道を志して声楽をやったりしていくなかで、「私だったらこの旋律のあと、こういきたいな」「もっとこういう詩の歌を歌いたいな」っていう気持ちが湧いてきて。中学生になった頃に、自分の好きな旋律と好きな言葉で音楽をやりたいと思うようになりました。
―そこから、初めてご自身の作品を世の中に発表したのは、どんな形を通してだったんですか?
糸奇:2011年に大好きなゲームの主題歌をカバーして、動画サイトにアップしたのが初めてでした。大学生になってDTMソフトを買って、自分のオリジナル曲を作り始めたんですけど、そのときは「こんな音色があるんだ」「こんなふうに音を重ねるんだ」って実験的に曲を作ってて。当時は初音ミクが流行っていた頃で、ボーカロイドの曲でもない、無名の人のオリジナル曲はなかなか聴かれない状況もあったので、カバーにしようと思ったんです。
―確かに、2011年頃はボーカロイドが流行っていましたね。ボカロシーンから出てきた米津玄師さんのような存在が注目され始めたのも、そのぐらいの頃でした。
糸奇:米津玄師さんはすごく尊敬しています。米津さんの作るものは、音、歌詞、歌い方、それに絵や動画もすべてがひとつの世界に繋がっている。表現が自己完結していて、すごいなって思います。私も、そういう世界が作れたらいいなって思うんです。
―糸奇さんは、子供の頃はどんな子でしたか?
糸奇:幼い頃はとても明るい性格だったんですけど、小学2年生の頃に、スイスのジュネーブに父の仕事の都合で引っ越したんです。そこで、言葉の違いや文化の違いで、伝えたいことが言えなかったり、人種差別みたいなものを経験したこともあって、大人しくなってしまったんですよね。
―小学生には重すぎる経験ですね。
糸奇:大事な友だちが悩んでいるのに、「悩んでいるの?」って訊いても言語の違いで力になれない無力さを経験したり、でも逆に、言葉はわからないけど仲良くなれるっていうことも経験できたり。それで、ちょっと複雑な性格になって日本に帰ってきた気がします。身ぶり手ぶりで話すことも増えたし、目をじっと見る癖がついてしまったりしたので、そういう海外生活で身についたものをなるべく押さえなきゃと思って、中高生の頃は、ちょっと引っ込みがちなキャラになってしましました。
―ジュネーブで暮らしていた頃の経験は、今の糸奇さんの創作に影響を与えていると思いますか?
糸奇:とっても思います。日本とヨーロッパではクラシックの扱われ方が全然違うんですよね。ジュネーブにいた頃に旅行でロンドンに行って、そこで『オペラ座の怪人』を観たときに「私は歌う人になろう」って決心したんです。
「なりたい自分」とか「近づきたい自分」みたいなものとして「糸奇はな」がいる気がします。
―『オペラ座の怪人』は、当時の糸奇さんに何を与えたんでしょうか?
糸奇:物語がすごく悲しいんです。当時は小さかったので、怪人さんの闇をそこまで理解はしていなかったと思うんですけど(笑)、怪人さんが出てきただけで照明が真っ赤になったりするのが、当時の自分からしたら、仲間外れにされている子みたいですごく可哀想に思えて。「怪人さん可哀想~」って泣いていました。
最後、主人公のクリスティーヌは怪人さんではなく幼馴染の男の子とくっついちゃうんですけど、私だったら、絶対に怪人さんを幸せにするのにって思ったんですよね。なので、いつか私がクリスティーヌになって新しい物語を作るんだって決意して、そこから声楽の道を志しました。
―オペラ座の怪人を救うために歌い始めたんですね。
糸奇:そうですね(笑)。怪人さんを幸せにする結末を描きたいと思ったんです。……今思うと、怪人さんは自分のなかにずっといる気がします。怪人さんはクリスティーヌに歌ってもらうために、ひとりぼっちでずっと曲を書いていて。でも、私は自分で作って自分で歌うので、自分のなかに怪人さんとクリスティーヌがいたらいいなって思います。自分のなかではずっと仲良しでいたらなって。
―声楽の道に進んだとき、人前で歌うことに対する勇気や度胸は必要ではなかったですか?
糸奇:それはあまり必要ではなかったですね。声楽では、歌い方の癖をつけてはいけないんです。正しい発声の仕方があるし、曲にも作曲者の意図や詩を書いた人の意図があるので、正しい歌い方とか、曲を通して表現しなきゃいけないことが明確で。
「私」という人格がそこにあるというよりは、人間の形をした楽器が、死んでいった作曲者や詩人たちの想いを代弁しているっていう感じ。自分の声も感情も全部材料で、それを通してひとつの世界を作るのは今でも好きだなって思います。自分のなかに作曲者や構成をする人がいて、代弁者としての自分もいるっていう、すべてを自分のなかで作れたら面白いですよね。
―じゃあ、「糸奇はな」という存在は、どこか自分自身の代弁者として存在している感じなんですかね?
糸奇:そうですね……本名ではないですし、「なりたい自分」とか「近づきたい自分」みたいなものとして「糸奇はな」がいる気がします。
クラシックや美しい詩、プログレにも共通するのは、現実の虚無感を紛わすことだと思う。
―聴いてきた音楽はクラシックが多かったですか?
糸奇:クラシックも多かったですけど、ロックやJ-POPも聴いていました。ロックバンドの精神性にも憧れていましたね。特に好きなのは、Pink FloydとKing Crimson、あと、Siouxsie & the Bansheesというバンドがすごく好きで。
―プログレやパンク / ニューウェーブ期のバンドがフィットしたんですね。
糸奇:そうかもしれないです。The Beatlesも好きですけどね。あとは、やっぱりクラシックの西洋音楽の精神性もものすごく好きで、特にヨーロッパの昔の詩人がすごく好きでした。一番好きな詩人は、イギリスのジョージ・ゴードン・バイロン(1788年~1824年)という方なんですけど、幻想的で繊細で、その繊細さのなかに胸を突き刺すようなものがあるんです。
壊れてしまいそうなガラスのようで、でも壊れるときにザクッと切りつけるような……美しいものが散る瞬間、でもその瞬間が最も輝いているという、表裏一体なこと表現する。そういう詩にはすごく影響を受けましたね。
―プログレやパンクに求めていたものも、そこに通じるものだったんですかね?
糸奇:音や言葉が、自分を違う世界に運んでくれるところは一緒だったと思います。King Crimsonの曲を聴いて、ピアノのドーンっていう音に頭を殴られたような気持ちになったり、バイロンの詩を読んで「ここではないどこか」にいる気になったり……。
そうやって新しい世界を覗けたり、ここではないどこかの空気に触れることができる醍醐味を、音楽や詩から感じていました。クラシックや美しい詩、プログレにも共通するのは、現実の虚無感を紛わすことなのかなって思います。
―「人は現実を直視して生きていかなければいけない」という考え方もあるじゃないですか。でも、糸奇さんが音楽に求めるのはそこではない。
糸奇:ないものねだりな性格なのかもしれないです。現実には存在しないものを、ないものと受け入れるのか、自分で作ったり、手に入れるために努力をするのかっていう違いだと思うんです。「ない」ものを、「目を閉じてあることにしよう」って思えたら、もしくは「ある」と信じることができたら、その人は幸せなんじゃないかなぁって思うんですよね。
糸奇:人には憧れや幻が必要だと思うし、虚構とか作りもののほうが綺麗に見えたり、舞台上の出来事のほうが、現実よりも現実味を持つことがある……私はそれが好きなんです。『オペラ座の怪人』も、舞台上の嘘の話ですからね。
―僕も、人には憧れや幻を信じる気持ちが必要だと思います。でも、それは現実の絶望や残酷さと表裏一体ですよね。
糸奇:そうですね。もちろん、恐怖もあります。たとえば、小さな島で暮らしている亀がいて、亀が一所懸命、島をぐるぐる回って「僕は世界を一周したんだ」と思い込んで幸せな一生を送ったとするじゃないですか?
でも実際には、その隣にもっと大きな島があって、その島の上を飛んで行く鳥は「小さな島で亀が幸せそうな顔をして死んでるなぁ」なんて思うかもしれない。自分はその亀になってしまわないかと思ってゾッとするし、そこに妙な虚無感や怖さを感じることもあります。
「なりたい自分になっても必要とされなかったら?」って……今、この問いに苦しんでいる人はいっぱいいると思う。
―そのたとえ話はつまり、外の世界の存在や、他人の視点を糸奇さんは意識しているということですよね。糸奇さんの作る曲――たとえば、“ROLE PLAY”などは、そうした外部との関わり合いのなかのどこに「自分」という存在を置くのか、ということがポイントになっているような気がします。
糸奇:そうですね。“ROLE PLAY”で書いているように、なりたい自分になれたとしても、それが他人に必要とされなかったり、社会的に無益であったら、私は寂しいなぁって思う。音楽もひとりよがりなものは作りたくないんです。自分が作って満足したものでも、誰にもわかってもらえなかったら、まるで違う言語で話しているみたいじゃないですか?
―糸奇さんがジュネーブで体験したように、ですね。ちなみに、“ROLE PLAY”はどういった想いでできたのか、もうちょっと具体的に教えてもらえますか。
糸奇:この曲は物語を想い浮かべたのが最初ですね。ロールプレイングゲームのような世界で、「勇者になろう」と思い立った人がいるんだけど、その世界には、誰もが認める正しい勇者がいて、「勇者は二人もいらないよ」って言われてしまう。勇者にはなれないなら、じゃあ何になろうかなって悩みながら転々としていくというような物語で。
―“ROLE PLAY”の歌詞世界とリンクしたシミュレーションRPG風の特設サイトを制作されていますよね。
糸奇:そうですね。この曲のテーマは、「なりたい自分になっても他人に必要とされなかったら、どうするの?」ってことなんですけど……今、この問いに苦しんでいる人はいっぱいいると思うんですよ。今の世の中、市場にはクオリティーの高いものが溢れているから、私のすごく好きな絵描きさんや漫画家さんでも、苦しんでいる方がいるので。
―今は「なりたい自分」になることは、意外と簡単な時代なのかもしれないですよね。ひとりで作り、ひとりで発信できるツールが充実しているから。でも、その先に進むこと――糸奇さんが言うように、「必要とされること」が難しい。糸奇さんは、どんなふうに人に必要とされたいと思いますか?
糸奇:う~ん……。
―じゃあ、質問を裏返します。糸奇さんは、どんなふうに人を必要としていますか?
糸奇:そうですね……とても綺麗な景色を見て、「あの人と一緒に見たいな」とか、「あの人と一緒にいれたらな」って思う……でも、そのときにその人が「いない」ことの方が、私にとっては大事なことのような気がします。
「不在」を感じる心って、自分のなかですごく大事にしていきたい部分で。「不在の在」とか「空席」とか、そういう言葉の存在感が私のなかでは強いんです。なので、最初の質問に答えると、「不在」を感じる人に、私の世界は必要としてもらいたいです。
―なるほど。
糸奇:私は、過去のことや今までの経験、「あのとき、ああ言えばよかった」っていう後悔とか、「あのとき見た景色はもう見れないんだなぁ」とか、そういう気持ちを掘り返して音や詩を作っている感覚があって。ある意味、どこにも行き場のない自分の気持ちが作品の世界になっているんです。
糸奇:だからこそ、落ち込んで、しゅんとなっている人に無理やり前を向かせたり、元気づけるのではなくて、その人が日常で表に出して言い表せないような負の感情だったり、切なさや寂しさを肯定して寄り添えるものにしたいです。
―ある意味でそれは、先ほど糸奇さんが言った、生きることの虚無から目を背けることと同時に、虚無を受け入れるということでもありますよね。でも、それこそが、芸術や虚構が人を生かす力なのかもしれない。
落ち込んだり、ひとりぼっちだったり、何かに飢えているのに何に飢えているのかわからない闇雲な人だったり……私の音楽は、そういう気持ちの人に届いてほしい。
糸奇:ジュネーブにいた頃、インターナショナルスクールだったので、日本人が同じクラスに3~4人いる時期もあって、そのなかに絵を描くのが好きな子がいたんですね。美術の先生は私のことを気に入ってくれていて、お祭りのときに絵を描くように頼んでくれたんですけど、そうしたら、その子が泣きだして。「私も絵を描くのが大好きなのに、どうしてあなたが選ばれるの?」って……。
そのとき、「なんで、私は海外に来てまで日本人にいじめられるんだろう?」って思ったんです。フランス人とかに「ジャポネ~」とか言われるのはわかるんですけど、よくある普通のいじめみたいなのもあったんですよね。
―なるほど……。糸奇さんは、言葉が通じないからこその断絶も経験していれば、言葉は通じないけど心が通じ合えるという経験もしていて、同じように、いくら言葉が通じたからってわかり合えない相手がいることも知っている。でも、それが糸奇さんの強みなんだろうと思います。人間は本質的に「不在」を抱えていて、だからこそ、誰かに何かを伝えたいと強く思い、実行できる。
糸奇:そうですね……何か不可能なこととか、どうしようもないことを前にもがいてみたら何かが変わるのかもしれないっていうことかなぁ。言葉が通じないからこそ、どうやって気持ちを伝えようかって、他の手段をいろいろ考えられるんです。ジュネーブにいた当時だったら、ピカチュウが好きな子にはピカチュウの絵を描いて渡したり。
音楽や詩もそうですよね。「好きです!」って言ってしまえばそれで終わってしまうけど、「好きです!」と言っただけでは伝わらない「好き」を伝えたいからこそ、世の中にはこんなにもラブソングが溢れているわけで。そうやって、別の手段に変えるエネルギーってすごいなって思います。できないことを前に絶望する時間も無駄ではないと思うけど、ずっと沈んでいる必要もないんですよね。手段を変える発想を持てばいいだけだから。
―糸奇さんのなかにある「不在」すら内包した世界が、この先、どんなふうに別の世界に届いたり、必要とし合ったりしていくのか、とても楽しみだなって思います。
糸奇:落ち込んだり、ひとりぼっちだったり、切なかったり、何かに飢えているのに何に飢えているのかわからない闇雲な人だったり……私の音楽は、そういう気持ちの人に届いてほしいなって思います。
- リリース情報
-
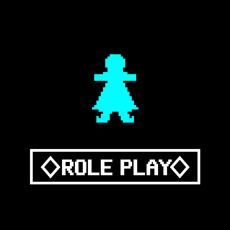
- 糸奇はな
『ROLE PLAY』(CD) -
2017年2月10日(金)タワーレコード限定発売
価格:1,620円(税込)
PLCD-0002
1. ROLE PLAY
2. Nightmare
3. RESET
4. パッチワーク
- 糸奇はな
- プロフィール
-

- 糸奇はな (いとき はな)
-
英仏の歌曲を吸収したボーカルパフォーマンスと、儚い内面性を表現する歌詞世界、クラシカルな要素が強くありながらも打ち込みを駆使した現代的かつエッジーなサウンドメイクで独自の幻想的な音楽を提示する新世代ハイブリッドアーティスト / シンガーソングライター。小学生の頃に観た『オペラ座の怪人』に衝撃を受け、憧れ、声楽を学び始めた後、オリジナル曲の制作を開始。2016年8月10日には初のフィジカル作品となる『体内時計』手づくり版を110枚限定リリースし即完売。この作品は1枚1枚手刷りした版画でCDを包みナンバリングを入れるという凝りに凝った作品。これが音楽関係者の間で話題となり、11月にはタワーレコード限定の全国流通版として『体内時計』レプリカ版がリリースされ話題となった。歌唱、作詞、作曲、アレンジ、打ち込み、楽器演奏、といった音楽にまつわる全てのことをひとりでこなし、それだけでなくイラスト、動画、漫画、版画、刺繍、ゲーム作りからモールス信号まで、様々なやり方で独自の世界を表現するマルチアーティスト。
- フィードバック 12
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-













