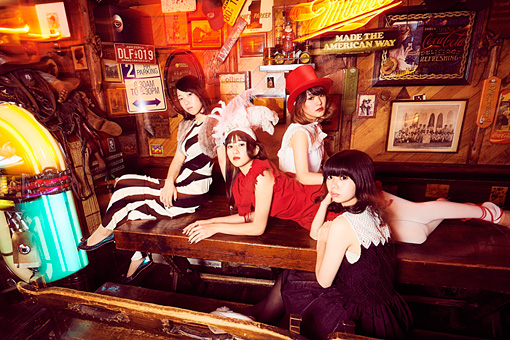高知県のとある高校のフォークソング部でコピーバンドをやっていた四人の女子高生が、周りの勢いに流されてオリジナル曲を作り、東京でライブをし、そのライブの勢いに流された現・所属事務所に声をかけられて、契約。本人たちも、周りの大人たちも、何らかの「勢い」というものに流されながら動いている――sympathyは、そんな不思議な力を持つバンドだ。
もちろん、その「勢い」の中心には、四人の若き女たちの内面から吐き出される、粘着質でキラキラとした音楽の存在がある。そんなsympathyが、遂にメジャーデビューを果たす。
高校卒業後、進路の違いでメンバーが全国に散らばり、四人での曲作りもままならなくなった。そう簡単にメンバーは揃わない、でも、バンドは生きている――この2年間のsympathyは、「バンド」というものが、いかに不思議な生命体であるかを生々しく実証する存在だったとも言える。唯一東京で暮らし、日本・音楽業界の中心地ともいえるこの地で「sympathy」の看板を背負い続けた柴田ゆうに、メジャーデビューにかける想いを訊いた。
前は、音楽はメンバーみんなと一緒にいるための手段だったんです。でも今は、音楽のために集まっている四人でもある。
―前回のCINRA.NETでの取材(女子高生はなぜ輝ける? 冷静に大人を裏切る現実主義なsympathy)のとき、柴田さんはまだ短大生だったんですよね?
柴田(Vo,Gt):そうですね。あのときは、短大に入って1年目でした。卒業してから、もうすぐ1年経ちますね。
―この1年間を、柴田さんはどんなふうに過ごしてきたんですか?
柴田:他のメンバーは地元の高知や京都で4年制の大学に通っているので、今、東京でsympathyとして動けるのは私だけなんです。なので、一人でラジオに出たり、ボイトレに行ったり、修行の1年間という感じでした。メンバーは次で大学4年生なので、あと1年、みんなが東京に来てくれるまでの地盤作りっていうイメージですね。
―他の三人も、大学を卒業したら東京に出てくることは決まっているんですか?
柴田:というか、「上京しない」とか言い出したら引っぱたきます(笑)。メンバーが東京に来たときは私の家に泊まるんですけど、深夜の暗い道を通って練習スタジオに行く途中、不動産屋さんの前で立ち止まって、「この家よくない?」みたいな話をしていて。一軒家を借りて一緒に暮らそうよ、という話はしていますね。「掃除は誰がするの?」みたいなルールも既に作り始めていて(笑)。
―前回のインタビューでは、「卒業後はたぶん就職する」「音楽1本を決意できる人はすごい」とおっしゃっていましたよね。実際、就職という選択は選ばなかったんですか?
柴田:選びませんでした。私は歯科技工士として就職する予定だったんですけど、医療系ってなかなか休みが取れないんですよ。おばあちゃんの入れ歯って、ないと困るものじゃないですか(笑)。だから、絶対に納期どおりに終わらせなきゃいけない仕事で、バンド活動とは両立ができないなと思ったんです。今はバイトをしながら音楽メインで生活しているんですけど、結局、こっちが楽しいからいいやって思っています。
―他の三人も卒業後は就職せず、バンド活動に専念する予定ですか?
柴田:私から「就職はやめて」って言っています。「上京したらなんとかなるから、お願い~」って。東京って、アルバイトでめっちゃ稼げるし、地方とは生活の感覚が違うから、とりあえず、こっちに来て一緒に暮らそうよって。
―「音楽で生きていくことは難しい」と言っていたスタンスから、明らかに変わりましたね。
柴田:そうですね。この1年の間にツアーを回ったりして、ライブに来てくれる人の表情を見ると、考えがすぐに変わりました。これまでは、音楽はメンバーのみんなと一緒にいるための手段だったんですけど、今は音楽のために集まっている四人でもあるし、関係性も「同級生」から「よき理解者」に変わったと思います。
「終わり」があるからこそ、女子高生であることに執着していたし、すがれたんだと思う。
―sympathyは四人の同級生としての繋がりが強かったし、特に柴田さんのなかには「女子高生でい続けたい」という気持ちも強かったわけですよね。そこから抜け出した後、それでも四人でバンドを続けていくことって、もう一度バンドを始めるぐらいの覚悟が必要だったんじゃないですか?
柴田:どうだろう……「もう一度始める」っていうことではないと思う。今だから思うんですけど、「終わり」があるからこそ、女子高生であることに執着していたし、すがれたんだと思います。感傷的になれる物事がないと、私たちは何もできなかったんです。
―なるほど。
柴田:でも、今は音楽をやっている「今」に執着しています。もちろん、「感傷」は私の本質だし、人間の本質って、そう簡単に変わらないとも思うんです。女子高生だったころに対して感傷は抱かなくなったけど、いつでも私は青春で、明日になったら「昨日はこうだったな」って、また違った種類の感傷に浸りながら生きていくんだと思う。
その感覚自体は変わらないかもしれない。でも、今はもう、普通に生きているだけで「虚無感」は潜んでいるものなんだって気づいたし、もし、自分が過去に抱いたのと同じ感情を抱いている人がいるなら、「私が、君の消化しきれない、その感情を曲にしてあげるよ」って思うんです。
シンデレラストーリーとも言われたけど、ここまで来て、「後に引けないね」って思ったんです。
―アルバム『海鳴りと絶景』から、リリースに先駆けて“泣いちゃった(4人ver.)”のMVが公開されましたけど、そもそも“泣いちゃった”は、前作『トランス状態』には弾き語りで収録されていましたよね。今回、四人で演奏したバージョンになったことに対して、周りからの感想は聞きますか?
柴田:「PVの雰囲気がいいね!」って言われます。前作でPVを作った“さよなら王子様”からガラッと変わったので。曲調自体はポップで明るいけど、歌詞は切ない、その感じと映像が合っていていいねって。
―弾き語りの“泣いちゃった”は、決してポップで明るい曲ではなかったですよね。
柴田:そうですね。弾き語りって、声の張り方やそのときの心境で曲が変わるんですけど、“泣いちゃった”は4人バージョンになったことで、安定した表現になったなって思います。
最後はアレンジャーのakkinさん(ONE OK ROCKのサウンドプロデュースなどを手がける)にお願いしたんですけど、4人バージョンのほうが、キラキラしていて、すごく爽快感があるというか。歌詞とは裏腹なポップさが切なさを煽ってくれて、すごくいい化学反応を起こせているんじゃないかなって思います。
―それって、“泣いちゃった”を作った当時の感情を、客観視して音楽のなかに永久保存することができた、ということでもあるんですかね?
柴田:あぁ~、そうですね。やっぱり、あのころとは自分自身が全然違いますからね。“泣いちゃった”を作った当時は、私は時間の流れに敏感で、高校を卒業したことを受け止めきれていなくて。「この先どうなるのか?」という不安も強かったんです。
とにかく未完成な、なんて言っていいかわからない感情を「空しい」とか「悲しい」っていう気持ちで曲に閉じ込めていた。でも今回、“泣いちゃった”をアレンジしたことで、時間の流れの残酷さや優しさを、聴いてくれる人に寄り添わせることができたんじゃないかなって思います。
―音楽が、自分たちのためのものではなくて、他者のためのものになった?
柴田:うん、そうだと思います。これまで音楽は、自分たちの生きた「記録」を投げつけるだけのものだったけど、今は、聴いてくれる人とコミュニケーションするためのものになったんです。高校のころからsympathyを始めて、地元のライブハウスの人に引きずられるように東京に連れてこられてライブをやって(笑)、そこで今の事務所に声をかけられて。
シンデレラストーリーとも言われたけど、ここまで来て、「後に引けないね」って思ったんです。それに、せっかく一度きりの人生なら、誰かに認められたいし、何かを残したいんですよね。自分が自分でよかったと思えるように生きていきたい。そのための手段がたまたま、自分にとっては音楽だったのかなって思いますね。
人が東京を選ぶんじゃなくて、東京が人を選んでいる感じって、あると思うんですよ。
―曲作りは、今でもメンバー間のLINEを使っているんですか?
柴田:そうですね、今でもLINEやSkypeを使ってやっています。遠距離での活動に関しては、たぶん、いいことなんて何ひとつないんですけど(笑)。でも、遠くにいるから愛おしいと思える部分もあるし、何より、曲作りの感動が大きいんです。
四人ともめちゃくちゃマイペースで、特にベース(今井なつき)は全然連絡をよこさなくて、「生きてるかぁ~?」って思ったりもするんですけど(笑)。でも、だからこそ四人で実際に合わせたときに、すごく感動できる。
―以前と比べて、自分たちから出てくる歌詞やフレーズに、変化を感じたりすることはありますか?
柴田:『トランス状態』では語感を大事にして、日本語の言葉遊びにいろんな気持ちを託していたんですけど、今は「託す」という方法で歌詞を書くことはなくなりました。もっと生々しいというか、夢見がちな歌詞ではなくなった。表現したいことを、ちゃんと伝えたい言葉と曲で形にできているなって思います。
―たとえば、ギターの田口かやなさん作の“海辺のカフェ”には「東京」という言葉が出てきますけど、四人のなかで唯一、東京に出てきた柴田さんから見て、この曲はどんな印象ですか?
柴田:<愛せども 東京 憎めども そこは東京>って歌っていますけど、愛しさ余って憎さ満点、みたいな感じなんじゃないかなぁ。東京って、人がどれだけ集まっても「東京」だし、人がどれだけいなくても「東京」なんですよね。
誰がいてもいいけど、その誰かがいなくても成り立つ街……そういうところが空しいんだと思う。人が東京を選ぶんじゃなくて、東京が人を選んでいる感じって、あると思うんですよ。
SNSで、自分の私生活を他人にペラ~っと見せて、第三者がいないと生きていけないのって、超空しいなって思う。
―東京が人を選ぶ。その感じ、わかります。
柴田:私たちがこれから音楽活動をしても、しなくても、どちらにせよ「音楽」は存在するのと一緒で。結局、誰がいてもいなくても地球は回る。極論はそうなんですけど、それでも、私たちはそこに存在していたいし……そんな思いを、「東京」っていう言葉に込めているんじゃないかなぁ。
―1年間暮らしてみて、柴田さんにとって、東京はどんな街ですか?
柴田:暮らしてみると、案外、あたたかいなって思います。道を訊いたら教えてくれるし。もちろん、今言ったような息苦しさもありますけどね。
才能ある人が多いから、自分の存在価値がわからなくなってしまうことはあります。いろんなことに触れ合う機会が多すぎるぶん、混乱してしまって、チャンスはいっぱい転がっているのに、勝手に勘違いして寂しくなっちゃったり。そういう虚無感は絶対に潜んでいると思います。
私は地元にいたころ、のほほんと生きてきたから、東京は、今まで見ていないふりをしてきた部分に向き合うきっかけをくれたなって。自分と向き合わせてくれる街ですね。
―“SNS”は柴田さんの作曲ですけど、前回のインタビューでも、Twitterでのエゴサーチの話などは出ていましたよね。ただ、この曲は本質的にはラブソングだと僕は思いました。
柴田:うん、そうですね。別にSNSをディスりたいわけではなくて。愛情をめちゃめちゃ込めていて、「私たちが本当に大事にすべきものって、画面の向こう側の人ではないんじゃない?」っていうことを伝えたかったんですよね。
SNSにご飯の写真を上げたりするのって、私はすごく「気持ち悪!」って思っちゃうんですよ。自分の私生活を他人にペラ~っと見せて、第三者がいないと生きていけないのって、超空しいなって思う。「何者かになりたいけどなれないこと」の発散手段がSNSなんだと思うと、「うわ~、人間じゃん」って(笑)。
―たしかに、SNSはすごく人間的なツールですよね。ただ、出てくるのが人の「こうなりたい」とか「こう見られたい」という「欲望」の部分だから、表面的なのに生々しいっていう。
柴田:私だってSNSは使うし、「SNSをやめろ」って言いたいわけではないんですよ。でも、「これ、人間じゃん」っていうところに気づいてほしいというか。ネットがあってもなくなっても、寂しいものは寂しいんですよ。
―……柴田さんって、すごくいろんな物事を冷静にジャッジされていて、大人ですよね。
柴田:そうなんですかね?(笑)……大人なフリをしているだけだと思いますけどね。喧嘩すると化けの皮が剥がれるんですよ。「アホ!」とか「バカ!」とか言えなくなるし、結局のところは感情的な生き物なのに、取り繕うために言葉を着せている感じがします。バカがばれたくないのかな(笑)。
メンバーの四人でいるときも、いい子ぶっちゃうんです、私は特に。コンプレックスが強いのに承認欲求がすごくあって、頭よく見られたいし、才能あるように思われたいし、あまりにも自分が普通だから変な人になりたいし……全然大人じゃないですよ。言いたがりなだけで、中身は子供です。
―そう自覚できるところが大人だなぁと、僕は思いますけどね。
柴田:……でも、「大人」とか「子供」とかってなんなんでしょうね? 人って、歳をとったところで気持ちは変わらなくないですか? 体だけ大きくなっていくというか。「大人は、いつから大人になったんやろう?」って思います。
「今」できることに、価値があるんです。そして、私たちが今できることって、やっぱりバンドなんですよ。
―今の話にも関連すると思うんですけど、今回、ジャケットにセーラー服を着た女性が描かれているのは、どうしてなんですか?

sympathy『海鳴りと絶景』ジャケット(Amazonで見る)
柴田:「セーラー服」っていうアイコンは入れたかったんです。高校時代に決別はできたんですけど、やっぱり、私たちの始まりであった女子高生や制服っていう要素は、愛おしいんですよ。ワンピースを着た、普通の女の子はやっぱり嫌だった。制服で制限された女の子であってほしかったんです。
奥田けいさんっていうイラストレーターの方が描いてくださったんですけど、奥田さんは、こうやって写真とイラストをコラージュした作品を作っている方で。今の私たちは、女子高生と大人の間のグレーゾーンから脱してはいるけど、大人にもなりきれていないと思う。そういう部分が表現できているんじゃないかなって思います。
―今日、お話を伺って思ったのは、今のsympathyにはプロのミュージシャンとして一本の芯が通りつつも、やっぱり中身はsympathyが標榜してきた「揺れるロック」ですよね。「今」を見つめる視点が鋭くなったことで、今まで以上に「揺れ」のふり幅は大きくなっているかもしれない。本当に生々しく、ドキュメントが音楽になっている。
柴田:そうですね……憧れるのは、世界観のあるアーティストなんですけどね。最近、シティポップとか流行っているじゃないですか。すごく憧れるし、私はもともと、椎名林檎さんが好きなので、魅せるライブも素敵だと思うし、世の中には素敵だと思えるものが溢れているんですけど……でも、理想どおりにはなれないんですよ。
もちろん、「したい」と思うことをできるようになりたいし、そうあるべきなんですけど、それ以上に、私には「今」できることのほうが、価値があるんです。そして、私たちが今できることって、やっぱりバンドなんですよ。
―柴田さんにとって、「バンド」であることの意義って、どこにありますか?
柴田:バンドって、人に寄り添えるものじゃないですか。特に、日本のバンドのよさってそこだと思う。聴き手との距離が近いというか。海外のアーティストって、カメラに囲まれてパシャパシャ撮られて、「アーティスト!」って感じがすごいですよね。でも、私はそうじゃなくて、もっと等身大で、聴く人に寄り添っていたい。
アーティストも人間だし、偉いわけでもなくて、自分の身を切って売っているという、他の仕事と商品が違うだけなんですよね。それにこっちは、中身が空っぽになったら終わりじゃないですか。それなら、私はもっと人に寄り添っていたいし、音楽に寄り添ってほしいし、救われたいんです。それが、私が音楽に抱いている希望なんですよね。
- リリース情報
-

- sympathy
『海鳴りと絶景』(CD) -
2017年2月22日(水)発売
価格:1,944円(税込)
VICL-647191. 泣いちゃった(4人ver.)
2. ドロップキック・ミッドタウン
3. 深海
4. 海辺のカフェ
5. SNS
6. 二十路
7. 魔法が使えたら
- sympathy
- イベント情報
-
- 『海鳴りのはじまり~駐輪場で待ち合わせツアー~』
-
2017年3月24日(金)
会場:高知県 高知X-pt.2017年4月1日(土)
会場:大阪府 阿倍野ROCKTOWN2017年4月2日(日)
会場:東京都 渋谷STAR LOUNGE
- プロフィール
-

- sympathy (しんぱしー)
-
女の子4人でできている高知県産、超絶無名バンドsympathy。高校の部活の小さな部室から生まれ、初ライブのコンテストでたまたま優勝、地元のライブハウスでライブをしながらオリジナル曲を作り始め、かくかくしかじかを経て1stミニアルバム『カーテンコールの街』を発表。絶賛遠距離中にもかかわらず、いつの間にやらレーベル・事務所と契約……! そして2ndミニアルバム『トランス状態』が出来上がり、あれよあれよと言う間になんとメジャーデビューが決定。もうウカウカしてらんない! 遠距離バンドはメジャーの舞台でどう生き残るのか! 乞うご期待! よそ見しないでね☆「sympathyは『揺れるロック』を推進します。」
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-