Perfumeの三人がそれぞれ世界3都市で行ったパフォーマンスを生中継で融合させた、「NTT docomo FUTURE EXPERIMENT」プロジェクト。ビョークが日本科学未来館で見せた、リアルタイム360°VRストリーミング配信。ブライアン・イーノのPVとして生まれた、人工知能を使ってニュース画像から人類の記憶を連想する映像システム。これらすべてを手掛けるのが、菅野薫だ。
ライブで起こる出来事と映像を融合させて生まれる表現は『リオ2016閉会式 フラッグハンドオーバーセレモニー』でも注目され、2020年の「東京2020 開会式・閉会式 4式典総合プランニングチーム」への参加も決定している。その彼が、映像表現の明日を担う才能を発掘、支援する『MEC Award 2018』のゲスト審査員を務めるという。その審査会場を訪ね、菅野自身の発想の源と、次の新しい映像表現について語ってもらった。
泣いても笑っても一回限りのことに賭ける。ライブパフォーマンスのような表現への関心が強くあります。
—菅野さんはもともと、データ解析技術の研究開発を担当していたそうですね。東日本大震災の際、被災地での移動を支援するためにホンダが公開したカーナビの通行実績情報マップがありました。菅野さんはこれをビジュアライズした『CONNECTING LIFELINES』などを手掛けていますね。
菅野:はい。僕はCMなどの制作ではなくて、マーケティングのためのデータの解析やビジュアライズなどを専門にキャリアをスタートしています。そもそも、学生時代の音楽活動から色々を覚えたこともあるし、刻一刻と変わり続ける情報をリアルタイムに表現していくのが自分の得意なアプローチ。育ち的に一回しか起こりえない、ライブパフォーマンスに近い表現への関心が強くあります。何度もテイクを重ねて、綿密に編集し、時間をかけてレンダリングするという意味での映像表現とは真逆とも言えますね。
—「対象を撮影して、再生する」映像とは対極的ですね。
菅野:そうですね。そのやり方を更に進化させる転機となったプロジェクトは『Sound of Honda / Ayrton Senna 1989』でした。1989年の鈴鹿サーキットでの日本グランプリでF1世界最速ラップを樹立したアイルトン・セナ(1994年没)の走行データをもとにして、同じサーキットにたくさんのスピーカーとLEDを設置し、彼の走りをエンジン音と光で再現したものです。これは、データから一度限り生み出したライブイベントなのですが、それだけでは観てもらえる人数がすごく少ない。だからその瞬間をドキュメンタリーの映像作品として記録して公開することで、最終的に非常に多くの人々に見ていただくことができました。
—『カンヌライオンズ2014』で最高峰ともいわれるチタニウム部門のグランプリをはじめとした15個のライオン獲得、『第17回文化庁メディア芸術祭』のエンターテイメント部門大賞など、数々の受賞も話題になりました。
菅野:たいていの広告は撮影前に綿密にストーリーや演出が設計されたフィクションです。でも、このプロジェクトは、実際にあったこと。走行データからサウンドを再現して、走行の軌跡を光で表現する。それが一回限りのライブイベントになる。さらに、その様子を記録したドキュメンタリー映像が広告になる、という特殊なものでした。
コンテを組んで、それに従って撮影し、CGを加えて……、という歴史がある常識的な広告映像の制作マナーからは完全に逸脱していますからね(笑)。でも、それ以降の自分のやり方を象徴づけたプロジェクトだったと思います。

『Sound of Honda / Internavi “Ayrton Senna 1989”』をVimeoで見る
—その「菅野さんのやり方」について、もう少し詳しく教えてもらえますか?
菅野:多くの広告における映像作品は、壮大なフィクションを通じて「本当のこと」を伝えることをやってきました。いまやCG技術のレベルの高さは、もう実際には何も撮影しなくてよいのではないか?と思えるほどで、それは視聴者側にもちゃんと認識されているので、映像は嘘をつく、全部虚構であるってことが前提で物語に移入しています。
でも僕のやり方は真逆で、「ある場所である瞬間に、本当に起きたことを残す」ことで、「それを可能にした本当のこと」を導きだす、という視点で作っています。
—菅野さんが携わった、『リオ2016閉会式 フラッグハンドオーバーセレモニー』での東京大会プレゼンテーションや、テクノロジーを駆使したPerfumeやビョークのライブ配信も、まさにそういうものでしょうか。
菅野:それらのプロジェクトは、セナのプロジェクトより更に一歩進めたと言うことができると思います。TVでは、昔に比べてリアルタイムで見る生放送は減りました。でも『紅白歌合戦』や『オリンピック』がいまでも生中継されているのは、いま起こっていることの瞬間瞬間をみんなで共有したいからですよね。そして、これらの仕事では、そういう生々しく届けられる現実のなかに「そんなことできんの?」と、びっくりさせるリアルタイムに処理された映像的な虚構が混ざってくる。
—たしかに、単なる生中継ではなく、いつも何らかの変換や融合の要素が加わる印象があります。
菅野:現実のなかにバーチャルな体験が越境してくる、ということですね。『リオ2016閉会式 フラッグハンドオーバーセレモニー』の中継映像におけるAR(拡張現実)はまさにそうです。カメラの視点が上空にブワーっと昇ってまた落ちてくる演出、あれは当然、実際にカメラがああいう動きをするわけではなく、バーチャル上での演出が織り交ざっているんです。
現実とフィクションを組み合わせるという意味では、映像の中で東京のマリオが土管に突っ込んでいくと、現実のリオのスタジアムの土管から登場する。それまでの僕の考え方をベースにさらに挑戦を広げていった感じです。
1万km離れた場所で同時にダンスする魅力を伝えるには、本当でなくては意味がないし、生中継でないと面白くない。
—ブライアン・イーノのPVとして制作した『The Ship - A Generative Film』はいかがでしょうか?
菅野:これはミュージックビデオなんですが、人工知能(このプロジェクトではあえて「機械知能」(Machine Intelligence:MI)と称している)が生成し続ける「見るたびに異なる映像体験」という点で、やはり一回性の強い映像なんです。ネット上で次々と提示されるいま世界中で起きている最新のニュースの画像をみたMIが、記憶している膨大な過去のイメージのなかから「これ同じようなものを、見たことある」と想起したイメージをゆっくり提示していくという作品です。MIによる見間違えとも言えるし、文脈の連想とも言える。それがどういう文脈から呼び起こされたデジャブなのかは誰にもわからないのですが、そこが「繰り返す人間の慢心や愚かさ」をテーマにしたブライアン・イーノのたてた楽曲やアルバムのコンセプトに呼応すると考えました。
僕はアーティストではなく広告屋なので、基本的に誰かのため、何かの目的のために機能する表現を作るのが仕事です。ブライアン・イーノのMVも、僕の作品ではなく、彼の作品をみんなで一緒につくったという感じです。彼が「これなら興味がある」と言ってくれて実現したので。
—菅野さんのお仕事には、新しいタイプの協働性も感じます。振付師からメディアアーティスト、プログラマーまで幅広い人々が関わり、それらを映像表現にまとめ上げることも多いですね。
菅野:広告はアートと違って個人技ではなく、プロフェッショナルの集合体であるプロジェクトチームによって制作される構造自体は、この半世紀ほど変わっていないと思います。特に映像分野は分担がよくできていて、CMプランナー、演出家、プロデューサー、制作部、美術部、車両部、照明部、スタイリストなどなど、役割は明確です。
菅野:一方で、僕の仕事は広告のプロジェクトのなかでも特に複合的で統合的な傾向があるので、チームがやたら大所帯になることが多いのと、関わる人の専門性が多岐に渡っていて、これまで広告制作には関わらなかったような人が入ることも多い。だから、クレジットの肩書きだけでは個々に何をしているのか全くわからないことが多い(苦笑)。つくる以前に、そのつくり方自体を発明している感じだから、個々の職能が簡単には説明ができないんです。
—作り方自体を発明しているとは、たとえばどんなことでしょうか?
菅野:Perfumeさんを起用したNTTドコモの『FUTURE-EXPERIMENT VOL.1 距離をなくせ。』の話をしましょう。これは、17年間ずっと一緒にいて活動してきたメンバー三人が初めてニューヨーク、ロンドン、東京に別れ、別々のステージで同時にパフォーマンスをし、それを5Gをはじめとした高速ネットワークや、高臨場感メディア同期技術「AdvancedMMT」で映像的に同期させて生配信したプロジェクトです。
僕はその企画と、全体のクリエイティブディレクションを担当しました。このプロジェクトには、プロジェクトの告知を担当するいわゆる広告的な、関和亮監督をはじめとした映像制作チーム、ADの上西祐理を中心としたグラフィックデザインチーム、木村浩康くん率いるウェブデザインチームもいますが、当然パフォーマンスそのものを制作するチームがいます。振付と演出はMIKIKOさん、テクニカルな領域の演出で真鍋大度くん率いるライゾマティクスリサーチも参加しています。
そして中心技術である3都市をつなぐネットワーク構築はNTTドコモの5Gの開発チームとNTT研究所を中心としたチーム。クライアント自ら開発することになります。これらをイベントとして実現させるプロデュースチームも必要でした。映像、デザイン、ライブパフォーマンス、デジタルテクノロジー、イベント、あらゆる異なる専門性の人が集って、ひとつの大きなプロジェクトをつくる。どういう才能を集めるかから企画ははじまっています。
—広告でリアルなイベントを生み出す手法を追求すると、必然的にそうなるのかもしれません。
菅野:そうですね。全然違う能力の人が協業するからこそ生まれる刺激もあります。先程の映像は、Perfumeの三人を順番にスタジオ撮影して、後から合成しても似たような映像はできるよね? と言われたら、それはそうです(笑)。だから、1万km離れた場所で同時にダンスする魅力を伝えるには、本当でなくては意味がないし、生中継でないと面白くない。何より、たった一度しか起こらない奇跡のような瞬間を、どうみんなと共有するかというのは、NTTドコモという通信企業のプロジェクトだからこそ大事にしたかったことです。
学生時代に音楽をやっていたことが、ライブであることを重要視する自分のアプローチにすごく影響している。
—映像がその技術とともに変化するのは当然ですが、お話に出てきた人工知能や通信ネットワークなど多様なテクノロジーの進化も、新しい映像と密に関わるようになってきたと感じます。
菅野:まず、テクノロジーはコミュニケーションを乗せるメディアを大きく変えました。昔から広告にはイベント部門もCM部門も、グラフィック部門もありましたが、別々に企画し制作していた。近年それらが密に連携する必然性が生じたのは、デジタルテクノロジーが新しいメディアをたくさん産み出していることが大きいと思います。コミュニケーションがより多様性と連動性を増して、手段を統合する必要性が強くなった。課題に対して、メディア「全部入り」で解決しなくてはならなくなってきている。
テクノロジーがもたらしたもうひとつの変化は、広告表現手法の拡張です。少し前までは広告の表現手法は比較的シンプルで、紙における静的なグラフィックデザインと、電波に乗せるのための短尺の映像制作が中心でした。それがいまは、メディアアートやデジタルアートの手法とも関わる広がりをみせている。つまりメディアが統合し、表現手段は拡張するという両面から変わってきているのだと思います。
—菅野さんも、その変化のなかにいるということですね。
菅野:表現の発明の前線は、どんどん変化していますから。僕のようなやり方の前には、デジタルクリエイティブといえば、Flash(アドビシステムズが開発する動画やゲームなどを扱うための規格)などを使ったブラウザ上でのインタラクティブ表現の発明が盛んな時期もありました。でも僕は、リアルな体験のなかにテクノロジーを介在させていくやり方にフォーカスしていった。元を辿ると学生時代に音楽をやっていたことが、自分のアプローチにおけるライブ性にすごく影響していると思います。
—ジャズバンドのギタリストで、作編曲を菊地成孔さんに師事していたそうですね。
菅野:ジャズをやっていました。即興の音楽が好きだったんです。それでコンピューターで即興演奏をやれないかと思ったりしていた。ラップトップでリアルタイムに取り込んだり生成したりするのは、映像より音楽が早かったですよね。それは単に、コンピューターの処理速度の問題でもあった。音楽の方が映像より即興性のある表現がもともとあったので取り込みやすかったのもあるでしょう。いまでは映像でも、そういうことが普通にゴリゴリできますけどね。
『The Ship』で協働したQosmoの徳井直生くん、『Sound of Honda/Ayrton Senna1989』のサウンドディレクターをお願いした澤井妙治くん、ライゾマティクスリサーチの真鍋大度くんなどは、もともとミュージシャンとして活動していて、それぞれの独自の表現に進んだ同世代の友人たちです。彼らがライブパフォーマンス的なものから各々の表現に入っていったのは、そういう音楽的なバックグラウンドや、制作環境の進歩が背景にあるのではないかと思います。また、彼らと仕事をしやすいのは、そういう文脈を共有しているからだと思います。
—新しい映像表現が生まれる道筋のひとつの例としても、とても興味深いお話ですね。
「極論を言えば、意味がわからない映像でもいい」という審査基準はかなり新鮮でした。最優先すべきは「新しさにつながる可能性」であると。
—ここで、菅野さんがゲスト審査員を務める『MEC Award 2018』のお話を伺いたいと思います。SKIPシティ映像ミュージアムが2012年にスタートさせた公募展で、映像表現の明日を担う才能の発掘とサポートを目指しています。ちょうどこの取材の直前に入選作を決める審査会があり、その様子を見学させていただきました。
菅野:全応募作品62点から入選5作品と佳作群を選び、後日、展覧会で大賞が決まる予定です。応募条件は15分以内の映像をYouTubeにアップすることだけ。ストレートな映像作品から、ドキュメンタリー、アニメーション、VR、映像インスタレーションまでが集まりました。
最初は「コレ、どうやって同じ土俵で審査するんだ」と思いました(苦笑)。広告やデザインの賞だと、ビジネス上の目的がある表現なので、ある程度カテゴリーをわけて競争軸を決めたうえで審査することが多いですから。全部並べちゃうんだと。ただ、型にはまらない新しい表現を発掘するうえでは、カテゴリを堅苦しく定義せずに間口を広げて受け入れるアプローチは良いと思いました。

『MEC Award 2018』審査会の様子。審査員四名が議論を重ね、入選作品を選定した
—審査会のプロセスについては、どんな感想を持ちましたか?
菅野:面白かったのは、アーティストの森弘治さん、キュレーターの四方幸子さん、ポリゴン・ピクチュアズ代表の塩田周三さん、そして僕、という異なる専門性の四人で一緒に審査すること。何より「極論を言えば、意味がわからない映像でもいい」という審査基準はかなり新鮮でした。作品個々の評価ポイントはあるとして、最優先すべきは「新しさにつながる可能性」であると。

渡辺栞『ワタヤ』 / 『MEC Award 2018』入選作品
—それは菅野さんが審査会の冒頭、改めて審査基準を確認した際に共有されたことですね。
菅野:そうですね。一方で、みなさん柔軟な思考の持ち主なので、各自の文脈の戦わせ方、共有の仕方のプロセスがすごく楽しかったです。審査会で話し合うなかで、四人の見方に変化が起きることもあったし、審査員それぞれが「これだけは入れたい」とこだわる作品があったのもよかった。
たとえひとりでも、ものすごく感情移入させる力があるというのは映像作品には重要な観点ですから。賛否両論をまきおこす作品もあった方がよいし、実際にそういう作品も選ばれています。

藤倉麻子『群生地放送図鑑』 / 『MEC Award 2018』入選作品
自分のすぐ上の世代を追随することは、たとえどんなに上手くても「新しさ」という点では一番むずかしいやり方と思います。
—必ずしも高く評価してはいない作品でも、審査会で「新しい映像表現」を議論するためにあえて挙げた方もいました。
菅野:そういう議論の仕方はアリでしょうし、僕もやりました。みなさん、優等生的な作品にはかなり厳しかったことも印象的でしたね。職人的なうまさや綺麗さが秀でていても、作家としての「汁」が出ていないものには冷たかった。その上で「あえてこう表現する」という選択も含めて、強い意志や作家性があふれ出るような表現でないと、「よくある感じだね」となりやすい時代でもあると思います。

今治建城『10424』 / 『MEC Award 2018』入選作品
—逆に、審査の話し合いのなかで高評価に変わっていく作品があったのも、興味深かったです。
菅野:例えばVRを使った作品で、一見ではわからない面倒臭い作り方に挑戦していることに、最初は審査陣が気づかなかったんですね。でもそのことを知ると、パッと見は軽い雰囲気の作品だけど、なかなか強い意志を放っているように感じられてくる。
これは努力を評価するといった話とは別で、YouTubeをスクリーンで審査するやり方ではなく、本格的なVR環境で審査できれば、自ずと伝わったかもしれません。同じことは、映像インスタレーションを撮影したものや、インタラクティブ性のある応募作の審査でも感じました。多様な形態の作品の応募を受け入れていながら、審査方法が共通なので、そこで損している部分をしっかり考慮して審査する必要がありました。3月の入選作品展では実物の展示作品をみて最終審査ができますが、ドキュメンテーションや応募の仕方が効果的でないと、良い作品でもそこに残れない可能性はある。

CuBerry『CuBerry』 / 『MEC Award 2018』入選作品
—審査側の課題ということですね。
菅野:YouTubeのリンクひとつで応募できること自体はいいと思うんです。なんだかんだ言っていまは、映像というメディアの波及力の強さが再確認されているタイミングだと思いますから。
オリンピックなどでも会場で実際に見る人は8万人ほどですが、最終的に20億人が、テレビやネットの映像を通して見るわけです。『Sound of Honda/Ayrton Senna1989』も、やはりインスタレーションだけでなく、映像にしたことで格段に多くの人に届いた。その一方で、新しい映像表現を発掘するという際には、審査方法もその拡張に対応していけたらいいですね。

清水はるか『I'm Alive』 / 『MEC Award 2018』入選作品
—時代性ということでは、TVに代わってスマホやネットを見る時間が増えた状況だからこそ、生まれたような作品もありました。一方で審査では、「やりたいことは伝わるが、それならもっとやりようがあるかも」という意見も何度か出ましたね。
菅野:広告の場合は、表現はテクニックの側面が強いので、「もっとこうしたらいいのでは」という議論にもなりがちですが、今回は必ずしもそういう視点だけで評価してはいけないですよね。アーティストは「これが自分のやりたいことだ」という意思が最も大事だと思うので、それを貫くことがよいのだと思いますから。
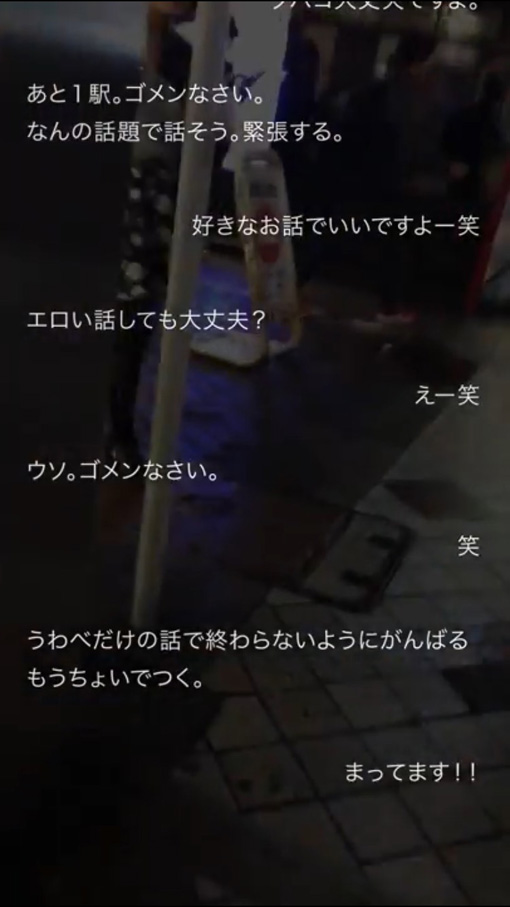
西片例『ここに来るひと』 / 『MEC Award 2018』佳作
—最後に、『MEC Award』が掲げるキーワードでもある「新しい映像表現」について、菅野さんがいま感じている可能性や予感があれば教えてください。
菅野:今後どのあたりの領域に注目すべきなのか、という話がもしあるとするなら、僕は知っていても秘密にしたいです(笑)。ただ、さかのぼれば、印刷技術の登場が視覚表現の幅をものすごく広げたように、基本的には常にある種のテクノロジーがメディアを生み、その上に表現が生まれるのだと思います。
そう考えると、いまは新しいメディアがどんどん生まれている状況ですから、全ての新しいメディアに表現がのせられる可能性があると思った方がいいですね。逆に、自分のすぐ上の世代を追随することは、たとえどんなに上手くても「新しさ」という点では一番むずかしいやり方だと思います。それより、まだ誰も用いていないメディアやテクノロジーに映像表現を乗せていくことができれば、新しいものにつながる可能性は高いでしょうね。

3月17日(土)から開催される『MEC Award 2018入選作品展』。大賞は3月17日(土)に会場で最終審査を行い、同日発表されます。当日17:30~に映像ミュージアム受付にて係員に「CINRAを見た」と伝えていただけると「MEC Award 2018入選作品展」のオープニングに参加いただけます(サイトを見る)
- イベント情報
-

- 『MEC Award 2018 入選作品展』
-
2018年3月17日(土)~4月8日(日)
「MEC Award 2018入選作品展」のオープニングにご招待
会場:埼玉県 川口 SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ 映像ミュージアム
時間:9:30~17:00(入場は閉館の30分前まで)
休館日:月曜(祝日の場合は翌日)
料金:大人510円 小中高生250円3月17日(土)当日17:30~に映像ミュージアム受付にて係員に「CINRAを見た」と伝えていただけると、「MEC Award 2018入選作品展」のオープニングに参加いただけます。
- プロフィール
-
- 菅野薫 (すがの かおる)
-
電通CDC / Dentsu Lab Tokyoエグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター / クリエーティブ・テクノロジスト。テクノロジーと表現を専門に幅広い業務に従事。本田技研工業インターナビ「Sound of Honda/AyrtonSenna1989」、Apple App Storeの2013年ベストアプリ「RoadMovies」、東京2020 招致最終プレゼン「太田雄貴Fencing Visualized」、国立競技場56年の歴史の最後の15分間企画演出、GINZA SIXのオープニングCM「メインストリート編」、BjörkやBrian EnoやPerfumeとの音楽プロジェクト等々活動は多岐に渡る。JAAA クリエイター・オブ・ザ・イヤー(2014 年、2016年) / カンヌライオンズチタニウム部門グランプリ / D&AD Black Pencil / 文化庁メディア芸術祭大賞 / Prix Ars Electronica栄誉賞など、国内外の広告、デザイン、アートなど様々な領域で受賞多数。
- フィードバック 2
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-







