平成元年に鳥取で生まれ、ロシアやイランなどで過ごしたのち、現在は千葉を拠点に活動を続けるシンガーソングライター、折坂悠太。近年は宇多田ヒカルがフェイバリットに挙げるなど幅広い注目を集めている彼のニューアルバム『平成』が、10月3日にリリースされる。
無垢な言葉と世界各地のルーツミュージックを吸収したその歌世界は唯一無二。寺田燿児ら折坂のライブパフォーマンスを支えてきた馴染みのメンバーに加え、トラックメイカーのRAMZAらも参加した新作には、凄まじいスケール感を持つ異能のシンガーソングライターである折坂の才気が迸っている。
平成のはじまった年に生まれた折坂は、平成が終わりを迎えようとしているこの2018年に何を歌おうとしているのだろうか? 「終わり」と「はじまり」の気配に満ちた新作の話を中心に、独自の宇多田ヒカル論やさまざまな歌唱法を駆使することで増幅される身体性についてなど、インタビューのテーマは多岐に渡った。
僕は「平成」を自分にとっての肩書きのようなものとして捉えている。
—『平成』を掘り下げるにあたって、平成元年生まれの折坂さんが「平成」という時代をどのように捉えているのかお訊きしたいです。
折坂:個人的な面とパブリックな面があるんですけど、個人的な面でいえば、僕は「平成」を自分にとっての肩書きのようなものとして捉えているんです。
—肩書きですか。
折坂:はい。僕は鳥取生まれだけど育ったのは千葉で、海外で生活していた時期もあって、地元といえる場所がないまま育ってきた。そういうこともあって、自分にはルーツがないと思っているんです。でも、「平成元年生まれ」という肩書きが、そうした出自のなさを穴埋めしてくれるんじゃないかと考えていて。それは要するに「何にもない」ということでもあって、そんな所在のなさが「平成」という時代とも共通するものなんじゃないかと。

—「何にもない」というアイデンティティーを示すものでもあると。
折坂:そうですね。昭和は戦争や、それに続く高度経済成長などいろんなことがあったわけですけど、平成は「自分たちの時代を作るんだ」という意識もそれほど共有されないまま、経済だけがひたすら下っていった印象があるんです。自分はまさにそういう時代に生まれ、そういう時代を生きてきたというコンプレックスが少しだけあるんだと思います。
今回の『平成』というアルバムは、そんな自分の出自のなさに正面から向き合ったものなんです。平成という時代が終わってしまうということもあって、そういう自分に向き合わないといけないと思ったんですね。
—たしかに、平成って非常に捉えどころのない時代だったと思っていて。昭和のようにわかりやすい物語があるわけでもないし、実態が掴みにくい。今回のアルバムは、捉えにくくてモヤモヤとした「平成」という時代に、新しい言葉と音によって実態を与えようとするものなんじゃないかと思ったんですよ。
折坂:そういうところはあるかもしれませんね。今回のアルバムに“みーちゃん”という曲がありますけど、みーちゃんというのは自分の姉のことで、幼少期の他愛のない記憶をもとにしているんですね。そういうモヤモヤとした記憶に音をつけて実態化した曲もありますし。
—今回の収録曲は、そのように具体的な体験や記憶に基づいたものが多いんでしょうか?
折坂:“みーちゃん”のように古い記憶に基づいたものもあれば、いま自分が思っていることや、物語そのものを創作したものもあります。時代も幼少時代を舞台にしているものもあれば、震災後のこともあって、平成というお題に合わせてさまざまなエッセイを書いた感覚に近いんです。

—なるほど。今回はその一方で私小説的な感覚が滲んでいる曲もありますよね。
折坂:内容は多岐に渡っているけど、全部私小説といえば私小説だと思います。これまでのアルバムではこの世にいない人や、まだ生まれていない人、もしくは自然に対して歌っているような感覚があったんですけど、今回のアルバムに関してはいま生きている自分であるとか、顔が見える人たちのことを歌おうと思った。そのあたりの感覚は以前と真逆かもしれません。
音楽家の立ち位置や活動のあり方そのものが少しずつ変わってきていることを実感する。
—何か視点が変わるきっかけがあったんでしょうか?
折坂:弾き語りのツアーで地方を回る機会があって、そのときに各地の人たちと出会ったことが一番大きいと思います。それまでは、日本はお先真っ暗だと思っていたんですよ。経済もどんどん低迷してるし、社会に希望を持てなくなっているし。でも、ツアーに出てみたら、各地でちゃんとがんばってる人たちがいて、東京にいるときにはわからない視点があることに気づいたんです。
それが自分にとっての希望だったし、それからいまの時代が立体的に見えるようになった。いまを嘆くだけでもなければ、楽観的になるのでもなく、もっと大きく現在を捉えられるようになったんでしょうね。“坂道”の歌詞にはそういう部分が如実に出ていると思います。細く暗い道を歩いているんだけど、想像ができないことが起きる予兆もあって、そういう感覚を表せないかなと思いながら歌詞を書きました。

—そういえば、宇多田ヒカルさんがとあるインタビューで折坂さんの“あさま”(2016年発表の1stアルバム『たむけ』収録曲)に衝撃を受けたと話されていましたよね。そのことについてはどう思われましたか?
折坂:めちゃくちゃ嬉しかったですね。宇多田さんが『Fantôme』(2016年)をリリースしたときのインタビューは全部読んだんじゃないかな。音楽の世界のトップにいる方とは思えないぐらい共感できる話をされていて、すごく感じるものがあったんです。
—どのような部分に共感を覚えたのでしょうか。
折坂:子育てのことも話されていたんですけど、僕もちょうど子どもが生まれて間もなかったんで、すごくわかることばかりで。

折坂:僕、音楽によって大きな成功を収めた人は何かを手放さなきゃいけないんじゃないかと思っていたんですけど、宇多田さんのインタビューを読んでいたら、いままでの感覚を手放すことなくやっていけるんじゃないかと勇気づけられたんです。
もちろん宇多田さんは音楽家として特別な存在だと思います。でも、彼女の活動を見ていると、音楽家の立ち位置や活動のあり方そのものが少しずつ変わってきていることを実感しますし、そこに希望を持てるんです。
—宇多田さんは、“あさま”のどのような部分に反応されたんですかね。
折坂:『RISING SUN ROCK FESTIVAL』で小袋(成彬)さん(2018年4月リリースに宇多田ヒカルをプロデューサーに迎えてデビューした作・編曲家、サウンドプロデューサー。宇多田ヒカルの『Fantôme』および、『初恋』にも参加)と初めてお会いしたんですけど、「どこに衝撃を受けてくれたんでしょうかね?」と聞いてみたんですよ。小袋さんは「あの曲、めっちゃよくないですか? すごくピュアだし」と言ってました(笑)。
たしかに、僕の曲のなかでも“あさま”は際立ってピュアだと思うんですよ。あの曲は僕が通っていたフリースクールの行事で北軽井沢に行ったときのスケッチなんですけど、裏の意味もないし、「この曲で売れてやろう」という思惑もない。できたことで完全に満足したという曲なんですよ。他の曲は「聴いてくれた人にこう感じてほしい」という欲が多少なりともあると思うんですけど、“あさま”にはそれが一切なくて。そういう音楽って案外ないと思うし、そこに宇多田さんは反応してくれたのかもしれない。
作詞するときの感覚は宇多田さんとは違うかもしれないけれど、最終的な理想はすごく近い気がしてる
—“あさま”の言葉の選択やメロディーの組み立て方は、唱歌(明治から昭和にかけて文部省が教科用に編纂した歌曲)に近いものがありますよね。宇多田さんはそうした歌詞の組み立て方にも衝撃を受けたんじゃないかと想像します。
折坂:僕が宇多田さんのことを尊敬している理由の1つに、語呂の個性があるんです。聴いていてちょっと聴き流せないぐらいの字余りとか、話言葉をそのままメロディーにあてはめているところがある。それが僕の耳には言葉と歌がぶつかり合って聴こえるんです。そのきわどさを、圧倒的な譜割りのセンスと歌唱によって、違和感なくあそこまでのポップミュージックに昇華してしまう。
宇多田さんの最近の歌って、ものすごく拍が複雑なんですけど、それがさらに自分の語呂感を活かす要素になっている。そこが宇多田さんの曲を聴いていて熱くなるポイントでもあるんです。

—折坂さんは自分の語呂感についてどう意識していますか?
折坂:僕にもそういう語呂の個性はあると思います。でも、自分は言葉と音がぶつかり合うことへの恐れがあって、メロディーに沿って言葉を綺麗に並べるという作業をやりすぎるぐらいやってしまう。字余りに対して潔癖性的な感覚があるんでしょうね。そのために、今は使われていない古語を持ってきたりするんです。
—『ざわめき』(今年1月リリースのミニアルバム)に収められた“芍薬”には唱歌“夏は来ぬ”からインスパイアされた中古日本語(平安時代中期に用いられた、日本語の文語体の基礎となる言葉遣い)が使われていましたが、言葉と音を並べるときに必然性があればそういう古語も使うと。
折坂:そうですね。あと、作詞するときの感覚は宇多田さんとは違うかもしれないけれど、最終的な理想はすごく近い気がしてるんです。宇多田さんと自分を比較するのはすごくおこがましいんですけど。
折坂:僕の場合、言葉をメロディーにあてはめていくときにどうしようもなく出ちゃう潔癖性なところが自分の語呂感だと思う。宇多田さんには宇多田さんの語呂感があって、それぞれの個性だと思うんですよね。自分の言葉と音楽の調和を考えてやっているという意味では、理想は近い気がしてるんです。こんなことを言うと、宇多田さんのファンから怒られるかもしれないけど(笑)。

自分の身体から出たものにウソはないし、生身の個体から発せられたものってオリジナルだと思う。
—今回のアルバムではありとあらゆる歌唱法が駆使されていますよね。“逢引”には演劇的な語りが出てきますが、こうした語りはどこから出てきたものなのでしょうか?
折坂:自分としては浪曲(三味線を伴奏にして独特の節と語りで物語を進める語り芸。浪花節ともいう)と口上、それとポエトリーリーディングのミックスというイメージです。ライブではお客さんに向けた口上をやることもあるんですが、それは完全に河内音頭からの影響なんですよ。浪曲のような語りものは河内音頭で初めて触れましたし、そのインパクトがすごく大きくて。ライブのなかでやってきたそうした口上が、少しずつ曲のなかに浸出してきたということだと思います。
—浪曲的な語りと音楽がシームレスに繋がっている表現って、遠藤賢司さんとも通じるものだと思うんですよ。
折坂:もしかしたら遠藤賢司さんの影響もあるかもしれないです。遠藤さんはライブ中に歌舞伎の見得みたいなことをやったりされていましたけど、僕はああいうものに熱くなるところはあって。あと、ライブ中に故人のものまねをしながら説法みたいなことをやるAZUMIさん。あのすごさに触れた影響はどこかにあるかもしれません。

—今回はバンド編成のアルバムですが、アンサンブルの中心になっているのはあくまでも折坂さんのガットギターですよね。ドラムとベースによるリズムが中心にあるのではなくて、ガットギターを弾く折坂さんの身体性が真ん中にある。そうした身体性は折坂さんが意識されてきたことでもありますよね。
折坂:身体性に関してはものすごく意識しています。さっきもお話したように、コンプレックスとして抱えていた自分の「出自のなさ」を補うために身体性を高めてきたような感覚がある。自分の身体から出たものにウソはないし、生身の個体から発せられたものってオリジナルだと思うんですよ。
—いうなれば、「折坂悠太」という替えの存在しない個体から発せられている以上は、唯一無二のものであると。ホーミーやヨーデルのような歌唱法をされますが、ああいった歌唱法もまさに声を通して身体性を表現するものですよね。
折坂:そういう表現方法をどんどん増やしていきたいと思っています。ただ、ホーミーを取り入れているからといってモンゴル音楽をやりたいわけではないんです。
僕自身、あるジャンルや文化的潮流のなかに自分がいるという実感を全然持てず、どこにいてもしっくりこなくて。ホーミーやヨーデルも身体性を表現する手段というか、その歴史や文化的な背景とは別に、自分という生身の身体を通してオリジナルな表現をしているという感覚なんです。
僕らは「戦争の気配」みたいなものを常に感じながら生きてきたと思うんです。
—“逢引”は「恋と戦争」をテーマにしたダブルミーニングの曲だそうですね。
折坂:そうですね。若い世代が何も言わずに死んでいくということと、若い男女が夜の町に消えていくという意味を重ね合わせた、ちょっときわどい曲なんです。僕は「割り切れないもの」が好きなんですけど、恋も戦争も割り切れないものだと思っていて。そういうものをともに提示したいという感覚は常に自分のなかにあります。
—先ほど「平成というお題に合わせてさまざまなエッセイを書いた感覚」とおっしゃっていましたが、平成は戦争がなかった時代でもありますよね。
折坂:日本に限ればそうですけど、海外では絶えず戦争が起こっていたわけで。それに僕らは、親や祖父の代から遠くない過去に戦争があったということを聞かされ続けて育ってきた世代でもある。そうした過去の戦争と、今まさに迫っている戦争の両方のイメージがこの曲の背景にはあると思っていて。平成の日本で戦争はなかったけど、僕らは「戦争の気配」みたいなものを常に感じながら生きてきたと思うんです。
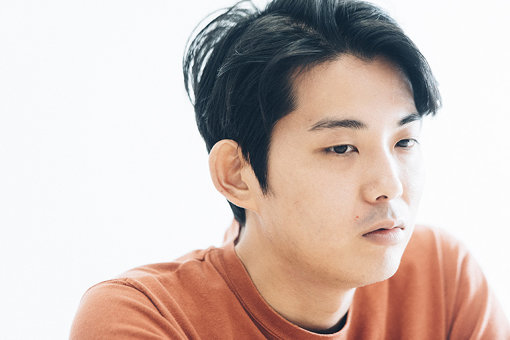
—そうですね。しかもその気配がより現実的なものになりつつある。
折坂:僕、Twitterでも政権批判の投稿をする寸前までいくんですけど、最終的にはいつも投稿できないんです。「俺の表現はそこじゃないだろ」という意識がどこかにあるんでしょうね。わかりやすい反戦歌を作るんじゃなくて、“逢引”みたいな形で表現したいんです。50年後に聴いてもおもしろいと思えるものとして形にしたい。
その時代固有の背景から生まれた切実なものがあれば、何十年も前に生まれた音楽だとしても決して古くならないと思うんですよ。歌としておもしろいものを作りたいし、日々暮らしているいまの日本の空気感をそのまま出すことが必要だと思っているんです。
僕は「源流」になりたいんです。
—今回のアルバムのなかでそうした切実さをもっとも感じさせたのが、“さびしさ”という曲でした。
折坂:“さびしさ”は今回のアルバムのなかでも思いのレンジが一番幅広いと思いますし、アルバムの構成として全曲がこの曲に向かっている感じがするんですよ。
何かの思想のもとに集まるものって僕はあまり信用してないんです。みんないろんな立場があるだろうし、「私たち」っていう言葉で括れることってあまりないと思うんですね。「俺たち同じ人間じゃん」といってもやっぱり壁はある。でも、ただ1つだけ、生まれ落ちた1人の人間としてのさびしさをみんなが抱えているという意味では、「私たち」と言っていいんじゃないかなと思っているんですよ。
—そこでいう「さびしさ」とは、孤独感とは違うわけですよね。
折坂:そうですね。僕も家に帰れば家族がいるけど、「さびしいな」と思うことはあるわけで。さびしいから人間は寄り合って生きるということもあると思うし、同じ人間にはなれないという、どうしようもないさびしさもあると思うんですね。誰もが自分の居場所を見つけようとしている途中にあると思うんですよ。誰もそれを邪魔してはいけない。

折坂:たとえば、相模原の障害者殺傷事件。あの犯人は「障害者は生きる意味がない」ということを言うわけですよね。あの事件が起きて以降、僕はずっとそのことを考えていて……。こういうことを言って曲が色づけされるのはよくないことかもしれないけど、僕は彼が言ったことに対しては全身全霊をかけて否定し、反論していきたい。上辺の言葉だけじゃなくて、具体的に心を動かす表現によって否定していきたいんです。
僕は近年ずっとそういうことを考えてきたんですけど、そうした思いが“さびしさ”のなかの叫びに集約されてるんじゃないかと思っている。だから、「ようやくこういう曲を作れた」という実感があるんです。
—そういう意味でも、今回のアルバムは折坂さんがこれまでやってきたことの1つの到達点だとも感じたんですよ。
折坂:音楽をやってきて、いままでの追い求めていたものを1つの形にできたんじゃないかという気持ちは僕自身もあります。そういう作品を1枚作れたので、次はヘンなものを作ってもいいんじゃないかと思ってて(笑)。

—折坂さんが歌い手として目指しているのはどこなんでしょうか?
折坂:僕は「源流」になりたいんです。ヒップホップでいえばサンプリングする側じゃなくて、サンプリングされる側になりたい。もちろん自分という存在のなかにはさまざまなものが流れ込んでいると思うけど、それを自分の身体を使ってアウトプットするという意味では「源流」になれるんじゃないかって。
今後の展望としては、ライブにせよ音源にせよ、もうちょっと立体的な形で表現していきたいと考えています。もしかしたら音楽だけじゃなくて文章や映像を伴うものかもしれないけれど、作りたいものの空間的なイメージは漠然とあるんです。その主軸にあるのがすごく簡素化された歌で、それこそ“あさま”みたいなものなのかもしれないけど。
—新しいものを作っていきたいという欲求が高まっている?
折坂:やる気は高まっています(笑)。今回のアルバムを作ったことで頭のなかにあったものを出しきったというより、どんどん創作欲が湧いてきているんですよ。“さびしさ”のような曲を作ることで、ここまでこだわり続けてきた意味からようやく解放されたので、次は単純に音のおもしろさや空間みたいなところにこだわったものを作れるんじゃないかと。次の展望はそういうところにあります。


- リリース情報
-

- 折坂悠太
『平成』(CD) -
2018年10月3日(水)発売
価格:2,700円(税込)
ORSK-0051. 坂道
2. 逢引
3. 平成
4. 揺れる
5. 旋毛からつま先
6. みーちゃん
7. 丑の刻ごうごう
8. 夜学
9. take 13
10. さびしさ
11. 光
- 折坂悠太
- イベント情報
-
- 『平成 Release Tour』
-
2018年11月22日(木)
会場:愛知県 名古屋 Live & Lounge Vio
料金:3,000円(ドリンク別)2018年11月24日(土)
会場:大阪府 心斎橋 CONPASS
料金:3,000円(ドリンク別)2018年12月2月(日)
会場:東京都 渋谷 WWW
料金:3,300円(ドリンク別)
- プロフィール
-

- 折坂悠太 (おりさか ゆうた)
-
平成元年、鳥取生まれのシンガーソングライター。幼少期をロシアやイランで過ごし、帰国後は千葉県に移る。2013年よりギター弾き語りでライヴ活動を開始。2014年、自主製作ミニアルバム『あけぼの』を発表。2015年、レーベル『のろしレコード』の立ち上げに参加。2016年には自主1stアルバム『たむけ』をリリース。その後は合奏(バンド)編成でのライヴも行う。2017年8月18日には、合奏編成にて初のワンマンライヴとなる「合奏わんまん」を代官山 晴れたら空に豆まいてにて行い、チケットは完売。同日より合奏編成で録音した会場限定盤「なつのべ live recording H29.07.02」を販売開始する。2018年1月17日、合奏編成による初のスタジオ作EP「ざわめき」をリリースする。2018年2月より半年かけて、全国23箇所で弾き語り投げ銭ツアーを敢行。10月3日に最新作『平成』をリリース。独特の歌唱法にして、ブルーズ、民族音楽、ジャズなどにも通じたセンスを持ち合わせながら、それをポップスとして消化した稀有なシンガー。その音楽性とライヴパフォーマンスから、宇多田ヒカル、ゴンチチ、後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)、伊集院光、小山田壮平(ex: andymori)、坂口恭平、寺尾紗穂らより賛辞を受ける。
- フィードバック 18
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


