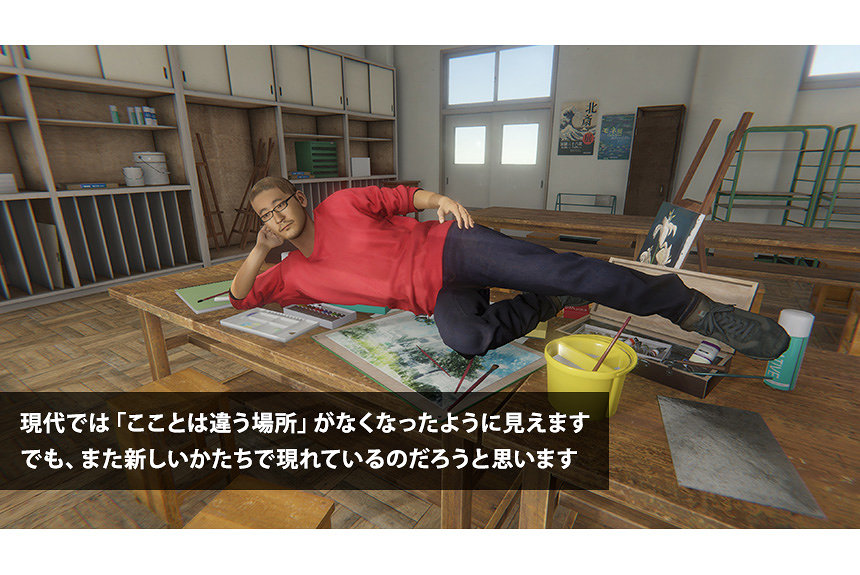2010年代は、スマホや仮想空間をめぐる技術の普及によって、現実とインターネットの距離が急速に縮んだ時代だった。2000年代後半に活動を始めた谷口暁彦は、こうした新技術がもたらすリアリティーの変化を、ユーモアと深い考察を通じて示してきたメディアアーティストだ。自身のアヴァターや身近な日用品が登場するその作品は、忘れがたいインパクトを与えると同時に、見るものの世界に対する眼差しを静かに変えていく。
そんな谷口の初となる劇場作品『やわらかなあそび』が、10月より開催されている『フェスティバル/トーキョー19』のプログラムとして上演される。この公演を機に、彼にこれまでの活動の歩みを尋ねた。谷口は、いかにネットアートに出会い、変わり続ける社会の中で独自の表現を作り上げたのか? そして、「いまここ」を強く意識させる劇場空間にヴァーチャルな世界を介入させる、今回のパフォーマンスでの挑戦とは?
ネット世界と現実の関係を探る原体験
―谷口さんが、インターネットや画面上の世界と、現実との関係性に興味を持った原体験はなんですか?
谷口:よく覚えているのは、初めてインターネットにつないだ中学の頃に見た、なんの変哲もないニューヨークの交差点を映したライブカメラの映像です。うちの姉は工学・情報系の人で、当時はパソコンを自作したりしていたんですが、彼女が余ったパーツで作ってくれたパソコンでそれを見ました。テレビのように編集されず、ただ一箇所を映し続ける映像で、遠く離れた別の場所でリアルタイムに起きている出来事が、埼玉の田舎で見れることに、不思議な感覚がしたのを覚えています。
また、子どもの頃にプレイしたビデオゲームも大きかったです。1997年に発売された『moon』(アスキー)というRPGがあるのですが、これは勇者になって敵を倒すのではなく、なんの理由もなくモンスターを殺したりする「悪者」としての勇者から世界を救うゲームなんです。ゲームや遊びの前提を疑ったり、メタ的に捉えていた作品で、すごく印象に残っています。

メディアアーティスト。多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース講師。メディアアート、ネットアート、映像、彫刻など、さまざまな形態で作品を発表している。主な展覧会に『[インターネット アート これから]——ポスト・インターネットのリアリティ』(ICC、2012年)、『SeMA Biennale Mediacity Seoul 2016』(ソウル市立美術館、2016年)、個展に『滲み出る板』(GALLERY MIDORI。SO、東京、2015年)、『超・いま・ここ』(CALM & PUNK GALLERY、東京、2017年)など。
―ゲームというと、大学院時代の初期作品『jump from』(2007年)は、スーパーマリオを使った作品でしたね。鑑賞者がマリオをジャンプさせると、谷口さんがプレイする過去の実写映像が画面に挿入され、時間感覚が混乱させられる作品です。
谷口:そうですね。ただ、最初からコンピューターやゲームを使った作品を志向していたわけではないんです。僕はもともと彫刻学科に入学したのですが、学科の空気に馴染めず、3年生から情報デザイン学科に編入しました。『jump from』は、当時よくつるんでいた油絵科の友人から聞いた作品のアイデアから着想した作品です。
そのアイデアとは、あるギャラリーに、その建物の駐車場に黄色いスポーツカーが停まっている様子を描いた絵が飾られている。それを見た鑑賞者は驚く。なぜなら、自分が同じ車に乗ってきたからだ……というものです。つまり、ある種の預言として機能するような絵画というものでした。
もちろん、そんな絵は描くことができないというか、その不可能性がロマンチックなんですが、コンピューターやプログラムを使えばそんな構造を身も蓋もない感じで作れてしまうのではないか、と思ったんですね。メタフィクションに関心があったので、どんな構造を使えばそうした作品を作れるかを考える中で、ゲームを使うアイデアに至ったんです。
―テクノロジーの使用は、作品コンセプトの要請によるものだったんですね。メタフィクションへの関心はどこからきたのですか?
谷口:僕が学生の頃、90年代後半から2000年代頃に登場したラップトップミュージシャンからの影響があったと思います。具体的にはOvalや Alva Noto(ともにドイツの音楽ユニット、音楽家)といったアーティストたちです。僕も当時、Max/mspなどを使用して、ラップトップミュージックを作っていました。特にOvalがそうだったのですが、彼らには、あたらしい音楽を生み出すためには、そのためのツール、ソフトウェアから自作しなければならないというような「制作に対するメタな態度」があったんですね。
Oval『Systemisch』(1994年)を聴く(Apple Musicはこちら)
―大学院修了後、活動を本格化する中ではどんな出来事がありましたか?
谷口:2000年代後半はTwitterが普及し始めた頃で、ネット上で友達の友達くらいまでの距離でゆるやかに繋がっていたように思います。仲間内と公共の間くらいの領域でちょうどよく活動できていたというか、騒げていたところがありました。当時、僕は同級生の渡邉朋也くんと「思い出横丁情報科学芸術アカデミー」というメディアアートの架空の学校を作り、夜な夜な Ustreamで配信を行いながら批評活動のようなことをしていていました。それもやはり当時のインターネットの雰囲気でできたことのように思います。
また、そうした活動を通じてネットアートのユニット「エキソニモ」の千房けん輔さんと出会いました。当時、千房さんは「Webの質感」という言葉を使われていて。たとえば、「(ファイル形式の)JPEGとGIFではどちらが硬いか?」といったような、一般的には謎な(笑)、けれど現代的な感覚について言及していたんですね。このような問題についての議論が、2012年に開催された『[インターネット アート これから]——ポスト・インターネットのリアリティ』展(ICC)につながりました。
―同展は、その数年後に日本でも広く注目された「ポストインターネット」という概念や感覚を先駆的に取り上げた展示でした。
谷口:そうですね。その頃はネット由来の質感に、多くのアーティストが注目していました。たとえば2010年から2012年頃にかけて「GIF」が再注目された時期もありました。当時、アンソニー・アントネリスというアーティストの「putitonapedestal.com」というGIF画像を架空のギャラリー空間に展示することができる作品があって、それに影響されて僕も「GIF 3D Gallery」という、3次元の仮想空間にGIF画像を展示することができるネットアート作品を作っていたりしました。

現実とヴァーチャルの境界が曖昧になった時代を表現するために、谷口が使用したのは「日用品」
―谷口さんはたびたび、ネット接続に面倒なプロセスが必要だった時代と、スマホの普及によって常時ネットとの接続が可能になった現代のギャップについて語っています。
谷口:かつて、インターネットはわざわざ接続して別の世界にログインするものだったわけですが、それが常時繋がっていて、メールや通知が来るたびに、スマホの入ったポケットがブルっと揺れる。それは明確にリアリティーが変化した感覚がありました。
もうひとつ象徴的だったのがGoogleマップやストリートビューの登場です。 現実の世界がインターネット上に複製されていて、かつ「現在地」ボタンを押すと、インターネットの側から自分がどこにいるかを教えられるわけですよね。つまり、完全に現実とインターネットが重なり、同期してしまっていて、現実とは異なる場所としてのインターネットは、もうそこにはないように思えてしまったんですね。

―現実とネットの境界がますます曖昧になった2010年代半ば以降、谷口さんの多くの作品にご自身のアヴァターや身近な生活空間が登場するようになったのは興味深いことだと思います。こうした作風に向かった経緯とはなんだったのでしょうか?
谷口:時系列に沿ってお話しすると、最初に自分の生活空間を題材にしたのは『実家3D』(2010年~)でした。これはラップトップでのライブパフォーマンスのためのソフトウェアです。実家の仮想空間の中で、サウンドファイルと紐づいた様々な日用品を放り投げながら、音と映像をコンポジションしていくライブパフォーマンス作品です。
この作品の背景には先ほど挙げたような、僕が当時影響を受けたラップトップミュージシャンへのアンチもありました。というのも、しばしばそうしたアーティストのライブでの映像は、黒い背景に白い線や幾何形態が明滅したりするようなミニマルで抽象的なものばかりだったんですよね。それらの表現は、人間の知覚や身体にダイレクトに働きかけるものでもあって、そこに面白さや魅力があるんですが、僕はそれとは逆のことをしなければと思ったんですね。つまり具象的で、ドメスティックで、過剰な意味が出てきてしまうようなことがしたいと思ったんです。
―それで日用品を出そうと。作品では、具体的な商品が膨大に登場しますよね。
谷口:そうですね。たとえば、サランラップなどが登場しますが、具体的な商品を出すことの面白さは、そこにヴァーチャル空間と現実との記号的な一致や、二重性が生まれることだと思います。
そんな考えを発展させて、2015年でのライブの際、実際の会場や演奏する僕の姿も含めてヴァーチャルに構築した『hyper experimental live performance set』を作りました。音楽を作るために、楽器やソフトウェアから作るというアプローチを、もう一段メタ的に捉えるなら、それらが置かれた空間とか場所の問題になるんじゃないかと思ったんですね。そんなことを考えて制作した作品でしたが、ここで初めて2Dの僕のアヴァターが登場しました。そこで目指していたのは、「私」というものがこちら側にも、向こう側にもいるという二重の状態です。その意味では「谷口暁彦」のアヴァターも日用品と同じような必要性から生まれてきたのだと思います。

―記号の二重性によってなにを表現したいのか、もう少し聞かせてください。
谷口:たとえば、単純に僕がアヴァターを操作しながら「私はいまここにいる」と発話すると、それだけでどの空間のどの時制に存在するのか分からなくなるんですよね。そうした不確かさが表現したかったのだと思います。また、スーパーマリオを使った『jump from』という作品を制作したときから、画面の中で起きていることをたんにフィクションのままにしたくないという意識がありました。作品って、どんなに現実の問題を取り扱っていても、基本的にはフィクションなんですよね。もちろん、フィクションだからこそ作品を通じて様々な可能性や未来について思考することができるんですけど、そのフィクションがどのように現実に作用できるかについて考えたかったんですね。このあたりは、僕が大学でメディアアートについて学んでいたことも大きいと思います。つまりこれはインタラクティブアートの問題でもあるわけです。インタラクションによって、たんに作品の見た目が変化するようなものではなくて、相互にフィクションと現実、あるいは作品と鑑賞者が、どのように影響を及ぼしあうようなことができるのかという問題です。
具体的には画面の中と外をどのように繋げるのかということを考えていました。日用品の使用も、みんなが目にしたことのあるものが画面の中に登場することで、その日常の世界と作品とを繋げるようなことがしたかったんですね。
ネットと現実がさらに近いものになった現在における新たな同期とズレ
―日本のメディアにおいて「ポストインターネット」という言葉が注目されたのは2010年代半ばでしたが、より近年のネットと現実をめぐる動きで気になっていることはありますか?
谷口:ネットがオルタナティブでもなんでもなくなった、ということは思います。国内的にネットが社会のインフラとして強く意識されたのは2011年の東日本大震災だったと思います。その頃からネットが本当に公共空間のようになってしまった。トランプ(米大統領)が Twitter で発言しているなんて、以前の感覚からするとすごく異常な状態だと思うんですね。

―そうした中、近年では「ダークウェブ」と呼ばれる、検索に引っかからないネット上の空間への注目も高まっています。
谷口:そうですね。僕自身はダークウェブについてあまり詳しくないのですが、ヴァーチャルな空間にオルタナティブな居場所を見つけたいという欲望は、インターネット黎明期から変わらずにあったものだと思うんですよ。僕の「GIF 3D Gallery」も、ある意味ではそんな古くからのネット文化に連なるものという意識がありました。現代では、そうした「こことは違う別の場所」が一見なくなったように見えますが、また新しいかたちで現れているのだろうと思います。
個人的に、最近関心を持っていたのは「VR Chat」です。ヘッドマウントディスプレイを装着して、ヴァーチャル空間で様々な人とアヴァターを通じてコミュニケーションを行えるサービスなんですが、2018年、VR Chatに参加中のユーザーが持病の発作で倒れてしまう事件がありました。
ほかのユーザーはその人を助けようと試みるわけですが、助けようと近づいてもアヴァターの身体に触ろうとするとすり抜けてしまう。そもそも、倒れて苦しむアヴァターに触れることができても、それは実際に発作によって苦しんでいるユーザーを助けることとは無関係なんですよね。結局、その発作を起こしたユーザーは、無事に回復して命に別状はなかったそうです。VR Chatは、ヘッドマウントディスプレイやセンサーによってユーザーの身体をヴァーチャルな空間へと同期させているのですが、この事件は、仮想空間内で同じ場を共有しているユーザーたちの身体は、そもそも現実にはバラバラな場所にいて、お互いに触れることもできず、無関係なんだという事実を明らかにしてしまったんですね。僕はこの事件を知ったとき、辛いというか、ちょっと切なくなってしまった。
―ヴァーチャル空間に、生の「現実」が入り込んでしまった瞬間ですね。
谷口:そのユーザーたちが同じ場所に共存することが可能だったのは、じつは現実には同じ場所にいないからこそだった、というように思ったんですね。つまり、Photoshopのレイヤーのように、同じ場所で重なっているように見えるためには、それはそもそも異なるレイヤーに存在していないといけないというか。今年制作した「んoon」(ふーん)というバンドの“Gum”という曲のミュージックビデオは、そんなことを考えながら制作していました。そこではいくつかのキャラクターがひとつの場所で重なり合い、キメラのようになって蠢(うごめ)いています。でもそれが可能なのはそのキャラクターの身体が空虚で、互いに触れることなく無関係だからなんですよね。こうした問題は、今回の劇場作品とも関わるものかもしれません。
―初となる劇場作品『やわらかなあそび』は、どのようなものになる予定ですか?
谷口:まだ未決定の部分が多いのですが、形式的には、かつて無声映画の内容を生で解説する活動弁士という人たちがいたじゃないですか。おそらくそれに近いかたちで、スクリーンの横に僕がいて、エッセイのようなテキストを朗読しているというものになると思います。
それらのテキストは、主にヴィデオゲームなどにおけるコンピュータの中のシミュレーションの問題についてのものです。そうしたシミュレーションされた世界の中では現実の物理法則に即して様々な出来事が再現されるわけですが、たとえば僕も作品制作に使用しているゲームエンジンにはラグドールと呼ばれる物理演算のシステムが標準で用意されています。それは気絶したり死亡したキャラクターの脱力した身体の動きを再現するための機能なんですね。つまり、しばしば現実で起きた場合には事故や悲劇のように見える出来事が当たり前のように機能として用意されているのです。しかしそれ自体は現実とは直接に関係がなくて、どこか空虚で「安全な事故」のように存在している。そうしたシミュレーションされた仮想空間と、現実との関係の中にある、一種のズレや空虚さがこの作品のテーマになってくると思います。

―近年、話題を集めるメディアアートには、観客を映像の世界に没入させるタイプのものも多いですが、今回お話を聞いて、谷口さんはずっと現実と仮想空間の境界を問うてきたのだと感じました。ゆえに谷口さんの作品は、決して居心地はよくない。むしろ、そのあいだに生まれるズレを通じて、両者の関係の再考を迫るものが多いですね。
谷口:そうですね。作品を見る人の感覚が、作品の鑑賞体験を通じてちょっとでも変わってほしいと思っています。マリオを使った初期の作品から、近年のアヴァターを使った作品まで、見る人の主体性がバラバラになったり、時間の感覚が伸びたり縮んだりする感覚を作ろうとしてきたように思います。僕は、自分がわりと優柔不断のせいもあってか、あんまり主体性がなくて、自分の存在が不確かになることのほうが面白いという感覚があります。そういう不確かさについて、ずっと考えている気がします。
そして、こうした分裂したり、不確かになった主体の感覚は、ネットが現実に重なった世界では、誰もが日常的に体験していることだと思います。ただ、同時にそうした感覚はどこか抑圧されているものでもある。僕は、作品を通してそうした感覚について考えているのだと思います。

- イベント情報
-

- 『フェスティバル/トーキョー19』
-
2019年10月5日(土)~11月10日(日)
会場:東京都 池袋 東京芸術劇場、あうるすぽっと、シアターグリーンほか
主催:フェスティバル/トーキョー実行委員会
「トランスフィールド from アジア」共催:国際交流基金アジアセンター『やわらかなあそび』
2019年11月9日(土)~11月10日(日)
会場:東京都 池袋 シアターグリーン BIG TREE THEATER
演出・出演:谷口暁彦『Sand(a)isles(サンド・アイル)』
2019年10月28日(月)~11月10日(日)
会場:東京都 池袋 周辺
演出・設計:JK・アニコチェ × 山川陸『Bamboo Talk(バンブー・トーク)』『PhuYing(プニン)』
2019年10月25日(金)~10月27日(日)
会場:東京都 池袋 東京芸術劇場 シアターイースト
振付:ウンラー・パーウドム、ヌーナファ・ソイダラ『To ツー 通』
2019年11月2日(土)~11月4日(月)
会場:東京都 池袋 シアターグリーン BIG TREE THEATER
企画・出演:オクイ・ララ × 滝朝子『トランスフィールド from アジア トーク』
2019年11月2日(土)、11月3日(日)、11月9日(土)
会場:東京都 池袋 東京芸術劇場 シンフォニースペース他『ファーム』
2019年10月19日(土)、10月20日(日)
会場:東京都 池袋 あうるすぽっと
演出:キム・ジョン
作:松井周『新丛林 ニュー・ジャングル』
2019年10月18日(土)~10月20日(日)
会場:東京都 池袋 東京芸術劇場 シアターウエスト
コンセプト・演出・出演:香料SPICE『Strange Green Powder』
2019年10月24日(木)、10月26日(土)、10月27日(日)
会場:東京都 池袋 豊島区立目白庭園 赤鳥庵
振付・演出:神村恵『Changes シーズン2』
2019年11月2日(土)~11月4日(月)
会場:東京都 池袋 HUMAXシネマズ
ディレクション:ドキュントメント『オールウェイズ・カミングホーム』
2019年11月9日(土)~11月10日(日)
会場:東京都 池袋 東京芸術劇場 シアターイースト
原案:アーシュラ・K・ル=グウィン
演出:マグダ・シュペフト『NOWHERE OASIS』
2019年11月1日(金)~11月10日(日)
会場:東京都 池袋 東京芸術劇場 劇場前広場 ほか
コンセプト・ディレクション:北澤潤『ひらけ!ガリ版印刷発信基地』
会場:東京都 大塚 ガリ版印刷発信基地
ディレクション:Hand Saw Press
- プロフィール
-
- 谷口暁彦 (たにぐち あきひこ)
-
メディア・アーティスト。多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース講師。メディア・アート、ネット・アート、映像、彫刻など、さまざまな形態で作品を発表している。主な展覧会に『[インターネット アート これから]——ポスト・インターネットのリアリティ』(ICC、2012年)、『』SeMA Biennale Mediacity Seoul 2016』(ソウル市立美術館、2016年)、個展に『滲み出る板』(GALLERY MIDORI。SO、東京、2015年)、『超・いま・ここ』(CALM & PUNK GALLERY、東京、2017年)など。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-