古きをたずね、新しきを知る。温故知新の精神は、ときに懐古主義にもなってしまうが、かつての熱量に触れ「いま」を再定義することには意味がある。そんな気持ちにさせてくれるインタビューをお送りしたい。日本を代表するテクノミュージシャンであるKEN ISHIIが、2019年に2曲のMVを発表した。1つは、彼自身を国際的なスターダムに押し上げた傑作“EXTRA” へのオマージュシーンも登場するアルバムリード曲の“Bells of New Life”。そして、“EXTRA”やその参照項たる大友克洋の『AKIRA』と時代を同じくするビデオゲーム『パックマン』の生誕40周年を祝う“JOIN THE PAC”だ。
それらの映像を担当したのは、ディレクターに椎名林檎など数々のアーティストのMVを手がけた児玉裕一と、VR制作などを手がけ、今回のMVのクリエイティブディレクターを努めた土井昌徳。このビジョン豊かな三人の鼎談だ。
『AKIRA』ってあまりにも鮮烈すぎて、簡単にその上位バージョンが現れる感じがない。(KEN)
―児玉さんが監督を、土井さんがクリエイティブディレクターを努められた“Bells of New Life”のMVには、1995年に発表されたKENさんの伝説的な曲“EXTRA”のMVへのオマージュシーンも登場しますね。アニメーターの森本晃司さんによる同MVは、1988年公開の、やはり伝説的なアニメーション映画『AKIRA』とも通じる描写があります。そして、みなさんは全員が大の『AKIRA』好きだとか!
児玉:やっぱり『AKIRA』も“EXTRA”もめちゃくちゃ衝撃でしたからね。KENさんが森本さんにMV制作を依頼したのも、やっぱり彼が『AKIRA』の作画を担当されていたのがきっかけですか?
KEN ISHII:『AKIRA』の衝撃は間違いないです。映像にしても音楽の使い方にしても、それまでのあらゆる映像とは一線を画していて、公開当時の僕はごく普通の少年でしたけど、記憶に強烈に焼きついてました。その後に音楽の世界で活動するようになって、ヨーロッパのレーベルから新作を出すにあたって「なにか特別なアイデアがないか?」といわれたんです。そのときに出てきたアイデアが『AKIRA』の森本さんにお願いするということ。でも、まさか本当に作っていただけるとは夢にも思っていませんでした。なんのコネもなかったですし。
でも、大友克洋さんや森本さんが根城にしてる店に、物怖じしない当時の担当者が突撃したんですよ。僕ら全員20代で血気盛んだったから。

「東洋のテクノ・ゴッド」との異名を持つ、アーティスト、DJ、プロデューサー。1年の半分近い時間を海外でのDJで過ごす。︎1993年、ベルギーのレーベル「R&S」からデビュー、イギリスの音楽誌「NME」のテクノチャートでNo.1を獲得。1996年アルバム『Jelly Tones』をリリース。このアルバムからのシングル「Extra」のアニメーションMV(映画「AKIRA」の作画監督/森本晃司監督作品)が、イギリスの“MTV DANCE VIDEO OF THE YEAR”を受賞した。2017年にはベルギーで行われている世界最高峰のビッグフェスティバル<Tomorrowland>に出演するなど常にワールドワイドに活躍している。
児玉&土井:(笑)
KEN ISHII:それで一緒に飲んでみると、大友さんも森本さんもテクノ好きでよく聴いてると。森本さんのスタジオを訪ねてみると、実際にデスクにステレオがあって、並んでるCDもテクノばかりで、聴きながら作画をしているとおっしゃっていました。そこからはトントン拍子で話が進みましたね。
―あの独自の世界観もそのやりとりから生まれたのでしょうか?
KEN ISHII:MV中で使っているSEの提供とかはしてますけど、あとはもう森本さんにお任せでした。アニメってそう簡単に個人で作れるものではなくて、大きなチームで時間とお金をかけるから、できる冒険も限られているんです。でも音楽のMVであれば好きなことを大胆にできるんじゃないかと森本さんはおっしゃってたんですよ。はじめて自分の映像をつけてみたい音楽に出会えたともいっていて、かなり燃えてやってくださいました。
―いい話ですね!
児玉:僕の『AKIRA』との出会いは、2つ歳上のいとこのお兄ちゃん経由でした(笑)。やたらカラフルな漫画の単行本を「やばいやばい!」って読んでいるのを脇から見ていて「へー?」って思ってたんですよ。それで、その後映画化されるというのを知って、たしか10歳くらいで映画館に観に行ったんです。

映像監督。1975年生まれ。東北大学理学部化学系卒業。広告代理店勤務を経て独立。2006年より「CAVIAR」に所属。2013年9月「vivision」 設立。 CM、MVなどの演出を手掛ける。近作にHONDA「HONDA JET」 asics「ぜんぶ、カラダなんだ。」SoftBank「しばられるな」椎名林檎MV「鶏と蛇と豚」など。 リオ五輪閉会式の五輪旗の引き継ぎ式における東京パートのチーフ映像ディレクターを務めた。
―早熟な10歳(笑)。感想はどうでした? けっこうグロいシーンもありましたが。
児玉:「ぜんぜん意味がわからないけど、スゴイ!」って大ショックでした。そしてまた時間が飛ぶんですが、大学生のときに“EXTRA”MVを見るわけです。その頃になるといろんなカルチャーにも触れて楽しみつつも、なにかもやもやするようなものも抱えていたんですが、“EXTRA”MVが目の前に現れたことでそのもやもやに「パチン!」とピースがハマったように感じました。その後は“EXTRA”MVと『AKIRA』を交互にエンドレスで見続ける……そんな学生時代でしたね。
土井:僕の『AKIRA』ショックは深夜のお風呂上がりでした(笑)。風呂から出て、テレビをつけたらちょうどクライマックスの鉄雄がわーっとなってるところで「なんだこれは!」と。それで翌朝学校に行くと、たまたま趣味の合う友だちも放送を見ていて「昨日のアレ、見た!?」って盛り上がったんです。僕は地元が千葉なんですけど、その日の放課後に津田沼の本屋さんに走って、即単行本を買いに行くっていう(苦笑)。
その後にいろいろ掘っていくんですけど、そういえば映画が公開されていた8歳くらいの頃の記憶に、主人公の金田がバイクでスライドさせるイメージがあったことを思い出したりしていって、そうやって一気に糸がつながっていった感じです。KENさんの“EXTRA”MVとの出会いも、昔パルコの上にあったギャラリーでやっていた大友克洋の展示会でした。
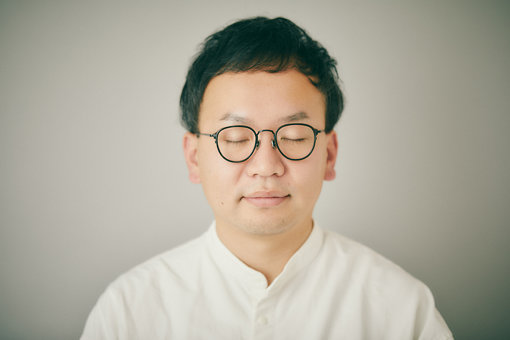
株式会社HERE.代表取締役社長/クリエイティブディレクター。学生時代より映像制作を始め、VJ(Visual Jockey)として数多くのライブでの映像演出に参加。CGプロダクションでのVFXデザイナーを経て、映像作品のプロデュースやライブエンターテイメント空間、商業施設における映像演出を手掛ける。
KEN ISHII:やっぱり脳裏への焼きつけ方の強さが違いますよね。他のSF超大作って続編があったりすると、最初の衝撃が更新されていく感じがあるんですけど、『AKIRA』ってあまりにも鮮烈すぎて、簡単にその上位バージョンが現れる感じがない。だからずっと残るんだろうなっていまの話を聞いていて思いました。
あと、音楽もかなり不思議ですよね。あのオリジナリティーあふれる音楽が、よくアニメ映画の音楽として企画を通ったと思います。そこもトンガっていた。
児玉:KENさんはあの音楽を当時からテクノミュージックとしてとらえてましたか?
KEN ISHII:昔もいまもテクノって感じではないかもしれません。とにかく独創的。それがあんな大作に使われるっていうところが「かっこいいなー」と。森本さんとの思い出でいうと、“EXTRA”の中で壁面に実写映像が映っていて、若き日の僕が出てるんです。それでなにか食べてるんだけど。
―蕎麦かなにかでしたっけ?
KEN ISHII:あれはね、ワカサギの揚げ物。南蛮漬けかな?
児玉:え! 僕、ずっとカニか焼き鳥だと思ってました。
KEN ISHII:あれは中打ち上げを兼ねてみんなでご飯を食べてるところなんです。みんな楽しい気分で「撮影していい?」って森本さんが撮った映像。だから、画面の外にはじつは大友さんもいるんです。
全員:へー!
児玉:何回もビデオを止めて見ていたのにワカサギと気づきませんでした……。長年の謎が解けました。
1990年代にあった「センス・オブ・ワンダー」の世界を映像化したかったんです。(児玉)
―今回の“Bells of New Life”のMVを依頼されたときはどんな思いだったのでしょう?
児玉:身に余る依頼で緊張しつつ、様々にアイデアを出し合う中で最初の段階では「EXTRAの続編になったら面白いよね」なんて雑談を交わしていたんですけど、もしも本当に続編を作るのだとしたら、それは絶対に森本さんによるアニメ以外にはありえないわけで。

それで、KENさんの音源を繰り返し聴きながら考えていたんですけど、やっぱり長年のファンとしてはそうしているだけでテンションが上がる。はじめてテクノを聴いた頃や、はじめてクラブに行ったときのこと、1990年代当時のテクノや、WARPレーベルのMVのことなんかがものすごい勢いでフラッシュバックしてきて、「この時代を映像化したい」と閃いたんです。
じゃあ1990年代初頭の「時代の感覚」ってなにか? いろんなものが思い浮かびますけど、僕らが目を留めたのは、インターネット登場以前の噂だけで成り立っていた、都市伝説とかそういうわくわくした「センス・オブ・ワンダー」の世界でした。
―たしかに“Bells of New Life”MVには新人類的な子どもたちが登場しますね。超能力のような力を持っていて。あと個人的にヒットだったのが、彼らが遊んでいるのがPlayStation VRだったり、カセットビジョン(1980年代初頭にエポック社が発売したゲーム機。ファミコン発売前に大ヒットした)だったりして、過去と現代が混ざり合っているところです。
児玉:そう。時間軸がめちゃくちゃなんです。でも、それこそが2020年の世界だと思うんです。すべての事象が並列的に陳列されていて、自分の意思で調べて、好きなものを自由に得られるような時代。1990年代初頭と現在のミックスが“Bells of New Life”のMVなんです。
それから、この企画が動き始めたときに、この曲が生まれたきっかけがお子さんが生まれたことだとKENさんから聞いたのも大きいです。僕も土井さんも最近父親になったばかりで、子どもっていう存在に対する興味が強くあったんですね。僕らからするとまったく未知のよくわからない存在であって、その内側には正体のわからない、でもとてもよいものが詰まっている生命体。それはかつて僕らが子どもだったときに大人たちが感じていた感情かもしれず、そのあたりも昔といまをつなぐヒントになっています。
KEN ISHII:絵的にはきれいでさわやかだけど、よくよく見てみるとミステリアスなんですよね。ちょっと影もあって。

児玉:僕が子ども時代の記憶で強く印象に残っているのが、世田谷の中学校で卒業生たちが学習机を9の字に校庭に並べた、机「9」文字事件。当時「9は光GENJIのメンバーから一人減った数だから殺害予告なんじゃないか」とか物騒な噂があって。
土井:あとは1999年に人類が滅亡するという、ノストラダムスの大予言。
児玉:僕たちは本気でそれを信じてた世代ですからね(笑)。そういうミステリアスな世界観を背景に、KENさんの音楽の気持ちよさ、子どもたちが輪になって踊っている様子を空中から撮っているイメージなんかが浮かんで、これでいこう、と。
KEN ISHII:いまおっしゃっていた話の全部が詰まった仕上がりになりましたよね。子どもが生まれたときにできた曲ということで、「これまでの活動を一回仕切り直すぞ」くらいの気持ちもありましたよ。曲作りでうまくいくときって、たいていの場合、目的意識がはっきりしているとき。今回もスコーンとできたし、ふだんはけっこう悩むタイトルも自然と浮かんできました。だからとてもクリアーなんですよ。曲の構造もとってもシンプルだし。
土井:個人的にテクノミュージックに対して、ポジティブで明るい未来のイメージがあるんですけど、“Bells of New Life”はまさにそこにハマる曲でした。且つ、13年ぶりにリリースするKENさんのアルバムのタイトルが『Möbius Strip(メビウス・ストリップ)』なのも(参考記事:KEN ISHII×ジェフ・ミルズ ダンスミュージックはもっと進化する)、僕にとっては“EXTRA”から始まった自分のテクノ史がメビウスの輪のように循環してスタート地点に戻ってきて、そこからまた新しいものが始まる、という感じがあって。テクノを聴いて青春期を過ごした同世代の人たちが、「またテクノを聴きたい」「クラブに遊びに行って一晩中踊りたい」と思いはじめるきっかけになるようななにかを作りたいという気持ちがありました。

1990年代にはたしかに暗いところもあるんだけど、それを視界に入れながらもポジティブでありたいと思っていました。
―ポジティブさの裏側に闇があるのも1990年代の特徴ですね。バブルの残滓がありつつも、オウム真理教の事件や阪神大震災が起きました。鬱々とした『新世紀エヴァンゲリオン』の放送もこの頃です。
土井:ものすごい勢いの裏に、強烈な「死への不安」がありましたよね。僕が“EXTRA”に出会ったのも中学二年の多感な時期でしたから、愛情もあり、怖さもあり、という感じでうまく消化しきれない複雑さがいまもあります。だからこそ、そういう陰の1990年代に対して、いまは陽のコンテンツを作るべきだと思うんです。だからこそ“Bells of New Life”のMVでは青空を映しています。

KEN ISHII:まさにそういう映像を作りたいなと思っていたから、みんな同じことを考えていてよかったです。1990年代にはたしかに暗いところもあるんだけど、それを視界に入れながらもポジティブでありたいと思っていた気がしますね。
音楽的にも本当に新しいものが次から次へと出てきて、とくにダンスミュージックやエレクトロニックミュージックに関しては、ある意味での黄金期といえます。さらに、音楽の作り手がリアルになってきたのもこの頃。1980年代は「大きなイメージ」「手の届かないもの」を人為的に作り出すフィクショナルなところがあったけれど、1990年代は「本当にこいつがこの音楽を作っているんだ」っていうリアルさがあって、それを世界中の人間が支持してくれる感じがありました。実際、自分だってただの学生でしかなかったのが、レコード会社にカセットを送ったら、それがいきなりレコードになってデビューしたわけで、「自分にもできるかもしれない」っていうわくわく感の尽きない時代だったんです。
児玉:国内外を問わず、小さなレーベルがすごくよい音楽をいっぱい出してましたよね。その各レーベルを信頼しながらジャケ買いしていくのも楽しかった。

KEN ISHII:ただ「あの頃はよかった」みたいな話ばかりしててもイケてない感じがしますね(苦笑)。でも、やっぱり素晴らしい時代でした。
ところが2000年を超えるとテクノもその役割を変えていく。かたちが定まって世間に行き渡ると、次にやってくるのは誰もが「最大公約数」を取ろうという方向に舵を切っていくんです。ダンスミュージックがどんどんコマーシャルになっていって、ついにはEDMみたいなものが生まれて、アメリカの田舎町の子どももエレクトロニックミュージックを聴くようになった。それは喜ばしい成功ではあるけれど、ある意味では進化の終着点かもしれない。だからこそ、いまポジティブなものを作りたいのかもしれないですね。

土井:以前、KENさんが「テクノミュージックは祭囃子をシンセサイザーでやっているような感覚なんだ」って話してたんですよ。それはすごく共感するところで、祭りの太鼓を聴いたときのような高揚感がテクノにはある。クラブに行くのも、お酒をバカみたいに飲んで爆音を浴びて意識を失って、それがストレス解放になって……みたいなのではなくて、もっとスポーツ的なピュアな楽しさや高揚感を得られる体験だったんです。いまみたいなモヤモヤした時代だからこそ、そういったピュアさをもう一度大事にしたいと思うんです。
かつてあった「たまり場」の熱量を再起動したかったんです。(土井)

―その意味では、児玉監督と土井さんが関わったもう一曲の“JOIN THE PAC”もポジティブですよね。伝説的なゲーム「パックマン」の誕生40周年を祝福するオフィシャルテーマ。
KEN ISHII:ブランドを展開しているバンダイナムコエンターテインメントさんとは、これまでにも「アスレチックVR PAC-MAN CHALLENGE」PVの楽曲制作でご一緒してるのですが、その縁で、今回の世界キャンペーンでも声をかけていただいたんです。
―パックマンの誕生が1980年ですから、『AKIRA』の時代とも共鳴するものがありますね。
KEN ISHII:そうですね。ただ、パックマンって本当に世界中で愛されているアイコンですけど、『AKIRA』と違って意外と日本で生まれたってことを知らない世代も多い。ですから今回の曲でも、パックマンの象徴的なフレーズやSEをふんだんに使ってパックマンのカルチャーを印象づけつつ、知らないうちにからだが動き出してしまうダンスミュージックの楽しさも入れ込もう、というのがコンセプト。
児玉:曲を聴いて「こんなアッパーな曲をKENさん作るんだ!」ってびっくりしました。
KEN ISHII:自分でもかなり頑張りました。
児玉:この踊りたくなる感じは、テクノの文脈の外にも波及する力があるなと思いました。それこそ「パリピも踊らせちゃうぜ」というか(笑)。自分も制作当時、Netflixで『ヒップホップ・エボリューション』や『ゲットダウン』を見てヒップホップ熱が再燃しておりまして……そういえばパックマンの生まれた1980年は、まさにヒップホップの黎明期でもあり。それでできたのが今回の映像なんです。
―「PAC MANIA」なるスペースでB-BOYたちが踊るっていう。
児玉:クラブでもありつつ、ゲームセンターでもある場所。子どものときに感じていたゲームセンターの不良なイメージと、でも異常にかっこいい、っていうイメージの融合。そしてそれはあの頃のクラブの感じにもあって、その全部をごちゃごちゃにしてハンバーグみたいにこねたわけです。でもそれって必然的じゃないですか。音楽もゲームもカルチャーですから。
KEN ISHII:僕もちょっとだけ出演してるので撮影現場に立ち会ったんですけど、すっごい楽しかったですね。ビデオの明るい感じが撮影中も続いていて。
土井:ポジティブさですよね。サウンドシステムを中心とした手作りのウェアハウスパーティーに、みんなが自慢の一張羅を着てやって来て、四つ打ちで踊りまくる。そういう、かつてあった「たまり場」の熱量を再起動したかったんです。
KEN ISHII:人が集まるところにはやっぱり熱が生まれますからね。さっきの話にも通じることで、「俺にもできるかも」と誘発されるような環境が必要ですよ。1990年代のダンスシーン、クラブシーンって、単に楽しいだけじゃなくて、そこから学んだり挑発されることで新しいものが生まれる時間と空間だったんですよ。端的にいって、それは希望でした。
いまのダンスミュージックはあまりにも消費物みたいになっていて、一曲一曲の賞味期限も短いし、とにかく音楽の数が多すぎるし。その状況で、他とはちょっと違うもの、違うなにかが乗っかっているものを作りたいなと強く思っています。そして願わくば、そこに一番に乗っているものは「希望」であってほしい。
児玉:だから、今回のKENさんのアルバムには気合を感じます。CDエクストラもつけて7インチレコードもつけてポスターもつけてって、もう「物質感の塊」じゃないですか。そのリアリティーでもって時代に楔を打っていく感じは、かつての音楽のシーンにあったものだから、グッと来てしまう。
KEN ISHII:記憶から絶対に消せないものを、って感じで(笑)。
児玉:それが、令和元年に出たっていうのが希望です。

- リリース情報
-

- KEN ISHII
『Möbius Strip』完全生産限定盤 Type A(2CD+7インチアナログ盤) -
2019年11月27日(水)発売
価格:5,060円(税込)
UMA-9130~2[CD]
1. Bells of New Life
2. Chaos Theory
3. Take No Prisoners(Album Mix)with Jeff Mills
4. Vector 1
5. Green Flash(Album Mix)with Dosem
6. Silent Disorder with Go Hiyama
7. Prism
8. Vector 2
9. Skew Lines
10. Polygraph
11. Quantum Teleportation with Jeff Mills
12. Vector 3
13. Like A Star At Dawn[CD-EXTRA]
・JOIN THE PAC(Official Theme Song for PAC-MAN 40th Anniverary : Club Mix)
・Bells of New Life MV&25周年スペシャルインタビュー映像
・KI Möbius Strip オリジナルフォント(Mac,Windows,Unix対応 OpenType PS)[7インチアナログ盤]
1. EXTRA('95 Original Video Edit Rematered)
2. JOIN THE PAC(7” Version)
※全世界1000セット限定、7インチサイズハードカバー仕様、折込ポスター付
- KEN ISHII
-
- KEN ISHII
『Möbius Strip』完全生産限定盤 Type B(2CD) -
2019年11月27日(水)発売
価格:3,630円(税込)
UMA-8130/1[CD]
1. Bells of New Life
2. Chaos Theory
3. Take No Prisoners(Album Mix)with Jeff Mills
4. Vector 1
5. Green Flash(Album Mix)with Dosem
6. Silent Disorder with Go Hiyama
7. Prism
8. Vector 2
9. Skew Lines
10. Polygraph
11. Quantum Teleportation with Jeff Mills
12. Vector 3
13. Like A Star At Dawn[CD-EXTRA]
・JOIN THE PAC(Official Theme Song for PAC-MAN 40th Anniverary : Club Mix)
・Bells of New Life MV&25周年スペシャルインタビュー映像
・KI Möbius Strip オリジナルフォント(Mac,Windows,Unix対応 OpenType PS)
- KEN ISHII
- プロフィール
-
- KEN ISHII (けん いしい)
-
「東洋のテクノ・ゴッド」との異名を持つ、アーティスト、DJ、プロデューサー。1年の半分近い時間を海外でのDJで過ごす。1993年、ベルギーのレーベル「R&S」からデビュー、イギリスの音楽誌「NME」のテクノチャートでNo.1を獲得。1996年アルバム『Jelly Tones』をリリース。このアルバムからのシングル「Extra」のアニメーションMV(映画「AKIRA」の作画監督/森本晃司監督作品)が、イギリスの“MTV DANCE VIDEO OF THE YEAR”を受賞した。2017年にはベルギーで行われている世界最高峰のビッグフェスティバル<Tomorrowland>に出演するなど常にワールドワイドに活躍している。
- 児玉裕一 (こだま ゆういち)
-
映像監督。1975年生まれ。東北大学理学部化学系卒業。広告代理店勤務を経て独立。2006年より「CAVIAR」に所属。2008年、カンヌ国際広告賞、クリオ賞、ワン・ショーの世界3大広告賞全てでグランプリを受賞。2013年9月「vivision」設立。CM、MVなどの演出を手掛ける。近作にHONDA「HONDA JET」asics「ぜんぶ、カラダなんだ。」SoftBank「しばられるな」椎名林檎MV「鶏と蛇と豚」など。リオ五輪閉会式の五輪旗の引き継ぎ式における東京パートのチーフ映像ディレクターを務めた。
- 土井昌徳 (どい まさのり)
-
株式会社HERE.代表取締役社長/クリエイティブディレクター。学生時代より映像制作を始め、VJ(Visual Jockey)として数多くのライブでの映像演出に参加。CGプロダクションでのVFXデザイナーを経て、映像作品のプロデュースやライブエンターテイメント空間、商業施設における映像演出を手掛ける。また日本においてプロジェクションマッピングをいち早く空間演出に取り入れ、東京を中心に数々のプロジェクションマッピングの企画・演出・制作を手掛ける。近年ではVirtual Realityコンテンツやドームコンテンツの制作にも携わる。
- フィードバック 4
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


