集う人々を包むように、また風景に溶けていくように、記憶をつないでいく無数のシャボン玉。アーティスト、大巻伸嗣の代表作の1つ『Memorial Rebirth』は、過去から未来へと続く記憶の再生をテーマに各地で展開されてきた。
なかでも特別なのが、2011年から東京都足立区で継続する『Memorial Rebirth 千住』だ。同区で展開されているアートプロジェクト『アートアクセスあだち 音まち千住の縁』とのタッグでほぼ毎年開かれ、進化してきた、通称『千住のメモリバ』(参考:足立区名物「シャボン玉」祭に5千人が集結 大巻伸嗣インタビュー)。
大巻自身が「自分の作品であることを放棄するところから始まった」という特異な協働は、10年近くを経て「皆がその場の発言者になる」ことを期した、新たなスタートラインに立とうとしている。プロジェクトの牽引者であり一員でもある大巻に、現在形の思いを聞いた。
「自分の作品にしたいという思いを放棄すること」から始めたんです。
―『Memorial Rebirth 千住』(以下、『千住のメモリバ』)のプロジェクトが始まったのは2011年。準備を重ねて2012年に「千住いろは通り」の商店街で初開催されました。あいにくの雨模様ながら、いくつものシャボン玉が通りを包み込む様子は、特に子供たちが大喜びだったと聞いています。

大巻:「千住いろは通り」は昔ながらの商店街ですが、路面電車が廃線になったことで、今はメインストリートから少し外れているような場所です。でもだからこそ、ここで始めたかった。これは以降『千住のメモリバ』が「つなげて、ひらく」ことを意識してきたことに通じています。

1971年岐阜県生まれ。東京藝術大学美術学部彫刻科教授。『アジアパシフィック・トリエンナーレ』や『横浜トリエンナーレ2008』、『アジアンアートビエンナーレ』など世界中の芸術祭や美術館・ギャラリーでの展覧会に参加している。展示空間を非日常的な世界に生まれ変わらせ、鑑賞者の身体的な感覚を呼び覚ますダイナミックな作品『Liminal Air』『Memorial Rebirth』『Echoes』を発表している。
大巻:実施に至るまでには、いろんなことが初めてで大変でした。たとえば、本番直前に警備スタッフが足りないとわかって、区内で青少年委員や地域活動を熱心になさっている方にお願いして仲間を集めてもらったりして、なんとか無事に開催できた。
その方は一見ちょっと強面で、若いころ結構やんちゃもしていたという人ですが(笑)、本番を見てすごく感動してくれて、この景色を今後も子どもたちに見せたいと、今でも区内の様々な人のつなぎ役になってくれています。
―『音まち』は、その名の通り音をテーマに、地域における人と人の縁(えん)を育てようというアートプロジェクトです。これまで他に実施されてきた、大友良英さんや野村誠さんなど、音楽家の方のプロジェクトと共にありつつ、『千住のメモリバ』は具体的な音が主役ではないようにも思います。
大巻:確かに、プロジェクトのコンセプト上、音がテーマになっていました。でも僕は、まちの中で「まだ聞こえていないけれど大切な音」のようなものを探すのも大事ではと感じたんです。そのとき、自分の作品『Memorial Rebirth』(以下、『メモリバ』)が生かせたらと考えました。シャボン玉は音を出さないけれど、その一つひとつに、目には見えない色々なものをイメージすることができるからです。
―まちの人々の記憶や夢など、様々な思いを乗せた音符が広がり、それらに耳を澄ますような感覚でしょうか。
大巻:当初は僕自身も千住にアトリエがあったこともあって、アーティストがその時だけやってきて行うイベントやワークショップの限界も、かなり批判的に意識していました。その場限りで終わるだけは、地域に根ざす意味が薄れてしまう。

大巻:ですからここでは、継続的に関わることでの可能性を考えたいと思った。この点は大友さんや野村さんのプロジェクトも同様ですよね。だから最初に「ここで30年は続けたいです」と事務局にも伝えました。
―メモリバは『横浜トリエンナーレ2008』で初めて実施されて以降、大巻さんの故郷である岐阜など各所で展開されてきました。その土地ごとの記憶を過去から未来に「再生」するというコンセプトは一貫していますね。ただ、千住では毎年継続してきたことで、独特な展開をした印象があります。
大巻:僕は『千住のメモリバ』を、「自分の作品にしたいという思いを放棄すること」から始めたんです。もともと『音まち』は、まちなかでのプロジェクト。アートって何? という人と一緒に作っていくものだと考えています。
―アーティスト個人の作品に地域が協力するのとは違う?
大巻:これがアートです! と一方的に告げるのとは違うところから人と一緒に何が作れるのかを探っていくなかで、自分の作品を「使う」のも面白いと思ったんです。結果的に、『千住のメモリバ』は、僕自身まだ見えていなかったものを見せてくれました。

―「縁」というキーワードについてはいかがですか? 地域おこしなどとも違う、より個々の生活者が主語になる言葉だと感じます。
大巻:『千住のメモリバ』は、従来の「まつり」をとらえ直したものです。いわば「縁」を結ぶ場所ですね。たとえば同じ地域に住んでいながら、コミュニティーの中で結ばれていない人もいます。家庭の事情でそうした機会を作りづらかったり、国外含め他地域から移り住んできたりした人もいる。地域内の結び付きは、昔のように強くないところが多いんです。
そういった地域と結びつきが薄い人が増えると、まつりも一部の人のものになっていき、以前のような役割は果たせなくなっていく。こう考えると、『千住のメモリバ』は新しいまつりゆえのニュートラルさがある。昔から続くまつりも大切だけど、誰でも入ってこられる良さも活かしていきたいと思います。

地域の人たち自身がパフォーマーなのだということを、問いかけたかった。
―さきほどの「作品であることを放棄した」というのは、なかなか強烈な言葉ですね。でも、地域に丸投げしたのではなく、むしろ大巻さんは『音まち』に最も長くコミットしてきた作家のひとりですよね。
大巻:1度やると人が集まって、あちらこちらで自然発生的に人のつながりは生まれていく。でもその繰り返しになるより、『千住のメモリバ』は進化するべきではと考えてきました。

大巻:だから2回目の開催(2012年11月、千寿本町小学校)では皆で踊れる『しゃボンおどり』を作ったり、3回目(2013年、千寿常東小学校)ではその踊りに、地域の風景や記憶をもとにした歌詞をつけたりと、新しい要素が加わっていきました。
―そういったアイデアは、どんな風に生まれていったのですか?
大巻:『しゃボンおどり』についていうと、最初のきっかけは、当時よく通っていた飲み屋のお母さんがシャンソン歌手だったことです。彼女が『千住のメモリバ』で何か歌ってくれたらいいなという話になった。
彼女も「歌うわ!」と言ってくれて、それなら歌詞はワークショップで作ろう、曲や踊りは東京藝大の学生だったアーティスト集団「くるくるチャーミー」に相談しよう、という感じで広がっていきました。
大巻:第3回では夜の部も初開催しました。千住にキャンパスのある東京電機大学の方々とワークショップも実施して、その縁はシャボン玉マシンの準備や操作を行う、地元ボランティアによるテクニカルチーム「大巻電機K.K.」の結成にもつながっています。


―実施する度にキーパーソンが生まれて、つながっていった?
大巻:そうですね。でもそれは意識的に探したというより、向こうから現れてきてくれたという感覚です。
―毎回、開催場所を変えているのも特徴ですね。商店街で始まり、今お話のあった第2回と第3回は、それぞれ小学校を舞台にしています。
大巻:足立区は物価が安いとか人が親しみやすいとか、住みやすさを感じるところもあるけれど、ポジティブな面ばかりではない。古くからある独特な地域的課題も抱えているし、一方で日本各地と同様に核家族化が進んでいたり、昔ながらの商店に代わって大手チェーンの店舗が進出したり。かつてほど地域の中につながることができる場所が多くはなくなってきているんです。

大巻:小学校を会場にしたのは、そうした中で、子供を起点にすることで大人同士もつながる機会があると考えたからです。そこから地域の盆踊りに関わる方々など年配世代ともつながり、世代を超えたコミュニケーションが生まれました。その上で、皆で『千住のメモリバ』を一緒にやることが、上の世代から子供たちへ何かを伝えられる機会にもなればという考えもありました。
―さらに、第5回(2015年)、千住の魚河岸・足立市場を会場した際は、日中は市民中心に開催された一方、夜の部では、プロのパフォーマーたちが舞台表現を披露するという変化がありました。
大巻:ここまで『千住のメモリバ』を一緒に盛り上げてきた地元の人たちに、同じ場でプロの人たちの表現を見てもらいたいと考えたんです。しゃボンおどりの先生でもあった、くるくるチャーミーがパフォーマーとして踊り、即興での生演奏、舞台照明、演出もプロの仕事。昼のワイワイした感じとは違って、夜の部は会場がシーンとなったんですよね。
―シーンとなったというのは、『千住のメモリバ』を地元で盛り上げてきた人たちが、プロの表現のすごさを知った体験でもあった?
大巻:もちろん「こうなってください」とは言いません。でも、表現者の本気の発動というのを一緒に見てもらいたかった。それを観て変わることが確実にあったと思うんです。命が燃えるような感覚だったり、地域でやっていることを誇りに思う気持ちだったり。何より、『千住のメモリバ』の中では地域の人たち自身がパフォーマーなのだということを、問いかけたかった。また、そこから地域の教育にもつながるものが生まれてほしいとも思いました。

大巻:このことは次年度以降に登場した「音まちビッグバンド」(2016年、千寿青葉中学校)や、「ティーンズ楽団」(2017年、関屋公園)、「ティーンズ合唱団」(2018年、西新井第二小学校)の動きともつながっていきます。加えて、表舞台に立たない運営側の人たちにとっても同様のことだと思っているんです。
たとえば、シャボン玉の発生マシンをどう配置するかというフォーメーションも、「今回はどうしますか?」と問いかけてアイデアが出たら、「なぜそうするか?」を皆で考えていく。


―互いが学び合う場所にもなっているんですね。
大巻:2019年度の試みとしては、ある学生メンバーの提案をきっかけに「メモリバ学校」を企画し、小中高生などと創作を体験する催しを開催しています。これはまさに、自分たちで教育の場を作っていく試み。まちなかで世代を超えた文化的な学び合いが継続的に広がっていけば一番いいですね。

―お話を聞いていて思うのは、地域外の人にも開かれたイベントである一方で、地元の人たちとの共創に、より重きが置かれてきたのだなということです。
大巻:『千住のメモリバ』に関しては、取材依頼も「TVで紹介したら人がいっぱい来ますよ」みたいなお誘いはほとんどお断りしてきたんです。そういうことで浮かれていたら、皆が本当に見たい、新しい縁を自分たちで作っていくことで生まれてくる景色が見えなくなる。
でも1つだけ、2017年に『千住クレイジーボーイズ』という地域ドラマで『千住のメモリバ』が登場するシーンがあるんです。それは地元の人たちにも判断してもらい、僕も監督さんが持ってきてくれた台本を見て考えた上でOKとなりました。皆さん喜んでいたようで、これはドラマ自体が主人公の「再生」の物語だったこともあって、響くものがあったのだなと思います。

『千住のメモリバ』が続いていけば、周辺でなく中心になる。
―大巻さんは今、世界各地の展覧会やアートフェア、さらにファッションショーなどで、アーティスト個人として活躍しています。ご自身の中でそうした活動と、『千住のメモリバ』はどのように共存しているのですか?
大巻:僕は表現というのは「発言」だと思うんです。千住あるいは足立区は、現代では東京の中心というより周縁的なとらえられ方があると思います。そして、もちろん皆さん自分たちの地域を愛しているけど、実際は課題も色々ある。
特に公共のプロジェクトでは、そうした課題を扱うのは、難しいことです。外側からは中々ほぐせないから、内側から考えて取り組んでいく。そういうことを考えながら『千住のメモリバ』をやってきました。

大巻:開催場所を毎回変えていくことも、そのための選択の1つでした。前回までを支えた人がバトンを渡しながら、次の場所を手伝い連携して協働していく。
こういうプロジェクトなので、受け入れ側も簡単ではありません。でも、2018年に住民の方から声をかけてもらったことがきっかけで、初めて千住以外の場所、足立区西新井で開催が実現したんですね。今後も足立区内で広がっていくと良いなと思っています。
―そこでも継続性がカギになりそうですね。
大巻:そう、最初に『千住のメモリバ』を始めるとき「30年やりましょう」と話したことにもつながります。30年やったら子は親になり、まちの記憶がつながっていく。
公的な文化支援の多くは数年単位で切れるけれど、こうして続いていけば、『千住のメモリバ』が足立区に対して、あるいはより広く「発言」できる存在にもなっていく。周辺でなく中心になるんです。だからここまでは、「まずは」の10年だったとも言えますね。

大巻:10年近く続いたことで、ある種の新しい物差しのようなものが見えるようにもなってきた。それは、人が変化していくプロセスが、時間と共に見えてくる貴重な経験でもありました。単発的な表現でインパクトを与えることだけではできないことが、『千住のメモリバ』では起きるんです。
―30年やりましょう、との言葉で始まった試みが、もうすぐ10年。1つの節目かもしれませんが、これからについてどう考えていますか?
大巻:ここからの20年について思うのは、僕がいなくてもまちの人たちが勝手にやってもらえるようになれば素晴らしいなということ。そのためにはプロジェクトの自活力を上げていく必要がある。
今すでに、プレイベントなどは市民の方が中心になっているので、たとえば小規模なメモリバを出張できる半商業的な活動を取り入れて、経済的な自律性を高めることも可能性があるかと思います。

―最初に商店街で開催されて以来、「つなげて、ひらく」ことが『千住のメモリバ』のテーマだと伺いました。進化を続けて、いま次のスタートラインに立っているという気持ちも?
大巻:そうですね。ここからはこれまで以上に、市民の皆さんが表現者です。「人間は誰もが芸術家」という言い方もあるけど、僕は必ずしも芸術家ではなくてもいいと思う。
大事なのは、自分のいる場に対して、意識を持って向き合い、取り組むこと。結局それが人間にとっての「作ること」なのだと思います。そして、そこからどんな声が、音が聞こえてくるのかに期待したいです。
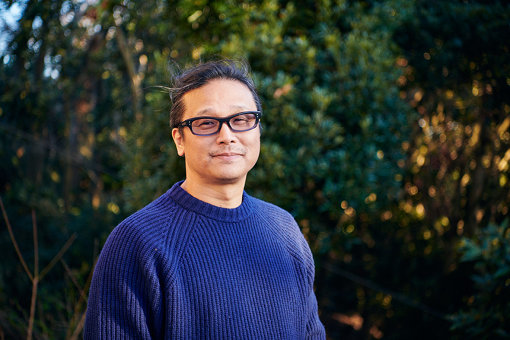
- プロジェクト情報
-
- Memorial Rebirth 千住
-
約50万~100万個のシャボン玉で、見慣れたまちを一瞬にして光の風景へと変貌させる現代美術家の大巻伸嗣のアートパフォーマンス『Memorial Rebirth』(通称:『メモリバ』)。千住では、2012年3月にいろは通りから始まり、区内の小学校や公園など毎年場所を変えながらリレーのバトンのように手渡されてきました。その過程で、オリジナルの盆踊り「しゃボンおどり」が誕生したり、まちの記憶や風景を描いた歌詞ができたり、夜空にシャボン玉を飛ばす「夜の部」が始まったりと、その形を変えながら、まちの様々な記憶と人をつないでいます。
- イベント情報
-
- 大巻伸嗣『Memorial Rebirth 千住 2020 舎人公園』
-
日程:2021年3月頃を予定
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、当初予定していた日程を延期しました。
※詳細は随時、音まちウェブサイトやSNSにて発信いたします。
- プロフィール
-
- 大巻伸嗣 (おおまき しんじ)
-
1971年岐阜県生まれ。『トーキョーワンダーウォール2000』に『Opened Eyes Closed Eyes』で入選以来、『Echoes』シリーズ(資生堂ギャラリー、水戸芸術館、熊本現代美術館、東京都現代美術館等)、『Liminal Air』(東京ワンダーサイト、ギャラリーA4、金沢21世紀美術館 、アジアパシフィック・トリエンナーレ2009年、箱根彫刻の森美術館等)、『Memorial Rebirth』(横浜トリエンナーレ2008)など、展示空間を非日常的な世界に生まれ変わらせ、鑑賞者の身体的な感覚を呼び覚ますダイナミックなインスタレーション作品やパブリックアートを発表している。
- フィードバック 5
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


