最近、街が窮屈な場所になっていないだろうか? 何をするにも許可がいり、目立つことをしたらすぐに白い目で見られる。誰もが自由に使える場所であるはずの公園では、もはやキャッチボールが禁止されている。一体、街とは誰のための場所なのか?
そんな硬化した都市との関係を、身体を使った「遊び」を通して変えていこうとするプログラム『Town Play Studies』が、渋谷パルコに新設された10代のための学び舎「GAKU」にてスタートする。「段ボールを使って街にパーソナルスペースを見つける」「さまざまな場所の温度や照度でビンゴをする」など、その内容はどれも簡単で少し変わったものばかり。普段とは違うその行為を通して、参加者の都市を見る眼差しは変化していく——。
今回は、同プログラムで講師を務める若手建築家・海法圭と、都市を舞台にそこに潜む多様な人の存在を感じさせる作品を手掛けてきた演出家・高山明の対談をセットした。最近の都市や公共空間に対する違和感から始まった対話は、各々のジャンルや経験を基点にしながら、縦横斜めに広がっていった。
短期間に都市が形成されるなかで、いろんなものが硬直化している。(海法)
―『Town Play Studies』は、12~18歳を対象に、「遊び」を通して都市や公共への意識を育むプログラムです。企画の背景にはどのような思いがあるのですか?
海法:ひとつは、いまの社会の不寛容さに対する疑問です。建築の世界にいるとよくわかるのですが、いま、デザインの多くは人間関係や責任問題で決定されています。たとえば、「このデザインにしたことで誰か怪我をしたらどうする?」「じゃあ安全にしよう」と、多くのことがリスク回避の思考で行われていて、新しいことに挑戦することが難しくなっている。

1982年生まれ。2007年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程修了。2010年海法圭建築設計事務所設立。人間の身の回りの環境と、人知を超えた環境や現象などとの接点をデザインすることをテーマに、壮大でヴィジョナリーな構想から住宅やプロダクトの設計まで、スケールを横断した幅広い提案を行う。
海法:また、コロナで少し状況は変わりましたが、多くの人が「職場」と「家庭」という二箇所を往復する生活をしていて、自らの所在が限定されることに息苦さを覚えている感覚があります。作り手としても生活者としても感じるこうした都市固有の問題を、普段の設計とは異なるアプローチから、中高生と一緒に考えられないか。そんな思いが、街での「遊び」を切り口にしたプログラムの背景にあります。

高山:街の不寛容さという感覚に共感します。昨年、『TOKYO 2021』という展覧会で『個室都市 東京』という作品を展示しましたが、あれは2009年の『フェスティバル/トーキョー』で発表した作品。池袋の西口公園に仮設のプレハブを建て、24時間営業の個室ビデオ店を開くものですが、おそらく現在ではできないでしょう。あらゆる場所が管理の対象となり、都市で遊ぶことが難しくなった。

高山:僕は2009年以降、日本で劇場作品を作っていませんでした。それは劇場の外に自由と可能性を感じたからですが、今度は逆に街中が不自由になったため、2017年、自由を守ってもらおうと劇場に戻りました。そういう転倒があります。
海法:子供が自由に選択肢を見出して遊ぶべき公園でさえ、多くの行為が禁止されている状況がありますね。大人も、街ではカフェに行くとか買い物をするとか、消費を前提とした限られた選択肢のなかでしか行動できなくなっている。
それに対して『Town Play Studies』では、たとえば参加者にモノと人のスケール感を架橋する存在である段ボールを持って、渋谷の街に繰り出してもらいます。自分にとってのパーソナルスペースを見つけて、「都市に居場所を発見する」感覚を掴んでもらうプログラムなどを展開しようとしています。
そんなことを考えている自分から見ると、『個室都市』をはじめとする高山さんの活動は制約のなかでかなりギリギリを攻めているな、と。

高山:いろいろ追いかけられた経験がありますから。
海法:(笑)。それはアートや演劇だからこそ可能だと思っていて、良くも悪くも建築基準法などの法律を知っている建築家が同じことをやるのは難しい。今回、「遊び」を謳うのもそれと関連していて、一種のパフォーマンスにすることで自由度が上がると思っているんです。
―真面目に街中でやると誰かに怒られるようなことでも、「遊び」、つまり一種の遊戯性をまとうことで、都市ともう少し柔らかい関係を結べる可能性がある、と。
海法:そうですね。人が過密に集まる現代の「都市」は、いわゆる近代化で生まれたもので、たかだか150年程度の歴史しかない。そこに大量の資本が投入され、短期間に都市が形成されるなかで、いろんなものが硬直化していると思うんです。
そこに介入して都市を揉み解したいという思いは、近年の若手建築家によるリノベーションの隆盛や、「パブリック」と「プライベート」の二元化に対し、その境界にさまざまな人たちが独自の集合をつくる「共」や「コモンズ」と呼ばれる領域を再び見出そうとする動きにも現れています。

高山:いま、建築倉庫ミュージアムで『模型都市東京』という展示をしているのですが、そこではシェアハウスに住む人や、移動しながら生活するアドレスホッパーと呼ばれる人に注目しています。彼らを見ても思いますが、どの都市にも不自由さは当然あるけど、管理するのが人間なら、そこに自由を見出すのもまた人間なんですよね。
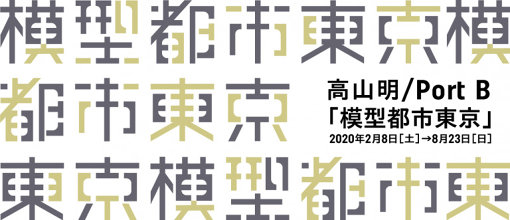
高山:僕は、マクドナルドの店舗で難民による講義を聴く『マクドナルドラジオ大学』というプロジェクトを行っていますが、実際にマクドナルドは難民や移民にとって重要な居場所になっている。資本にがっつり抑えられた場所であっても、ユーザーの創意工夫によってその場をハッキングして自分なりに上手く使いこなす人は必ず現れるんです。
『マクドナルドラジオ大学』はフランクフルトで始まりましたが、ユーザーの創意工夫による場所の読み替えの例は、ヨーロッパよりも東京の方が多い気がします。背景には、東京の街における、ヨーロッパに比べて圧倒的に曖昧な公私の区別や、治安の良さといった特徴もあるかもしれない。その意味で、東京は「遊び」と相性が良いとも言えると思います。

未知の観客に偶然出会うためには、一回、コンテンツになり切ってしまう方がチャンスがある。(高山)
海法:『マクドナルドラジオ大学』では実際のマクドナルドとのコラボを達成され、『東京ヘテロトピア』という別プロジェクトでは、今後、東京メトロとのコラボも行う予定だとお聞きしました。日本において、そうした大企業と協働できるのは素晴らしいですね。
一方、その協働では、活動のコンテンツ化も求められることになるでしょうか? ふいに入った店内で、人種や目的などが異なる人々が思い思いに過ごしている場に、講義をする人と聞く人が混在一体となって混ざりあっている様子が『マクドナルドラジオ大学』のダイナミズムとも思っていたので。学校という体裁をとる『Town Play Studies』でも、コンテンツ化の度合いが悩みどころです。個人的に、中高生には日常生活のすぐ隣にあるものとして、「遊び」を体験してほしいと思っています。

高山:たしかに、教育パパやママが「やれ」という感じで「遊び」をコンテンツ的に消費させるのは違いますよね。ただ、『マクドナルドラジオ大学』や『Town Play Studies』を行うGAKUもそうですが、「学校」というフレームにあえて乗ることの可能性もあると思います。
一般に学校はかなり制度化され、管理された場所になっている。僕自身、小学生の子供が1人と幼稚園児が1人いますが、とくにコロナ禍以後、学校に行く必要があるのかと感じました。しかし子供にとって管理がないことがいいことなのか、とも思う。管理されることで、子供はそこからどうやってはみ出すかを必死に考えますから。
つまり、毒にも薬にもならないものより、あえて有害なもの、毒を取り込んだ活動の方が可能性があると思うんです。コンテンツ化についても、自分のプロジェクトがあたかも最初からマクドナルドや東京メトロのコンテンツだったかのように認識されることを期待しているんです。

―高山さんが昨年の『あいちトリエンナーレ』の騒動のなかで立ち上げた『Jアートコールセンター』も、「合同会社」の体裁を取っていました。あれも、一種の公共サービスに擬態しながら、社会のインフラに溶け込むことを目指されていたわけですよね。
高山:そうです。最近は完全にその方向ですね。マクドナルドは全国に6000のフランチャイズがあり、東京メトロの利用者数も我々の演劇の観客とは比べものにならない。未知の観客に偶然出会うためには、一回、コンテンツになり切ってしまう方がチャンスがあると思うわけです。
海法:『Jアートコールセンター』の取り組みは僕も驚きました。アートプロジェクトでありながら、公共サービスという制度に入り込むのがすごい。そんなことができるんだと。

高山:演劇は、近代以降は主に制度の外で「芸術」として展開されてきましたが、もともと古代ギリシャでは、制度側の人間が国家イベントとして行う「取扱注意」の芸術だったんです。つまり反制度的ではなく、いわば「中の人」が、制度の内側からそれを揺さぶろうとしていた部分があった。いま、演劇は制度の蚊帳の外で、そうした力を失っていますが。
その意味で、僕が建築を羨ましく思うのは、まだ物理的に制度に介入できるところです。僕が付き合いのある磯崎新さんなんかを見ても、制度や権力の内側で、あるいは外枠ぎりぎりのところで、それをずらすことをつねに考えられている。古代の演劇人ってこういう感じだったんだろうなと思います。
―制度の内にいながらその枠を意識してずらすことは、それが制度であるがゆえに、普段の生活のなかでは難しいですよね。GAKUの学校というフレームや、『Town Play Studies』の「遊び」というコンセプトは、その思考に参加者を違和感なく誘い込む意味でも面白いと思います。
海法:そうですね。普通の学校とGAKUが決定的に違うのは、GAKUはクリエイターと中高生がガチンコでぶつかる場所であること。たとえば、みんなで家を設計するとしても、大人がある程度正解を知っているうえで規範を示してそれを再生産してもらうようなかたちにはなっていない。答えのないものを一緒に探していく場所であると理解しています。


海法:その先では、学校のビルディングタイプ(用途ごとの施設の典型的な型)自体にも揺さぶりをかけられるかもしれない。たとえば以前、観客席に囲まれた屋根付きのスタジアムを見て、ここが学校になったら面白いなと思ったことがあったんですね。スタジアムのなかで「あの辺が3年B組」とか、「全校集会はマイクを使えば一発」みたいな。そうした新しい学校のためのヒントを探る場所でもあると、個人的には思っています。
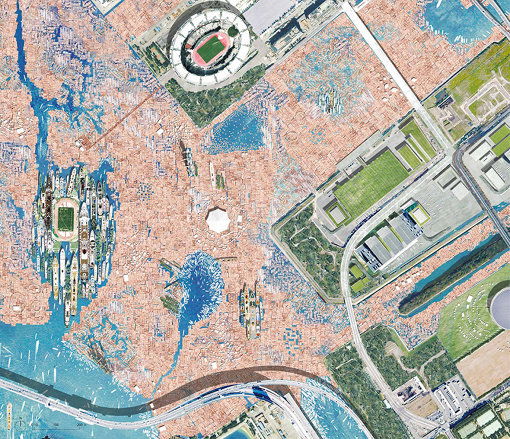
高山:あと、面白いのは学校行事ですね。たとえばアメリカのマイク・ケリー(1954~2012年)というアーティストは、アメリカのアイデンティティーを探るなかで学校行事がその核だと考え、作品としてそれをイミテーション(真似)しています。だけど、真似れば真似るほど制度からこぼれ落ちるものが浮かび上がり、ズレが出てきて面白いんです。
高山:僕も『東京修学旅行プロジェクト』という活動で、中国などの修学旅行を調べて追体験しました。すると、ただ修学旅行というフィクショナルなフレームがあることで、「身振りが人の認識を変える」という演劇の基本的な機能が働き、東京という都市や修学旅行自体への見方も変わるんです。「演じること」には、そうした可能性がありますね。

ネガティブに感じられるものからしか、人の知覚は変わらない。(高山)
海法:さきほど、建築家は制度に直に介入できるというお話がありましたが、たしかに公共建築が多く建てられた磯崎の時代には、そうした側面があったと思います。ただ、現在はその数は減少して、小規模なリノベーションが増えている実情がある。じゃあ、いま建築家が何をしているかと言うと、住民とワークショップを開き、誰もが建築を主体的に考え、愛着を持てるための場を設けることで、公共との応答を行っている部分があるんです。

海法:そのなかで思い返すのは、ワークショップというのは、もともと演劇の世界から出てきた取り組みであることです。つまり、ある枠組みのなかで役や身振りを与えられ、何かしらのゴールを目指していく。その点、僕は磯崎の時代とは違う意味で、演劇と建築が近い位置にあるような気がするんです。けっこう同じことをしているんじゃないかな、と。
高山:たしかに、ワークショップのような場を通して市民と結ばれる関係は、建築でも演劇でも近年ますます重要になっていますね。一方、僕が思うのは、ある種の不自由さをどう考えるかということです。それは、一種の暴力性と言っても良い。つまり、「こういうことをやれ」という指示のようなルールがあった方がいいのか、ない方がいいのか。

高山:最近の動きを見ると、演劇でも、建築でもそうだと思うのですが、協調性の高いものの方が尊ばれている傾向がある。でも、それは考えものだと思うんです。住民ワークショップの危うさは、やはりそこでは協調性が重視されることです。暴力性がなくなる。
僕はそれがつまらないんです。僕自身は、誤解を恐れずに言えば、いかに人に暴力的に介入するかに興味があります。なぜかと言うと、違和感や戸惑いや躊躇など、一見ネガティブに感じられるものからしか、人の知覚はなかなか変わらないと思うからです。
現に、協調的な演出家より、独裁的な演出家の方にクリエイティビティーが見られることはよくある。もちろん、その毒の部分を、そのまま出しても現在では通用しないし、やってはいけないことだと思います。でもだからこそ、それをいかに上手くやるのかが問われている。ワークショップにせよ集団作業にせよ、毒の部分こそが重要で、それがないと凡庸なものにしかならないと思うんです。

海法:わかります。いまの日本の公共建築でも、設計者の選定段階で提出するプロボーザルでいかに綺麗な文句を並べ立てるか、「みんなのための建築」的なビジョンや説明を提出できるかが求められてる。選定後もその言葉たちにしばられてしまい、言葉を乗り越えていくような本来のクリエイションが起こりにくくなっています。
ただ、先ほど言いたかったのは、その後のワークショップのなかでいかに住民の意見を取捨選択をして、それをどう建築にフィードバックするのか、そこにはまだデザイン、つまり、一種の演出家としての演出の余地があると思うんですね。
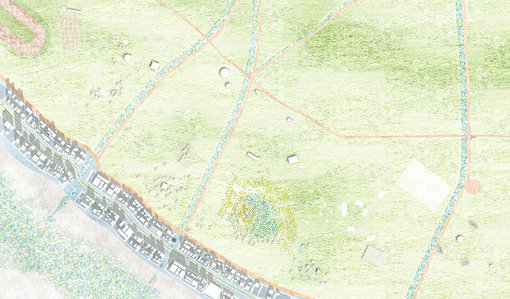
高山:なるほど。僕もワークショップをやるときは、できるだけエラーが発生するようにしますね。たとえば『修学旅行』なら、難民の人を招いて、その人にガイドしてもらう。すると、僕らがガイドするよりも明らかに混沌とするんです。なかなかまとまらなくて難しいんだけど、既知の人に頼んで予定調和になるより、そちらの方が面白いんですよ。
―高山さんは活動のなかで、つねに難民や外国人といった不安定な存在に着目されてきました。それは以前、高山さんが避難生活を送られていたことも関係しますか?
高山:そうですね。僕は一時期、ある事情から家に帰れなくなり、2か月ほど避難生活をしていました。すると、街の見方が変わるんです。たとえば、インターネットカフェやマクドナルドには深夜でもこんなに人がいるんだ、とか。
『東京ヘテロトピア』の裏テーマは「亡命」なのですが、難民や避難民、あるいはホームレスの人というのは、いわば都市の「エラー」を生きざるを得ないわけです。その目線を短期間だけでも体験できたことは、とても大変でしたが、重要なことでした。
そうした非常事態や難民生活は、演技でもいいからやってみるとものの見方が変わると思います。マクドナルドがあんなにありがたい場所だとは、普段は思わなかったですから。

みんな、逃げられる社会に行きたがっているんだと感じます。(海法)
高山:GAKUの良さのひとつは、全12回の授業を、知らない人たちと受ける点だと思います。既存の学校だと、人間関係が面倒くさい。でも、知らない人が集まるというのはわりと演劇的で、終われば「さよなら」できるわけでしょう。そういう場所はいまは意外とない。ずっと一緒にいると辛いと思うんです。
海法:人類学者の西田正規さんが「定住革命」と言っていて。人類は400万年ほど遊動生活をしてきて、定住したのはたかが1万年前。そこで農耕が始まるわけですが、そのとき人間の社会は、逃げられる社会から逃げられない社会に変換したと彼は言うんです。
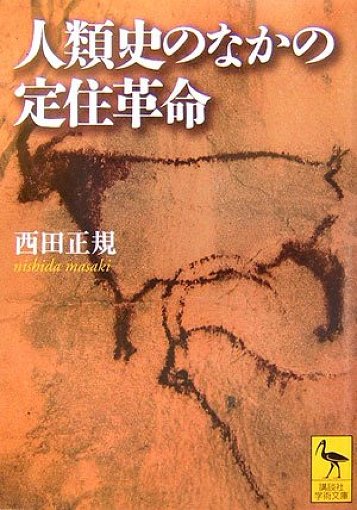
『人類史のなかの定住革命』講談社学術文庫(Amazonで見る)
海法:その視点で見ると、高山さんが『模型都市東京』で着目されたアドレスホッパーや、職場や家をシェアをしている人たちというのは、自分の所在や存在や居場所をある特定の場所や帰属に定めるのではなく、遊動させている人たちだと思う。定住生活を前提にしつつ、それを少しゆるやかに広げている。
みんな、逃げられる社会に行きたがっているんだと感じます。そして「都市の遊び」という今回のテーマも、定住生活をしなければいけない都市のなかで、いかに放浪的なもの、遊動的なものを見つけ出すのかという試みなのかなと思う。
高山:定住社会のなかで、いかにその外部との通路を作るのかという視点は、僕もとても興味を持っています。おそらく、神というのはそういう存在でもあったのでしょう。神を設定すると息苦しい定住社会のなかに縦軸ができて、少し風通しが良くなる。

海法:僕は普段からレクチャーの際、最初に雪の降る東京の風景を見せるんです。その風景が好きなんですが、なぜかと言うと、その日だけは遅刻しても仕方ないと言ってもらえる感じがするから。
雪という自然物が、人が人を許す強さを与える。あらゆる場所に神が宿っているという日本人の宗教観、自然観は、人以外のものとのふとした接点に神性を見出すようなところがあります。そうした、日常的な身体スケールの現象と、自然に限らずとも人智を超えた大きな現象との接点の模索は、建築家としての僕の設計のテーマでもあります。

高山:すごく重要なことですね。僕は前からオペラという芸術が気になっていて。一見時代錯誤にも見えるその表現が、なぜヨーロッパでは芸術の王様的に扱われているのか。
オペラというのはルネサンス後期の16世紀、古典古代の復興が興るなか、ギリシャ悲劇はすべて歌によって演じられていたという誤解から生まれたそうなんです。その後、19世紀までにオペラの形式は確立するのですが、重要なのは、この16~19世紀というのは、科学技術が生まれ、個人主義が台頭し、神が上手く機能しなくなった時代であることです。
僕らが生きているのは、その延長線上の世界ですから。神を設定することができない現代において、世俗的な世界に神の代替物への通路をいかに作るのか。それはあらゆる芸術が取り組むべき課題として、相変わらず僕らに求められていると思います。

―最後に、現在のコロナ禍についても聞かせてください。高山さんはさきほど避難生活という非常事態のなかで都市への眼差しが変わったと話されましたが、それで言えば、世界中の都市がロックダウンされたコロナ禍は、多くの人が都市を普段とは違う目で見る機会を与えたと思います。その時代に、『Town Play Studies』という取り組みが始まる意義とは?
高山:僕は演劇をやっているつもりなので日本の芸能のことを考えるのですが、芸能というのは本来「まれびと」の芸術であるわけですね。都市の外側からやってきて、風通しを良くして去っていく人たちが芸能の民だった。
都市に住む人たちは、その出し物に一瞬外部を感じて、ふたたび都市生活に戻っていく。それが都市を維持するために必要だと知っていたから、昔の都市に住む人たちは、外部や自分たちと異なる存在にも寛容だった。

高山:今回のウイルスも、まさにそうした外部性を帯びているわけですが、しかし、それに対する現代の人たちの反応は以前とはまるで違うものだったと思います。コロナ騒動の初期には外国から帰国してきた人たちが差別され、いまは「夜の街」と呼ばれる繁華街で働く人たちが社会の外側に追いやられている。
都市が持っていた外部への寛容さ、非日常的な時間や空間に対する想像力、それがコロナと同時に排除されている気がします。この『Town Play Studies』は、そうした外部への寛容さや想像力を回復する試みでもあるのではないでしょうか。ウイルスが入ってくると塞いでしまった外部との空気穴を、どうつなぎ直すのか。
海法:コロナ禍について思うのは、自分の身体をみんながここまで意識した時期はなかったのではないか、ということです。そのなかで街はどうだったかと考えると、カーテンがいつもより開いていた気がする。
それは、普段家にいない人がいたこともあるし、女性一人ではなく男性もいるから安心ということもあるかもしれない。いずれにせよ、みなが身体と対話しつつ自分の居場所を心地よくすることに、カーテンを開けるという小さなレベルで向き合っていた。

海法:それは、高山さんのやられている演劇などの祝祭性と比較すると小さいんだけど、日常の祝祭性をコロナの渦中でも身体と話しながら獲得しようとしていた試みに思えます。そういう観点から『Town Play Studies』を見ると、このプログラムも、日常のなかに小さな祝祭性をいかに作るのかという実践なのかなと思う。自分の身体を使った「遊び」を通じて、日常やまちのなかに小さな外側を見つけ出す。そんなことを、『Town Play Studies』ではやろうとしているのかなと思います。
高山:『東京オリンピック・パラリンピック』が予定通り行われていたら、まさに大きな祝祭が都市を覆うことになっていたわけですよね。それがコロナで延期になり、身体のようなもう少し小さなものに目を向けなくてはいけなくなった。もちろん大変な面もあるけど、僕はそこに良い面もあったと思うし、新しい可能性が生まれていると思います。

- プログラム情報
-

- 『Town Play Studies』
-
隔週火曜日 16:30-18:00
対象年齢:12~18歳(中学生・高校生)
渋谷を舞台に、都市と建築、人のダイナミックなインタラクション<遊び>を生み出すことから、これからのまちの可能性を探ります。
- 施設情報
-

- GAKU
-
10代の若者たちが、クリエイティブの原点に出会うことができる「学び」の集積地。アート、映像、音楽、建築、料理など、幅広い領域で、社会の第一線で活躍するアーティストやデザイナー、先進的な教育機関が、10代の若者に対して、本質的なクリエイティブ教育を実施する。10代の若者が、本物のクリエイターと実際に出会い、時間を過ごし、ともに考え、試行錯誤をしながらクリエイションに向き合うことで、まだ見ぬ新しい自分や世界、すなわち、原点のカオスに出会うことを目指す。ディレクターには、writtenafterwards(リトゥンアフターワーズ)のデザイナー山縣良和を迎え、世界的評価を受けるファッション・スクール「ここのがっこう」、カルチャーWEBメディアCINRAによるオンラインラーニングコミュニティ「Inspire High(インスパイア・ハイ)」などが集まり、感性、本質的な知識、自己と他者の原点を理解する精神を育むプログラムを構成する。
- プロフィール
-
- 海法圭 (かいほう けい)
-
1982年生まれ。2007年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程修了。2010年海法圭建築設計事務所設立。人間の身の回りの環境と、人知を超えた環境や現象などとの接点をデザインすることをテーマに、壮大でヴィジョナリーな構想から住宅やプロダクトの設計まで、スケールを横断した幅広い提案を行う。
- 高山明 (たかやま あきら)
-
1969年生まれ。2002年、演劇ユニットPort B(ポルト・ビー)を結成。実際の都市を使ったインスタレーション、ツアー・パフォーマンス、社会実験プロジェクトなど、現実の都市や社会に介入する活動を世界各地で展開している。近年では、美術、観光、文学、建築、都市リサーチといった異分野とのコラボレーションに活動の領域を拡げ、演劇的発想・思考によって様々なジャンルでの可能性の開拓に取り組んでいる。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


